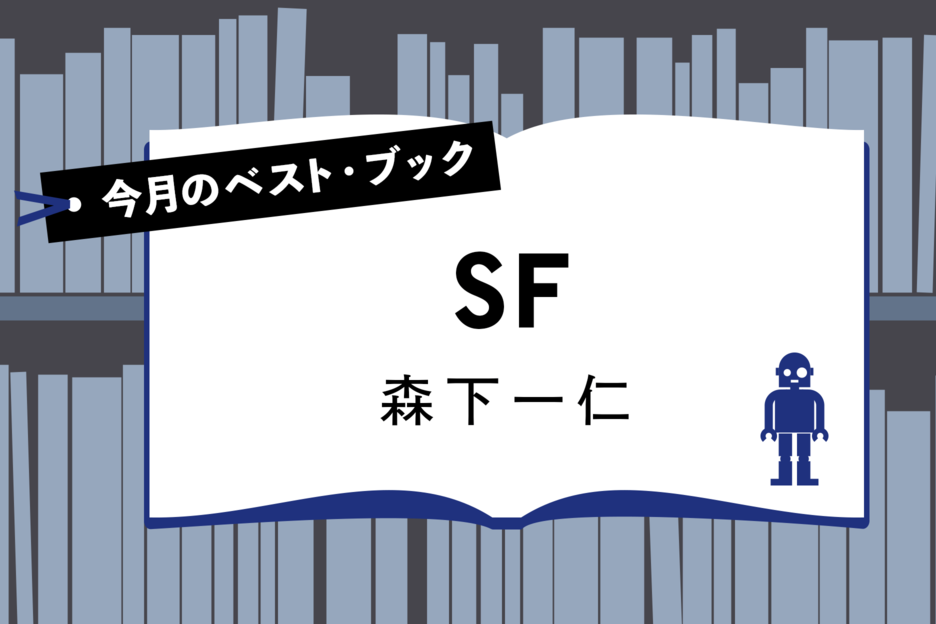今月のベスト・ブック

装幀=川谷康久
『百年文通』
伴名練 著
早川書房
定価 1,650円(税込)
はるか昔、文通をしたことがあります。
1回目は小学生の頃、相手は同学年の男子。2回目は高校生の頃、相手はやはり同学年の女子でした。いずれも雑誌の投書欄に記されていた住所氏名が手がかりで、最初はこちらから、2度目は先方からの申し出。知らない土地の、知らない人との手紙のやりとりは心弾むもので、甘い、良い思い出です。
しかし、伴名練の『百年文通』において少女同士がやりとりをした結果は、個人的な思い出などにとどまらず、世界全体を変えてしまうことになります。もっとも、ここでの文通で遠く離れているのは、場所ではなく、タイトルどおり、100年という時間なのではありますが。
きっかけは、撮影用に貸し出される神戸の古い屋敷を、市内に住む小櫛一琉(15歳)が訪れ、書斎にあった机の引き出しを開けたこと。中に1枚の紙が入っていたのですが、彼女はそこに書かれた達筆な文字を読むことができず、かろうじて読み取った「戀」の1文字から、これはラブレターに違いないと判断します。興味津々、何とか読み解こうと付箋を貼ったりしているうちに時間が経ち、紙を引き出しに戻して帰ろうとします。が、そこで付箋を剝がし忘れたことに気づき、慌てて引き返して引き出しを開けます、しかし、そこにあるはずの紙がない……。
実は、この引き出しは100年の時を超えて中身を往復させるシャトル運搬機だったのです。こうして年号が令和に変わろうとする頃の日本に暮らす一琉と、大正時代の女学生、日向静とのやりとりが始まります。
静は一琉よりひとつ年下で、とんでもない行動力の持ち主。一琉がうっかり送ってしまったスマホを使いこなし、横ピースの自撮りを送り返してきたり、教えたレシピで作ったクレープを売りさばいたお礼として一銭青銅貨(現代では5000円で売れる!)をくれたりします。
かくして時を隔てた友情が育まれてゆくのですが、100年前の日本ではスペイン風邪が大流行し、静も罹患してしまいます。彼女を救うため一琉が大奮闘するうち、すぐにこちらの世界でも新型コロナが流行し始め……。
原稿用紙にして二百数十枚のこの作品は、2021年、〈コミック百合姫〉の表紙(!)に毎月連載され、その後、一迅社から電子書籍として配信、大森望編『ベストSF2022』(竹書房文庫)に収録という経緯をたどって、ようやくここに1冊の単行本としてお目見えした次第。すでに名声の高い傑作といっていいのですが、今回、加筆修正が施され、SFとしての立体感がさらに増しています。幅広い読者層にお勧めいたします。
オラフ・ステープルドン『火炎人類』(浜口稔・編訳)は、『スターメイカー』『最後にして最初の人類』『シリウス』につづく、ちくま文庫4冊めのステープルドン本。H・G・ウェルズとA・C・クラークら現代作家をつなぐ重要なSF作家の作品が手軽に読めるようになったことはありがたい限り。
表題作はステープルドン(1886-1950)が生前最後、1947年に発表した中編。休暇で湖水地帯を訪れた男が、わけのわからない衝動に駆られて山中で穴を掘り、マッチ箱ほどの小石を見つけます。宿に持ち帰ったその石を、暖炉の火に投げ入れると、石は明るく輝き、中から小さな炎が立ち上がりました。それは「まばゆく輝く小さな木の葉か若樹、あるいは微風のなかで傾き加減にすらりと伸びたミミズのようだった」。
地球上の生きものとはまったく異なる形態をもつ知性体との遭遇の物語です。この〈ほのお〉は燃える石炭から熱エネルギーを得て蘇り、地上のあちこちにいる仲間とともにテレパシーで、男に自分たちの由来や存在の目的を語ります。
異種生命体として〈ほのお〉のあり様に驚かされますが、それより、彼らの知性の進化がステープルドンの宇宙哲学と密接に結びついていることに注目しなくてはなりません。それは人間がこの宇宙に誕生した意義と共通していて、すべては「コスモスにおける精神の目覚め」を目的としているというのです。
同じことは巻末に置かれた講演「惑星間人類?」でも「コスモス的目覚めのなかでコスモスを成就する」と語られています。
付け加えれば、この講演はA・C・クラークの依頼により1948年に英国惑星間協会で行われたもので、この中でステープルドンは、人類の進歩は「幼年期の病苦を乗り越えて(中略)自覚的な青年期の生へ」参入すべきだと言っています。クラークが代表作『幼年期の終り』を著したのは4年後、1952年のことでした。本書は、他に短編9編とラジオドラマのシナリオを収録。
日本SF作家クラブ編の書き下ろしアンソロジー第6弾は『恐怖とSF』(ハヤカワ文庫JA)。まえがきで同クラブ会長の井上雅彦さんが述べているように、恐怖とSFは親和性が高い。戦後、英米SFが紹介された頃、『宇宙恐怖物語』とか『宇宙の妖怪たち』といったアンソロジーが世間の耳目を集めたものでした。本書には、ラフカディオ・ヘルンとゾンビ、台湾の甘藷という取り合わせが意表を突く溝渕久美子「ヘルン先生の粉」をはじめ、20の力作が収められています。秋の夜長を怖い話で過ごすのも一興かと。