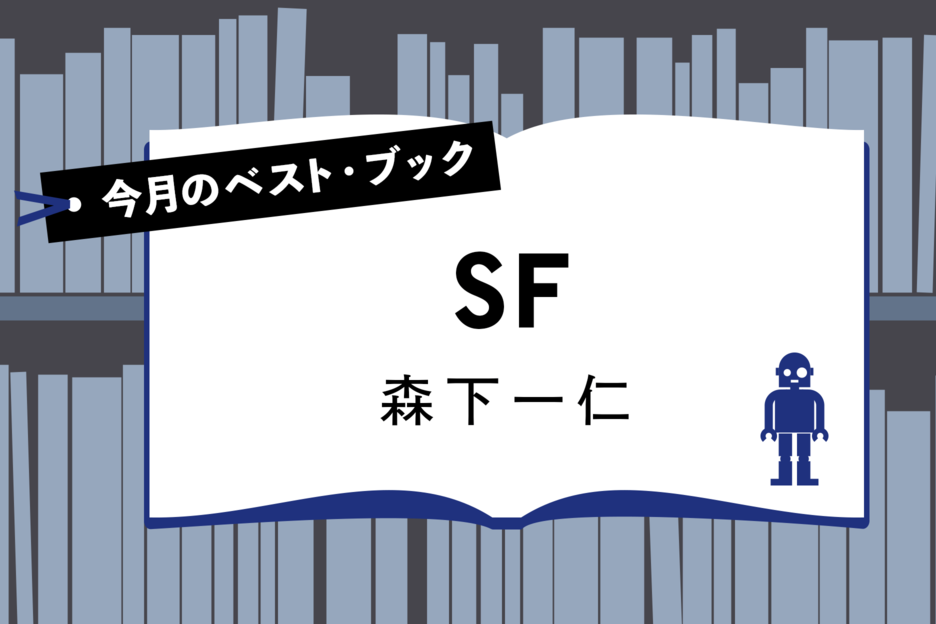今月のベスト・ブック
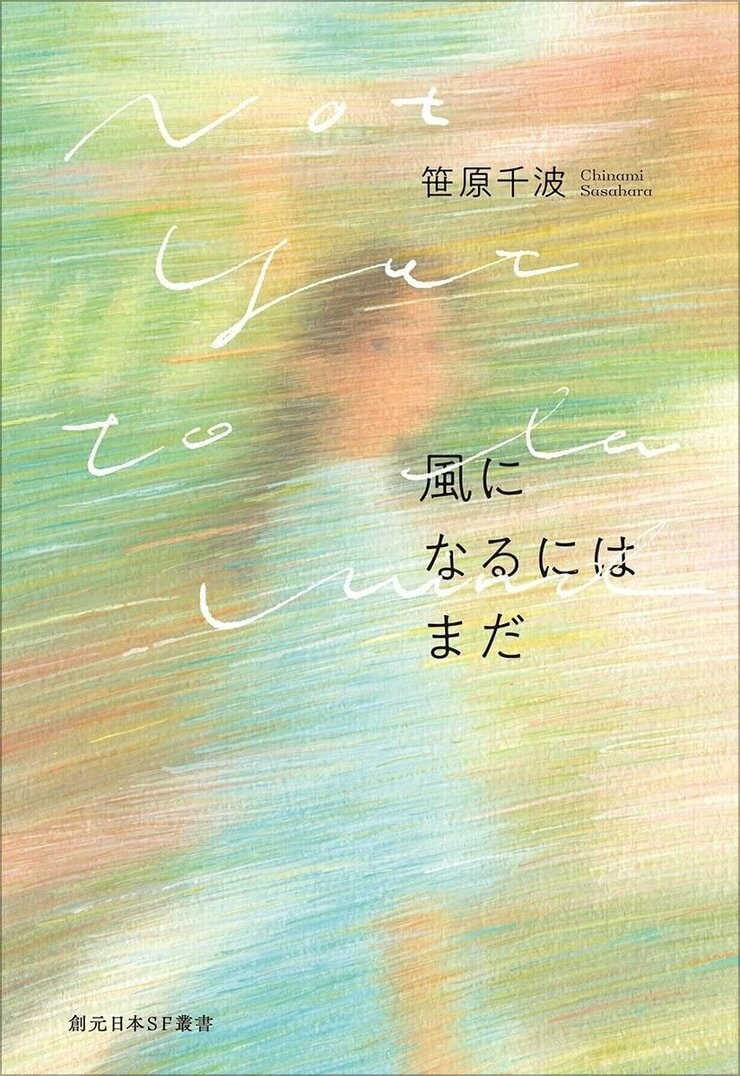
装幀=小柳萌加(next door design)
『風になるにはまだ』
笹原千波 著
創元日本SF叢書
定価 2,090円(税込)
サイバースペースと言ったり、メタバースと言ったり。要するに情報だけで成立する、もうひとつの世界なのですが、そこに人間が移り住むことができるとしたら、いったい何が起こるのでしょうか。
SFでは1980年代からの大きなテーマで、ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』をはじめとして、壮大で派手な冒険が展開される作品が多い。ところが、第13回創元SF短編賞を受賞した笹原千波の『風になるにはまだ』では、ごく日常的で繊細な世界が情報空間に出現しています。大がかりなテーマパークと小ぢんまりとした盆栽のように、欧米と日本の文化や考え方の違いが反映されているのかもしれません。
ここで描かれる情報世界には、健康な人もそうでない人も移り住むことができますが、現実世界とダブって存在することはできません。どちらに住むかを選択しなければならないのです。転生する際には病気や障害は取り除かれ、今までどおりの生活が維持できるので、いきおい情報人格と化するのは現実世界での活動に不安を抱えている人が多くなります。病院や介護施設の代わりになっているという側面もあるように見えます。
表題作は、以前、創元SF短編賞を受賞した際に紹介しましたが、この主人公の場合、原因不明の病気で失った色覚を情報化処理によって取り戻し、アパレルデザイナーとしての仕事を続けることができるようになります。必要な情報のやりとりは、遠隔通信をおこなう要領で現実世界とも可能なのです。
本書は、情報世界と現実世界での人々の交流をテーマとする6編からなる連作集。どれも壮大なものではなく、個人と個人の密接なつながりに焦点が当てられた繊細なものばかり。先にいった表題作は、一時的に肉体感覚を借りる契約をした情報人格と、体を貸した若い女性の、双方の視点から語られます。数時間だけ現実世界に戻ることができたアパレルデザイナーが久しぶりに衣服の手触りを味わう描写が見事。
「手のなかに花なんて」では、逆に、認知症の初期で情報化した祖母を、孫娘がアバターとなって訪ねます。「限りある夜だとしても」は現実世界でのエピソード。情報化を決意した男と、その友人の交流が語られます。「その自由な瞳で」は情報世界で生きる若い男女の話。相手の五感を一時的に借用するという設定が刺激的。「本当は空に住むことさえ」は、情報世界の建築物を設計する女性建築家と、その構造設計を担う現実世界の男性との物語。情報が創り出す自由奔放な世界で、建築物やさまざまな物体にリアリティを与えることの重要性が考察されています。
巻末の「君の名残の訪れを」は、現実世界で一緒に暮らしていた女性2人が、共に情報世界に移り住んだ顚末について。この作品では、情報人格にも「散逸」と呼ばれる「死」が訪れることが正面切って取り上げられています。つまり作者は情報世界においても、人はこの世を去ってゆく運命を免れないという設定を採用しているのです。なぜでしょう?
この設定は作品全体の魅力と深く結びついているように思えます。入念に描写される建築物や服飾品、庭や植物などの自然、それに何より、輪郭のくっきりした個性的な登場人物の造形は、人間と、それを取り巻く空間が一瞬ごとに色を変えるかけがえのないものだということを強調しているようです。永遠に変わらない不朽の存在などはない。現実の死と情報世界の死とを重ねることで、作者はそのことを指摘し、今を生きることの大切さを示唆しているように思いました。
エミリー・テッシュ『宙の復讐者』(金子浩訳/早川書房)は、アスタウンディング新人賞の後、本書でヒューゴー賞を獲得した新進女性作家の新趣向スペースオペラ。
主人公のヴァルキア(時に応じて「キア」とも「ヴァル」とも呼ばれる)は、17歳の女性戦闘員。小惑星と宇宙船が合体した宇宙要塞「ガイア・ステーション」で生まれ育ち、集団で戦闘訓練を受けながら、地球を滅ぼした敵「マジョダ」との戦いに臨む日を待ち焦がれています。しかし、いざ成人となる節目で彼女に割り振られた役割は、次の世代を産むことに専念する「ナーサリー」。つまり母親になることだったのです。
これに納得しないヴァルキアは、捕虜の異星人イソを人質にしてガイア・ステーションを脱出、惑星クリソテミスに逃亡します。そこには彼女の姉とその息子が居ました。彼らがここにいる経緯を推察したヴァルキアはガイア・ステーションがとっている戦時独裁体制に疑問をもち始めます。そして、時間と空間を超越する真実追究の旅に出るのです。
作者はもともとファンタジー作家としてデビューした後、SF長編としては第一作となる本書で高い評価を得ています。そのせいもあってか、この宇宙SFには敵との対決シーンや異星人との交流など、どこかファンタジーめいた手触りが感じられます。
さらに、スペースオペラとして特筆すべきは、性的多様性(LGBTQ)が多くの場面で重要な役割を果たしていること。男性優位の社会体制や覇権主義が一般的だったスペースオペラに新しい視点を持ち込み、なおかつハラハラドキドキのアクションシーンを織り交ぜながら、ラストのカタルシスへと向かうプロットは画期的といっていいでしょう。