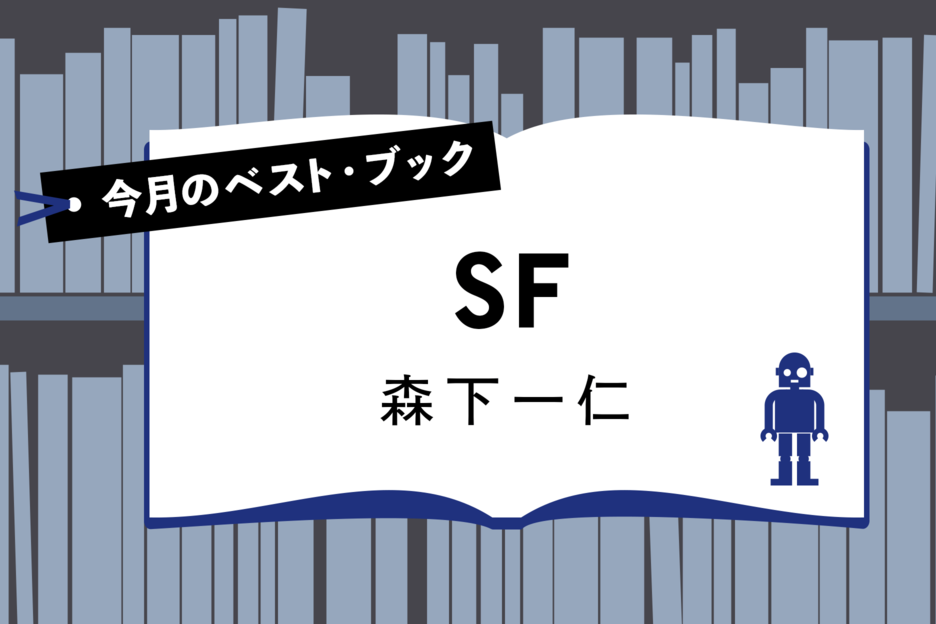今月のベスト・ブック
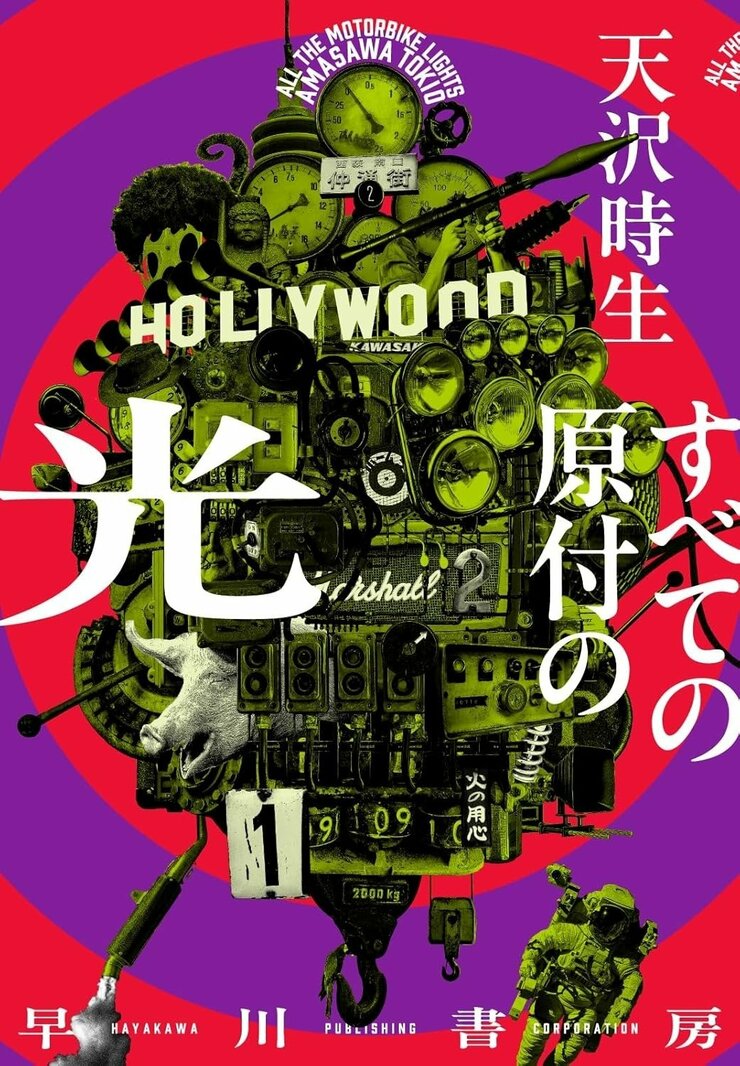
装幀=コードデザインスタジオ
『すべての原付の光』
天沢時生 著
早川書房
定価 2,420円(税込)
あぶない、あぶない。うっかりお宝SFを見落としてしまうところでした。入手が遅れたので「もう見送ろうかな」と思いながら読んだ天沢時生『すべての原付の光』は、今年の日本SFの中でもピカピカと輝く逸品。
まずは著者紹介から。
天沢時生さんは、1985年、滋賀県近江八幡市生まれ。2018年「ラゴス生体都市」で第2回ゲンロンSF新人賞を、翌年「サンギータ」で第10回創元SF短編賞を、それぞれ受賞。本書がデビュー作品集となります。
突拍子もないアイデアのもと奔放な展開を見せるアクションSFが真骨頂かと思いますが、何よりも文章がカッコイイ。
〈天に百億の星が満ちていた。1つの時代が終わり、また1つの時代がもうそこまで来ていることを告げる3つの星が、南の空に正三角形を形作る。砂嵐は止み、乾燥地帯は凪の海原のように青い〉――格調高い部分を引用してみましたが、実際はもっと猥雑で、意外性に富み、ユーモアが効いた文章が満載。文体の魅力では当代随一といっていいかもしれません。
物語そのものは、パンクでヤンキーで突き抜けていて、笑えます。「ショッピング・エクスプロージョン」は次のような幕開き――〈2049年、超安の大聖堂サンチョ・パンサの創業者コモミ・ワタナベはGAFAを超えて世界の救世主となった〉。資源枯渇で動植物由来の食品が手に入らなくなった社会を救ったのは、「凝縮陳列」や「POP爆撃」を売りものに東京・府中市から興ったディスカウントストア(モデルは明白ですね)だった。自然増殖するバイオ商品『自生品』が誕生し、店に溢れて人々のライフラインとなったのだ。店は全世界に進出してゆく。しかし、今度は店そのものが自己増殖を始め、地球は店の海と化した。〈人類に滅亡をもたらすものの正体、それは核戦争でも疫病でもなく、大型ディスカウントストアだったのだ〉。
表題作は滋賀の大型ガレージのようなところに拉致された不良中学生たちが「神殺し」の弾丸となって異世界に撃ち込まれる、というもの。ゲンロン賞の「ラゴス生体都市」は未来のアフリカ・ナイジェリアが舞台。セックスも恋愛も禁止された超管理社会で、木の股から生まれた青年が、ポルノを武器に革命を起こします。残る「ドストピア」も「竜頭」も粗筋だけでは意味をなさないほど。それでいて、ディテールは入念で、文章はビシッと決まっています。驚き、あきれられた方はぜひとも手にとってみてください。
エドワード・ブライアント『シナバー 辰砂都市』(市田泉訳/創元SF文庫)は、戦後のアメリカSF黄金期と80年代のサイバーパンクの間に生まれた、洗練され、SF性にこだわった作品群のひとつ。はるかな未来、隔絶された時空にたゆたう小都市の日々を描く8編から成っています。
このオムニバス作品がJ・G・バラードの愛すべき短編シリーズ〈ヴァーミリオン・サンズ〉から刺激を受けたものであることは、知る人ぞ知るところ。しかし、気だるく魅力的な日常の雰囲気は似ているとしても、こちらはもっとしっかりしたSF的基盤の上に築かれています。戦後SFを築いた1人であるバラードがSFの枠組みにさほどとらわれず、一方、SF二世ともいうべきブライアントはあくまでSFであることにこだわったということなのかもしれません。
シナバーでの暮らしに不自由はなく、人々は連日、パーティーを楽しみ、奔放な性生活を享受し、芸術や趣味に時間を費やしています。何がこの生活を可能にしているのか? 各編を読み進めるにつれ、都市の様子が浮かび上がって、その謎も見えてきます。中ほどに置かれた「ヘイズとヘテロ型女性」では、タイムマシンで1963年の世界から到着した少年が、永遠の若さを保つ美女に思春期の願望を充足させてもらうのですが、その過程でこの未来都市の性や家族のあり方を知ります。解説の大野万紀さんが、とっかかりにこの作品を勧めているのも的確なアドバイスといえるでしょう。懐かしく感じる反面、まだまだ新鮮さを失わない名作。
アレステア・レナルズ『反転領域』(中原尚哉訳/創元SF文庫)は、現代にゴシックロマンスを甦らせたような奇怪なSF。
極地探検航海の船の上から話は始まります。船医であるコードは仕事をこなしながら、趣味の小説を執筆し、乗組員に披露しては好評を博しています。が、ただ1人の女性乗客であるエイダだけは辛辣な批評を浴びせてきます。船が目的地に近づいたと思われる頃、コードは甲板でマストの下敷きになり意識を失いかけます。もうろうとするコードに、そばに来たエイダが言うのです――「もう、コード先生ったら、今回はこんな死に方をしてなんの役にも立たないわ」。
実のところ、コードは何度も死んでは生き返り、似たような探検に参加していたのです。北極圏、南極圏……さらには宇宙空間での旅にまで。
謎は物語の成り立ちそのものに関わっていて、それには「反転」という位相幾何学の問題が関わっていたり、人工知能が絡んでいたり、宇宙空間では「エーテル通信」なるものまで使われ、プロットはサービス満点。怪奇な物語を可能にするためなら何でも使おうというのが作者の姿勢なのでしょう。