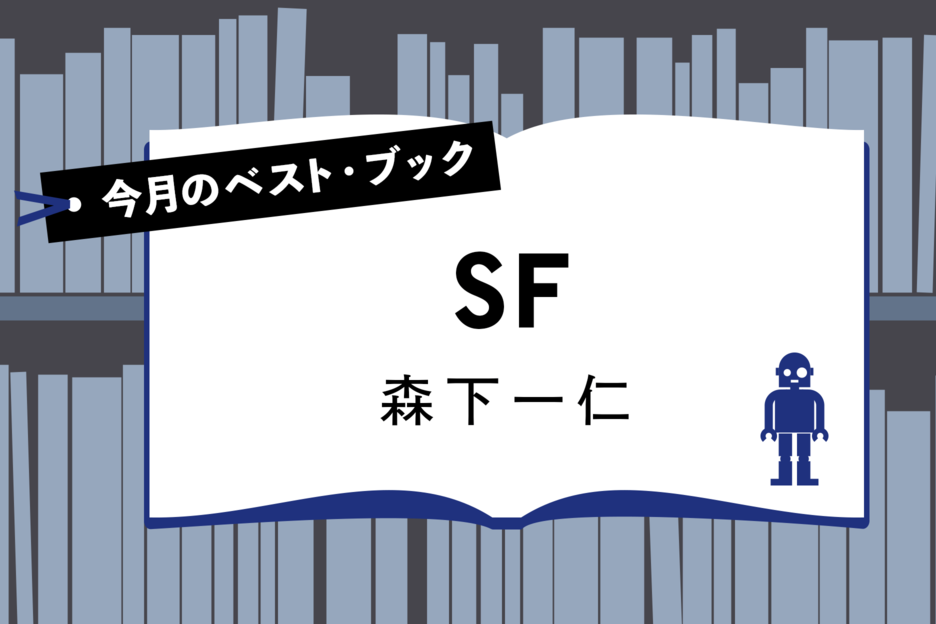今月のベスト・ブック
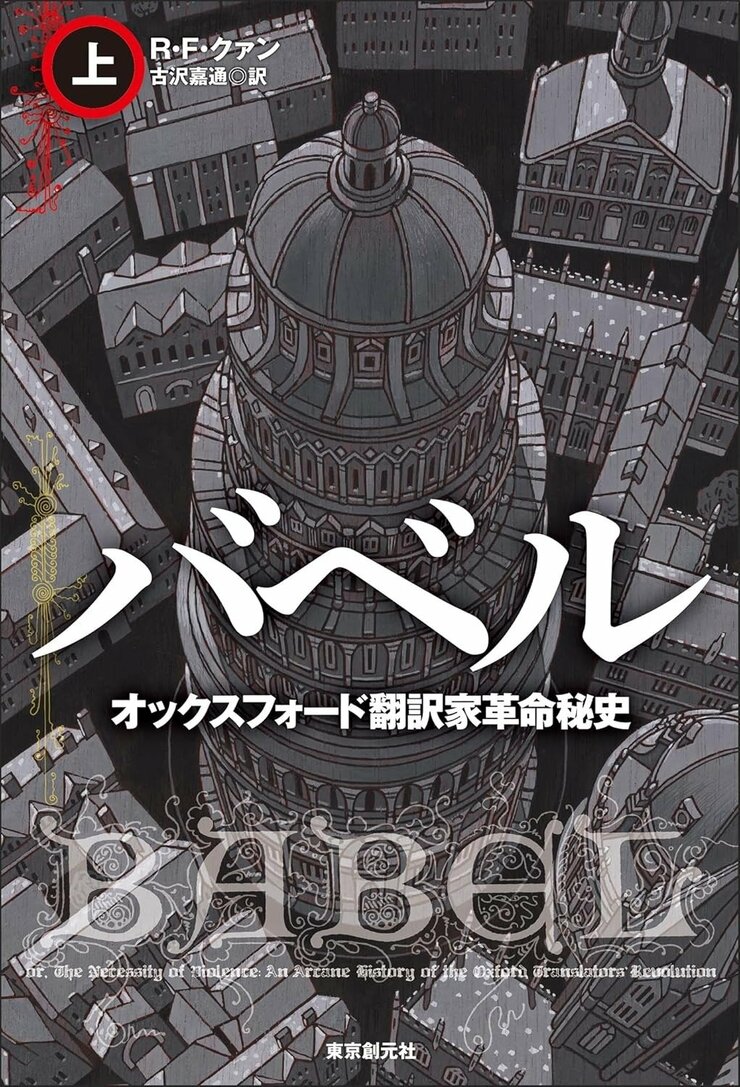
装幀=岩郷重力+W.I
『バベル オックスフォード翻訳家革命秘史』(上・下)
R・F・クァン 著
古沢嘉通 訳
東京創元社
定価 上・3,300円 下・2,750円(税込)
R・F・クァンの長編『バベル』。このタイトルは、いうまでもなく旧約聖書の「バベルの塔」から来ています。天に届く塔を築こうとする人間の試みをくじくため、神が人間の言葉を乱した。その結果、人はさまざまな言葉を使うようになり、互いに心を通わせることができなくなった、というものですね。
著者レベッカ・F・クァンは中国生まれでアメリカ在住。物語は19世紀前半、ヴィクトリア朝が最初期の英国オックスフォードに「バベル」という名を冠した建物が存在し、そこでは魔術的テクノロジーが研究、運用されているという設定のもとに展開される改変歴史ファンタジーです。この“魔法”以外はほぼ実際の歴史を下敷きにしており、読者は由緒ある学問の街で青年たちが学び、論争し、愛し、憎み合う姿を生き生きと思い描くことができます。産業革命と植民地主義が進展する時代の青春群像劇でもあるのです。
ではなぜ建物の名が「バベル」なのか?
それはここで世界のたくさんの言葉が研究されているから。ラテン語、ギリシア語、英語、フランス語、中国語、カリブ海諸島のクレオール語……いくつもの異なる言葉を操れるようになることが、最初に触れたバベルにおける魔法の核心をなしているのです。
どういうことかというと、たとえば「無形」という中国語と「invisible」という英語の対を考えてみます。どちらも日本語にすると「見えない」ですが、それぞれの言語を母語とする人が抱く概念は、翻訳された他の言語のものとは微妙に異なるはず。バベルのテクノロジーにとっては、この、言語化できないニュアンスこそが大事なのです。
物語に即してさらに説明してみれば、まず「見えない」を表わす中国語と英語、双方の言葉を刻んだ銀の棒があります。両方の言葉の概念を熟知する人物がこの棒を振ると、当人やそばの人物が街角から消え失せてしまうのです。「四人は存在していたが(中略)形のないものだった。漂い、広がった。彼らは空気となり、煉瓦壁となり、丸石となった」という状態。おそらく日本語の「見えない」と「invisible」の対だと、また違った消え方になるはず。それぞれの言語が帯びているニュアンスの相互作用で、魔法の効果が変わってくるのでしょう。ある言語から別の言語に移す時に失われる「何か」を、棒の銀が捉え、実際の作用として働かすといいます。だから、バベルにはさまざまな言語に堪能な人たちが集められ、特異な、目覚ましい効果をもつ言葉のカップルを探しているのです。
魔法の説明が長くなりました。本来の物語は、中国から来たロビン、インドから来たラミズという2人の青年男子、そしてハイチから来たヴィクトワール、地元英国のレティシアという2人の女性──この4人が中心となって進行します。中でもロビンが主人公役となるのですが、彼らはバベルで銀の棒による魔法を基礎から学び、昇級試験を経ながらだんだんと成長し、それとともに大英帝国繁栄の秘密と問題点を悟るようになります。銀の棒による魔法は、医療、生産活動、交通など、社会のいたるところに浸透している一方で、その秘密は英国のみが独占し、世界の富を収奪しているのです。バベルは大英帝国繁栄の中枢ともいえる存在なので、その責任を問う秘密結社の攻撃の的となっているのでした。ロビン自身、バベルの成果を上げるために仕組まれたおぞましい陰謀のもとに誕生させられたことが判明します。
汚濁が渦巻く激動の世界を懸命に生きてゆく若者たちの姿が胸を打ちます。社会の矛盾を撃つ彼らの姿勢は時代を超えた重いテーマといえるでしょう。翻訳の不可能性論議を始めとする言葉の面白さも読みどころ。多くの魅力をもつ本書は、ネビュラ賞、ローカス賞、華語科幻星雲賞翻訳部門などいくつもの賞に輝き、多くの言語に訳されています。
昨年11月刊なので紹介が遅すぎますが、『ラブ・アセンション』(ハヤカワ文庫JA)は『ジャイロ!』で第45回群像新人文学賞(「早川大介」名義)を、『ヴィンダウス・エンジン』で第8回ハヤカワSFコンテスト優秀賞を獲得した十三不塔の書き下ろし長編。読むのが後回しになっていましたが、いざ手にとると、期待を遥かに上まわる面白さのエンターテインメントSFでした。
話の素材は恋愛リアリティ番組。1人の男の愛を12人の女たちが奪い合う過程を同時進行的にカメラが追うという番組で、ドラマが展開する舞台が軌道エレベーターの途中であったり、参加女性の誰かにエイリアンが寄生していたり、あるいは、制作者の息のかかった「キツネ」と呼ばれる存在が交じっていたりという工夫が凝らされていたとしても、なんだか薄っぺらくて、どこを楽しめばいいのか、すぐには呑み込めない感じ。
ところが、話は番組制作者の思惑どおりに進行してゆくものの、念入りに作り込まれた登場人物たちの経歴や恋愛観、生き方などが突拍子もないもので、当然、彼らが巻き起こす騒動も桁外れのとんでもなさ。読んでいて、そんなことになってるの!? まさかそれは!? と呆れ、驚くことの連続なのでした。恋愛至上主義が臆面なく謳いあげられ、しかもそれが嫌味なく納得できてしまうのは、見事としかいえません。滑らかな文体も心地よい。「愛の昇天」という破天荒なドラマに盛大な拍手を送らざるを得ませんでした。