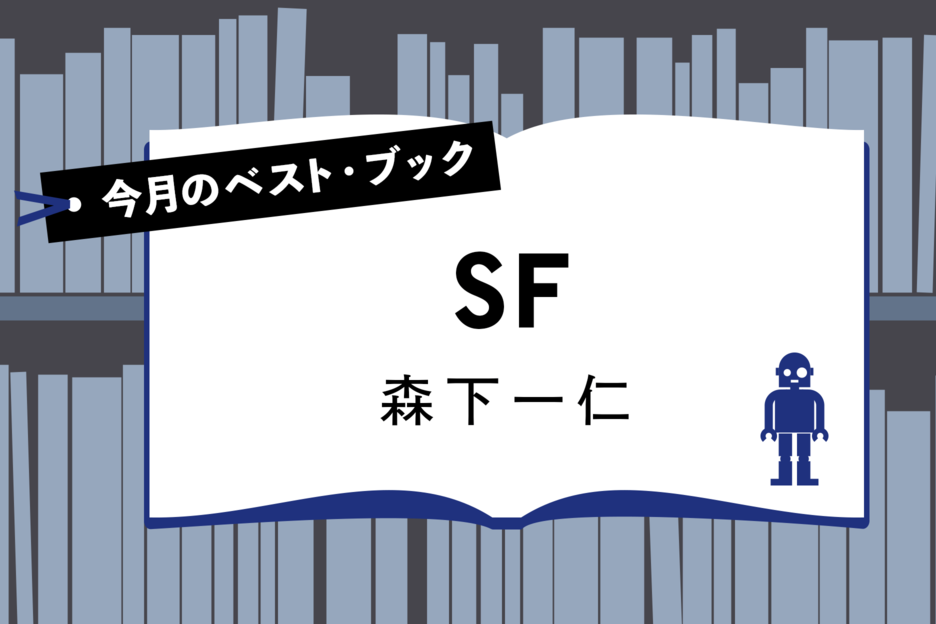今月のベスト・ブック
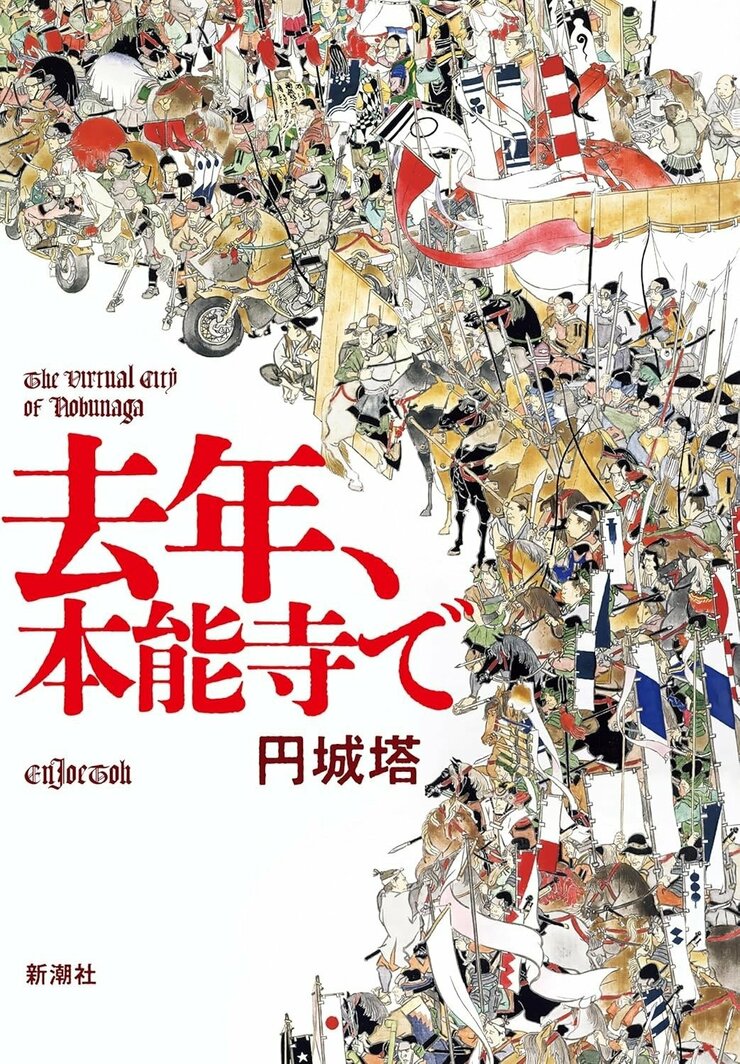
装幀=新潮社装幀室
『去年、本能寺で』
円城 塔 著
新潮社
定価 2,090円(税込)
NHK大河ドラマはほとんど見ませんが、『光る君へ』は見ました。やはり物書きの姿には興味があります。藤原道長との関係はさておき、紫式部のイメージにはさほど変化がありませんでした。ただ、思い浮かべる顔が吉高由里子になってしまうのに参ってます。
この大河ドラマ。脚本の原則は、視聴者の関心を呼ぶようなドラマチックな展開を心がけながらも、史実にはあくまでも忠実に、ということだそうです。
そういう意味では、円城塔の歴史小説集『去年、本能寺で』も同じかもしれないと思いました。本書には歴史上の人物(中には人物でないものもいますが)を主人公とする11の作品が収められています。
基本は史実に忠実。しかも最新の情報に基づいています。が、それ以外の部分はぶっ飛んでいる。常識を超越した、とんでもない物語が繰り広げられます。
史実に忠実でありながらとんでもないというのはどういうことか。冒頭の「幽斎闕疑抄」は文武両道に長けた戦国武将・細川幽斎を扱ったものですが、その幽斎が、関ヶ原の戦いの直前、徳川方について丹後田辺城に籠った際のこと──〈このとき幽斎、67歳。軍事AIであると同時に、文事AIとしての名が高い〉などと語られるのです。
また、やはり戦国武将として知られる斎藤道三を扱った「三人道三」では、48歳の道三のもとへ若き明智光秀がある情報をもたらしますが、その日を〈道三のもとに、一大秘事がもたらされたのは昭和48(1973)年のことである〉と記すのです。これは、光秀の報告内容である「道三とされてきた人物は2人いる(もう1人は父親)」ということを記した「六角承禎条書」が昭和四十八年に発見された“史実”にもとづいていますが、道三本人の生きた時代をわざと無視しています。
細川幽斎がAIだったり、自分が2人いることに気付いた斎藤道三があたふたしたりするのは、現代人である作者から見た、常軌を逸した歴史人物像といっていいでしょう。その視点がいかにも円城塔流。笑えます。
表題の『去年、本能寺で』は、アラン・レネ監督の映画『去年マリエンバードで』のもじりですが、時間と空間をシャッフルした、美しくも難解な名作のタイトルを借用した意図は、既存の歴史像を打ち破り、時空を超越した、突拍子もない物語を編んでみようという意欲の現れでしょう。11編はバラバラではありますが、作者の頭の中では、最後に置いた表題作で全体をまとめようという心づもりがあったことが随所から見てとれます。情報量豊かで、機知に富んだ、楽しい連作集。
高野史緒の新作書き下ろし『アンスピリチュアル』(早川書房)は、他人の“オーラ”が“視える”女性が主人公。
「オーラ」という言葉にはいくつかの意味がありますが、ここでは、その人のもつ気分やエネルギー、運命などが入り混じったもの。スピリチュアル系で使われている概念そのものなのでしょう。中年に足を踏み入れようかという主人公・祝子が視る光景──〈行き交う人々を包んで視えるオーラは、淡い赤や淀んだ緑、とげとげしいピンク、ふんわりと輝くオレンジ、でこぼこの多色など、目が痛くなるほど多彩だ〉。一方、祝子自身のオーラは茶色。平凡な日々に疲れ、夫の不貞に愛想をつかしているのです。そんな彼女の前に、ある日、少年のような印象の若者・優が現れます。彼のオーラがまったく視えないことに驚くとともに、優しくて、不思議な能力をもっている優に、彼女は惹かれるのです。
SFとして見れば超能力者同士の恋愛物語ということになるでしょうか。近未来の日本が舞台で「歌舞伎町構造体」と呼ばれる、風俗とスピリチュアルの魔界があったりしますが、ヨガや瞑想にハマる中高年や、占いに夢中な若者たちの姿は、現代そのものといってよさそう。その中で生き、もがく祝子と優がどんな運命をたどるのか。年齢を超えた祝子の愛がせつない。また、スピリチュアル現象を単に理解不能な超常現象と捉えず、その根拠となる脳生理学的メカニズムをほのめかしたり、超常現象そのものの根本を現代宇宙論に求めたりするところも、この作者らしいところ。とことん突っ込んでゆく姿勢に感服しました。
ラヴァンヤ・ラクシュミナラヤン『頂点都市』(新井なゆり訳/創元SF文庫)はインド発の近未来ディストピアSF。
インド南部の都市ベンガルールが舞台。従来の国家は崩壊し、〈ベル機構〉と呼ばれる統治機関が生産性第一、戒律重視の階層社会を築いています。作品は短いエピソードを積み重ねる形で、格差と規律に縛られた過酷な生活を描くのですが、その内容は英米のディストピアSFの系譜をきっちりと継いでいます。個人的には、冒頭の「義賊の植えた樹」がお気に入り。植物というものを知らない下層階級「アナログ民」のもとへ、上位民の土地から樹木の種子をもたらす怪盗の話。
インドといえば、かつては英国が支配し、西洋文化の伝統が根づいている国。現代はハイテク国家に変身しようとしているところなので、SFが盛んなのも不思議ではありません。映像メディアの方ではSF大作がヒットしたりしていますが、今後は小説も続々と紹介され、アジアのSFの豊饒さをさらに増してくれるでしょう。