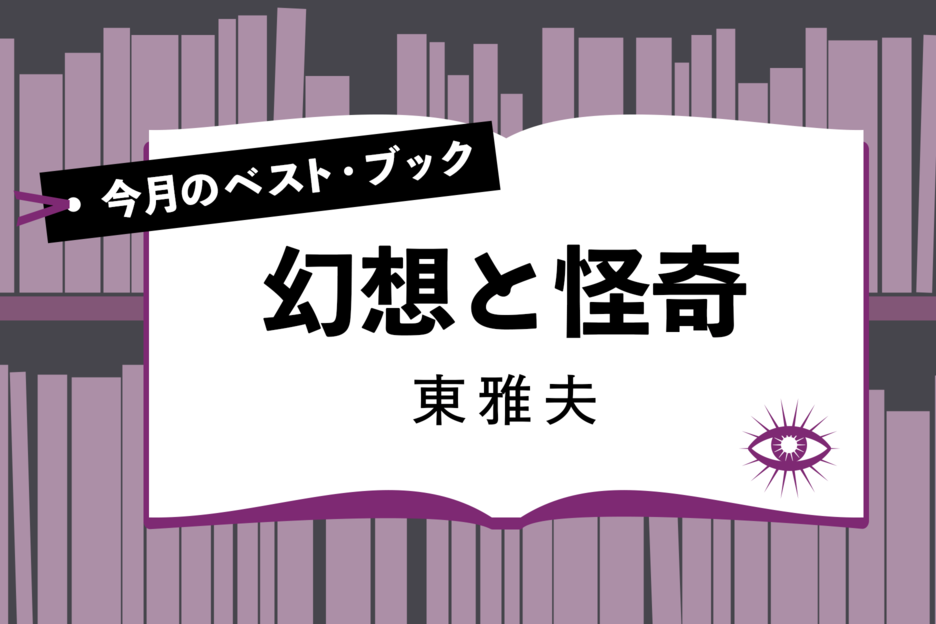今月のベスト・ブック
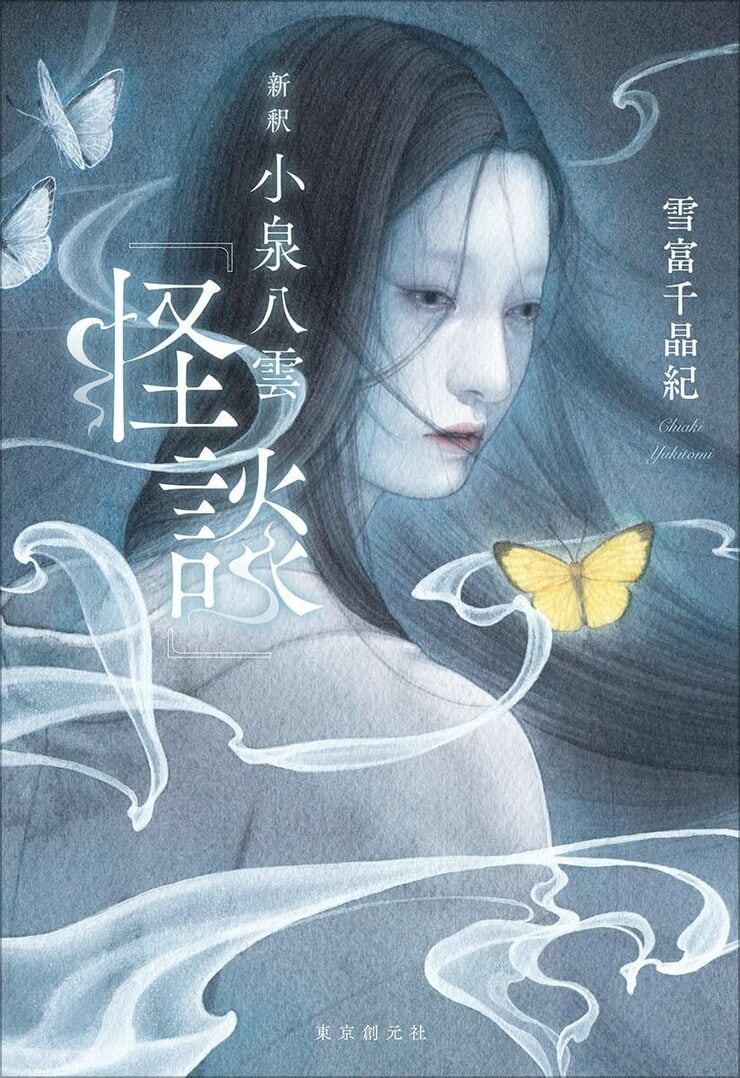
装幀=長崎綾(next door design)
『新釈 小泉八雲「怪談」』
雪富千晶紀 著
東京創元社
定価 2,200円(税込)
今回は私が何かと編纂や帯文で関与した「小泉八雲本」の大特集を、お送りする!
なぜ今、八雲の人と作品に、新たな関心が集まっているのか?
答えは、まもなく放送が始まるNHKの朝の連続テレビ小説『ばけばけ』。同作のヒロインとなる小泉セツ(節子とも)は、八雲の妻となり、日本語に不自由な夫に代わり、来日後の代表作『怪談』などの素材を古書や古雑誌から蒐集・解読、夫にその内容を語り聞かせた、いわば事実上の「共作者」と言ってもよいような、重要な存在だったのだ。
まずは、その『怪談』所収の有名な物語群を、本歌取りするようにして現代に蘇らせた新鋭作家・雪富千晶紀の短篇集『新釈 小泉八雲「怪談」』から。
素材となった原話は「ゆきおんな」「ろくろ首」「水飴を買う女」「耳なし芳一」「貉(のっぺらぼう)」の全5篇だ。
作品によって、ミステリー風味あり、恐ろしくも心温まるファミリー・ストーリーありと、それぞれ現代的なアレンジが施されていて、読み手を飽きさせることがない。
とりわけ私が瞠目したのが、巻末に据えられた「『贖罪』という名の人形」だった。
主な舞台は、軽井沢近郊にある、自殺した「球体関節人形」作家の家。遺作展の準備を進める学芸員の主人公は、そこで「貉」の怪異と遭遇し、思いがけない「秘事」に直面する……。八雲の原作には無い「人形奇譚」としても読みどころ満載な大力作である。
雪富の短篇集にも収録されている「耳なし芳一」の原話は、八雲怪談の代表作として幾度となく紹介され、「日本昔話」のシリーズなどでアニメ化もされている有名な作品であるが、作家の円城塔による『怪談』の新訳版(KADOKAWA)には意表を突かれた。これは「源氏と平家の戦い? なにそれ?」という日本史に疎い欧米の読者を意識した、達意の翻訳になっていたからだ。
その円城を翻案者に起用した岩崎書店の〈八雲えほん〉シリーズ、第1巻『因果ばなし』(絵は中川学)と第2巻『ミミナシホーイチ』(絵は長田結花)が、まもなく発売される。前者は恐怖とユーモアとエロチシズムの絶妙なミックスに、後者は絵巻物を想起させるような妖美な「和」のテイストに、それぞれ特色があって、新時代の「八雲えほん」の名に恥じない仕上がりだ。
いわゆる「学校の怪談」ものに押されて、しばらく一線を退いていたものの、もともと児童書の世界では、ながらく八雲の『怪談』は不変のスタンダード・ナンバーだった。その久々の復権も夢ではないと感じさせるような八雲リバイバルの行方を、今後も注視してゆきたいと思う。
ここで少々趣きを変えて、下楠昌哉編訳の異色のアンソロジー『雪女・吸血鬼短編小説集』(平凡社ライブラリー)を。
これはタイトルからも察せられるように、来日以前のラフカディオ・ハーン(=小泉八雲)による異色の吸血鬼小説群に、古今の名作吸血鬼譚を加えて成った、まことにユニークな着想のアンソロジーである。
実はハーンは、来日を果たすはるか以前から、妖艶な女性の吸血鬼(その代表例はゴーティエの「クラリモンド」である)が登場する小説に、過剰なまでの関心を寄せており、来日前にも「春の幽霊たち」や「死せるクレオールの幻影」といった掌編を、来日後には「忠五郎の話」という吸血鬼小説の先駆となる作品を、書き残しているのだった。
思えば、あの『ドラキュラ』の作者ブラム・ストーカーもまた、ハーンと同じアイルランド人であった。そうした方面でのハーンの知られざる業績に、アイルランド文学の優れた研究者たる下楠氏が、こうして新たな光を当てたことの意義は大きいと思われる。
最後に、もう1冊のアンソロジーを。
〈文豪とアルケミスト〉とのコラボで話題を呼んでいる田畑書店の〈ポケット・アンソロジー〉シリーズから『幽霊と旅をする』と題された「小泉八雲 短篇アンソロジー」が刊行された。編纂者は……恥ずかしながら、私である。
八雲に関しては、これまで多くの講演をしたり、雑誌特集を編んだりしてきたのだけれど、なぜかアンソロジーを編む機会には恵まれなかった。そのため「得たりや、おう!」という感じで、お引き受けした次第。
編纂にあたっては、「小泉八雲を根っからの日本人だと思っている」御仁が少なくないという嘆かわしい現状を踏まえて、来日以前の作品をメインに据えた構成とした。
米国南部での新聞記者時代の心霊ルポ「さまよえる亡者たち」(牧野陽子訳)や、H・P・ラヴクラフトとの驚くべき共通性を窺わせる「きまぐれ草(抄)」(平井呈一訳)、さらには、かのゾンビ現象にいち早く注目した「わが家の女中(抄)」(遠田勝訳)等々、ハーンはその文学的出発の当初から、呆れるほどに「幻想と怪奇」の人だったのである。そのフランス幻想文学に対する陶酔ぶりと没入度の深さときたら、ひそかに私は、「米国南部の澁澤龍彥!」と呼びならわしているほどである。日本では、ともすると『怪談』のワン・ブック・オーサーと見做されがちな八雲に、こうした知られざる一面があることを、是非この機会に多くの方に知っていただきたいと思う。