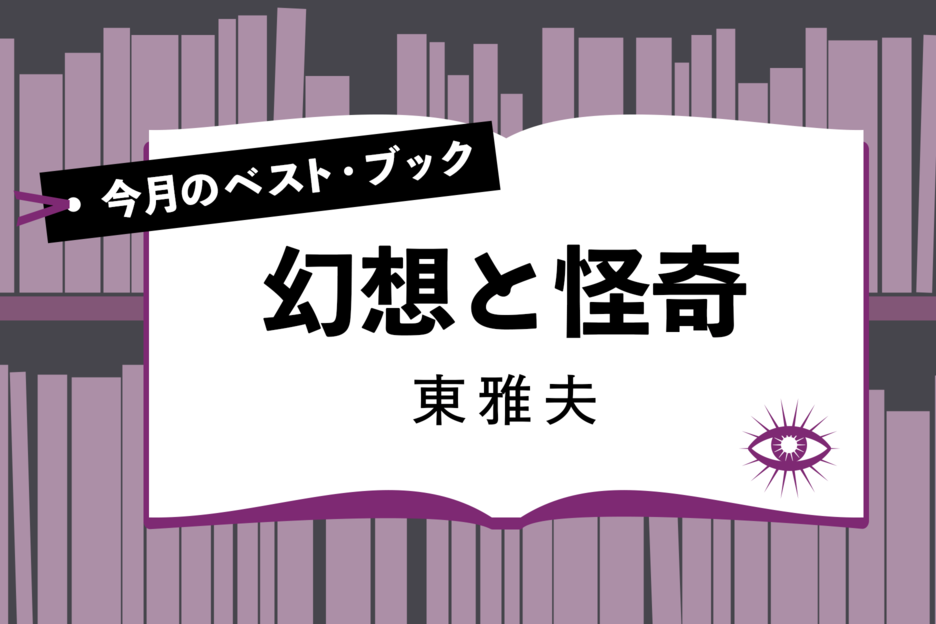今月のベスト・ブック
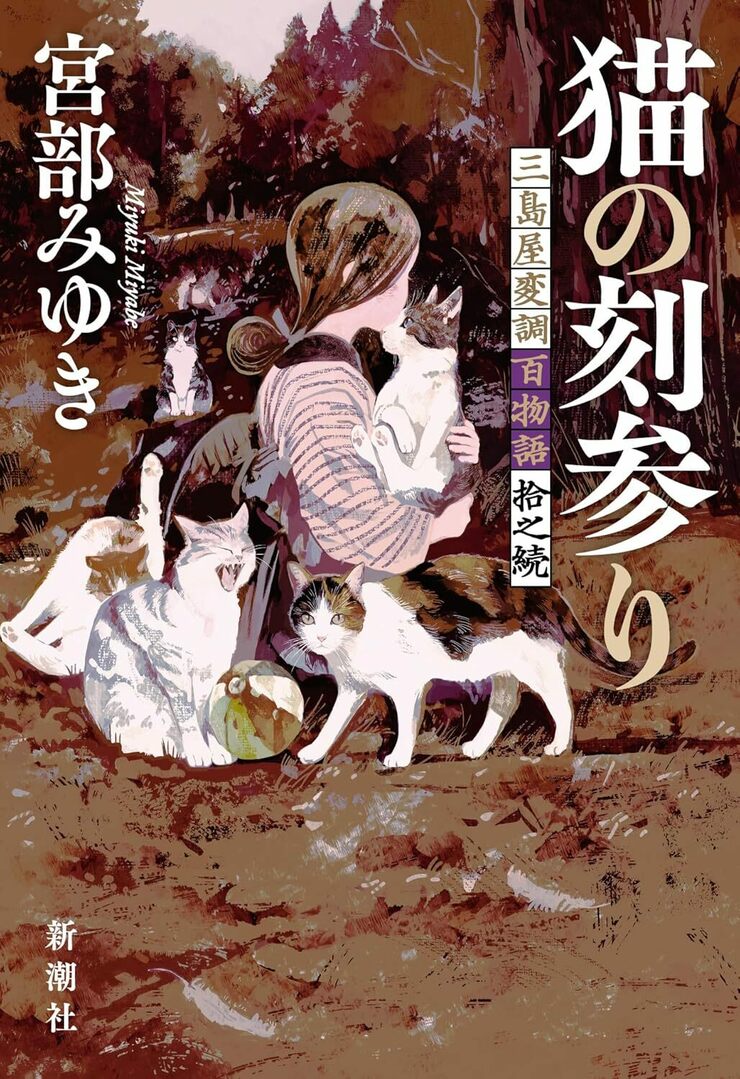
装幀=新潮社装幀室
『猫の刻参り 三島屋変調百物語拾之続』
宮部みゆき 著
新潮社
定価 2,530円(税込)
宮部みゆきが、各種の紙誌を舞台に嬉々として書き継いでいる〈三島屋変調百物語〉の大河連作シリーズも、ハッと気づけば、本書『猫の刻参り』で、10冊目。時の経つのは早いものだ。
区切りの巻に相応しく、本書の巻頭に掲げられているのは、満を持しての「化け猫」小説と相成った。
語って語り捨て、聞いて聞き捨て……話者と聞き手が一対一で「黒白の間」に対峙する三島屋の流儀(それゆえ「変調」と銘打たれているわけだが)に変わりはないが、初代の「聞き役」であった娘「おちか」が他家へ縁づいたため、同家の次男坊・富次郎が「2代目」の聞き手に就任したことは、本シリーズを以前から愛読されている方なら、先刻御承知だろう。
今回は、その富次郎が、絵師になりたいというかねてからの秘めたる願いを、父親に思い切って打ち明けるくだりから、ゆるゆると物語は幕を開ける。
こういう人情話的なくだりを書かせると、作者は実に達者なもので、家業の手伝いを放棄してまで、望みの絵師に弟子入りしたいと思い詰めた若者と、息子の成長ぶりを温かく見守る父親とのやりとりに、読んでいるこちらも、思わず引き込まれてしまった。
しかしながら、これはあくまでも序の口、オードブルである。いよいよ物語の語り手である「元・口入れ屋」の大年増「お文」の登場で、にぎやかに本編へと入ってゆく。
この「お文」という名前に、私は早くも「おや?」と身構えることになった。何故なら、この名は、作者が敬愛する作家・岡本綺堂の代表作〈半七捕物帳〉の記念すべき第1話「お文の魂」の幽霊ヒロインの名前だからだ。実はこの話には「お住の霊」というタイトルの実話と思しい原話があって、こちらは純然たる怪談話なのだ!(「お文の魂」は、いちおうミステリー仕立てになっている)。まあ、綺堂版は「おふみ」、宮部版は「おぶん」で、この点でも一線を画してはいるのだが。
話が横道に逸れたが、「猫の刻参り」は、この「お文」が、母方の祖母にあたる「おぶん」から聞かされたメルヘンめく不思議な話……という体裁になっている。
何度も話に出てくる「猫の刻」とは、真夜中のことで、月の表面に猫の肉球さながらの模様が浮き出て、それと知られるとのこと。普通は人間には見えないが、ごく稀にそれと気づく人もいて、大の猫好きだった「おぶん」も、その1人。彼女は「猫の宮」に参籠して「猫神様の巫女」となる資格を与えられたのだった。
おぶんが巨大な「ねこじゃらし」に隠された猫神様のお宮へ急ぐシーンは、作者の筆も実に活き活きと嬉し気に躍っていて、全編きっての見せ場となっている。まるで「ジブリ」のアニメさながらである。
後半、おぶんを虐げた連中に、恐ろしい「罰」が下されるシーンの悲痛さも凄まじい。自分の「恨み」を晴らす代償として、おぶんは大切なものを犠牲にしなければならないのだった……。このあたり、猫化けの恐怖が迫真の筆致で描かれていて、さすがというほかはない。その裏には、不当に虐げられた「猫」と「女性」たちへの作者の共感と憤りの念が漲っていて、胸を打つ。新たな展開への予感に満ちた大力作であった。ちなみに詳述は避けるが、続く話が河童テーマというのも、綺堂先生の「お照の父」を思わせて「参りました!」と項垂れるしかなかった。
ちなみに綺堂先生といえば、その「おばけずき」の遺徳を顕彰する「こども怪談コンクール」が、養嗣子である岡本経一氏の出身地・岡山で今年も開催される方向で話が進んでいるようで、欣快に堪えない。
これは今は亡き「てのひら怪談」シリーズの流れを汲む800字のミニマム怪談だが、やはりその系譜に立つ『ひとひら怪談』が「森にしずみ 水にすむ」の副題を付して二見書房から公刊されたのも、大いに心強い出来事だった(薄禍企画・編著)。
どこか宮沢賢治の恐怖童話めく「巡回バス」の岩城裕明、二重写しの恐怖が鮮やかな「ねじれ森」の澤村伊智、呪いの五寸釘の残響のみが木霊する「今はもういない」の織守きょうや、タブー侵犯の恐怖が身に迫る「轢いた」の浅倉秋成、個性的な副題に最も忠実な「井戸の底」の篠たまき……現代ホラーの精鋭たちによって紡ぎ出される「ひとひら」の恐怖、不意打ちの恐ろしさを、これは間違いなく、じっくり堪能できる1冊である。
月そのものをテーマとする、まことに浮世離れした西崎憲編のアンソロジー〈12か月の本〉が、このほど国書刊行会から発刊された。第1回発売は、『4月の本』から『6月の本』までの3冊。
いきなり1冊目を開くと、巻頭が太宰治の「春昼」(よく知られた泉鏡花の、ではなくて!)ではないか。11日は、我が誕生日だ。
藪から棒に「四月十一日。」で始まる短章である。妻と妹を連れて、近くの「武田神社」へ満開の桜を見物に赴いた作者。
「サクラの満開の日と、生れた日と、こんなにピッタリ合うなんて、なんだか、怪しい。話がうますぎると思う」と思案する作者。
桜を見ると、蛙の卵を想起すると語る妻。 この他愛なさが心地よい。