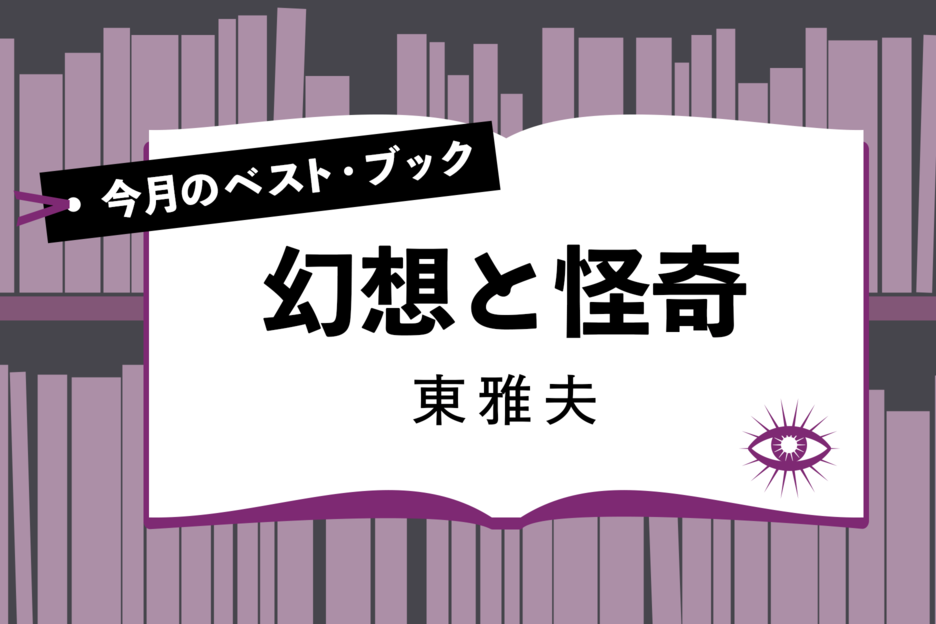今月のベスト・ブック

カバーデザイン=柳川貴代
『ドイツロマン派怪奇幻想傑作集』
ホフマン、ティーク他 著
遠山明子 編訳
創元推理文庫
定価 1,320円(税込)
正直に白状しておくと、私が生まれて初めて、「おお、これぞ、本格的なゴシック・ロマンスだ!」と感激した作品は、斯界の始祖たるオトラントでもヴァテックでもなく、実のところ、E・T・A・ホフマンの『悪魔の美酒』(ここは是非とも訳題を明記しておこう!)であった。緑の造本が印象的だった河出書房の世界文学全集の1巻だ。
当時はまだ本場英国のゴシック小説が訳出される前の時期であり、海外文学の世界で当時すでに「文豪」の仲間入りをしていたホフマンの長篇代表作に白羽の矢が立ったのも、まあ無理からぬところと肯かれる。平井呈一や生田耕作の名訳群が晴れて世に出るのは、それよりやや後年のことに属するからだ(当時は『オトラント城奇譚』という元祖ゴシックの存在は、名のみ高くして実物にお目にかかることのできない「高嶺の華」だったのである。何種類もの訳書が出ている現在では、信じられないかも知れないが……。新人物往来社の〈怪奇幻想の文学〉シリーズで、オトラントの本邦初訳が出たときなど、かなりの大騒ぎだったと記憶する)。
さて、かつては、ドイツ系の怪奇小説といえば、種村季弘さんや池内紀さん、前川道介さん(雑誌「幻想文学」でも大変お世話になった)らの独擅場だったものだが、時移り世相が変わり、このほど創元推理文庫から久々に刊行された『ドイツロマン派怪奇幻想傑作集』では、編訳者に(小生とほぼ同年配の)遠山明子さんが起用されている。
ティークの「金髪のエックベルト」に始まり、ホフマンの「砂男」に至る構成は堂々たる王道で、間にフケー、ハウフ、アルニムの代表作を挟んでいる点もまことに手堅く、本書1巻をもって、ドイツ・ロマン派の本領を窺い知ることは、十二分に可能だろう。
ホフマンはさておき、ティークに関しては「金髪~」も「ルーネンベルク」も、私は今まで子供向けの本でしか読んだことがなかったので、原文に忠実な遠山訳に接して、初めてその真価に触れた気がした。
地の文の合間合間に、いかにもロマンチックな詩の文章が挿入されるのは、ロマン派小説の常套だが、ティークの場合、大自然の可憐さを湛えつつも、そのあわいを生きる人々の残酷な運命をも予感させる点で、一頭他に先んじている感があった。
親しい友人でもあったホフマン作品との類縁性を感じさせるコンテッサの2篇(「死の天使」「宝探し」)は、本アンソロジーで唯一といってもよい未紹介作家だが、本家ホフマンを批判しつつも、「おまえ……同じ穴のムジナだろう?」と思わずツッコミたくなるような愉快な作風で、異彩を放っていた。
先ほど名前を出した種村季弘の知られざる拾遺集というべき『種村季弘・異端断片集 綺想の美術廻廊』(芸術新聞社)が、種村文献蒐集の「鬼」というべき齋藤靖朗の監修により、このほど上梓された。種村氏が亡くなったのは2004年のことなので、実に没後20年を経ての刊行となる。表題にもあるとおり、断簡に近いような文章にも、いかにも筆者らしい閃きが潜められており、独特の「コク」がある「タネムラ節」を、久方ぶりに堪能することができた。20年後のいま読んでも、古臭い感じがまったくしないところが、実に素晴らしい。現在の若いおばけずき画家たちに何を感じ取ったか、御本人に聴きたいところだが、それが最早かなわないことだけが、唯一物足りない。嗚呼……。
最後は、このところ、何故かオカルト映画付いている加門七海(ハリウッドで映画化されると話題の旧作長篇『203号室』とか、佐藤嗣麻子監督による『陰陽師0』の呪術監修担当とか! 等々……)の書き下ろし新刊ホラー『黒爪の獣』(光文社文庫)。タイトルの「黒爪」とは、もろもろの「穢れ」を宿した「負」の存在全般を示唆する言葉と思しい。主人公の1人である暗い美青年の身にまとわりつく、仄暗い「穢れ」の象徴でもあるのだけれど。
舞台は、史上空前の「眠らない町」歌舞伎町を有する現代の新宿。日本中の「穢れ」を詰め込んだかの如き、この殺伐とした街で、日々刻々と拡がる異常な事態。神社の拝殿で連続する胎児の無残な遺死体……次の殺害事件は、どこで!?
静穏な暮らしを切望し、新宿の高級ビルに隠れ住む「占い師」の美しい兄妹と、ひょんなことから知り合った硬派の刑事。妹によって喝破される両者の宿命は、やがて絡まり合い、未曾有のオカルト事件へと……。
作品の中盤で、兄妹の兄・悠希が、刑事の魚名に漏らす告白──「どの世界を見て、何を感じるか。人間なんて色々知っているつもりになっても、結局は自分の視界の届く範囲を真実、現実として、その中で物事を判断しているだけだろう?」は、意外に作者自身のホンネに近いのかも知れない。
物語は中盤以降、胎児連続殺害遺棄の真犯人(その正体は「陰陽師気取り」の一種の愉快犯/このあたりにも、作者の当節における「呪物」流行な風潮への厳しい批判的まなざしが看取されるのだが……)が突き止められるあたりから急転直下、晴れて解決へと向かうのだが。事件そのものはやや小ぶりだが、「新宿」という街の無気味な魔性が、強く印象に残る作品ではある。私自身は、やたらと歩きにくくて、嫌いな街だが(笑)。