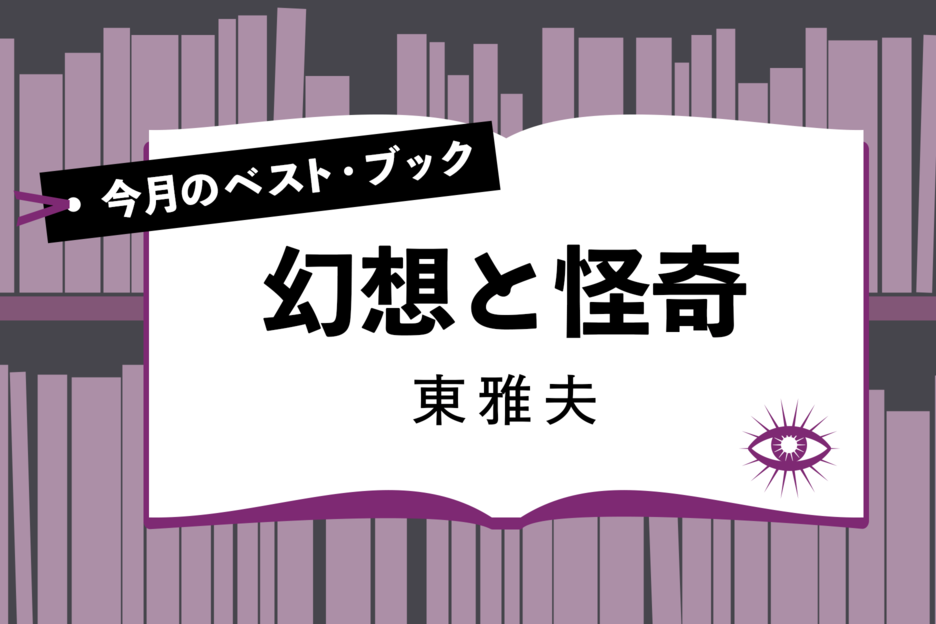今月のベスト・ブック
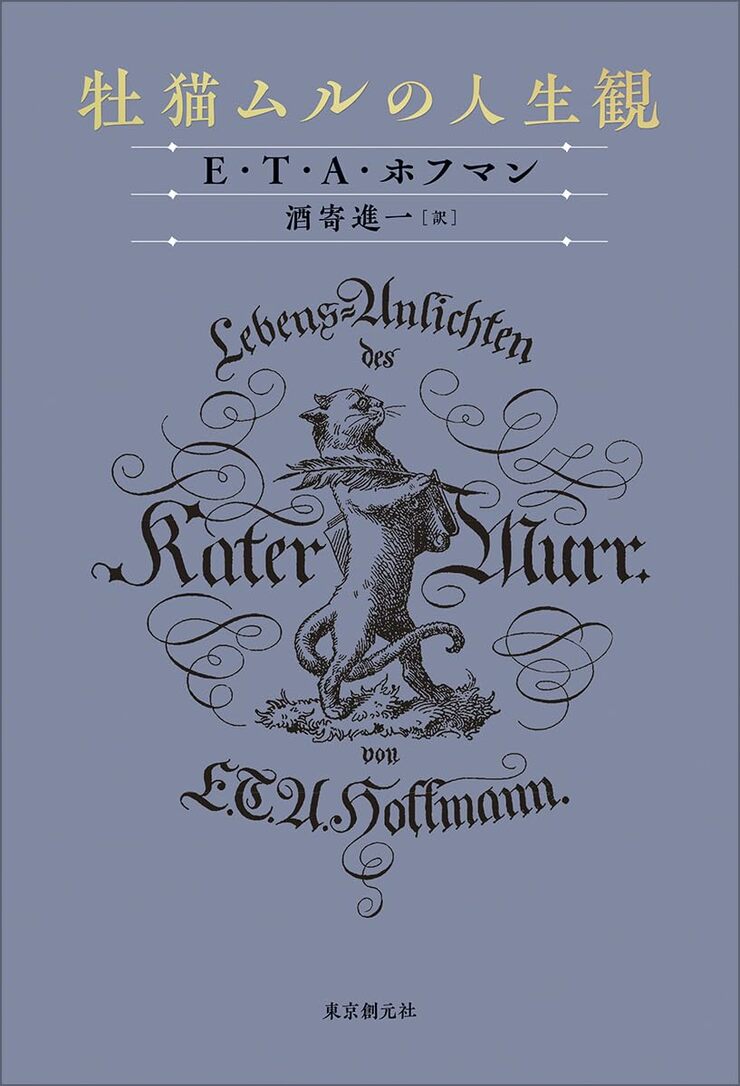
『牡猫ムルの人生観』
E・T・A・ホフマン 著
酒寄進一 訳
東京創元社
定価 3,960円(税込)
エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン……このページをご覧の方なら先刻御存知の向きも多いだろうが、「お化けのホフマン」の通称でも知られる、ドイツ・ロマン派の文豪である。その通称は、彼が好んで悪魔や妖精や幽霊や、果ては本物そっくりの機械人形などといった異形のものどもを愛で、作中に登場させたことに由来している。
昼は謹厳な法律家、夜は放恣な妖怪物語作家という、2つの異なる顔を器用に使い分けたことでも知られている(その極端な二重生活が、本来「詩人」体質であった彼の死期を早めたとする説もあるのだが……)。
日本でも戦前からホフマンの名前はよく知られており、その作風の類似から、わが泉鏡花の文学と比較されたりもしてきた(わが国では一部の文学通を除いて、いわゆる「ゴシック文学」の移入紹介が極端に遅れたため、戦前は「お化けの」と形容される有名作家が、ドイツのホフマンくらいしか知られていなかった、といういささか情けない裏事情もあるのだが……)。
もうひとつ、日本文学との関連で忘れることができないのはホフマンが、文豪・夏目漱石の出世作にして誰でも知ってる代表作『吾輩は猫である』に重大な影響を及ぼした(かも知れない)とされる、奇態奇妙な大部な長篇小説『牡猫ムルの人生観』を手がけているという点だ。
漱石自身はホフマンの先行作を、読んだとも読まないとも微妙な形で書いているが、当時のホフマンは実際に猫を飼っていて、その細やかな「猫愛」は、本篇にも横溢しており、それがまた重要な読みどころとなっている。漱石もまた猫を大いに愛していたことは、最近、新潮社から出た宇津木健太郎の時を隔てた続篇『猫と罰』にも明らかだろう。
その文学史的名作である『牡猫ムル……』が、このほどドイツ文学者・酒寄進一氏(おや、小生と同い年ではないか!)の手で新たに全訳された。すでに既訳もあるとはいえ、近年は入手しづらくなっていたので、この新訳版の登場は大いに歓迎したい。しかも、さらに嬉しいことには、「訳者あとがき」の最後に『ムル……』の序言を模して、訳者は次のように記しているのだ!「──かの賢く、知性を持ち、怪奇をよくし、奇想天外だったホフマンは苦悩に満ちた生涯の半ばで病死したものの(引用者註『ムル……』も全3巻の予定が、作者急逝のため惜しいかな2巻までで中断している)、その作品は不滅である。機会があれば、ホフマンの手になる小説のさらなる翻訳に取り組みたいと切に願うものである。乞うご期待!」
酒寄氏と創元社の健闘を切に祈りたい。
ところで泉鏡花といえば、いわゆる「深川もの」の第1作となる短篇小説で、後に挿絵画家たちの作品に小村雪岱が彩色を施し、伝説の豪華本として再刊もされた『繪本辰巳巷談 』が、このほどデザイナー柳川貴代による新たな判型と装幀で復刊されるはこびとなった。出版業界初の試みとなる、クラウドファンディングによる豪華本出版である。版元は初刊時と同じ春陽堂書店(つくづく息の長い版元であることよ!)。ちなみに本書の解説は私が、雪岱ほか挿絵画家たちの解説は鏡花研究会の新鋭・富永真樹が担当している。
本作「辰巳巷談」は、洲崎遊郭の元遊女に惹かれる美青年を中心に、破滅的な恋と人情の高まりを描いた作品だが、鏡花はその後も一連の〈深川もの〉の集大成というべき長篇「芍薬の歌」に至るまで、一貫して深川の地に関心と愛着の念を抱いていたことが察せられる。何故そこまで、鏡花は深川に惹かれたのか? 若き日、先輩格の広津柳浪や小栗風葉、柳川春葉ら同輩たちと洲崎界隈に遊んだ想い出の地であることも重要だが、それ以上に鏡花自身が水辺の幻妖を好んで描く作家であることに起因するのではないかと、私は以前から思っている。仄暗い死への誘惑と母胎回帰の甘美な憧憬を、もろともに感じさせる幻想的な〈水〉の描写は、鏡花文学の重要な特質となっているからである。江戸の面影を今に残し、運河特有の昏い水路が縦横にはしる「水の深川」の光景に接して、若き日の鏡花も魂が震えるような感慨をもよおしたことは想像に難くない。なお、本書の副読本として、先年私が編纂した『あやかしの深川』を御参照いただけると幸いである。
最後に1冊、異色の民俗探訪書を紹介しておこう。井上真史『現代「ますように」考 こわくてかわいい日本の民間信仰』(淡交社)である。これは一部の物好きが知っているかも知れない同人誌「現代〈ますように〉考」をもとに1冊にまとめられた、真正の奇書。副題にあるとおり「日本の民間信仰」に関する本、ではあるのだが、そこに「こわくてかわいい」という言葉が付されている点に注意が必要。「怖さ」と「可愛さ」が同居する民間信仰って……そんなの、あるの!? と思う方と、ああ、分かる分かる「コワカワ」なあの感覚! と言う方。不幸にして私は、本書でも触れられている某所や某々所に取材で出没したことがあるので(あまつさえ本書の第三章に登場する京都・瑞泉寺では、秀次公の首塚の上で演じたことも!)遺憾ながら後者に属する。堤邦彦氏の序文によると、著者は「神隠し」に遭いかけた、稀有なる体験の持ち主とか。です・ます調で書かれたこの本自体が、何だか妙に怖ろしいのです……。