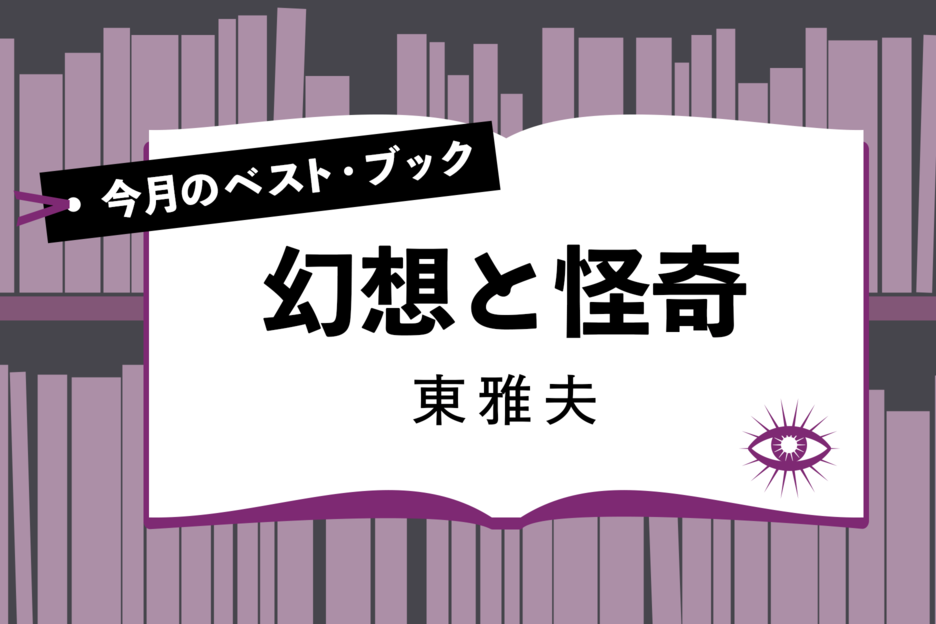今月のベスト・ブック

『吸血鬼ヴァーニー或いは血の饗宴 第一巻』
J・M・ライマー&T・P・プレスト 著
三浦玲子&森沢くみ子 訳
国書刊行会
定価2,750円(税込)
この欄で紹介する書物は、基本的に、全国どこの書店でも購入したり、注文して取り寄せたりできる本に限られている。要するに、市販品ということだ。従って、いわゆる「同人本」は残念ながら対象外なのだが、今回ばかりは例外的な措置を認めていただこう。
その書物の名は……三橋一夫著『新ふしぎなふしぎな物語』、版元は書肆盛林堂(杉並区西荻南2の23の12 盛林堂書房内)である。ミステリー・ファンの間では、よく知られた古書店が、副業(趣味?)で始めた個人出版社だが、商業出版では企画が通らないようなマニアックな書目を、矢継ぎ早に少部数刊行して、注目を集めて久しい。
とりわけ本書は戦後、特異なファンタジー作品を体系的に発表して、終刊間際の「新青年」誌を支え、識者の注目を集めた作家・三橋一夫が、友人(というか横須賀線の「呑み仲間」)である吉田健一のもとに託したままになっていた未発表原稿が、横浜の神奈川近代文学館で先年開かれた吉田健一展で紹介され、それに着目したミステリー研究家の森英俊の編纂で、史上初めて書物の形で刊行されたという、曰く付きの1冊なのである。
三橋の代表作は『ふしぎなふしぎな物語』と題する4巻本の連作短篇集として、かつて春陽文庫から刊行されたことがあるので、本書の題名を見て、ピンときた向きもあることだろう。まさに本書は、『ふしぎな……』の後を継ぐべき、すでに故人である作者にとって最後の作品集となったわけだ。
収録された作品は、全10篇──どれをとっても、あの懐かしい三橋一夫ならではの味わい、怪奇味と幻想味が、ほどよくブレンドされて、ほろ苦いペーソスを醸し出す、絶妙の仕上がりである。
愛娘の結婚に悲嘆する紳士が、寂しさのあまり1羽の山鳩に化身し、妻もその後を追う「山鳩」、新妻に無能ぶりをなじられ、新居からも追い出された男が、幽霊屋敷の住人と意気投合して新生活を始めるという珍無類な着想の「再婚通知」(吉田健一の短篇集『怪奇な話』を彷彿せしめるのは、果たして偶然だろうか?)、天狗小僧・寅吉の物語を、講談調で再話してみせた「こうだん風砲」、同じく人間界に入り込んだ天狗や河童が巻き起こす奇妙な騒動の物語「峠から来た客」「水居の人」、万事に不器用で仕事を喪い困惑する男と、献身的な愛妻との、民話風の哀感あふれる物語「鈴石」等々、どれも一読、心の琴線に触れる作品群だ。
今回あらためて感じたのは、水木しげるの妖怪漫画(奇しくもほぼ同時代!)との意外な共通点だ。天狗や河童や幽霊が、人間に交じって登場するばかりでなく、作品全体を覆う独特のペーソスやイロニーに共通した「匂い」が感じられたのである。三橋の描く愛すべき「ダメ人間」たちと水木翁のそれとの、何とまあ絶妙な同臭感ただようことか!
このほど仕切り直しで、国書刊行会から続行されることになったシリーズ〈奇想天外の本棚〉。その第1弾となるJ・M・ライマー&T・P・プレストの伝説の大長篇『吸血鬼ヴァーニー 或いは血の饗宴』(三浦玲子&森沢くみ子訳)の記念すべき第1巻が、ついに刊行のはこびとなった!
その冒頭の1章が「恐怖の来訪者」の訳題で初紹介されてこのかた(本邦初訳は、昭和46年刊の月刊ペン社版『アンソロジー 恐怖と幻想 第1巻』だった)、何度か全訳の噂も出たものの、その膨大さゆえか遂に実現することなく、とうとう半世紀……ようやくにして、待ち焦がれた続きの部分を読むことができた、感慨たるや!(真正のリアルタイム読者である私なんか、マジで50年間、待ったわけよ!)なるほどこれは当時の英国で全盛を極めた〈ペニー・ドレッドフル〉(=大衆向けの血みどろ残酷読物)の、好くも悪しくも一典型といえよう。意外に展開はスピーディーで、吸血鬼の生贄たる良家の娘フローラと、彼女を守る兄や恋人たちと、因縁を秘めた老獪な吸血鬼ヴァーニーとの、緊迫の攻防戦が、テンポよく描かれてゆく。
ただ、ひとつ気がかりなのは、本書が全何巻で完結するのか、どこにも記されていないことなのだが……まあ、それはともかく、つつがなきスピーディーな邦訳刊行を期待したいと思う次第。長丁場だが、頑張って!
最後は、相変わらず快調なペースで新作を世に問い続けている澤村伊智の最新刊『さえづちの眼』(角川ホラー文庫)。なんと〈比嘉姉妹〉シリーズ初の中篇集で、「母と」「あの日の光は今も」そして表題作の3篇から成る。短からず長すぎない〈中篇〉というジャンルは、ホラーという分野には最もお誂え向きの長さではないかと思うのだが、もっぱら掲載媒体の都合で、日本ではなかなか定着しづらい憾みがある。
本書冒頭の「母と」は、どこにも行き場のない〈不良〉少年少女の苛立ちや葛藤を、痛烈に、ヒリヒリと描き出して、この長さの美点をよく顕わしていると思う。
特に瞠目させられるのは、得体の知れない怪異の描き方。こどもたちを命がけで保護しようとする〈おっちゃん〉と〈悪しきモノ〉との対比、それを目撃する主人公の少年の恐怖と緊張……いやはや、恐れ入りました、という感じ。後半の意外な展開も、上手い! 蛇神の祟りを描く表題作も、伝統的な蛇の恐怖描写を踏まえていて思わず惹きこまれる。