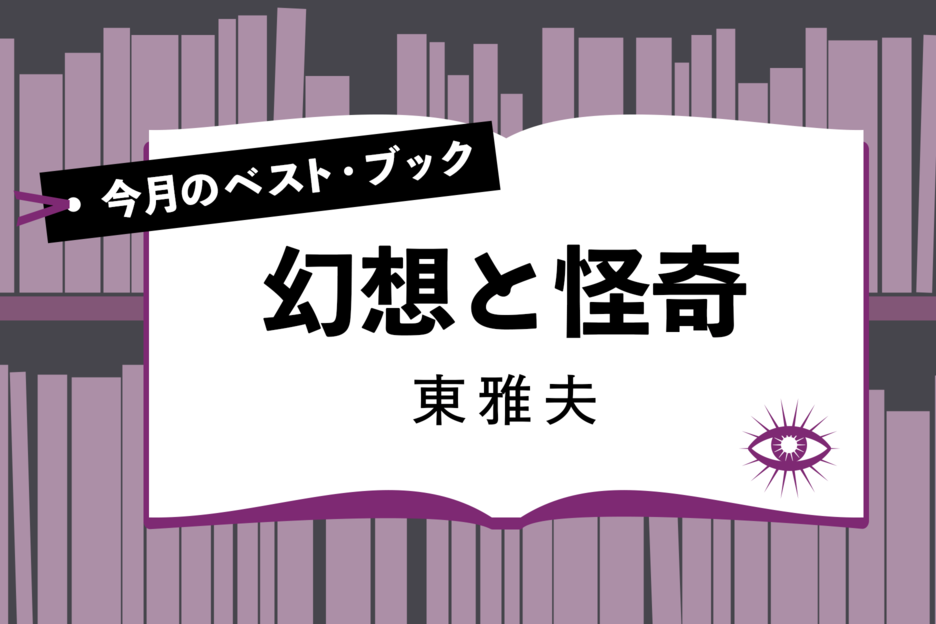今月のベスト・ブック

装画=玉川麻衣
『蒼い夜の狼たち』
寺崎美紅・作/玉川麻衣・絵
たばやま観光推進機構
定価2,200円(税込)
妖怪やら神霊やら眼に視えない存在たちを描かせては、当代に並ぶものなき若き名手のひとり玉川麻衣が描き出す、霊なる狼たちの図像に、國學院出身の学芸員・寺崎美紅が物語を付けた、異色の絵本『蒼い夜の狼たち』が、このほど刊行された。
舞台となるのは〈山梨県の北の果て〉の丹波山村の〈さらに果て〉にある山奥の七ツ石神社。住民の高齢化によって、参詣する人も少なくなった神社は崩れかけ、お社を護る狛犬ならぬ一対の狛狼たちも、いまや半壊の有様……これ、実は、紛れもない実話である。
狼とひょんな縁で結ばれた著者の寺崎氏は大学卒業後、単身「丹波山村」に移り住み、学芸員として七ツ石神社の再建に取り組んできた。やはり山歩きが趣味という玉川氏と知り合い、彼女が憑かれたように描く神狼像を柱に据えた丹波山村PRを展開、無事に神社再建という大事業を成功させ、次に取り組んだのが、この絵本の制作・刊行だった。
物語は、狛狼の化身たる一対の神狼が、老齢で眼を病んだ村人を救うため、大切にしていた〈月のかけら〉を用いてしまい、そのため一匹は霊力を失い、姿も薄れてしまう。
あわや七ツ石の信仰もこれまでか……と思われたそのとき、幽けきSOSの遠吠えを聴き取った霊峯・三峯山の狼たちが決起して、さらに広い世界へ向けて、吠え立てる!
「七ツ石の狼を想ってくれているもの、どうか応えてください」
出たよ、三峯山! 自慢じゃないが、書評子は、生まれてこのかた、三峯神社の氏子として、毎年参籠を欠かさない(詳しくは、東雅夫&加門七海編著『響鬼探究』国書刊行会を参照)。神狼の皆さま方とも、毎年挨拶を交わす仲なのだ(笑)。幻想文学アンソロジストなどという稼業を続けているのも、思い返せば、幼少期の三峯山での不思議体験に起因すると云っても、過言ではない。
ちなみに寺崎さんの神狼体験も、三峯神社の奥宮参拝がきっかけだったそうで、物語に並々ならぬリアリティが感じられるのも、それ故だろう。しかしリアルというならば、何と云っても玉川さんの圧倒的な画力──山中を躍動する狼たちと、かれらの切なる遠吠えと、降りそそぐ流星群と──が、本書のすべてを支えているといってよかろう。まさに神がかった魅力を湛えた一巻である。
シャーリイ・ジャクスンといえば、『丘の屋敷』や『ずっとお城で暮らしてる』など、幽霊屋敷テーマの傑作を遺した米国の女性作家として、愛好されるホラー・ファンも多いだろう。そんな彼女の長篇第一作が、ようやくにして邦訳された。それが『壁の向こうへ続く道』(渡辺庸子訳/文遊社)である。
本書には、後年の作品に見られるような、超自然的要素は稀薄である。いや、ほぼ皆無といってよいかも知れない(最終章に至って不可解な惨劇は起こるが、それも表面的にはいたって現実的なものだ……)。
本書は、サンフランシスコの郊外に静かに佇む造成地の住民たちによる群像劇で(ちょうど1940年代、戦時中の出来事だ)、多くの家族の日常生活における、些細なあれやこれやが、ひたひたと描き出されているのだが、私は本書に接して、何故あのモダンホラーの帝王スティーヴン・キングが、ジャクスン作品の熱心な支持者であったのかが、分かったように思った。
たとえば、こんな一節──「つねに物事の真実を把握したいと切望する作家にとって、ジャクスンの文章は、まちがいなくあこがれの対象たりうるに違いない。いくぶん過多とも思える言葉の奔流。部分部分もさることながら、全体としてながめてこそ生き生きしてくる言葉の群れ。このような段落についていちいち分析的にあげつらうのは、姑息以外の何ものでもあるまい」(スティーヴン・キング『死の舞踏』安野玲訳)
思うに、キング流ホラーの一大特色でもある群像劇の呼吸は、余人ならぬジャクスンのこうした初期作品から学んだものではないのか……そんなことを、つらつら考えてしまうのだ。戦後ホラーの里程標となった大作家の原風景ここにあり、ともいうべき作品である。
ところで、日本でスティーヴン・キング作品といえば、すぐさま連想されるのが、その表紙画を長らく描き続けている画家・藤田新策の名前だろう。このほど上梓された『STORIES 藤田新策作品集』(玄光社)は、キングや宮部みゆきら多くの著者たちの作品と向き合い、〈僕としては極力読み込んでから物語世界を表現するよう心がけています。また、じっくり読むことで自分では思いつかないようなモチーフやシチュエーションに出会える面白さもあります〉(本書「まえがき」より)と語る著者の真面目を、存分に堪能できる自選代表作品集となっている。
冒頭から全体の半ば近くを占めるキング、クーンツ、マキャモンらモダンホラーの人気作家たちの作品群は、やはり圧巻。個人的には、繁茂する植物群の妖しさが印象的な『トミーノッカーズ』や『ドロレス・クレイボーン』に惹かれる。こうして、その変遷ぶりを眺めていると私も、著者のいう〈ここ30年のモダン・ホラーの歴史を眺めているよう〉な心地に陥って、やたらと懐かしかった。
また巻末に収められた「ゲーム・児童書・絵本」の部では、知られざる魅力の一端に触れることができて、新鮮な驚きを覚えた。