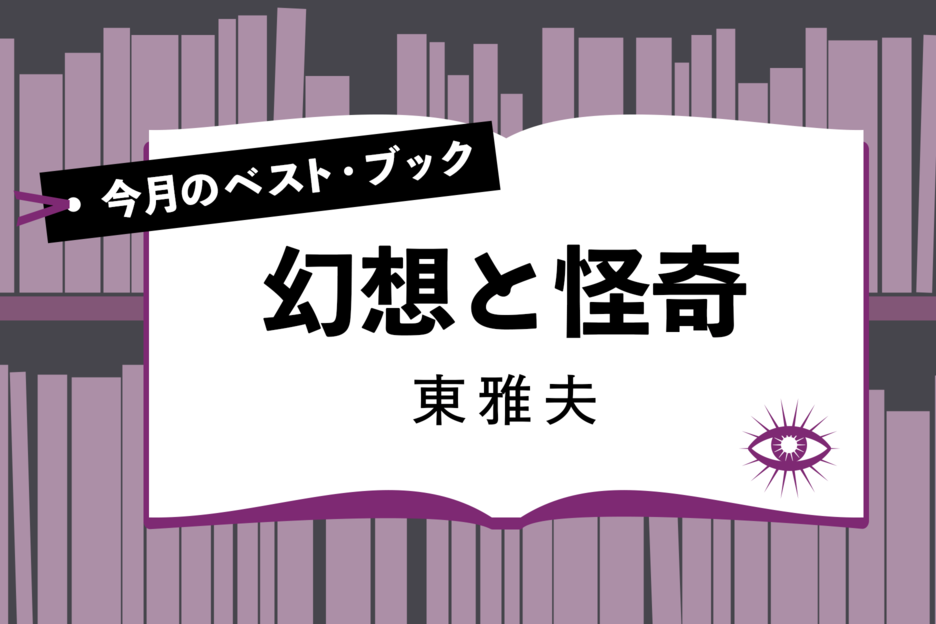今月のベスト・ブック

『虚魚』
新名 智 著
KADOKAWA
定価1,815円(税込)
漫画家の近藤ようこさんには、以前「幽」でオリジナル異界漫画の連載をお願いするなど、何かとお世話になってきた。田中貢太郎や折口信夫らの難しい文豪怪談のコミカライズにも、果敢に挑戦されていることは、御存じの向きも多かろう。
そんな近藤さんが、澁澤龍彦の遺作となった長篇遍歴ファンタジー『高丘親王航海記』のコミカライズに意欲を示されていると伺ったのは、かれこれ3年前の夏ごろだったろうか。掲載誌「コミックビーム」の版元であるエンターブレインさんとは、同じ角川つながりで、アンソロジー『ドラコニアの夢』などを出している小生に、澁澤龍子夫人との仲介役として白羽の矢が立った。かくして初夏の1日、通い慣れた北鎌倉の道を、白亜の澁澤邸へ御案内することになった次第。
近藤さんの画風と『高丘親王』の世界には明らかな親和性があって、そのクオリティを疑う必要はカケラもなかったが、巻が進むにつれ、その妖しくも美しい世界観は、いやましに高まり、この最終巻(KADOKAWA)でひとつの絶巓を極めた感が深い。静かに、たおやかに、死へと赴く親王を描いて、かくも典雅な……現世と異界が混淆された摩訶不思議な世界を描かせては、当代に並ぶものなき作者の真骨頂が、ここに示されたと感ずる。長丁場、本当にお疲れさまでした!
『虚魚』(KADOKAWA)と書いて〈そらざかな〉と読む。釣り人が自慢するため、釣果を実際より大きく言うこと、またその実在しない魚のこと──と、本書の冒頭には註記されている。これは怪談実話界隈に棲息する人々にも当て嵌まりそうな格言で面白い。
「いやあ、こないだ凄い怖い話を聞いちゃってサア……」と言われて、耳そばだてて聞くと、たいした話ではなかった、という経験をされた実話好きは、少なくあるまい。特に、いわゆるコンテスト形式で話に優劣をくだす傾向が強まってから、そういう弊害が増えた気がするのは……気のせいかしらん!?
さて、本書は〈人を殺せる〉くらい怖ろしい怪談を求める実話好きの主人公と、呪いか祟りで死ぬことを願っている友人とが、ひょんなことから〈虚魚〉にまつわる怪談に触れて、その淵源を求め、実際に河川を遡上するという物語である。探索行の果て、彼女たちを最後に待ち受けるモノとは……。
まことにリアリティのある設定で、横溝正史ミステリ&ホラー大賞選考委員のひとりである綾辻行人氏が〈着地の形も非常にきれいで、ラストの何ページかで僕は感動すら覚えた〉と賞讃しているのも、肯かれる。堂々たる大賞受賞作といってよかろう。
まあ、これは、私自身がかつて「ムー」や「幽」の雑誌企画で、似たような探訪企画を試みていたということも、なにがしか影響している可能性はあろう。実際の探訪では、そうそう都合良く怪異が起きることはないのだが、それはまあフィクションだから(笑)。というか本書においても、途中で肩すかしを食わされかねない事態に陥るくだりがあって、おお、よく分かっておるなあ……と感心させられたものだ。
作者は90年代生まれの新進気鋭、とのことだが、早くも次回作が愉しみである。
K・R・アレグザンダーの長篇『湖の中のレイチェル』(金原瑞人+小松かほ訳/小学館)は、ジュブナイル向けのモダンホラー。乱暴者の主人公サマンサは、唯一の親友で内向的なレイチェルを、ふとしたことから湖に突き落としてしまい……しかしレイチェルは翌日、何事もなかったかのように、学校へやってくる。したしたと水を滴らせながら。全篇にあふれる水への恐怖。異形のものと化した親友に怯えるサマンサは、周囲の人々に救いを求めることもできず、やがて……。
実は本書のあらすじを見て、オヤと思った作品があった。宇佐美まことのデビュー作にして、第1回「幽」怪談文学賞の受賞作「るんびにの子供」である。こちらもまた水妖としての妖しい少女にまつわる怖ろしい物語なのだが、やはり、というべきか、その表出方法には、洋の東西の違いを感じざるをえなかった。それが〈水〉に対する日本人と欧米人の感性の差違なのか否かは、よく分からないのだけれども……。
最後は珍しくノンフィクションを。双葉社から刊行された蒲池明弘『聖地の条件』は、元新聞記者の著者が、神社の淵源をたどって出雲大社をはじめとする〈国つ神〉系の神社群に注目。それらが黒曜石や翡翠といった鉱物資源の産出・流通と不即不離の関係を有することを手がかりに、日本全国の主要な神域を探訪し、いわば〈神社以前の神社〉の幻影を執拗に追い求めるという、まことに刺戟的なルポルタージュの書である。
ちなみに筆者は現在、コロナ禍を逃れて、縁故ある金沢の事務所で仕事をしているのだが、我が父祖の地である石川県小松市も、古来重要な碧玉の産地であったことを、本書によって教えられた。日本列島の形成史と重なり合うかのような、旧石器時代にまで遡る本書の悠久たるタイムスパンが、決して他人事ではないと示唆されたような心地がして、印象に残った。〈学術書ではないことに開き直って、神々の道を暴走しすぎてしまったかも〉と著者は「あとがき」に記しているが、半可通たる読者としては、そうした暴走もまた愉しからずや、の心境であった。