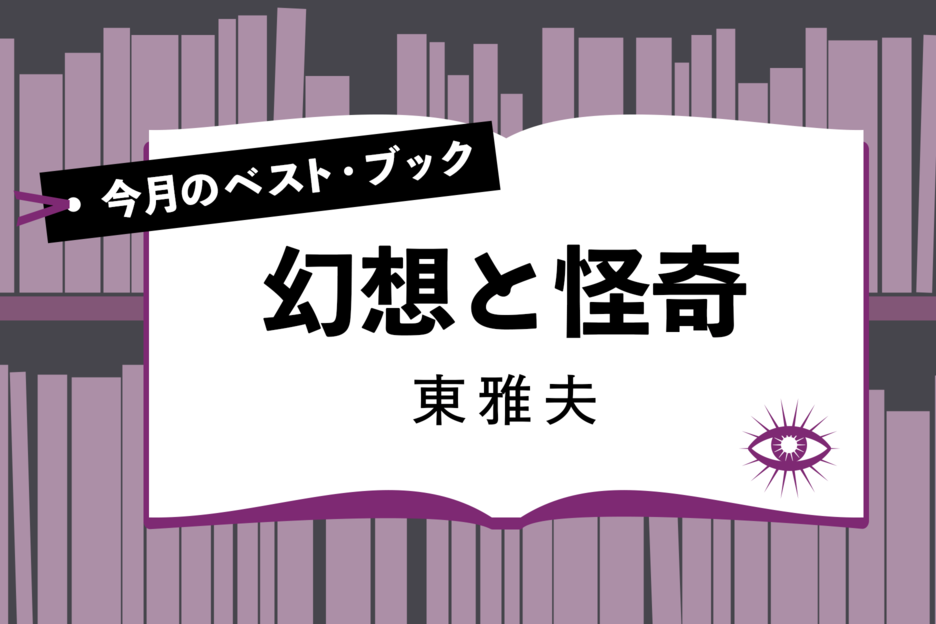今月のベスト・ブック
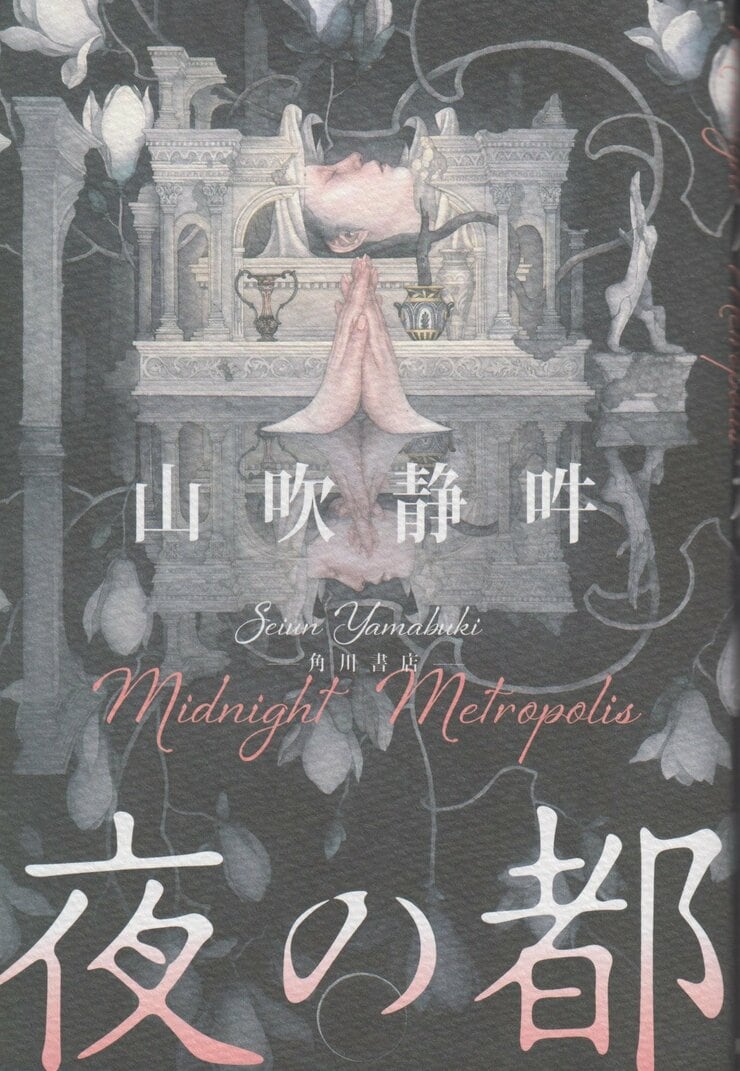
装画=朱華「眠る島」
『夜の都』
山吹静吽・著
KADOKAWA
定価1,870円(税込)
海外の幻想文学に関心を寄せていらっしゃる方々であれば、〈ピラネージ〉という特徴ある名前を聞いたら、奇妙な廃墟や途方もない牢獄の光景を、すぐさま想起されるのではないか、あるいは、そこから派生して(本書の装丁に抜かりなく採用されている)世界の終わりの光景を描いた画家モンス・デジデリオをも連想されるのでは……などと、私のような澁澤龍彦&山尾悠子フリークの年寄りは思ってしまうのだが、最近の若者は、そこまでの思い入れはないのかしらん。
本書『ピラネージ』(原島文世訳/東京創元社)に付された簡潔な訳者あとがきには、〈この名はローマの古代遺跡を描いた版画で知られる18世紀イタリアの版画家・建築家〉であるピラネージに由来する……と記されるのみだった。
3巻本のデビュー大冊『ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレル』(ヴィレッジブックス)で一躍脚光を浴びた新鋭スザンナ・クラークが、なんと16年ぶりに発表した2作目の長篇である本書は、しかしながら、頁をひらくと同時に、まさに〈ピラネージ〉の絵画世界を髣髴させるような、驚異的な幻想空間へと読者を拉し去る。古代地中海風の彫刻によって埋め尽くされ、絶えず潮の干満によって洗われる、途方もない規模の、奇妙な館……そこに暮らす生きた人間は、たったの2名──その名もピラネージと呼ばれる青年と、「もうひとり」と呼ばれる謎めいた年長の人物。
あたかも館そのものが1個の閉じられた世界であるかのような物語の構造は、なるほど作者が大きな影響をうけたというアルゼンチンの幻視者ホルヘ・ルイス・ボルヘスや『ナルニア国ものがたり』のC・S・ルイスを想起させるが、一方で、われわれ日本の読者にとっては、徹頭徹尾〈幻想質〉に浸された言葉のみで形づくられた、山尾悠子の幻想文学世界を強く想起せしめるに違いない。
また、それらの一方で、本書には英国文学のお家芸たる海洋幻想譚の血脈が、覆いがたく流入していることも指摘されて然るべきであろう。〈信天翁〉の突然の乱入のくだりなどに、それは歴然かと思われる。
清新な才能によって新たに生み出された、醇乎たる幻想文学の佳品を、もう1篇。
戦時中を舞台に『遠野物語』風の土俗の妖異の跳梁を描いた『迷い家』で2017年、第24回日本ホラー小説大賞の優秀賞を受賞した山吹静吽の受賞後第1作が、5年余の沈黙を経て、ようやくに刊行された。題して『夜の都』。時は1920年代の前半、舞台は日本とおぼしき「東洋の島国」だが、主人公はライラという名の14歳の英国少女。父親の東洋出張に同伴して、見知らぬ新興国に新たに建てられた西洋風ホテルに滞在する勝ち気な少女は、エキゾティックな同地の伝承に触れ、どこか『竹取物語』の世界を連想させる、高貴な〈月の姫〉に仕えるという魔女と、不思議な電話機を通して会話を交わすようになるのだが……。「あまりにも美しく無慈悲な魔法少女物語」という一見、場違いにすら思える帯の惹句に、嘘偽りは無い。
私が何より驚かされたのは、ライラが師事する謎めいた魔女の名が「クダン」であることだ。漢字で書けば「件」……人面牛身で、生まれ落ちると間もなく、真正の予言をすると伝えられる伝説の幻獣である。そう、昨年末に拙著『クダン狩り』(白澤社)で採りあげた、あのクダンなのだ! これが単なる偶然の一致でないことは、作中にも「彼女が指差す薬屋の看板には人の顔をした牛らしき珍妙な絵が描かれていた」云々と、かつて街中に実在したクダンの絵姿が言及されていることにも明らかだろう。
ちなみに、日本で最初に自著の中で、この〈クダン〉に言及した文学者といえば、ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲だった。そう、ライラより30年近く昔、現実の日本にやって来て、印象的な旅行記や名著『怪談』を遺した、あの八雲である。本書終盤のクライマックス・シーンには、関東大震災とおぼしき大地震の描写が登場するが、八雲ゆかりの横浜グランド・ホテルもまた、震災で深刻な被害を被り、八雲家の恩人だった米国軍人M・C・マクドナルドは、その際にホテル倒壊の犠牲となっている。横浜は、本書の主要な舞台となる〈オロガミ〉と呼ばれる、架空の小都会のモデルに相応しい土地のような気もするが、真偽のほどは定かでない。
洋風ホテルのオーナーである老媼トキとクダン──ふたりの〈魔女〉と、新時代を担う魔女ライラとの烈しい相克が、本書全篇を通じての主題となっている。最後の最後まで、二転三転、息も継がせぬストーリーが、夢の世界と現実世界を股にかけて展開される大力作。〈水棲動物〉だの〈旧神〉だの、思わせぶりなネーミングも登場して愉しい限りだ。
そんな『夜の都』を読むうえで、恰好のハンドブックとなりそうなのが、リチャード・サッグの『妖精伝説』(甲斐理恵子訳/原書房)である。「本当は恐ろしいフェアリーの世界」という副題が、本書の第一の特色を雄弁に物語っていよう。膨大な民間伝承を援用しつつ、著者は「妖精を実際に見た人たち」の物語を跡づけてゆくのである。ティンカー・ベルの艶姿の影に秘められた、世にも無気味な妖精世界──いったん魅入られたら最後、逃れるのが難しい世界を解き明かす好著だ。