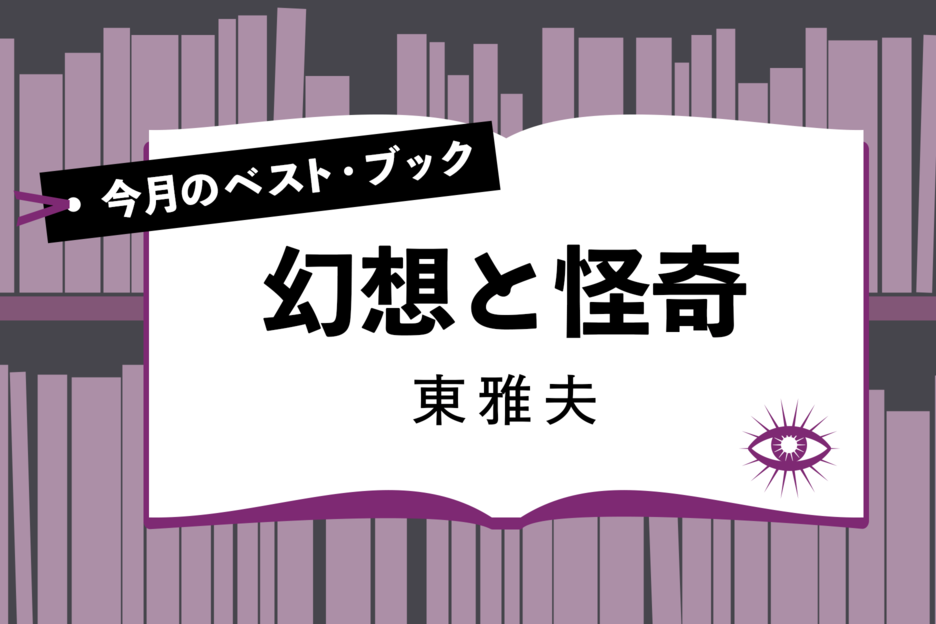今月のベスト・ブック

装幀=岡本歌織(next door design)
『ポルターガイストの囚人』
上條一輝 著
東京創元社
定価 1,870円(税込)
ひとめ見た瞬間から、なんとなーく、いやあ~、な気がしたものだ。
そう、東京スカイツリーの話である。
そもそも、あそこの根元は、怪談ニッポンの原点ともいうべき『東海道四谷怪談』の「本当の舞台」になった、とも伝えられる、あまり縁起が良いとは言えない場所(婉曲表現)であることについては、雑誌「幽」第17号「ふるさと怪談」の特集に掲載した東雅夫「スカイツリーとふるさと怪談」および加門七海「四谷怪談ゆかりの地に生まれて」に詳しい。私の書いた文章から、ちょっと引用しておこうか。
〈とりわけ「スカイツリーの下をお岩は流れる」と題されたパンフレットの解説には興奮を禁じえなかった。松島氏はその中で、鶴屋南北『東海道四谷怪談』における「四谷」の該当地として、これまでの定説である雑司ヶ谷の四谷家以外に、本所中之郷村(現在の墨田区東駒形付近)の四ッ谷という地名を挙げ、そこが現在、東京スカイツリーの聳え立つ北十間川沿いの一帯に当たることを指摘されていたのである〉
この松島茂氏(地元の郷土史家)による御指摘は、今でも大変な卓見であったと私は思っている。
そう思って見れば、スカイツリーのふもとには、なぜか「本所七不思議」関連の案内板が設置されていたり(実際の「御当地」とはかなり距離があるんだけどね……むしろ両国でしょう、御当地というなら)して、どうも妖しい。というか、あの不気味な立ち姿を見れば、こ、これは、妖しいと、気がつくはずではないか! 地元商店街の方には申し訳がないのだが。
いずれ才能あふれる誰かさんが、この塔を舞台にした世紀の怪談を発表してくれるだろうと期待していたら、第1回創元ホラー長編賞を受賞して彗星のごとく出現した期待の新鋭・上條一輝氏が、やってくれました!
思いのほか早く登場した第2作『ポルターガイストの囚人』は、な、な、なんと舞台が「雑司ヶ谷」、しかも物語のクライマックスを迎えるのが、スカイツリーの頂上! という大胆不敵な趣向である。
受賞作『深淵のテレパス』でも大活躍した「あしや超常現象調査」のメンバーおよび関係者たち、それも晴子や越野や倉元&犬井らレギュラー陣に加えて、チョイ役かと思っていた桐山ちゃんまで堂々の出演を果たしているのだった。
二転三転どころか四転も五転もする先の読めない展開といい、読むほどに謎を深める超常現象といい、恐るべきリーダビリティの高さは健在。なにより地底世界が舞台となった1作目に対して、今回は天上の楼閣というべきスカイツリーが舞台……この鮮やかな対比の妙は、泉鏡花や赤江瀑の傑作戯曲を連想させるではないか!
全篇これでもか、とばかり、愉しませていただきました。
こちらは毎年恒例となった平凡社ライブラリー「文豪怪異小品集」シリーズ。このほどその第14弾として『深夜の祝祭 澁澤龍彥怪異小品集』が刊行された(今年はイレギュラーで『怪獣談 文豪怪獣作品集』も刊行されているが、こちらは私にとって最初のアンソロジーとなった『怪獣文学大全』の復刊だったのだ!)。
私が澁澤アンソロジーを編纂するのは、本書で3冊目。既存の2冊は、どちらもエッセーおよび評論が主体で、個人的には「小説家・澁澤龍彥」の真髄を示すような傑作選をぜひとも編みたい、と以前から思っていたのだが、今回、唐突に「少女/女妖」というキイワードが天啓のごとく閃いたことで、本書を実現させることが出来た次第。積年の懸案が解決したばかりか、第2部として、澁澤さんに御寄稿いただいた「幻想文学」関連の文章までひとまとめに載せることができて、嬉しいこと、このうえない。ちなみに第3部の「地妖について」も、三浦半島出身の小生にとっては、愛着尽きない作品ばかりで、これら3部を1巻に収めることができたのは、幸甚至極であった。
ちなみに「女妖」というのは、要するに「女性の姿をした妖かし」の意味だが、澁澤氏の初期から晩年にいたる文業を顧みるとき、おのずからこの言葉が否応なく想起される。いや、澁澤さんこそ心底、女妖に憑かれた作家、と呼んでも過言ではなかろう。その実態は、ぜひとも本書に結集された作品を賞玩していただきたいと思う。
小野不由美の『営繕かるかや怪異譚』(KADOKAWA)も、はや4巻目。2篇目の「迦陵頻伽」というタイトルに、澁澤さんの『高丘親王航海記』を、はからずも連想させられた。こちらは東洋奇譚ではなくて、現代日本を舞台にした物語だが、鳥の姿をした「内神様」の功徳によって、知らぬ間に守られている一族の話。
鳥といえば「夜明けの晩に」も、タイトルから想像されるように、「かごめかごめ/かごのなかのとりは」の歌にまつわる話。あの歌、よくよく聴いてみると、なんとなく不気味というか不吉なものを感じさせる歌だが(以前この歌の謎を追って、某「ムー」誌で紀行をしたことがあったな~)、そうした不気味さは、この不穏な物語からも感じ取ることができるだろう。