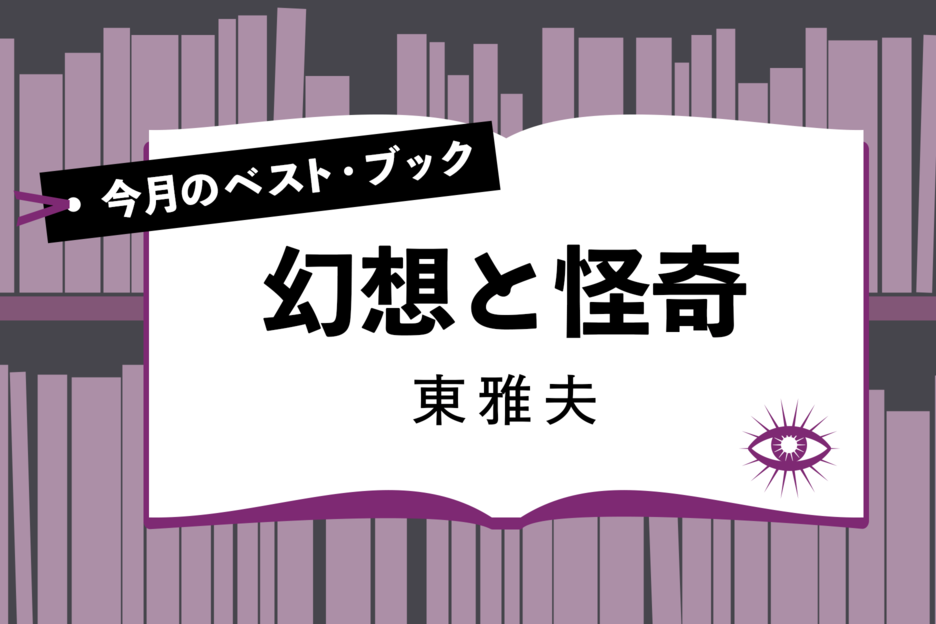今月のベスト・ブック
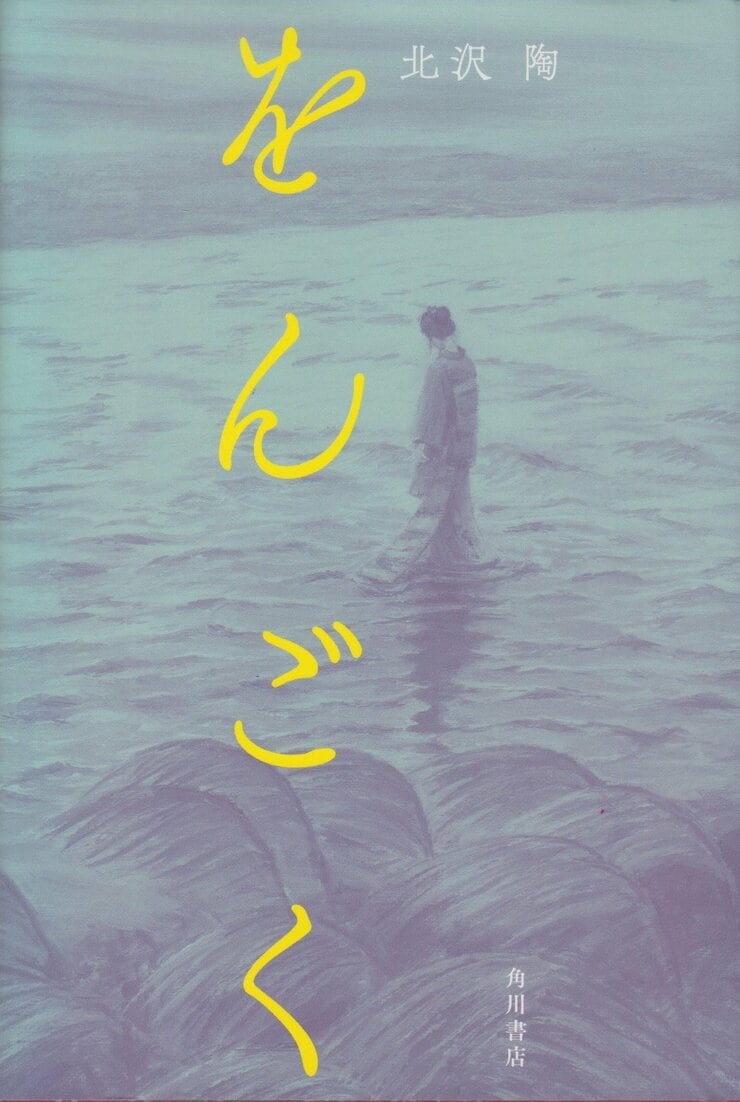
装丁=池田進吾
『をんごく』
北沢 陶 著
KADOKAWA
定価1,980円(税込)
今月は、自前の編纂書の話題から始めるとしよう。このほど、新潮文庫から初めて(註釈付きで!)上梓するはこびとなったアンソロジー『外科室・天守物語』である。
今からちょうど150年前となる1873年(明治6年)、石川県金沢市に、ひとりの文豪が誕生した。後に『金色夜叉』で、若くして文豪と呼ばれた尾崎紅葉の高弟・泉鏡花である。当時、紅葉率いる硯友社の牙城と呼ばれた文芸雑誌「新小説」に、20歳そこそこの若さで、「外科室」「夜行巡査」を始めとする問題作を次々と発表、それらは〈深刻小説〉と称され、大いに話題を呼んだ。
やがて鏡花は、故郷・金沢や隣県・富山に伝わる妖美な怪異伝説の数々に取材した「高野聖」「蛇くひ」などの作品で一躍文名を高め、明治・大正・昭和の3代にわたり息長く、文豪としての独自の地歩を築いてゆくのだった……。
本書は、怪奇幻想文学の巨星としての鏡花の真価を示す作品ばかり、全8篇の小説や戯曲を集成したアンソロジーである。かつて、あの三島由紀夫が「昼間の空にうかんだ燈籠のように、清澄で、艶やかで、細緻で、いささかも土の汚れをつけず、しかもまだ灯されない、何かそれ自体無意味にちかいような果敢なさの詩である」と称賛を惜しまなかった不朽の絶筆「縷紅新草」をはじめ、白鷺城を舞台に妖怪変化が乱舞する「天守物語」や、初期の名作短篇として近年評価の高まる「化鳥」など、必読の作品ばかりを厳選収録している。先に双葉文庫から刊行した『耽美と憧憬の泉鏡花』と一対をなす傑作選として、御賞味いただけたら幸いである。
第43回となる「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」は、北沢陶の『をんごく』が、大賞に加えて読者賞とカクヨム賞まで、3賞を同時受賞する圧倒的な結果となった。綾辻行人さんの選評に拠れば、「文章が、とにかく良い。客観的に見て『巧い』し、その巧さが実に心地好い。第一幕第一節──冒頭の『口寄』のシーンに続いて、40×40の字詰めで6.5枚ぶん、主人公の来歴が語られる。ここまで読んだ時点で僕はもう、原稿の何カ所かにサイドラインを引いて『巧い!』と書き込むなどしている」と、手放しの絶賛ぶりである。また「文章の良さゆえに人物が生き、風景が生きる。大正時代末期の大阪を舞台とするこの物語の“世界”に、するりと引き込まれる」ともあって、まことに言いえて妙だ。
実はこの冒頭部分、私は「口寄」という特徴的な一語、さらに大阪・船場という舞台から、生粋の関西人・折口信夫の名作怪談「生き口を問ふ女」を、ゆくりなくも連想したのだけれど、なるほど本書においては、生きている主人公にも増して、今は「をんごく(=遠国/厭国!?)」の住人たる亡き妻・倭子の面影が、ことあるごとに、大正期という影多き舞台装置のあわいから、ひょいと偲び出ては、生者たちを震撼させるのであった。そしてまた、両者の間を妖しくも繋ぐのが、「エリマキ」と通称される「顔のない」男の存在だろう。
トリプル受賞の名に恥じない、一読驚嘆必至の作品なので、ぜひとも御一読をお勧めしておきたいと思う。
〈ビブリア古書堂の事件手帖〉で人気を博している三上延の新作『百鬼園事件帖』(KADOKAWA)もまた、驚くなかれ、戦前の日本が舞台。しかも主人公は、内田百間──芸の細かいことに、作中では百ケン(門構えに月)ではなく「百間」だが、これも実は史実に基づいている。当時の百間先生は、その筆名を用いていたのだ。
百間を主人公にした変な小説といえば、先年惜しくも物故した久世光彦の遺作『百間先生 月を踏む』が有名だが、本書もまた、なかなかに奇妙なテイストにあふれた連作集である。
主人公は、百間のドイツ語の教え子である大学生の甘木くん──わざわざ、この名前を選んでいることからして、作者はただものではないことが分かる。「某」(=なにがし)を2分割して「甘木」、これは百間自身が、好んで起用した仮名なのである。百間文学の愛読者ならば、すぐにピンとくる名前である。
尋常でないのは、それのみに留まらない。甘木くんは、神楽坂のカフェで偶然、同席することになった百間と、着ていた背広をうっかりして取り違え、帰宅することになるのだが、その古ぼけた背広は、百間の師匠であった夏目漱石が生前、愛用していたものだったのだ!
その夜、甘木は下宿で不思議な夢を見る。夢の中で彼は、奇妙な人物に変じて川の中へずんずん入ってゆき、「深くなる、夜になる、まっすぐになる」という、何やら呪文めいた文句を唱えているのだった……と、ここまで書けば、すでにお分かりの向きもあるだろう。これは、漱石の連作集「夢十夜」所収の1篇「第四話」である。と同時に、百間が同篇から多大な影響を受けて、『冥途』に始まる連作集を手がけていることも、先刻御承知かも知れない。
というわけで、続く「猫」「竹杖」「春の日」の連作群のいずれにも(題名からして「いかにも!」なのだが……)、作者のただならぬ「百間愛」が横溢しているのだった。ぜひ続刊を期待したくなる1冊だ。