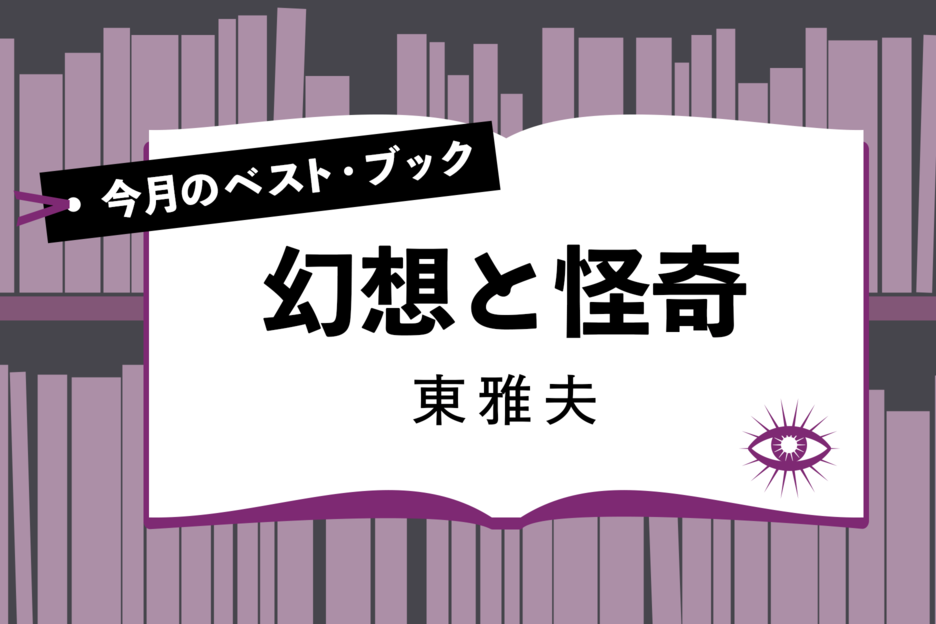今月のベスト・ブック
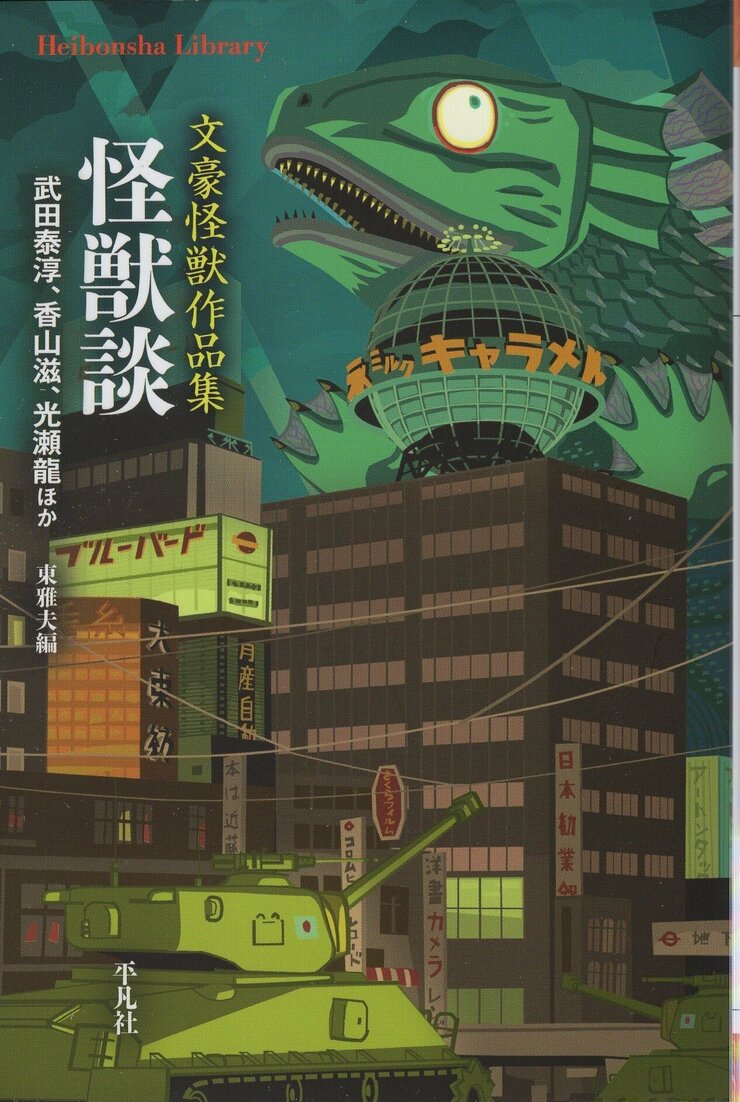
装幀=中垣信夫
『怪獣談 文豪怪獣作品集』
武田泰淳、香山滋ほか 著
東雅夫 編
平凡社ライブラリー
定価 2,420円(税込)
1998年の8月4日──今からかれこれ27年前となるこの日は(少なくとも小生にとっては)、忘れがたい日となっている。別にもったいを付けるまでもない、私が「アンソロジスト」として、正式なデビューをした日なのだ。
もちろんそれまでにも、幻想文学会出版局から何冊か、アンソロジー的な本は手がけていたし、さらに遡れば、古巣の青銅社で、畏れ多くも晩年の澁澤龍彥さんを監修者に迎えて、『幻想のラビリンス』と『幻視のラビリンス』と銘打たれた2冊本の日本幻想文学アンソロジーを編纂してもいたのだが、それらはあくまで「幻想文学会」として請け負った仕事なので、何だか気おくれがして、個人名は表に出していなかったのである。したがって、東雅夫の編者名を堂々と冠したアンソロジーとしては、同年の8月に河出文庫から出た『怪獣文学大全』が、初のアンソロジーとなったのだった。
まことに遺憾ながら、このマイ・アンソロジー第1号、残念なことに、とうとう重版が掛からなかった(同じ8月の20日、約2週間差で世に出たアンソロジー第2弾『妖髪鬼談』(桜桃書房)は、すぐさま増刷が掛かったというのに!)。
以来苦節ン十年、このほどようやく平凡社ライブラリーから、待望久しい新版が刊行されることとなった。題して『怪獣談』。再刊にあたっては、収録作品の徹底した見直しをおこない、これぞ決定版「怪獣小説集」! と呼びうる本となるように心掛けた。
当時のキイマンとなった「日本特撮の父」円谷英二特技監督のもと、東宝映画の製作陣と戦後文学および日本SF草創期の作家たちが相携えて生み出した日本独自の文化である「怪獣映画」の真価を後代に伝えるべく、小説・戯曲・随筆から厳選されたラインナップは、こちら!
香山滋・文/深尾徹哉・絵「怪獣絵物語 マンモジーラ」
武田泰淳「『ゴジラ』の来る夜」
中村真一郎・福永武彦・堀田善衞「発光妖精とモスラ」
黒沼健「怪奇科学小説 ラドンの誕生」
香山滋「S作品検討用台本(獣人雪男)」
福島正実「マタンゴ」
光瀬龍「マグラ!」「思い出の『マグラ!』」
香山滋「『ゴジラ』ざんげ」「怪獣談」
花田清輝「科学小説」
東山魁夷「怪奇空想映画療法」
三島由紀夫「『子供っぽい悪趣味』讃」
以上、我ながら、怪獣物特有の荒唐無稽さと夢のある展開に配慮した1冊に出来たのではないかと思っている。今度こそ、すんなり重版して積年の「借り」を返したい心境。
久方ぶりに「豪華本」と呼びたくなるような手の込んだ装幀・造本に、思わず「よ、快挙!」と掛け声をかけたくなったのが、小川未明研究で定評のある小埜裕二監修・解説による『愛蔵版 宮沢賢治童話集』(世界文化社)。同社の「創立八〇周年記念出版」として企画・刊行されたものらしい。賢治の長短代表作17篇を、グラフィックデザイナー日下明による全篇カラー挿絵入りで収録。しかも巻末には日下が所属する音楽ユニット「リペアー」による「宮沢賢治作品に寄せて」と題するオリジナル楽曲まで収録されているという凝った仕様。会社創立記念本だから、ここまで出来たのか……とも思うが、こうした凝った仕様の書物が、日常的に刊行されていた「大正」という時代の物凄さを、改めて実感せざるを得ない。こと書物に関するかぎり我々は100年前の大正期よりも豊かな時代を生きていると言えるのだろうか? はなはだ疑問に感じざるを得ないのである。
美術史家・喜多崎親の著書『暗示の構造 象徴主義絵画のレトリック』(三元社)が上梓された。〈モロー、ゴーガン、ルドン、クノップフ、ミュシャらの絵画が発する複雑で謎めいた効果を「暗示を創り出す画面のレトリック」の視点から考察〉と帯文中に記されている。
御存じの向きもあろうかと思うが、近年、編集稼業から足を洗って以降、美術エッセイ的な方面へと軸足を移している私としては、大いに興味深く読むことができた。
まずは大好きなフェルナン・クノップフの章から。「喚起する類似」と題されたこの章では、代表作の「青い翼」や「白、黒、金」から、「私は私自身に扉の鍵を掛ける」にいたる作品群(まさに「象徴主義絵画」の謎めいた真髄と言ってよかろう)に描かれたヒュプノス(=眠りの神)の像の意味するところを中心に、精緻な論述がなされてゆく。「そうか、そういうことだったのか!」と思わず得心させるような指摘が相次ぎ、本書がサンボリスムをめぐる分かりやすい手引きの書であることを実感させてくれるのである。
ほかに、英国の作家ブルワー=リットン卿の有名な怪奇小説「幽霊屋敷」に基づくルドンの石版画群が、「物語の語り手が目にした怪異や異常な印象などに限定して描かれている」「しかもその造形が、単一画面への複数の場面の融合や、ルドンの他作品との類似などによって、イメージの喚起力を高めている」ことの指摘なども、大いに興味深く読むことができた。怪奇幻想方面から象徴主義絵画に関心を抱く向きには必読の好著。