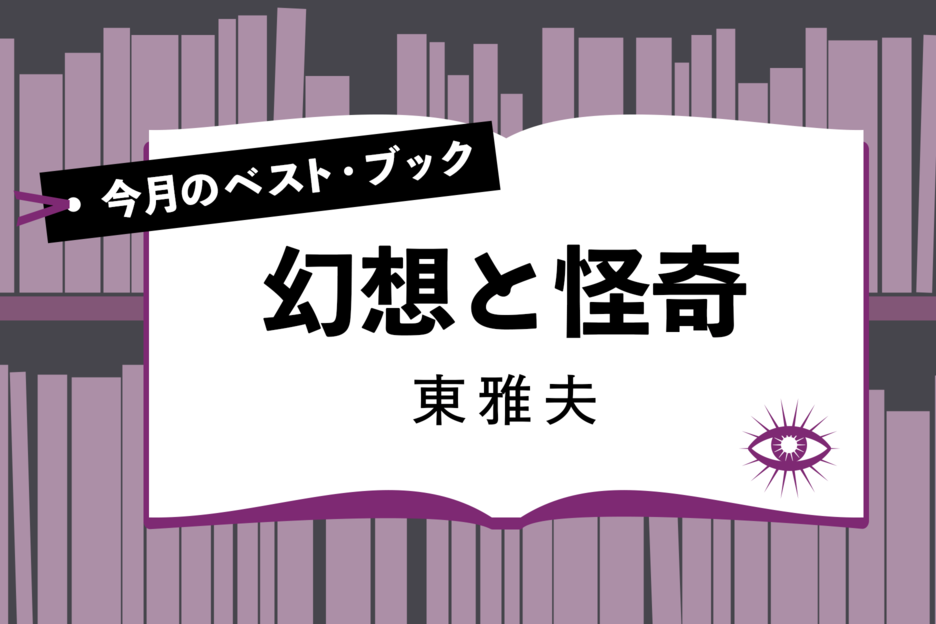今月のベスト・ブック

装画=中川学
『お住の霊 岡本綺堂怪異小品集』
岡本綺堂 著/東 雅夫 編
平凡社ライブラリー
定価1,980円(税込)
岡本綺堂といえば、本誌読者にとっては、何より〈半七捕物帳〉シリーズの生みの親という側面が有名だろう。捕物帳の発案者にして、和製シャーロック・ホームズの元祖。
とはいえ、綺堂の業績は、それのみに留まらない。代表作『修禅寺物語』をはじめとする戯曲作品の数々は、明治になって盛んとなった〈新歌舞伎〉の代表的演目として、歌舞伎ファンに支持されて久しい。
捕物帳(=読物)と、新歌舞伎(=戯曲)──双方の愛好者層が、果たしてどれほどの重なりを持っていたのか、いささか心許ないものがある。もちろん新派の名女形・喜多村緑郎のように、名優にして大のミステリー・ファンという変わり種もいないことはないが、これはやや特殊に属するだろう。
しかも、綺堂先生の場合、そこに、もうひとつの重要なファクターが介在するのだから、話は、いささかややこしい。そう、比類なき〈怪談の名手〉としての側面である。
今年2022年は、1872年に綺堂が誕生してから、ちょうど150年目となるメモリアル・イヤーだ。しかも、来たる2023年は、関東大震災から100年目の(こちらはあまり有難くない)メモリアル・イヤーでもある。震災の業火に、住みなれた麹町の居宅と蔵書のすべてを焼かれた綺堂が、手許に細かい資料がなくても執筆可能な分野として、怪談や巷談に新境地を見出したのは、すでに定説化している。怪談読物の名作シリーズ『青蛙堂鬼談』や『近代異妖篇』は、すべて震災後に誕生しているのである。
この千載一遇の好機に、怪談作家綺堂の復権を目論まなくて、どうするというのか……そんな小生の切なる願いが、天に届いたものか、岡山県の〈勝央美術文学館〉さんから、怪談作家綺堂に主眼を置いた、大規模な回顧展の御相談をいただいたのは、今年初めのことだった(北村薫さんの御慫慂に深謝!)。
同町は綺堂の養嗣子・岡本経一さん(出版社・青蛙房の社主)の出身地であり、同館には綺堂関連の豊富な資料が収蔵されている。そうした展示資料も活かしつつ、今年10月に〈奇譚の神様〉と銘打って、怪談作家綺堂の足跡をあとづける回顧展が開催される運びとなった。やれ、めでたやな!
編集者出身の小生、この機に乗じて、綺堂作品の〈記念出版〉を実現させたいものと、かねて心覚えの版元(双葉社も含む!)数社にお声がけをしたところ、真っ先に名乗りをあげてくださったのが、今回紹介する平凡社ライブラリー。毎夏恒例となった〈文豪怪異小品集〉の1冊として、小生編『お住の霊 岡本綺堂怪異小品集』が、このほど上梓された。もっぱら明治から大正期(要するに震災前)に書かれた初期作品の中から、短篇、戯曲、実話、随筆等々、怪奇色の濃い作品を厳選収録している。とりわけ冒頭に据えた連作〈五人の話〉は、1人1話の独白形式による作品で、後の『青蛙堂鬼談』などの原型に位置づけられよう。一部を除き、今回が史上初復刻の珍しい作品群ゆえ、御注目いただけたら幸いである。このあと10月へ向けて、白澤社から怪奇随筆集成、双葉社から豪華ハードカバーの怪談集成の刊行が予定されているので、刮目してお待ちいただきたいと思う。
青蛙房絡みの名著をもう1冊、いや正確には2冊か。柴田宵曲の『妖異博物館』といえば、正続2巻から成る江戸怪談の玉手箱……それこそ岡本綺堂作品の元ネタが、いともあっさりと開陳されているなど、その種のマニアには堪えられない名著だったが、このほど角川ソフィア文庫から『完本 妖異博物館』として、正続を合冊した1巻本の形で新たに上梓されたことは(しかも巻末には便利な索引付き)、大いに嘉すべきといえよう。その「あとがき」を記している青蛙房主人が、すなわち岡本経一翁である。
今回の「解説」は常光徹氏が執筆しているが、〈登場するのは俳人だけではない。小泉八雲、岡本綺堂、泉鏡花、夏目漱石、芥川龍之介、柳田國男、寺田寅彦など多彩だ。いずれも怪談つながりだが、周到な目配りと守備範囲の広さには改めて驚かされる。なかでも、八雲と綺堂について触れた箇所が目立つのは、二人が江戸の怪異譚を素材にした多くの作品を発表しているためである〉とあるのは至言だろう。綺堂再読のこよなき導きの書だ。
長篇デビュー作『虚魚』で第41回横溝正史ミステリ&ホラー大賞を受賞した、期待の新鋭・新名智の受賞後第1作『あさとほ』(角川書店)が上梓された。
怪談実話テイストが満載だった異色作『虚魚』に対して、こちらは〈ボーイ・ミーツ・ガール〉なテイスト(ただし、かなり捻った設定だが……)を基調に、国文学科の女学生群像を描いた、謎めいた物語である。〈神隠し〉が全篇のキイワードとなっているが(とはいえミステリー的要素は意外に稀薄)、同時にこれは、驚天動地のドッペルゲンガー小説でもあって、古典の中古文学をテーマとする奇書奇譚でもある……という、なかなかに凝りまくりの設定なのだ。元・国文科の不良学生だった小生などは、作中に、ひらひらとはためく妖しげな白布が出現した時点で、こ、こ、これはもしや!? と興奮を抑えられなかった。そして、またしても(『虚魚』と同じく!)最後に出現する〈河〉の描写……。信州から、いきなり出現した清新な才能の今後に、ますますの御注目を!