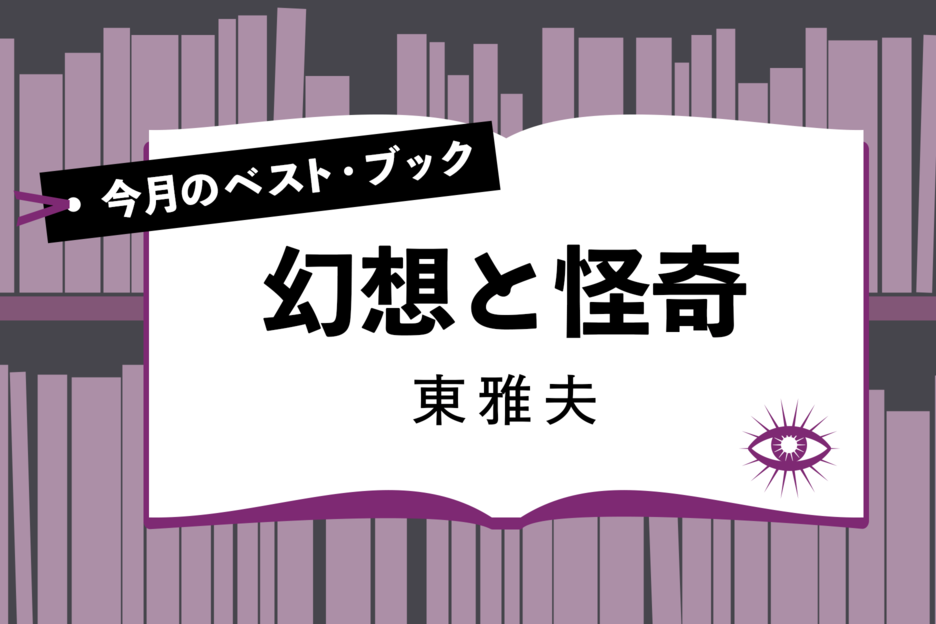今月のベスト・ブック
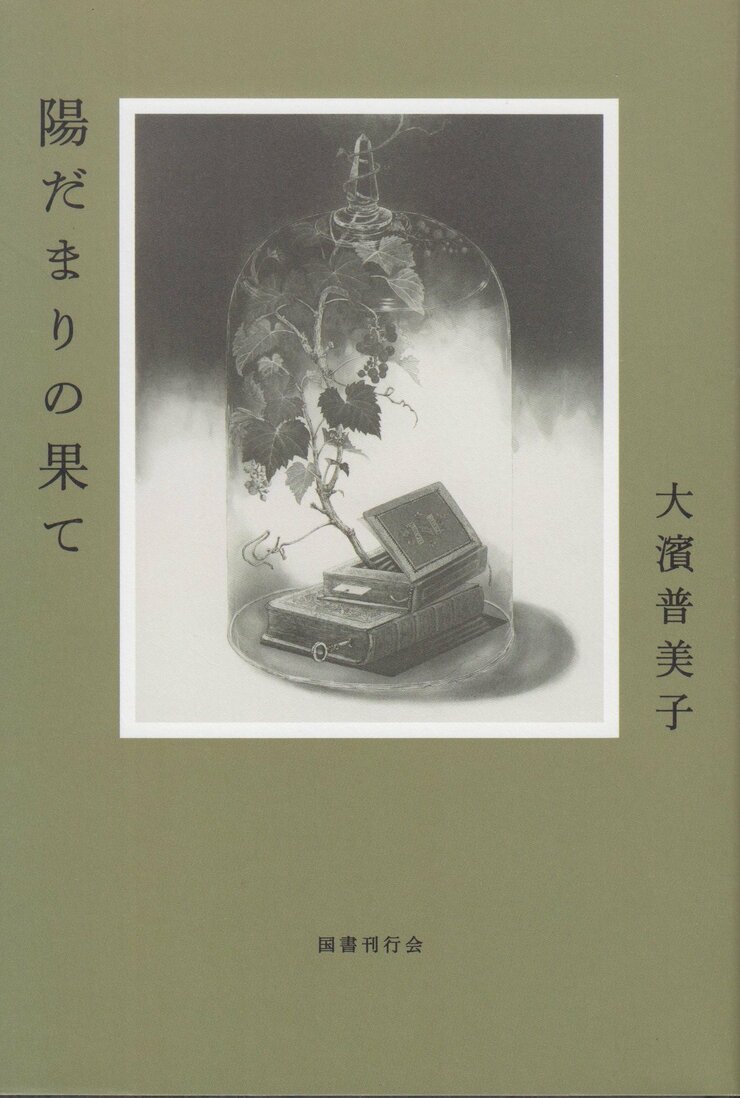
装画=武田史子
『陽だまりの果て』
大濱普美子 著
国書刊行会
定価2,420円(税込)
今年度の泉鏡花文学賞を、大濱普美子の短篇集『陽だまりの果て』が受賞した。
前作『十四番線上のハレルヤ』に帯文を寄稿したり、1作目の『たけこのぞう』収録作中の白眉「盂蘭盆会」を、いち早く創元推理文庫版『平成怪奇小説傑作集3』に採録するなど、もっぱら〈大濱応援団〉の旗振り役をささやかながら務めてきた小生としては、悦ばしい事このうえないのだが、その一方で、「3冊目の短篇集にしてようやく、大濱普美子の真価に気づいたのか……」という、いささかもどかしい想いもあるのは事実。
右の『平成怪奇小説傑作集3』の解題に、編者の考える大濱作品の特質を、約めてまとめておいたので、引用してみよう。 「山崎俊夫や畑耕一、そして原民喜ら耽美と幻視の作家たちを輩出した『三田文学』の伝統を現代に受け継ぐ大濱普美子は、海外在住ということもあってか寡作な書き手だが、『たけこのぞう』(2013)と『十四番線上のハレルヤ』(2018)という2冊の短篇集には、稠密な文体で眼前の現実の彼方に肉薄するかのごとき珠玉作が幾つとなく収められている」
そう、大濱普美子こそは、山崎俊夫や畑耕一の正系を現代に受け継ぐ、まことに稀有なる存在なのである(山崎俊夫や畑耕一……誰それ? などという初心な読者は……恐縮ながら、ここでは、とりあえず無視しておく。作家事典の類を調べてください……)。
さて、3冊目の短篇集となる本書においても、先に指摘したような「稠密な文体で眼前の現実の彼方に肉薄する」大濱作品の特質はいよいよ顕わである。たとえば、表題作冒頭の精彩を放つ文体──「廊下を、人気のない廊下を、ずっと奥のほうへと辿っていったところに、陽だまりがある。いつもそこのところに立ってじっと見ているのではないが、ほんとうはそこにそうして立って、じっと見ていたいのだが、ずっと奥の行き止まりまで行けば、いつもそこにある」明らかに意図的に繰り返される文体。そこには、本篇の語り手自身の寄る辺ない現実感が、裏返しに反映されているかのようではないか。
表題作や冒頭の「ツメタガイの記憶」から何より色濃く感知されるのは、「深く重い生と衰と死」(皆川博子による本書帯文より)である。とりわけ「衰滅」への憧憬に満ちた視線は顕著であり、彼我がいつしか混淆され判然としがたくなる、大濱作品の特色を成しているといえよう。玄妙妖艶なる老年期の文学、素晴らしい。
今年は本朝モダン・ホラーの元祖たる岡本綺堂の生誕150年ということで、つい先日綺堂の養嗣子にして青蛙房創業者でもある岡本経一や高弟・額田六福の郷里・岡山県勝田郡の勝央美術文学館で、生誕祭が挙行された。記念展示の監修役を務めた私も参加して、講演と朗読を披露したが、綺堂にちなんだ「怖い話」コンクールの受賞者(小中学生)も加わり、賑やかな催しとなった。
まあ本業がアンソロジストの私としては、150年記念出版となるアンソロジー3部作の最終巻『江戸の残映 綺堂怪奇随筆選』(白澤社発行/現代書館発売)の上梓が、きわどいタイミングで間に合ったことが、なにより嬉しかったのだが(笑)。
本書は、綺堂先生ならではの江戸懐古と怪談趣味にあふれた随筆選集である。例の半七親分や三浦老人を彷彿とさせる話好きの老翁が、思いいずるがまま語りだす懐旧談の数々……これが面白くないわけがあるまい。お得意の芝居絡みの怪談系話のほかにも、今回が初復刻となる「焼かれた夜」などの関東大震災関連の話や、綺堂お気に入りの温泉地・磯部鉱泉(群馬県)滞在から生まれた「磯部の若葉」「磯部のやどり」「山霧」などの知られざる名品群も併録されている。
綺堂怪談必読の名作を集めた双葉社版『岡本綺堂 怪談文芸名作集』に続いて、本書を送り出せた意義は、大きいかと思われる。ある意味、最も綺堂らしい、その本領と持ち味を窺うに足る一巻ではなかろうか。
以前、このページで、マリアーナ・エンリケスという新進スペイン語圏女性作家の、ちょいとラヴクラフト風味な好短篇集『わたしたちが火の中で失くしたもの』を紹介したことがあったけれども、どうやらこうした動きはエンリケスのみに留まらず、若いスペイン語圏女性作家に共通した傾向でもあると見えて、〈スパニッシュ・ホラー〉なる目新しい呼び名まで登場しているらしい。
『兎の島』(宮崎真紀訳/国書刊行会)のエルビラ・ナバロも、その1人。1978年生まれで、すでに長短篇小説やエッセイ集など幅広く活躍しているらしい。
本書の表題作は、都市部を流れる大河の中洲に、白兎の群れを放つ「発明家」の物語。瘴気を発して近寄るものもない中洲で、兎たちは異様な繁殖を遂げ、やがて生まれた子兎たちを捕食するように……。川名潤デザインによる、兎の画像を大胆にあしらった魅力的な造本とともに味読すると、なんとも不思議で面妖な味わいの渦中に突き落とされる。それは本書の翻訳者が、訳者あとがきで強調する、本書の「奇妙で不穏で恐ろしい」魅力に通底するものであるように思われる。
ほかに、耳から生えてくる「肢」に身体を乗っ取られる作家の話や、絶滅したはずの古代生物に魅入られた大公の話など。