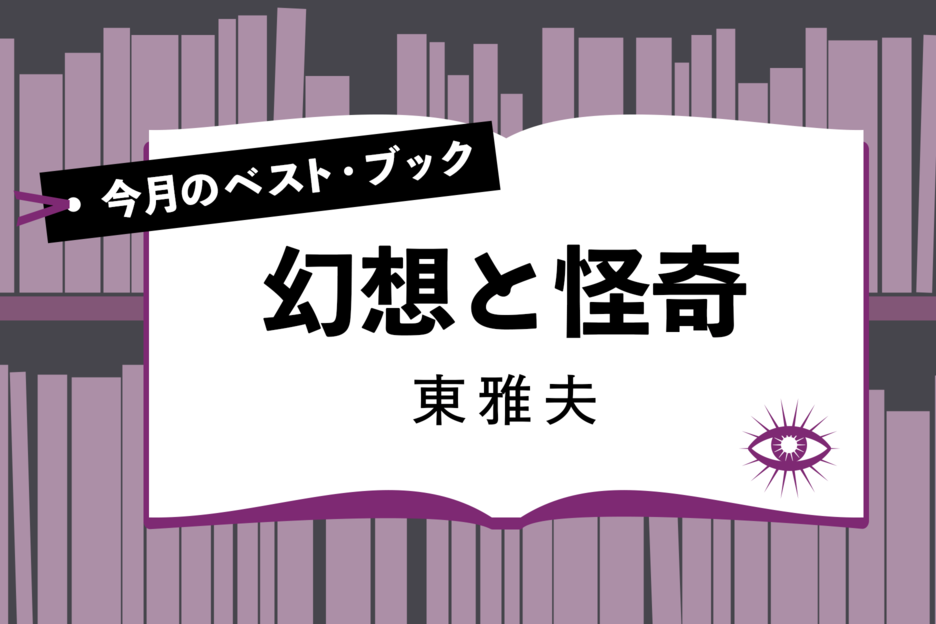今月のベスト・ブック

装幀=坂野公一(welle design)
『歴屍物語集成 畏怖』
天野純希
澤田瞳子他 著
中央公論新社
定価1,870円(税込)
このところ怪奇幻想方面に妙に熱心な中央公論新社から、新たな書き下ろし競作集が上梓された。「歴史」ならぬ『歴屍物語集成 畏怖』である。
収録作家数5名で「集成」と銘打つのは、如何なものかとも思うが(笑)、「歴史小説」+「屍」という着想は、これまで無かったもので、素晴らしい。
「歴史の底から『屍』が這い寄る」という印象的な帯文にあるとおり、本格的な骨法で綴られた歴史小説と、多くがアヴァンギャルドなゾンビ・テーマ小説との融合というのは、思えばこれまで、試みられたことがなかった。
しかも本書の場合、「元寇」の時代から泰平の江戸期まで、時代を追って、ゾンビたちの躍動(と呼ぶには、いささかヨタヨタしているのだが……)が描かれてゆく。裏テーマともいうべき「疫病」「感染」への恐怖も、いかにも現代性を感じさせて、良いスパイス味になっていると思う。
今回の企画の柱となった天野純希さんは、新進気鋭の歴史小説作家にして大のゾンビ・ファンという変わり胤(失礼!)──氏が寄稿された序文と跋文には、かの柳田國男御大までチラリと登場して、謎めいた物語に一条の光芒を投じている。
天野氏と矢野隆氏による男性作家陣の作品が、人とゾンビの凄惨な戦いにポイントを定めたアクション味満点の作品なのに対して、直木賞作家2名をふくむ実力派女性作家陣(西條奈加/蝉谷めぐ実/澤田瞳子)の作品は、愛くるしいゾンビ猫の恐怖譚あり、江戸を代表する戯作者・山東京伝先生と人魚妻との一読ホロリとさせる奇譚あり(ちなみに作中に登場する黄表紙『箱入娘面屋人魚』は実在する作品で、まあ飛んでもなくファンタスティックな筋立なのである)で、変格物のゾンビ小説(ゾンビもの自体が変格だろうが……という意見は敢えて無視する!)として、とても好く出来ている。
天野氏と矢野隆氏による男性作家陣の作品が、人とゾンビの凄惨な戦いにポイントを定めたアクション味満点の作品なのに対して、直木賞作家2名をふくむ実力派女性作家陣(西條奈加/蝉谷めぐ実/澤田瞳子)の作品は、愛くるしいゾンビ猫の恐怖譚あり、江戸を代表する戯作者・山東京伝先生と人魚妻との一読ホロリとさせる奇譚あり(ちなみに作中に登場する黄表紙『箱入娘面屋人魚』は実在する作品で、まあ飛んでもなくファンタスティックな筋立なのである)で、変格物のゾンビ小説(ゾンビもの自体が変格だろうが……という意見は敢えて無視する!)として、とても好く出来ている。
マリー・ルイーゼ・カシュニッツ──懐かしい名前である。かつて早川書房のファンタシイ文庫に「精霊たちの庭」が採録されて、それとなく注目していたのだが、ハッと気づけば東京創元社から、酒寄進一氏の編纂・翻訳による〈カシュニッツ短編傑作選〉が2巻まで刊行され、「戦後ドイツを代表する女性作家」とも見做されているらしい……。
というわけで、久しぶりに手に取った『ある晴れたXデイに』(酒寄進一編訳/東京創元社)だが、読んでいて思わず胸苦しくなるような、異様な切迫感は相変わらずだった(これは旧・共産圏の作家に共通して認められる特色なのだろうか?)。すなわち編者が強調する「シュールな筋立て」であり、すなわち「ティンパニの一撃」だろうか。
本書に収録の作品でいえば、巻末の「旅立ち」や「いつかあるとき」それに表題作が、その典型といえようか。パリを舞台にした「旅立ち」では、突然の目覚まし時計の消失が、駅へ行く途上での眩暈感覚へと直結し、「いつかあるとき」では、女性画家の大量の遺作を眺めるうち、錯乱に陥る男の言動へ繋がる。唐突な「世界の終わり」を確信する主婦の物語である表題作に漂う異様なムードも、比類がない。
「旅立ち」に引用されている急逝したユダヤ人作家パウル・ツェランにも繋がる、陰鬱だが不思議な魅力を感じさせる閉塞世界に、是非とも浸っていただきたい。
個性的な古書店にしてプライベート・プレスという独自の地歩を切り拓いてきた書肆盛林堂から、稲垣博訳の〈ペガーナ・コレクション〉第2期の1冊としてラドヤード・キプリング『幽霊の物語』(盛林堂ミステリアス文庫)が出た。
「ダンセイニ卿が当世紀最大の幻想作家と推す、ラドヤード・キプリングの幽霊物語集。単純な幽霊邂逅録を超え、人々の心の機微と悲哀、驚異と意外性が精緻に織り込まれた秀作揃い」という惹句に、嘘や偽りや誇張は微塵もない。あまりにも有名な代表作「彼等」や、「人力車の幽霊」などを読めば、この作家の偉大さ、視えない世界にそそぐ視線の透徹した凄みを実感できるはずだ。稲垣による「訳者あとがき」も、翻訳者ならではの視点から、キプリングという一筋縄ではいかない作家の特色を解明していて一読に値する。
最後は、諏訪哲史の『昏色の都』(国書刊行会)を。表題作の中篇に、「極光」「貸本屋うずら堂」の自伝風な2篇を加えた近作集である。表題作の「昏色の都」とは、死都の異名もあるベルギーのブリュージュのこと。幻想文学ファンには、フェルナン・クノップフが描く幾多の幻想絵画でもおなじみだろう。かく申す私も以前、美術雑誌に、クノップフ描くブリュージュの光景に関する随想を寄稿したことがある。
表題作は、生まれながらに視覚に障害を負い、奇跡的に快復したものの、ふたたび視力を失いつつある男を主人公とする、自伝風の作品。主人公の内面と、昏れなずむブリュージュ特有のすがれた光景とが、絶妙な対比を成して、まことに印象深い。一見すると、とっつきにくく感じる向きもありそうだが、奥深い味わいは癖になる。幻想文学上級者にお勧め。