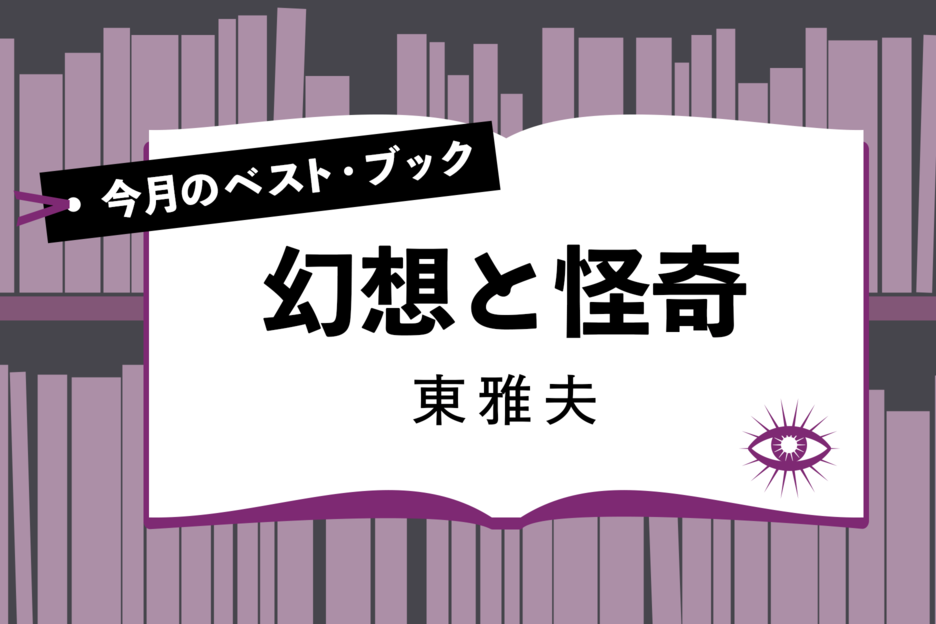今月のベスト・ブック

装幀=坂野公一(welle design)
『骨を喰む真珠』
北沢陶 著
KADOKAWA
定価 1,925円(税込)
谷崎潤一郎に、その名も『人魚の嘆き』と題する短篇があることを御存じだろうか。初出は大正6年(1917)の「中央公論」。長らく中公文庫から「魔術師」とのカップリングで刊行されていたし、また春陽堂書店からも先ごろ豪華本で復刊されたので、水島爾保布による典雅を極めた装幀・挿絵を堪能された向きもあるかも知れない。
ちなみに「人魚」といえば、日本画の巨匠鏑木清方にも「妖魚」と題する大作があって(発表は大正9年/1920)、こちらもまた水辺に横たわる裸体の女性の豊満な姿態に圧倒される。清方の良き盟友であった泉鏡花にも「人魚の祠」(大正5年/1916)という異色篇があることを想起させよう。
要するに「大正」という時代を考えるとき、私などが真っ先に思い浮かべるのは、人にして人に非ざる異形の生物たる「人魚」の図……エロチックなその姿なのだった。
デビュー長篇『をんごく』で横溝正史ミステリ&ホラー大賞の史上初三冠制覇を成し遂げた驚異の新人・北沢陶の受賞第1作となる長篇『骨を喰む真珠』は、大正期のエロチックなシンボルたる「人魚」の妖しさ、妖艶なその魅力を、これでもか! とばかり描き切った大力作である。しかも、同書に登場する人魚は1体のみではなくて……これ以上、その中身に踏み込むと剣呑だし、なにより読者の興趣を削ぐことにもなりかねないので止めておくが、まあ本書後半の壮絶な盛り上がりをお楽しみに、と言うにとどめておこう。
物語の舞台は『をんごく』同様、関東大震災の衝撃が消えやらぬ大正末期の大阪。新聞社に勤務する女性記者の新波苑子は、奇妙な身の上相談の手紙を受け取ったことがきっかけで、芦屋のお屋敷街に暮らす製薬会社の一家に「化け込み」と称する潜入取材を敢行することになる。そこで出会った美しい社長令嬢の礼以。他の家族は何故か礼以のことを異様に恐れているらしい……。礼以の絵の教師として同家に暮らすうち、苑子は新薬に秘められた恐るべき事実に気づくのだった。
あたかも西洋ゴシック小説さながらのひたひたとした筆致で展開される前半に比して、苑子の妹・栄衣が前面に躍り出る後半は、スリルとサスペンスの連続で、躍動感に満ちている。そして目を覆わんばかりの凄惨な真相……人魚伝説に隠された驚くべき秘密に気づいた作者の膂力に、ただただ敬服の一語。
まだ、こんな隠し玉があったのか! と驚かされたのが、フローレンス・パリー・ハイドの原作に、エドワード・ゴーリーが絵を付けた『ツリーホーン、どんどん小さくなる』(東京創元社/三辺律子訳)。ある日、突然、サイズが縮みはじめた男の子ツリーホーンの奇妙な物語。パパもママも学校の先生も、息子が小さくなったことに最初のうち気がつかず、まあ、のんびりしたもの。ゴーリーの挿絵も、いつもの黒いユーモアに満ちた毒のある作風とは異なる淡々とした筆致で展開してゆく。ちょっと不思議な一家の日常という感じの物語だ。この当たり前な感じが、逆に薄ら怖い、かも!?
翻訳家の垂野創一郎氏が、国書刊行会とタッグを組んで、またぞろあまり売れそうもない(失礼!)コアな幻想文学のシリーズを始めた。すなわち〈オーストリア綺想小説コレクション〉(全3巻予定)である。
その第1巻としてヘルベルト・ローゼンドルファー『廃墟建築家』が出た。「メビウスの輪のように連鎖する語りと夢の交響」と帯文に書かれているが、まさしくその通りの趣きで、どこからどこまでが夢やら現やら、読み進めるうちに判断が不能になるこの感触、きわめて夢そのものの手触りに近い。これぞ純正幻想文学! という感じ。
たまたま私は昨年末に某大学の講演会に呼ばれて、泉鏡花の「春昼/春昼後刻」の有名なくだりを朗読する機会があったのだが、あの放恣な、際限もない夢の連なりと酷似したものを実感した。垂野氏のマニアックな解説を読むと、ヘルツマノフスキー=オルランドの名前が頻出して、ああ、このノリかと納得するのだが、この手の幻想物語がお好きな方には、ぜひともお見逃しなく、と推奨しておこう。
最後にフィクションならぬコアな論考集を1冊。田中千惠子編『西洋文学にみる魔術の系譜』(小鳥遊書房)は、高山宏氏や鈴木潔氏ら懐かしい名前も散見される本格的な「魔術と文学」をめぐるアンソロジー。中島廣子「フランス十九世紀文学にみる音楽の魔力」など、『廃墟建築家』の副読本に(あちらはワグナーよりもむしろマーラーだが)なりそうな論考も見いだされる。
編者の田中氏はブルワー=リットンの翻訳などで知られるが、リットン卿もまた文学のみならずオカルティズムに関する深い造詣で知られた人物だった。そのことは最も人口に膾炙した代表作のひとつ「屋敷と呪いの脳髄」(別邦題に「幽霊屋敷」)でも、夙におなじみだろう。まさに編者に人を得た感じで、根占献一「フィチーノ、プラトン的・偽プラトン的伝統、魔術」、小澤実「中世北欧のルーン魔術」などという凄まじい目次に、「幻想文学」以外の誌面で、こうしてお目にかかることになろうとは思わなかった(笑)。こちらの論考集も、品切れ再版未定にならないうちに速やかに入手されることを、強くお勧めする次第である。