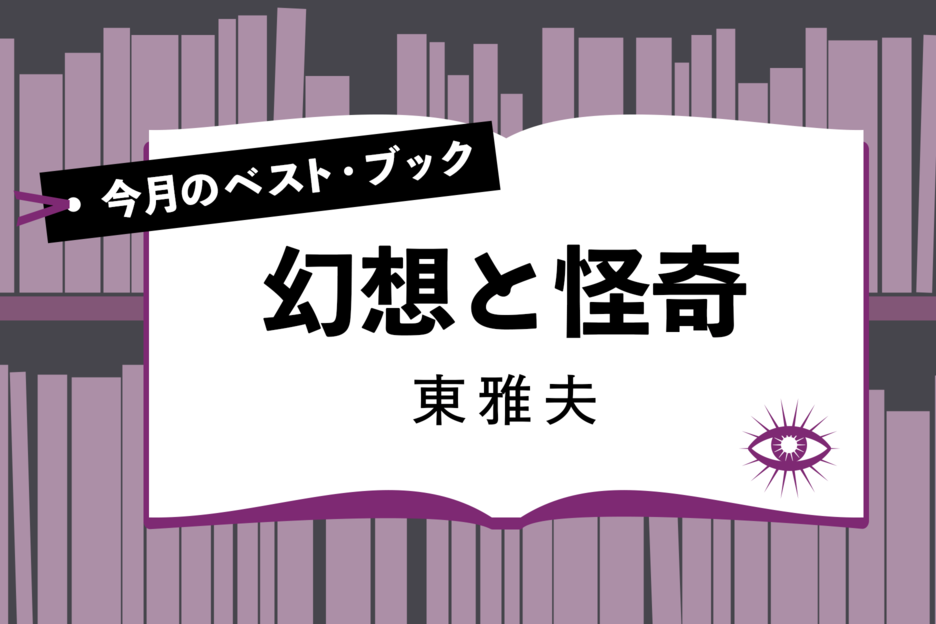今月のベスト・ブック

『ユドルフォ城の怪奇』(上・下)
アン・ラドクリフ 著/三馬志伸 訳
作品社
(上・下)定価各3,960円(税込)
〈文豪怪談ライバルズ!〉シリーズの第二弾として『鬼』(東雅夫編/ちくま文庫)が刊行された。漫画/アニメ『鬼滅の刃』の絶大な影響か、ちかごろ何かと注目を集める鬼たちだが、本書は日本幻想文学史の正系をたどりつつ、〈青頭巾〉〈伊邪那岐の黄泉降り〉〈安達ヶ原の鬼婆〉という代表的な三つの鬼譚にポイントを絞った構成となっている。
とりわけ近世怪異小説の代表作として知られる上田秋成『雨月物語』の雄篇である「青頭巾」については、円地文子による幽婉な現代語訳に、京極夏彦『鬼談』から採られた絶妙な本歌取り譚(著者自身による文字組みもユニーク!)に加えて、国文学の鬼才・高田衛による雨月論考まで加わるという充実の布陣。〈つのる愛〉ゆえに〈喰らうもの〉としての鬼の悽愴かつ哀れな宿業が、ひしひしと伝わってくるかのようだ。
ところで〈青頭巾〉の異形のバリエーションといえば、宇能鴻一郎の傑作短篇集『姫君を喰う話』(新潮文庫)の表題作もまた、酔漢のエッチなモツ焼き談義が、いつのまにやら〈喰うか、喰われるか〉テーマの王朝物語へと変換されたあげく、最後に〈青頭巾〉テーマが登場するという、とんでもない話。ぜひ『鬼』と併読をお願いしたい逸品である。
ちなみに我々の世代にとって、宇能鴻一郎といえば、筒井康隆編纂の名アンソロジー『異形の白昼』所収の「甘美な牢獄」なのだが、〈この世の地獄を描いて宇能氏の右に出るものはあるまい〉と筒井氏が太鼓判を捺す由縁は、表題作をはじめ「西洋祈りの女」「リソペディオンの呪い」などの本書収録作からも十二分に窺われるところだろう。
一方、鬼をテーマにした清新なファンタジイの新刊も。『星砕きの娘』で第四回創元ファンタジイ新人賞を受賞した松葉屋なつみの受賞第一作となる『星巡りの瞳』(創元推理文庫)は、前作と同じ、架空の〈敷島国〉を舞台とする壮大な架空世界譚。ただし時代は大きく遡り、古代日本を思わせる王朝小説となっている。
主人公の美丈夫・白珠は、将来は一国の主たることを期待される逸材だったが、ある事件によって右眼と宮城での地位をすべて喪失し、旧都「香久」へと放逐の身となる。
折しも、新都と旧都それぞれに、人の世の穢れから生まれた鬼たちが跳梁跋扈、白珠は数奇な縁で結ばれた美しき鬼の王「陽炎」を利用して、簇生する鬼たちを駆逐しようと試みるのだが……。
興味深いのは、しばしば「鬼」が「鳥」たちのアナロジーとして語られていることだ。そもそも、鳥の祖先は恐竜である、とする説は、いちがいに奇説とはいえず、なかなかに信憑性を有しているようなのだが、本書はこの仮説を、初めて小説に実践応用した好例となりそうだ。
そこで、ゆくりなくも想起されるのが……澁澤龍彦の遺作となった長篇『高丘親王航海記』である。巻末の名場面に顕われる少年の顔をした「うぐいすのような小さな鳥」しかり(鬼=鳥のアナロジー)、まだ見ぬ大陸へ向けて旅立つ主従の姿を描く余情纏綿たる幕切れしかり、二つの王朝物語の間には、いろいろと相通ずるところが散見されるように思われるのである。
アン・ラドクリフの代表作『ユドルフォ城の怪奇』上・下(三馬志伸訳/作品社)が、ついに日本語化された! 英国ゴシック文学に関心を抱く者なら、誰しも書名くらいは耳にしたことがあるだろう、伝説の大長篇である。なにしろ、あの夏目漱石が、英文学講義の中で早くも言及していたというくらい。邦訳の噂も一九七〇年代から、国書刊行会などを中心に囁かれ続けてきたものの、旧『幻想と怪奇』誌に、ごく一部の抄訳が載った程度で、その全貌は長らく神秘のヴェールの彼方に閉ざされてきた。
「刊行から二二七年を経て、今なお世界中で読み継がれるゴシック小説の源流」「不朽の名作として屹立する異形の超大作」といった帯文にも、本書を世に出す版元の自負と気概が感じられるだろう。
すでに同じ版元から『ヴィクトリア朝怪異譚』の訳書などがある三馬氏の訳文は、まことにツボを心得たもので、大変な長丁場を、よどみなく読み継がせる力を持っている。
とはいえ、巻頭から百ページを過ぎても、ヒロインのエミリーと、善良で薄倖な両親のまさしく〈ピクチャレスク〉な旅物語が、蜿々と続けられる展開は、読者サービス満点ないわゆるモダンホラー系作品を読み慣れた現代の読者には、いささか難物かも知れない。
私は前評判を参考に、覚悟を決めて(!)取り組んだので、ときおり古風な詩作品が挿入される典雅な展開に、「おお、これが音に聞くピクチャレスクかあ~」と嘆賞しつつ、読み進めることができた。
三馬氏の解説によれば、崇高と美のゴシック理論の構築者エドマンド・バークの影響をジャンルの始祖ホレス・ウォルポール以上に蒙ったのが、ラドクリフなのだとか。〈『ユドルフォ』における印象的な風景描写は、いわば恐怖を呼び起こすための絶妙な雰囲気作りという役割を果たしているのであり、その後今日に至るまで、風景描写をこれほど巧みに駆使して作品の効果を高めた作家はほかには見あたらない〉(本書解説より)
とにもかくにも、まずは虚心に読むべし!