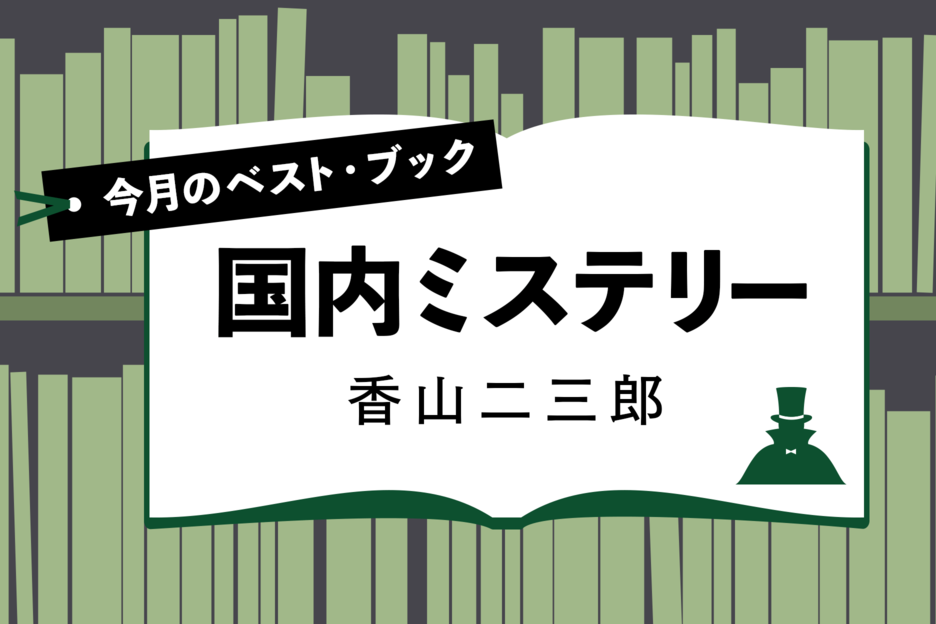今月のベスト・ブック
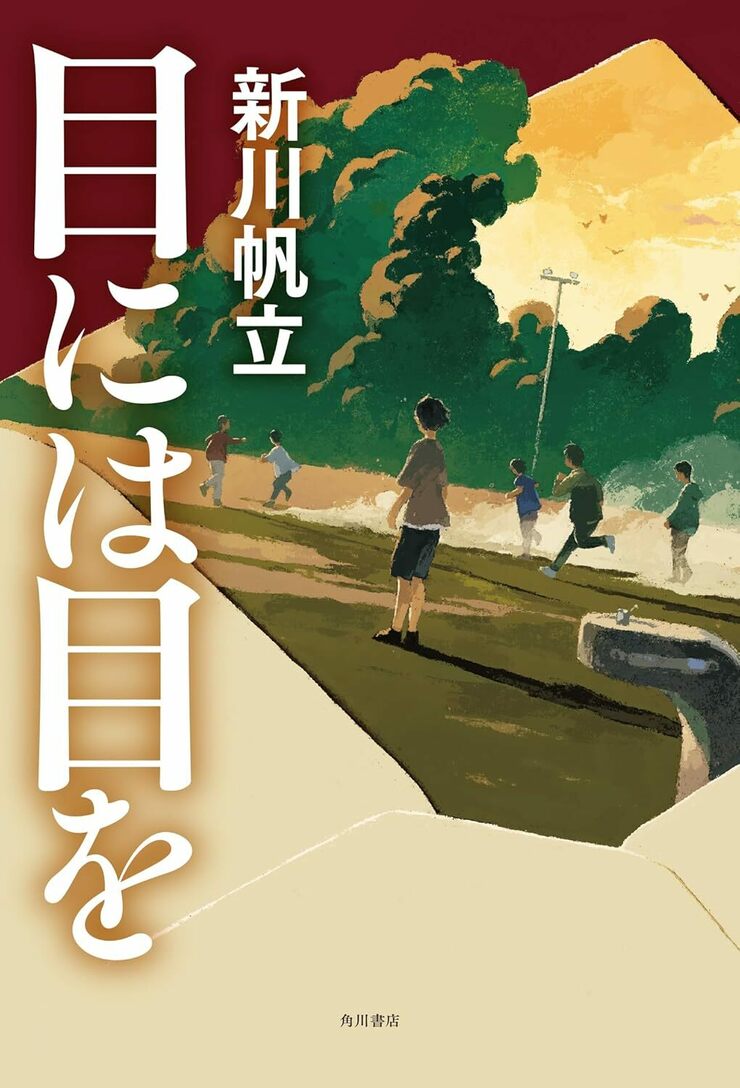
装幀=bookwall
『目には目を』
新川帆立 著
KADOKAWA
定価 1,870円(税込)
新人賞が取れるかどうかの鍵は基本がしっかりしているうえでどれだけ独自の趣向が打ち出されているかにかかっている! してみると今回(第23回)『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した土屋うさぎ『謎の香りはパン屋から』(宝島社)は不利だったといえるだろう。表題通り、大阪・豊中市のパン屋でバイトをする女子学生の姿を通して描かれた、誰でも楽しめる日常の謎系連作ミステリーだったから。
第1章はパン屋「ノスティモ」で働く市倉小春が同僚の由貴子と推しのライブビューイングに行く予定だったがドタキャンされてしまう。だが彼女は翌日、由貴子とバイトを替わったはずのレナ先輩の不審な受け答えやサーティワンの無料クーポンを無視したことから、ドタキャンの真相を見抜く。続く第2章はシフトを間違えたレナ先輩のヘルプに呼ばれたパティスリーの堀田紗都美がフランスパンの切り込み作業中に何故か固まってしまう謎に挑む。第3章では高校生のカップル客が大事なお守りにコーヒーを溢してしまった騒動を治めてみせるといった塩梅に、全5章ともパン屋をめぐる謎含みの出来事に対して、小春が毎度焼き上がったパンのように推理を膨らまして解決に導くという筋立てだ。
もちろんパン屋の話だから、物語に絡めて様々なパンがクローズアップされるし、どれもおいしそう。著者はプロの漫画家だが、小春も漫画家の卵という設定が効いている。日常の謎系ミステリーとしては完成度の高い1冊であるが、他では見られぬあざとい趣向に貫かれているかといえば、そういうタイプではない。そちらをお望みの向きにお奨めなのは、文庫グランプリ受賞作、松下龍之介『一次元の挿し木』(宝島社文庫)の方かも。
ヒマラヤ山中の湖で800人からの白骨死体が発見されるプロローグからしてインパクトは充分。本文に入っても主人公・七瀬悠が大ハンマーを抱えて葬儀に乗り込み棺を叩き潰すという荒業を披露してのける。もっとも棺の中は空なんだけどね。悠は4年前に行方不明になった義妹の紫陽を捜し続けていたが、日江製薬代表取締役の義父・京一は娘の葬式を上げようとしたのだった。その後、遺伝人類学を学ぶ悠は大学院の担当教授・石見崎からヒマラヤの湖で発掘された200年前の人骨をDNA解析にかけるよう依頼されるが、解析の結果、紫陽のものと一致した。悠は石見崎と相談すべく彼のもとを訪れるが、彼は何者かに殺され、研究室から古人骨も盗まれてしまう。悠は石見崎の葬儀で出会った姪の唯とともに真相究明に乗り出すが……。
つかみは万全。その後も短めな章立てで、ちゃぽんと音をたててポリタンクを運ぶ謎の大男・牛尾を随所で登場させたり、新興宗教・樹木の会を見え隠れさせたり、昭和の臭いを醸し出すジャーナリスト・平間を噛ませたりしながらリズミカルに展開していく。著者は執筆歴は浅いそうだが、ネタの古さが気にはなるものの、瀧井解説も褒めちぎっているように、確かにこれだけ書けていれば、将来性には期待が持てよう。土屋作品ともども、ぜひ。
今月はこのミス大賞大会ということで、3冊目はこのミス大賞の先輩受賞者の新作、新川帆立『目には目を』(KADOKAWA)。
少年Aが別の少年Xに暴行を加え死に至らしめた。15歳10カ月のAは検察官送致を免れ少年院に送られ、17歳の春に退院した。退院後は土木作業員として働き始めたが、勤務態度は悪く、半年後には仕事に出なくなった。欠勤が2カ月続いたある日、雇用主が部屋を訪ねると、そこにはAの遺体があった。容疑者はすぐに自首した。少年Xの母親だった。動機は復讐。事件はハンムラビ法典の一節を取って「目には目を事件」と呼ばれた。
本作はその事件に材を取り、Xの母がAと同時期に少年院ですごした少年Bの情報提供でAの所在を特定することに成功したことに着目、その密告者Bを洗い出そうとした犯罪ノンフィクションという体裁を取っている。
かくして基本は少年院にいた6人の少年の話が軸になる。人懐っこくて少年院の日々を楽しかったと語る大坂将也、幼馴染の娘に根は優しいと言われる大男の堂城武史、高IQゆえに生きづらいと語るシステムエンジニアの小堺隼人、マルチ商法にはまり高級車を乗り回す進藤正義、猟奇殺人犯として日常生活をアップする動画配信者・雨宮太一、そして少年院では無言を通した対人恐怖症の岩田優輔。皆、一見社会復帰を成し遂げたようで、実は歪みや欠落を留めたままであることが次第にわかってくるが、著者はただ彼らの談話を並べていくのではない。
途中で職員の話を挿入したり、セラピードッグ「きらら」殺害事件の謎をまじえたり、各種会のエピソードを入れ込んだりしながら話を膨らませていくのだ。その間合いを計った筆致が何とも素晴らしいが、何より少年6人の描き分けがきちんとなされていることが大きいというべきか。皆が皆、言っていることとやっていることが違うだろう、というか、内面と外面との齟齬が大きいというか、それはやがて語り手にも跳ね返ってくることなのだが、詳しくは本文にてお確かめを。
少年審判テーマのシリアスなリーガル・ミステリーとして、また小説内小説の手法を存分に生かした本書はまさに新境地を開く1冊と呼ぶにふさわしい。今月はこれにて決定!