今月のベスト・ブック
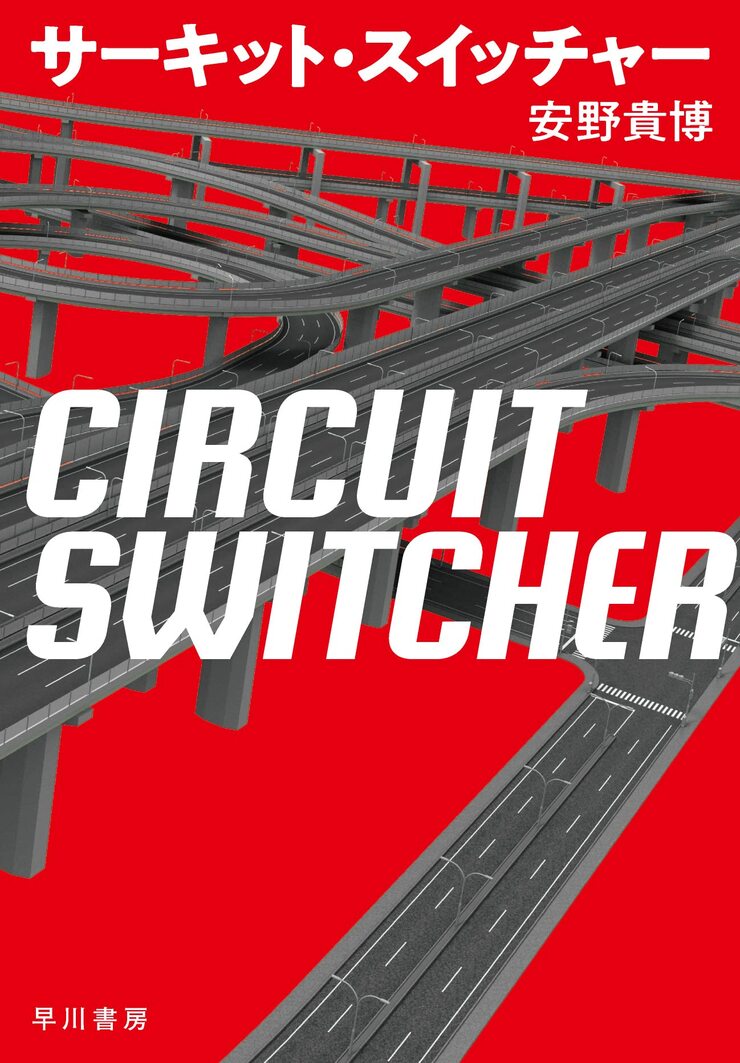
装画=Rey.Hori
『サーキット・スイッチャー』
安野貴博 著
早川書房
定価1,870円(税込)
さして興味のなかった北京冬季五輪だが、いざ始まるとやはり見てしまった。選手の技量といい撮影技術の進歩といい、どれも神業に近いが、もちろんそこには道具の力に因るところも大きいのだろう。そこで今月のベストミステリー選びも、まずはスポーツ道具にまつわる作品から始めようかと思ったけど、その前に1冊。宮内悠介『かくして彼女は宴で語る 明治耽美派推理帖』(幻冬舎)は、明治末期に実在した若き芸術家たちのサロンで繰り広げられる推理合戦の顛末を描いた連作集だ。全6話を収録。
1908年(明治41年)12月、医学を学ぶ傍ら詩や劇作で活躍していた木下杢太郎は仲間とともに新たな芸術運動を興すべく隅田川沿いの西洋料理屋「第一やまと」に集い、第1回〈牧神の会〉を開いた。北原白秋や吉井勇、石井柏亭、山本鼎等、芸術に憑かれた若き才能が談論風発する中、やがて3年前団子坂で起きた怪事件が話題に上る。菊人形が公衆の面前で“殺された”というのだ……。
第1話からヒネリのきいた不可能犯罪(!?)が呈示されるが、杢太郎たちの推理は迷走するばかり。そこで意外な名探偵役が登場するのだが、誰かは読んでのお楽しみ。普通の謎解きものと味わいを異にするのは、加害者、被害者の動機付け。医学に進むか、芸術の道に進むか迷い続ける杢太郎の苦悩とリンクさせた心理の解析が読みどころだ。また第3話や第5話、第6話は禁忌扱いされがちな当時の流行病や防疫を題材にしており、コロナ禍の現代を直撃している点でも読み逃せない。
さらに毎回杢太郎たちに饗せられるオリジナルな料理の数々も楽しみ。美食ミステリーとしても読み応えありだ。各篇の末尾に付された「覚え書き」で本書がSFの巨匠I・アシモフの『黒後家蜘蛛の会』の形式を借りていることが記されているが、けだしアシモフ小説にはない著者ならではの趣向に溢れた明治ものに仕上がっていよう。
ということで、スポーツ道具にまつわるミステリーに移ると、長浦京『アキレウスの背中』(文藝春秋)は公営ギャンブルの対象になった近近未来の東京マラソンを題材にしたサスペンスだ。都市マラソンを扱った対テロ活劇は今や珍しくも何ともないが、本書は細部が並みの作品とは大いに異なる。
2023年3月、政府認可の公営ギャンブル対象マラソン第1号、東京ワールド・チャンピオンズ・クラシック・レースが開催されることに。スポーツ・ビジネス界はIoC系と中露サウジアラビア系の新興勢との対立が続いていたが、そんな中、日本のスポーツメーカーDAINEXの推す日本人選手・嶺川蒼に今後競技会に参加するなと書かれた脅迫状が届く。警察庁は現代犯罪に対応すべく、各部署から特別編成した組織横断チームMITを立ち上げていたが、今また警視庁捜査三課の下水流悠宇警部補以下3名のチームを招集、DAINEXに派遣する。
国際スポーツはもとより、スポーツ・ビズ界の取材が行き届いており、シューズやウエアの開発って今ここまで進んでいるのかと感心することしきり。警察小説としても、縦割り、男尊女卑、所轄署との対立等、旧態依然の現状とそれを改善すべく新たな動きがつぶさにとらえられている。スパイ小説的な展開の中盤から後半は対テロアクションへと移っていくが、テロリストの手口も狙撃や爆弾を使った従来の犯行から新たなものへと変わっていて新鮮。ヒロイン像も元スポーツ選手で日本舞踊の師範であるなど凝っていて、とにかく独自性に富んでいる。このジャンルのファンには読み逃せぬ快作といっておく。
もう1冊も近近未来もの。安野貴博『サーキット・スイッチャー』(早川書房)は第9回ハヤカワSFコンテストの優秀賞受賞作。
2029年、日本は完全自動運転車が普及していた。そのアルゴリズムを開発した天才、サイモン・テクノロジーズ社社長・坂本義晴がムカッラフと名乗る男に襲撃される。男は自動運転車に坂本を監禁、尋問を始める。
完全自動運転(車)という道具立てはSF的だが、ストーリー的にはサスペンス、それも社会派ミステリータッチなので最新科学に疎い方も恐れるに足らず。
ムカッラフは坂本を殺人犯呼ばわりし、尋問する様子は動画配信サイトを通じて全世界に中継されていた。男は車が走る首都高の全面封鎖を要求、また車に爆弾を仕掛け、配信が停止されたら爆発すると脅す。一方、車にはねられ歩行障害者となった安藤太一警部補は上司の計らいでその捜査に参加することに。安藤は動画を配信するMe Tubeの岸田マリに会い、配信停止を求めるが……。
イスラム系のテロリストと思われたムカッラフだが、その正体と犯行動機は意外なものだった──いや、意外でも何でもなく、すっごく古典的なのだが、古典的であるからこそその悲劇性も際立つというものだ。自動運転は人が運転するより事故は少なくなるそうだが、それでもゼロというわけにはいかない。そこをアルゴリズムはどうしのいだのか。科学の進歩の盲点を突いた着想に拍手。むろん高齢者によるブレーキ操作の誤りが引き起こす人身事故が後を絶たない今、本書が描き出すのはまさしく、日常的な、すぐそこにある危機にほかなるまい。
今月は大接戦だが、困ったときは新人有利というわけで、BMは安野作品に進呈。




