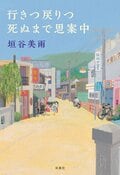小さな村の物語イタリア
先日、友人と会ったとき、BSテレビ番組「小さな村の物語 イタリア」を見たことがあるかと尋ねられた。
見たことがあると私が答えると、友人は言った。「僻地と言ってもいいくらいの田舎なのに、どの家の台所もなんであんなに清潔そうなんだろうね」
それは、まさに私が長年に亘り疑問に思ってきたことだった。田舎と都会の台所では、清潔感に大きな差があると考えていたのは私だけではなかったらしい。
この番組は、イタリアの小さな村々を巡って人々の暮らしを丁寧に追うものだ。放送が始まって既に二十年近くになるから、観たことのある人は多いのではないかと思う。
映し出される光景は、漁村だったり、雪に覆われた寒村だったり、山奥の村だったりと様々だ。イタリアの田舎の風景は美しい。四季折々の花が咲き、木々に果物がたわわに実り、犬や猫は自由に野山を駆け回っている。
そして一般家庭の台所にもカメラが入り、女性たちが料理を作る様子が映し出される。どの家の台所も惚れ惚れするほど素敵で可愛らしい。
私が田舎から上京して最初に驚いたのは、東京に住む人々の台所の清潔さだった。田舎者から見ると潔癖症と言ってもいいくらいで、流し台や調理台やガス台などは照明に反射して輝くほどだった。
当時は、さっと拭けばきれいになるガラストップのガス台などはなかった。少しでも掃除をさぼると、すぐに油がこびりついたり錆びたりする材質だった。それなのに東京に住む親戚や知人の家の台所はピカピカなのである。電子レンジに至っては、庫内に汚れひとつなく、昨日買ったばかりかと思うほどだった。
だが、イタリアでは山奥にある古い家であっても台所が清潔なのだ。ダイニングキッチン形式になっていて、流し台のすぐそばに、食事をするテーブルが置かれている。
一目見て使いやすそうだとわかる。棚もオーブンも作りつけで、日本の台所とは違い、棚などが手の届く低い位置にある。タイルや窓枠の色までがきれいで、棚の扉には彫刻が施されていておしゃれだ。
花柄のきれいなカーテンやテーブルクロスを選んだのは女性だろう。だが家の設計や建築のほとんどは、男性の手によるものだったのではないか。だとすれば、台所の造りを見ただけで、どれほど女性の意見を事細かに聞き、それらを取り入れて設計したかがわかる。それはつまり、女性がいかに大切にされてきたかを表しているのではないか。
清潔さに関しては、近代化されてからの歴史が、日本よりずっと長いからだろうと、私は勝手に結論を出した。
日本の台所は、戦前までは土間にあることが多かった。薪を使って煮炊きしたり、井戸から水を汲んできて大きな甕に溜めておいたりするから、床を張らず土足でなければならなかった。木造家屋だから、家の中で火を扱うのは危ない。囲炉裏や暖を取るための火鉢がせいぜいだったろうと思う。
テレビドラマなどで、外気温と大差ない真冬の土間で女性たちが料理を作る場面を目にすることがある。座敷とは違って、下が土となれば清潔を保つにも限界があるし、半分は屋外にいるような感覚だから、清潔観念も緩いだろう。
電気やガスが普及し、水道が家の中で使えるようになり、それが都市部だけでなく、農村や漁村にもだんだんと広がっていく。テレビのない時代では、文化的なものや新しい生活様式や考え方が、地方にまで行き渡るには時間がかかっただろう。そんな時代が、イタリアでは日本よりずっと早くに到来した。国全体が豊かになってからの年月も、日本よりずっと長い。
こういった、田舎と都会の台所の清潔さの違いの変遷というようなことを研究した文献があったら、是非とも読んでみたいと思う。
そういう私も、今や電子レンジは買ったときと同じくらいとまではいわないが、かなりの清潔さを保っている。調理が終わって扉を開けたとき、庫内に蒸気が充満して水滴がついているのを見たら、これぞチャンスとばかりにキッチンペーパーでさっと拭く。ただ単にそれだけのことだ。汚れているかどうかを見る間もない。たった数十秒で終わることなのに、それが習慣となるまでには時間がかかった。
「もう一つ不思議に思うのは、娯楽もないのに、どうしてイタリアの田舎の人たちはみんなあんなに楽しそうなんだろう」
私の疑問に対し、今度は友人が、「そうそう、それ」と同意した。
オープンカフェには朝早くから地元の高齢者たちが集まり、隠居の身なのか、のんびりとコーヒーを飲みながら世間話をしたり、チェスを楽しんだりしている。
ナレーターによると、いったん村を離れて都会で就職したり、学校に進学したりした若者も、Uターン希望者が多いという。
今ちょうど、二束三文でも売れない日本の田舎の空き家についての章を書いているところだ。それもあって、田舎暮らしの魅力の有無や違いはどこにあるのかが気になった。
東京一極集中はますますひどくなり、地方では仕事が見つけられないと聞く。だがイタリアの田舎も仕事がそれほどあるようには見えなかった。いくつものアルバイトを掛け持ちして生計を立てているシングルマザーも紹介されたが、彼女もまた人生を楽しんでいるように見えた。
言い換えれば、アルバイトを掛け持ちする程度でも十分生活できるのかもしれない。大学の授業料がとても安いから、子供の将来に不安を覚えることもないのだろう。
イタリアの村々には陰湿さがまるでないように見えるのは、私の錯覚か、それとも笑顔ばかりを映すカメラワークのせいなのか。それか、インドでの葬式の様子を映したドキュメンタリーを見たばかりだったからか。
インドに住むある男性は、明日の食事にありつけるかどうかを心配するほど貧乏なのに、父親が亡くなると、莫大な借金をして盛大な葬式をした。そうしないと、子々孫々まで村の人々に馬鹿にされ続けるからだ。
そこには田舎ならではの助け合いとか、お互い様というような温かい空気は欠片もない。
葬式があると聞けば、故人と面識のない人々までが一家総出で押しかけてきて、滅多にありつけないご馳走を食べ、酒を飲みまくる。まるでお祭り騒ぎといった調子で、故人を悼む雰囲気などまるでなかった。
どの国でも、豊かさを享受する以前は、これと似たような暮らしがあちこちにあったのだろうと思う。インドでも超富裕層となれば桁違いの贅沢ぶりだ。
二〇二四年の世界のGDPランキングでは、日本は四位でイタリアは八位だった。様々なハイテクの分野でも日本は先んじているように思っていた。
だが、イタリアの田舎には、経済的な数値では測れない成熟した社会があるように思える。真の豊かさとは何かを考え直してからの歴史も長いのだろうか。
ちなみに二〇二五年のGDPは、日本は現在五位のインドに抜かれるらしい。