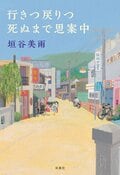睦月如月の復活を望む
いったい誰が睦月を一月にし、如月を二月にしたのか。
趣のある美しい月名なのに、残念で仕方がない。
それを考え始めたのは中学生の頃だった。英語のJanuary、Feburuary、March……月名のひとつひとつに語源があり、意味があると知ったのがきっかけだった。日本語の一月、二月、三月の呼び名の味気なさに気づいて愕然としてしまったのだ。
調べてみると、変更されたのは一八七三年(明治6年)だという。英語と同じように、それまでは意味のある月名だったのに、簡単な方がいいとでも思ったのか。
それとも、明治維新で和暦から太陽暦(グレゴリオ暦)に改暦されたときに、和風月名のままだと実際の季節感と合わないからと判断したのか。
季節感がずれるのならば、月名をずらすなりして、いくらでも工夫できるのにと思うと、再び悔しさが込み上げてくる。
月名の由来は諸説あるらしいが、例えば一月の「睦月」なら、睦び、親しくするという意味がある。正月に家族や親類が一同に集まって新年を寿ぎ、お祝いする月には相応しい。
こういった意味を知っていると、味わい深いし、覚えやすい。
二月の「如月」は、衣更着とも書き、着物を重ね着する寒い月という意味だ。
三月の「弥生」という名前の知り合いが私にも何人かいる。春の最後の月で、「弥」は「いよいよ」という意味だ。草木がいよいよ生い茂ってくるのを表しているらしい。
四月の「卯月」からが夏となる。白い可憐な「卯の花」が咲く季節で、その木を「うづき」と呼ぶ。実際には卯の花が咲くのは初夏の五月から六月であるらしいから、こういうところが太陽暦とずれているのかもしれない。
五月の「皐月」は、田んぼに植える苗を「早苗」といい、その作業をする時期として「早苗月(さなえつき)」。それが短縮し、「さつき」になったという説がある。
私が書く小説の主人公には、五月という名の女性が多い。そのことに気づいたのは、渡辺えり・高畑淳子主演の舞台『喜劇 老後の資金がありません』を観に行ったときだった。
義姉が「サツキさんっ」と厳しく詰め寄る場面で、「あれ? 今書いている小説の主人公も五月じゃなかったっけ」と思い当たり、自分でも驚いてしまったのだった。
登場人物が昭和世代となると、「子」がつく名前が圧倒的多数だ。似た名前ばかりだと読者が混乱するのではないかと気になり、「子」がつかない名にしようとする。だけど、今どきのハイカラな名前では昭和世代としてリアリティがないしなあ……などと考えると、行きつく先が「五月」なのだった。
六月の「水無月」は、夏の最後の月だ。梅雨なのに「水が無い月」とはどういうことかと、中学時代には疑問に思った。「無」は「の」の当て字らしい。田んぼに水を入れる月なので「水の月」なのだという。
七月の「文月」からは秋となる。稲の穂が膨らむのを見る月だから「穂見月(ほみづき)」と言い、それが変化して文月になったという説がある。その一方で、七夕には短冊に文字を書き、字の上達を願う節句でもあったことから、「文披月(ふみひらきづき)」となったという説もある。
世の中には、字の上手い人と下手な人がいる。努力の結果ではなく、視覚的センスとでもいうのか、つまり、生まれつきだとしか思えない。
どんなに下手な人でも、書道の先生に習いに行っている間は、まあまあの字を書く。だが、あくまでも「まあまあ」の域を出ない。習いに行くのをやめると、しばらくすると元の字形に戻ってしまう。
私の知人の中にも、惚れ惚れするような字を書く人が何人かいる。だが、習いに行ったとは聞いたことがない。そして驚くのは、年齢とともに、誰に教えられたわけでもないのに、味のある大人っぽい続け字に変化してくることだ。
それを考えると、絵を描くことや運動神経などと同様に、天性のものとしか思えないのだが、間違っているだろうか。
八月の「葉月」も、女性の名前にある。秋も半ばで中秋だ。木々の葉が落ちる「葉落ち月」が変化したという説がある。
九月の「長月」は、夜の長さのことを言う。夜が長くなり、月を眺めるようになる時期だ。
十月の「神無月」は、日本全国の神様たちが、出雲大社に出向いて人々の幸せの縁を結ぶ神々の大会議がある。そのため出雲地方では「神在月」、それ以外の地方では「神無月」となるのはよく知られている。十月生まれで「カンナ」という名前の知り合いがいる。
十一月の「霜月」は、霜が降りる月だ。この名前の喫茶店を知っている。
十二月の「師走」だけは「月」がつかない。冬に家々で僧侶を招き読経や仏事を行う習慣があり、この月だけは多忙で走り回るという説がある。
ああ、こんな素晴らしい月名があるのに、一月、二月、三月なんて、何と味気ないことでしょう。
悔しさが込み上げてきたときは、日月火水木金土が残っているだけでもマシじゃないかと自分を慰める。中国では曜日も一、二、三……なのだ。
町や公立学校の名前を見ても、残念でならないと思うことがある。
公立中学校は、○○第一中学、○○第二中学、○○第三中学……と続く。
どうしてこんなに個性のない名前にしてしまったのだろう。役所が整理しやすいからだろうか。最低でも地名をつけるなど工夫して、もう少し血の通った名前にできなかったのか。
卒業後も母校に愛着が持てる名前にすればよかったのにと、これも悔しくてならない。とはいえ、私自身が卒業した小中高ともに、こういった事例には該当しないので、大きなお世話なのだが。
少子化により、公立小中学校の廃校や併合が相次ぐようになったのは二十年以上も前からだ。「第一」から順番に名前をつけたのに、廃校などで途中の番号が抜けることはないのだろうか。
そして町名だ。○○一丁目、○○二丁目、○○三丁目……と続くのだ。
だが、私の住む街の周辺では、戦前からの町名が残っている。
戦後の整理統廃合を、当時の住民が猛反対したらしく、昔そこに何があったかを想像させる趣のある町名のままだ。
車のない時代だったからか、一つ一つの町の面積は小さい。都内であるにもかかわらず、一つの町に家が数十軒しかないため、郵便番号さえ書けば、あとは番地だけで郵便物が届く。
こういった町名は今後も残してもらいたい。もうこれ以上、昔の名前をなくさないでもらいたいと思う。
役所で命名権を持つエライ人は、効率ばかりを追う切れ者ではなくて、歴史や文化を大切にする人であってほしい。