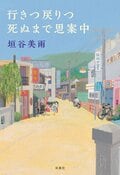インド旅行 その二
インドに行ってみて衝撃を受けたのは、貧しい子供たちの姿だった。
インドには歴然と貧富の差があった。何を今さら、そんなのわかりきったことじゃないか。そう思う人も多いだろうが、今まで行った他の貧困な国と比べて、子供たちの無為な一日の過ごし方を見て、何とも言えない悲しい気持ちになった。
インド憲法によって、カーストによる身分差別は禁止されたが、現在でもはっきりと残っている。そのことは、インド人の男性ガイドが「この職業はバラモンしか就けません」などと説明することからもわかった。
スジャータ村に行ったときのことだ。
お釈迦様が山の中で六年間修行し、衰弱した身体でその村にやってきたとき、スジャータという娘が、お釈迦様に乳がゆを与えたところ、みるみる体力が回復した。その後、お釈迦様はブッダガヤの地で悟りを啓いた──そういった逸話に由来する有名な村である。
その寺院へ向かう道の両脇には、子供やその母親たちが地面に寝そべっていた。観光客が通るたびに、寝そべった姿勢のまま手を出し、お金か食べ物を恵んでくれとせがむのだった。
誰かがお金かお菓子を差し出すと、いきなり一斉に立ち上がって激しい争奪戦となる。それらの機敏な動作を見る限りでは、身体は元気であるようだった。だが、観光客が通り過ぎてしまうと、また寝そべるのだった。
この子供たちの姿を見て、私は心が痛んだ。他国の貧困な子供たちに比べたら、知恵も工夫も見られなかったからである。
例えばモロッコに行ったときは、子供たちは葉の茎で編んだラクダの人形などをたくさん作ってきて、それを観光客に売ろうと必死だった。
いつか見たテレビ番組でも、南米の国ではボールが手に入らない貧困な暮らしの中で、紙や布を丸めてボール代わりにし、子供たちはサッカーに励んでいた。
このスジャータ村のように、日がな一日無為に過ごしている子供たちを、これまで見たことがなかった。たぶん家の手伝いもしないのだろう。
そもそも母親も一緒に寝そべっているのだから、家事というものがほとんどないのではないか。掃除、洗濯、料理のいずれもやらないのかもしれない。というのも、風呂に入る習慣も、衣類を洗濯する習慣もなさそうに見えた。何ヶ月も顔さえ洗っていないようだった。衛生観念だけでなく、料理を作る知恵も道具もないのかもしれない。
日本にも貧乏な時代があった。戦前戦後の苦しい時期もあった。だが子供が数人も集まれば、鬼ごっこやかくれんぼなどをして遊んだはずだ。
たとえボールや遊具がなくても、たくさんの遊びがあった。しりとりをしたり、みんなで歌ったり、じゃんけんをして「チ、ヨ、コ、レ、イ、ト」、「グ、リ、コ」、「パ、イ、ナ、ツ、プ、ル」などで誰が一番早く到着するかを競ったり、「花いちもんめ」をしたり、「夏も近づく八十八夜」などの手遊びもしたし、棒で地面に顔を描いて、じゃんけんで負けた方が口や鼻をひとつずつ消していって全部消えたら負けというような単純な遊びをした覚えもある。数え上げたらきりがないほどだ。
紐が一本あれば、あやとりをし、紙が一枚あれば折り紙をした。ゴムが一本あればゴム跳びをする。硬い紙が手に入ればメンコを手作りした男の子もいただろう。子煩悩な大人がいれば木片で独楽を作ってくれたこともあっただろう。
母親が家で内職をしていれば、それを手伝う子供もいたし、家事や農作業や商売などの家の仕事を手伝った子供も多かった。
そういった日本の暮らしの中で育ってきたから、子供の頃から何もせずに一日を過ごす姿に衝撃を受けたのだった。
自分以外に子供が一人もいない環境というのならわかるが、同年齢の子供がたくさんいて、そして互いに身体をくっつけ合うほどそばにいるのである。
百歩譲って、聡明な子は頭の中ではいろいろ考えているだろうし、観光客のちょっとした行動や言動から様々なことを学んでいるに違いないとは思う。だが、その学びの量が少なすぎると思うのだ。
たわいのない遊びから、子供はたくさんのことを学んでいく。ゲームの楽しさを知ったり、ルールを学んだり、走ったり隠れたりしながら全身運動をすることにも繋がる。そのうえ、仲間同士でコミュニケーションを図り、譲り合い、助け合う大切さを知るだろう。
帰国後、インド映画『花嫁はどこへ?』を観に行った。そこには貧困や差別、識字率の低さ、賄賂の横行が当たり前といった社会で暮らす人々が描かれていた。そんな中で、人々は少しずつ自由や権利に目覚めていく。私の中では、久々に感動した映画だった。
その映画を観てからは、私がインドで見た子供たちも、人生のどこかで挽回できる日が来ると信じたくなった。今は何もしない日々でも、大人になって働くようになれば、否が応でも様々なことを知るだろうから。
私自身も、年齢とともに体力がなくなったせいか、気づけばぼうっと何もせずに過ごしていることがある。
それまでの多忙な生活では、常に時間を大切にし、一分たりとも無駄にしてはならないと思って暮らしてきた。
自発的にそうしてきたように感じていたが、たぶん世間の空気や、周りの人々の影響だったのだろう。だからここにきて、その落差が激しく、ぼんやりしている自分に落胆することが増えた。
こんな生活じゃあダメだ。もっとちゃんとしなくちゃ。
そう強く思う一方で、この年齢になれば、既に引退して働いていない人も多いのだし、ゆったり無為に過ごしてもバチは当たらないのではないかと、自分を慰めたりすることもある。
だが、時間の無駄遣いに罪悪感を覚えてしまう習性は、たぶん死ぬまで治らない気がしている。
インドの子供たちを見て、上から目線で勝手に心を痛めているのも、大きなお世話なのかもしれない。自分を基準として考えているだけだ。
インド旅行の参加者でグループLINEが作られた。それぞれが撮った写真を共有するためだ。
そこで私は、今後の旅行の予定を尋ねてみた。すると、インドから帰った翌週から海外へ行く猛者もいた。他にも、翌月や翌々月から海外旅行の予定を入れている人が複数いた。
私と同い年の男性参加者は、LINEにこう書いてきた。
──明日死んじゃうかもしれないし、あさって認知症になっちゃうかもしれないので、五年以内に世界中を回ります。
それを読んで、私も身体が動くうちに、日本国中、そして世界中を旅したいと思うようになった。
旅行のためと思えば、節約もまた楽しい。