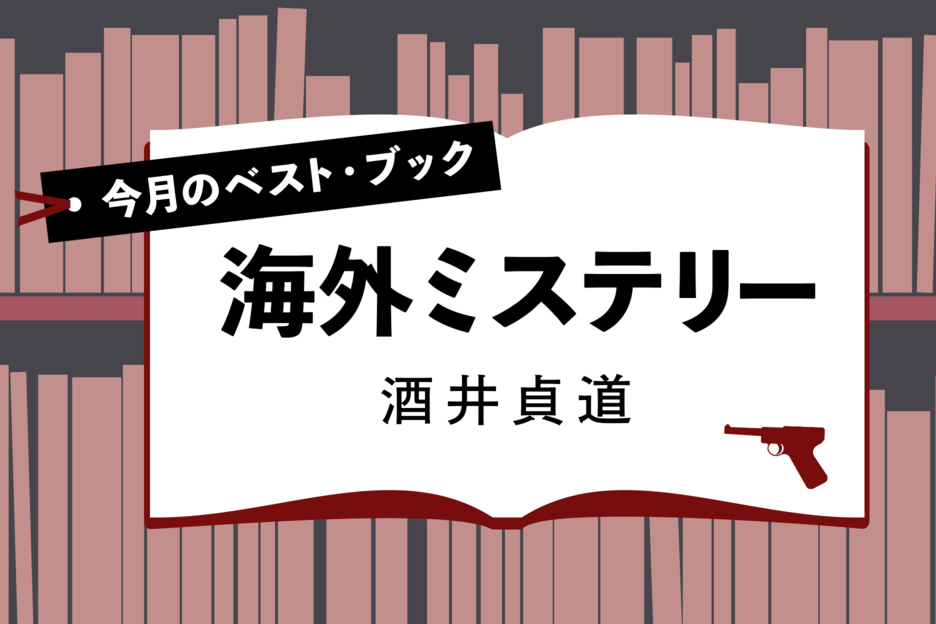今月のベスト・ブック
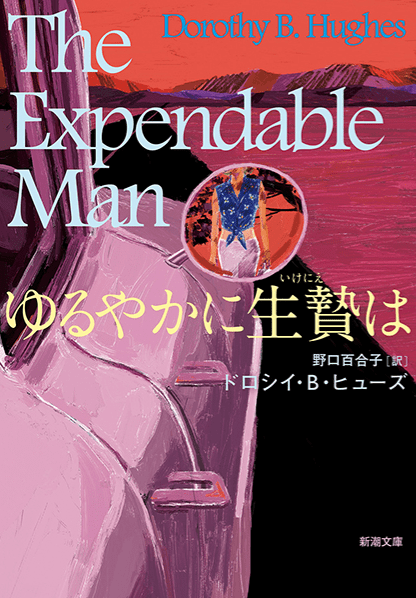
装幀=新潮社装幀室
『ゆるやかに生贄は』
ドロシイ・B・ヒューズ 著
野口百合子 訳
新潮文庫
定価 1,045円(税込)
今月は、小説の肝になる部分に触れると即ネタバレになる作品が多い。よって、有意なことが何も書けないか、書けても妙に抽象的になるかだ、書評家泣かせの月と言える。
ベスト・ミステリのドロシイ・B・ヒューズ『ゆるやかに生贄は』(野口百合子訳/新潮文庫)からして、肝心なところが書けない。1963年発表のこの物語では、ヒッチハイクで拾った若い娘に、青年医師ヒューが堕胎を依頼される。とんでもないと断って追い返したところ、翌日その娘が死体となって発見される。前日に彼女と一緒にいたところを目撃されていたヒューは、容疑者として警察に目を付けられてしまうのだ。ということで、この物語のプロットは、濡れ衣を着せられた主人公が、自分で疑いを晴らそうと頑張る、というものだ。ヒューに協力する頼もしいメンバーも登場し、緊張感溢れる展開もある。非常に上質なスリラーである。しかしこの小説は、それだけに留まらない、中盤で明かされる、ある事実によって、小説としての性質が、がらりと変わるのだ。
この急転は、小説の中身には影響するが、外面には影響を及ぼさない。世界は反転しない。プロットにも変化は生じない。主人公が濡れ衣を晴らすため努力する状況はそれまでと同じように継続する。しかしその意味合いが全く変わる。どう変わるのか? 62年後の現代の文明社会に、深く鋭く突き刺さるようにだ。書けるのはここまで。
しかし内容を詳解できない度合いは、『ゆるやかに生贄は』よりも、ピーター・スワンソン 『9人はなぜ殺される』(務台夏子訳/創元推理文庫)の方が高いかもしれない。アメリカに住む九人の老若男女(相互に知り合いでもない)に、彼らの名が記されたメモが送られてくる。そして、その九人が一人ずつ殺されていくのだ。彼らの中にFBI捜査官が含まれていて、全米各地の殺人事件情報を知る立場にある彼女がいち早く、連続殺人の発生に勘付く。しかし、メモには名前しか書かれておらず住所等はわからないので、捜査サイドは彼らがどこの誰なのか特定することから仕事を始める。地味である。一方、他の8人にも、小説はそれぞれパートを割り振っており、物語全体は群像劇的な展開を辿る。
どういう事件なのかが全くわからない状態が非常に長く続く。作中ではアガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』や『ABC殺人事件』がネタバレ付きで触れられており、この2作品に似た構図の事件であると匂わせてはくるが、これ以上のことは終盤にならないと書かれない。中盤まで五里霧中のミステリは多いけれど、本作はやり過ぎなほどで、普通なら途中で退屈してもおかしくない。でも読ませるのだ。群像劇を織り成す各人の描写が上質だからだろう。また、彼らに終焉をもたらす殺人シーンが、本当にいきなり起きて、定期的にギョッとさせてくるからでもある。不条理劇めいた死の訪れは癖になる。……書けるのはここまで。読者は必ず「これ、そういう話だったのか」と驚くことになるが、その内容は、もちろんここでは一切言えない。小説に翻弄されたり困惑したりするのが好きな人にはオススメだ。
物語に翻弄される度合いは、キャサリン・ライアン・ハワード『罠』(髙山祥子訳/新潮文庫)も大概である。主人公ルーシーは、妹が1年前に失踪している。妹は連続誘拐事件の被害者の1人と目されていた。やがて、犯人の魔の手から逃れてきたと主張する女性が発見され、事態は動き始める。ルーシーは他の被害者の家族と連携を取って、自力で妹を捜し始める。ルーシーの必死さがゆえに、物語は徐々に、この手の設定から推測される「常道」からずれていく。このずれ自体が読みどころであり、だからこそ、これ以上は書けない。最終的にはとんでもない所にまで行ってしまうが、それが何かも当然ながら書けない。衝撃的なのは保証できる。
サリー・ヘプワース『グッド・シスター』(梅津かおり訳/小学館文庫)も企みに満ちたスリラーである。結婚後も子どもができないことに悩む姉ローズを助けるため、図書館員ファーンは自分が代理母になったら良いと考える。ファーンは何らかの発達障害(恐らくASD)であり、悪気はないものの突拍子もない言動をよくとる。幼い頃から、そんなファーンをローズがフォローする生活だったようで、姉妹の絆は強い。それが、主に過去を振り返るローズの手記から明らかになっていく。話が進むにつれて、読者が展開や真相を推測できるような材料が増えていく展開を辿るため、この作品も実はこれ以上は書けない。驚くべき真相を知った後に読み返すと、構成がしっかりしているのがよくわかる。
最後に、今月唯一、書評家泣かせではない作品ケン・ジャヴォロウスキー『罪に願いを』(白須清美訳/集英社文庫)に触れておく。舞台はインディアナ州のうらぶれた田舎町(いわゆるラスト・ベルト地域)で、①火災現場で大金を見つけてネコババした男、②標準医療を受けさせてもらえず末期がんで余命幾ばくもない少女に同情している看護師、③妻と娘を同時に亡くした元不良の男が、それぞれ、皮肉な運命に満ちた顚末を辿る物語である。悲劇も喜劇も温かく描写されており、心に沁みる。と同時に、アメリカの田舎に漂うむせ返るばかりの閉塞感が、今のアメリカの闇を形成しているとも思う。必読。