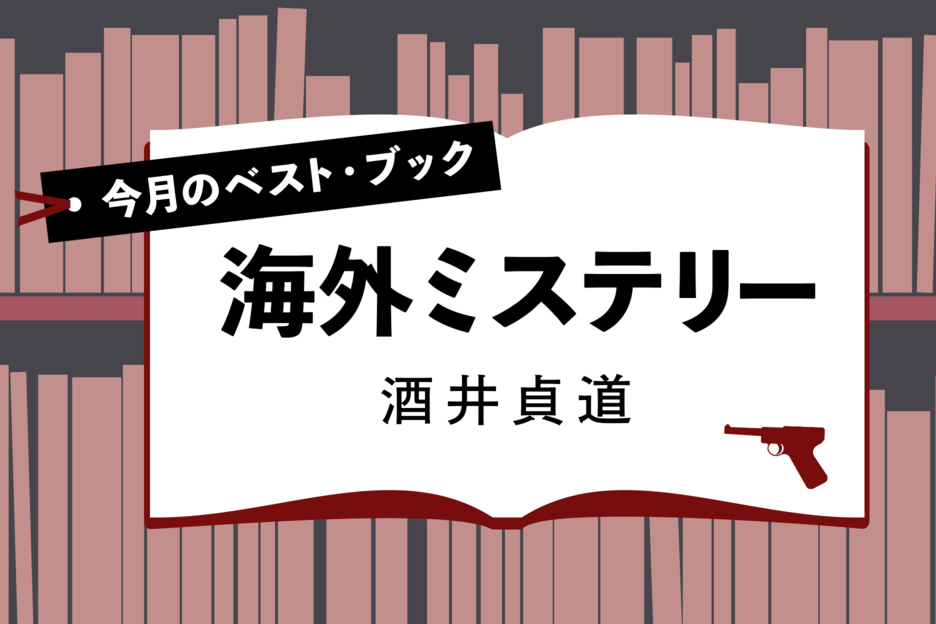今月のベスト・ブック
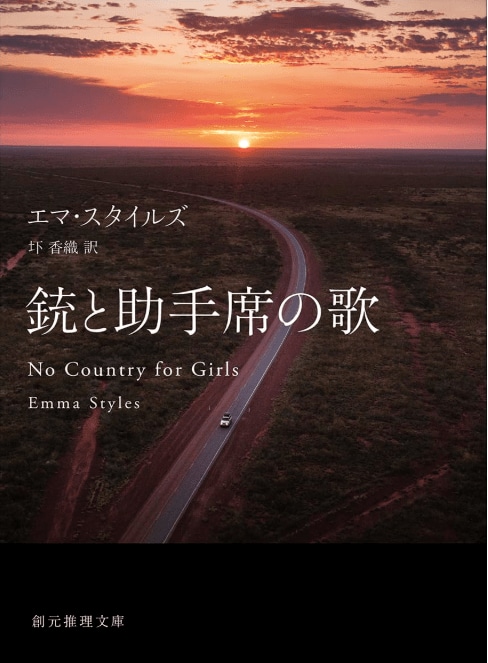
装幀=國枝達也
『銃と助手席の歌』
エマ・スタイルズ 著
圷香織 訳
創元推理文庫
定価 1,430円(税込)
2025年2月付刊行の翻訳ミステリは傑作快作が目白押しだった。実は先月号は3冊も2月新刊を先食いしたのだが、それでもなお弾切れとは無縁で、取捨に悩む。
まずは先月取り上げた『17の鍵』の続篇、マルク・ラーベ『19号室』(酒寄進一訳)を挙げる。20年近く前に失踪した妹がまだ生きていると確信する刑事トム・バビロンのシリーズを、創元推理文庫が2か月連続刊行してくれたのだ。ベルリン国際映画祭の開会式で若い女性が扼殺されるスナッフ・フィルムが流される。それが市長の娘らしいと判明した後は、ジェフリー・ディーヴァーを想起させるダイナミックな物語展開が楽しめる。トムの妹とそっくりの少女が見つかったり、副主人公の臨床心理士ジータ・ヨハンスの過酷な過去が明かされたりと、レギュラー陣の深掘りも鮮烈だ。前作よりも更に闇が深まった、東ドイツからの負の遺産も絶好調。前作を超える娯楽性が読者を魅了します。
ジェス・Q・スタント『ミセス・ワンのティーハウスと謎の死体』(唐木田みゆき訳/ハヤカワ文庫HM)は、お節介焼きの中国系アメリカ人ミセス・ワンが、自分の茶葉販売店で死体となっていた男の死の謎を、明るく楽しく軽挙妄動気味に追う、という物語だ。元気な60歳の主人公が、事件関係者と刑事と息子を最初から最後までずっと振り回し続ける。探偵役が他人を振り回す作品は数あれど、ここまでのべつまくなしなのは稀だ。しかし彼女の言動は不思議な爽快感を伴っており、関係者も徐々に心を開いていく。登場人物のルーツが多様で、アメリカ社会の複雑さを実感させるのも良い。ミステリ的な興趣にも不足はなく、特に伏線の配置には感心させられる。最初から最後まで楽しく読める、優れたコージー・ミステリだ。
ジャック・ケッチャムの短篇を19篇も収めた『冬の子』(金子浩訳/扶桑社ミステリー)は、残虐残酷な際物との印象を抱かれがちなこの作家が、実際には普遍的でソリッドな抒情性、格式、美を備えていることを、誰にでもわかるようはっきりと示す。長篇にもこれらの要素は必ずあって、だからこそこの作家は歴史に名を残す永続的な人気物故作家になりつつあるのだが、短篇(最長でも30ページ台)ゆえそれが目立つ。残酷な、或いは悲劇的な展開は多く、中には不条理な惨劇、幻想小説、奇想小説すらある。そのいずれにも刻印された、煌くばかりの痛切さはいかばかりか。フィニッシング・ストロークよろしく、意外な展開や結末を迎える作品が多いのも、ミステリ・ファンには嬉しいだろう。長篇のケッチャムはちょっと……という方も、この短篇集は味わうに値します。
ミシェル・ビュッシ『誰が星の王子様を殺したのか?』(平岡敦訳/集英社文庫)は、あの『星の王子様』に込められた暗号的な謎と、作者サン=テグジュペリの死の真相を追うフィクションである。著名な実在の人物と他人の小説を扱った物語ながら、想像力は一切の遠慮なく羽搏いており、意外極まる真相を繰り出してくる。『星の王子様』に魅了された人々で構成されるクラブのメンバーが奇人変人揃いなのも面白い。クリスティーの影響がこの作品ですら垣間見えるのは興味深かった。個性的という点では今月随一の珍品。
R・F・クァン『バベル』(古沢嘉通訳/東京創元社)は、オックスフォードで翻訳と銀を使った魔法により、19世紀イギリスを覇権国家に押し上げた、というSF設定を有する。主人公は中国で拾われた少年で、オックスフォードで魔法の勉学と仕事に励むうちに現実を知る。そこからの展開はまことにダイナミック。銀の魔法は明らかに、植民地主義および産業革命による社会的収奪の象徴であり、アヘン戦争に繫がる壮大な歴史絵巻を背景に、若者である主人公たちが友情と相克の人間ドラマを演じる。単純に面白いのはもちろん、人種差別や性差別も克明に描いており、テーマの訴求力も強い。今年を代表する娯楽大作なのは確実である。
ということで重量級も軽量級もよりどりみどりの当月ベストは、エマ・スタイルズ『銃と助手席の歌』(圷香織訳/創元推理文庫)としたい。アウトバックと呼ばれるオーストラリア内陸部の原野を通る3200キロにわたるハイウェイを、2人の少女が逃げる物語だ。姉の恋人を死なせてしまったチャーリーは、居合わせた大学生ナオと一緒に車で逃げる。チャーリーは怒りっぽく言葉遣いも荒い少女だ。一方のナオは比較的沈着ながら、秘密を抱え、チャーリーに同行しなければならない理由も隠している。自分たちと道路以外は人工物が何もない大自然をひた走る2人は、最初は衝突が多くギスギスし、時間の経過や状況の変化と共に、徐々に様子が変わってくる。その過程を生々しく描く筆致は、成長譚ないし青春小説としての強靭さを作品にもたらす。一方、彼女らには追手がかかっており、そちらの視点からはサスペンスが盛り上がる。もちろん、数百キロに1か所の割合で出現する町や集落での他者との触れ合いもあり、本書はロードノベルとしての性格も生じる。中でもチャーリーとナオの人間模様と関係性は本書の主軸であり、その心理的な変遷は複雑にして細かい。彼らをシスターフッドという単語に押し込めると、大切なものが抜け落ちてしまうだろう。鮮烈な犯罪小説、痛切な青春小説である。必読。