18 @noa-ano-days 2025/10/01 16:24
あたしたちはカフェを出て、大通りを並んで歩きはじめていた。
令那さんはあたしを安心させるみたいに、メンバー募集停止の投稿をした。でも、これで会が立ち直るのかは、よく判らない。
――〈XNS〉はこれから、どうなるんだろう。
トップワン。オニマル。舞依のこと。安定していたはずの〈XNS〉だったのに、気がつくとあちこちが軋んでいる。誰かと争いたいわけじゃないのに、敵がどんどん現れる。もううんざりだ。
「令那さん?」
いつの間にか、令那さんの足が止まっていた。
彼女の脇に、後ろからやってきた黒い車が停まった。窓にスモークが貼ってあって、中が見えない。昨日の二人組を思い出して、あたしは心拍数が上がるのを感じた。
こちらを向いた、助手席の窓が開く。
「すみません」と顔を覗かせたのは、マスクをつけた誠也だった。気まずそうな顔をしていた。
「いまお時間大丈夫ですか。ちょっと話したいことがあるんです」
「話って……何の?」
「いいから、早く乗れよ」
奥の運転席から声が聞こえ、あたしは声を上げそうになった。
ハンドルを握っていたのは、陸尚人だった。
後部座席は空っぽで、車内には尚人と誠也だけがいた。
ふたりは犬猿の仲で、グループの主導権を取り合ってバチバチやりあっているライバルだ――そう聞いたことがあるけれど、いまの誠也は、尚人の下僕みたいに見えた。苛立ったようにハンドルを握る尚人の横で、誠也はひたすら肩を縮めている。
車は、どこかのマンションの地下駐車場に入っていく。東京の景色がろくに判らないので、どの辺なのか判断がつかない。
駐車場脇のエレベーターで十階に上がると、東京タワーがやけに近くに見えた。もう二年くらい住んでいるのに、実物を見るのは初めてだ。尚人の慣れた足取りを見ると、ここが彼の自宅なのだろう。
「アユムさん――」
一番奥の部屋のリビングに入ったところで、令那さんが声を上げた。ソファに座っていたのは、鈴木アユムだった。解散した〈XROS〉のメンバーが、全員集合している。
「今日は来てくださり、ありがとうございます」
アユムはすごく背が高いけれど、元ボクサーで筋トレマニアだという尚人に比べ、どこかひょろっとしている。長い上半身を折り曲げて頭を下げる仕草に、なんだか毒気が抜かれてしまう。
「どうしても〈XNS〉のかたとお話をしたいことがあり、不躾ですがお招きさせていただきました。突然申し訳ありません」
「なぜ私たちのことを知っているんですか。誠也さんから聞いたんですか」
「というより、自宅から乃愛さんを尾行していました。令那さんが現れなければ、乃愛さんだけとお話しさせていただくつもりでした」
「どうしてあたしの家を――?」
口にしてみて、昨日の二人組をよこしたのが、トップワンでなくアユムだったのだということに気づいた。一旦撒いたつもりだったけど、実はあのあともずっと監視されていたのかもしれない。あたしが遙人の家を出て、自宅に帰るまで――。
「僕たちは、手荒な真似がしたいわけじゃないんです」
あたしが向けた敵意を、アユムは何ごともないように受け流す。
「あくまでも話し合いをしたいだけなんです。穏やかに解決できれば、それでいいんで」
「解決って、何のことですか」
「とぼけんな。誠也を洗脳しやがって」
令那さんに向かって、対面のソファから尚人が身を乗り出す。その横で、誠也は申し訳なさそうに俯いている。
「洗脳?」令那さんは、平然とした風に言った。「何のことですか? そんなことはしてないですよ」
「事情は誠也から聞いてんだよ。藍が生きてるとかなんとか、おかしなことを吹き込んでるそうだな」
「確かにそういう話はしていますが、決して〈洗脳〉なんかはしてません。私たちの会合は、参加するもしないも自由です。監禁して教えを無理やり叩き込んでいるわけじゃないしカルト宗教団体のように薬物を使っているわけでもない。私たちは穏やかに話し合い、祈りを捧げているだけです」
「そもそも〈藍が生きている〉という時点でおかしいんだよ。俺たちは葬式にも出たし、死体も見た。それで死んでないなら、なんなんだ」
「誠也さんは、遺体の身代わり説を唱えていましたが? 藍がどう生きているかは、私たちの中でも見解が分かれています。それぞれの方法で藍の生存と復活を信じ、祈りを捧げているんです」
尚人の右手が、感情を抑えきれないようにブルブルと震える。それでも令那さんに、ビビった様子はない。傍から見ているあたしですら怖いのに、すごい胆力だ。
「まあ、想定の範囲内かな」
いきり立つ尚人の横で、アユムは余裕ぶりながら言う。
「皆さんが何を信じようが、別に構いません。ただ、誠也を巻き込むのはやめてもらえませんか。長年の仲間がおかしな説にハマってるのが、耐えられないんです。それに、誠也が出入りしているというのは、皆さんにとってもリスクだと思いますよ」
「なぜですか?」
「〈XROS〉の元メンバーが藍生存説に傾倒しているなんて、トップワンとしては絶対に見過ごせない話だからです。いま、ウチの社内では藍に関する陰謀論が大きな問題になってます。楠木藍という名前は、いまやおかしな文脈を色々巻き込んでしまった。ネットには〈トップワンに殺された〉と主張している人もいれば、藍の写真を街中にベタベタ貼っている目的の判らない集団もいる。極端な自然農法団体のアイコンにも使われているし、女性叩きのシンボルにも用いられている。トップワンが何度も注意喚起しているのに、この流れは止まらない。僕や尚人も被害を受けているんですよ。もちろん、誠也本人も」
「私たちは静かに祈りを捧げているだけです。そんなことはしていません」
「それでも以前はトップワン糾弾の急先鋒で、会社の前で街宣してたでしょう? 社長はおたくを目の敵にしているんですよ。そんな状況で、誠也がもし〈XNS〉に参加しているなんて知ったら、ウチの社長はもう限界まで行きますよ。あなたたちはありとあらゆる微罪で訴えられ、週刊誌に追われ、下手したら逮捕されるかもしれない。社長は警察出身ですからね。とにかく、誠也を解放してください。あとは藍の生存説でも、宇宙人説でも、好きなだけ唱えてくださって大丈夫ですから」
アユムの見下すような口調は頭に来るが、冷静に考えると、彼の言う通りだと思えた。トップワンみたいな企業に本気で対策されたら、間違いなくもたない。
それでも令那さんは、すぐには答えようとしない。黙り込んで、何かを考えている。
「アイドルという仕事について、おふたりはどうお考えですか」
令那さんが唐突に呟いた。
「アイドルとは〈偶像〉のことです。私たちファンは、ステージ上にいる皆さんを見て、色々な感情になる。こんなに恰好いい人がいるのか。こんなにキラキラした世界があるのか。皆さんの華麗なパフォーマンスを見て、私たちは重苦しい現実から解放される。アイドルとはそういう仕事ですよね」
「概ね同意ですけど……それが何か」
「つまり、陰謀論と同じだということです」
「は?」
「トカゲ型人間が地球を支配しようとしている、911はアメリカの自作自演だった、新型コロナのワクチンは殺人兵器だ……陰謀論を信じる人は、ありもしない話を信じ込むことで、現実から解放される。外側から見ると異様に見えるかもしれませんが、中に入ってみたら、陰謀論の世界はシンプルで美しいんです。〈XROS〉が見せてくれた、数々の光景のように」
「殺すぞ、ババア」
「やめとけ」
尚人が立ち上がろうとするのを、アユムが制する。そんな彼の表情も、一変していた。
「尚人の暴言は、謝ります。ただ、僕たちもプライドを持って〈XROS〉をやっていたんです。侮辱するようなことは言わないでください」
「侮辱したつもりはなく、構造の話をしているんです。あなたがたは〈XROS〉において、生身の姿を晒しているわけじゃない。陸尚人は現実では『殺すぞ』も『ババア』と口にしても、〈XROS〉では言わない。あなたがたは余計な部分を切り落として、フィクションとしての陸尚人と鈴木アユムを作り上げて、観客に提供している。世界を都合よく解釈する陰謀論と、何が違うんですか」
「つまり、あなたは自分で認めているんですね。〈藍は生きている〉というのは、陰謀論だと」
「藍は生きています。陰謀論じゃない」
「支離滅裂だ。何を言ってるんだ」
「まだ判らないんですか。この世界には、陰謀論しかないんです」
威圧し続けていた尚人が、初めて臆した表情になる。アユムは表情こそ変わらないけれど、少し青ざめている。
「アイドル。陰謀論。どちらも複雑な現実を切り落とし、シンプルで美しい世界を作り上げ、それを信じるという特徴を持っています。でも、本当は全部そうなんです。あなたは私のことを〈頭のおかしい陰謀論女〉だと思ったでしょう。でも私は、自分がそんな人間ではないことを知っている。あなたの中にある私の像は、私の実態とズレた、陰謀論にすぎない」
「バカな。そんなことを言ったら、全部陰謀論になってしまう」
「そうなんです。私たちは陰謀論を通してしか、この世界と接続できない。藍は死んでいる。警察が発表したし、遺体も見た。でも、本当にそうなのか。藍が死んでいるかどうか、確実な証拠はありません。警察が嘘を言っているかもしれないし、遺体は身代わりかもしれない。あなたがたが信じている〈藍が死んだ〉という説は、なぜ正しいと言いきれるのか。それは陰謀論ではないのですか?」
「なら、これも陰謀論か?」
視界の隅で、尚人が素早く動いた。
風が吹いたあと、ゴキッという音が響いた。次の瞬間、令那さんが床に倒れ込んでいた。
「馬鹿野郎! なんてことをするんだ!」
アユムの慌てた声を浴びながら、あたしは令那さんのそばにかがみ込んだ。頬を殴られて、赤く腫れていた。
「全部陰謀論なんだろ? その痛みも陰謀論か? どうなんだ」
「何言ってんだよ!」覗き込む尚人の目を睨み返した瞬間、身体が震えた。この男は、その気になれば私たちを殴り殺せる――尚人の肉体と目の中に宿る狂気が、あたしを震え上がらせる。尚人はバカにしたように笑った。私たちを、嘲笑うみたいに。
「……なんだ、お前?」
いつの間にか、尚人の前に誠也が立っていた。尚人は苛立ったように舌打ちをする。
「何か文句あるのか? そういえばお前のことは、一度も本気で殴ったことなかったな。もう一緒にやることもない。ぶっ飛ばしてやろうか?」
「俺は、この人を信じるよ」
「あ?」
「藍は生きている。俺はその世界を生きる。お前はそっちの世界で生きていけばいい。俺たちのことは放っておいてくれ」
「完全にイカれたのか、お前。生きる必要なんかねえよ。ここで殺してやる」
「待ちなさい」
誠也の胸ぐらを掴んだ尚人に向かって、令那さんが言った。
赤くなった頬を歪ませて、口角を上げていた。
「私は、殴られなかった」
「あ?」
「私が殴られたという証拠はない。あなたたちの記憶も、私を殴った手の感触も改竄されたものかもしれないし、映像や音声が残っていたとしても、それは作られたものかもしれない。痛みなんて、脳が放つ信号にすぎない。私は、痛くない。そう信じれば……」
令那さんは、恍惚を感じているみたいな表情になる。アユムと尚人の顔が、恐怖に染まった。
「もう、痛くない」
病院に行くほどの怪我じゃない。家に帰って休むから、放っておいて――。
頑なに言う令那さんを説き伏せて、あたしはタクシーを捕まえた。誠也は話し合いがあるから、尚人のマンションに残るそうだ。
タクシーが着いた先は、二階建ての小さなアパートだった。少し意外な気がした。令那さんはいいところのお嬢様で、広い家に住んでいるのだと勝手に思い込んでいた。
「色々あって、住んでいた家にいられなくなってね。狭いし、ものがあまりないけど、気にしないで。というか、本当にたいしたことないから。もう全然痛くないし」
「ボクシングをやってた男に、顔を殴られたんですよ。たいしたことないわけがない。本当は病院行って、診てもらったほうが……」
「本当に大丈夫。気にされるほうがつらいわ」
そんな風に強く言われたら、もう何も返せない。「じゃあ、少し手当てだけさせてください」と言い、無理やり家に上がり込んだ。
間取りは1Kで、あたしや心春が住んでいる部屋とあまり変わりがなかった。玄関にはスニーカーが一足、部屋にはソファベッドと座卓とテレビがあるだけだ。生活をしていく上での、最低限のものしか置いていない感じだった。
「少し、横になっててください。救急箱はどこですか」
「洗面台の下に入ってる。お茶が飲みたかったら、冷蔵庫を開けて」
「あたしのことはいいですよ。休んでいてください」
強がっていても、やはり殴られたダメージは大きいみたいだった。部屋着に着替えもせずに、ソファベッドに寝転んでしまう。あたしは洗面所に向かった。本当はシャワーを浴びたいくらい全身がベトついていたが、せめて手だけでも洗いたい。
洗面台の前に立ったところで、あたしは不思議な感じを覚えた。少し考えて、その正体に気づく。
――鏡がない。
洗面台の前に、むきだしの壁があるだけだった。もともとそういう物件なのだろうけど、不便じゃないのだろうか。汗をかいたので少し顔を確認したかったけれど、あとで手鏡を見ればいいか。洗面台の下を覗くと、救急箱の中に冷えピタがあった。まとめて持っていく。
「……スマホ、鳴ってますよ」
令那さんの鞄の中から、スマホが振動する音が響いている。電話がかかってきているみたいだ。令那さんは疲れたように頷いただけで、取る素振りを見せない。
「昔の仕事関係なの」
そう呟いた瞬間、振動が止まった。
「もうやめてしばらく経つのに、いまだに連絡が来る。困ってるのよ」
「昔の職場から、電話がかかってきてるんですか」
「まあ、そんなものね。もう相手にするつもりなんかないのに、困ったものだわ」
「令那さん、何の仕事してたんですか」
冷えピタのフィルムを剥がしながら聞く。彼女の生活を見たことで、興味が生まれていた。でも、令那さんは答えてくれない。「ちょっと、自営業みたいなものをね」と、あからさまにお茶を濁されただけだった。
令那さんの頬は、さっきよりも腫れていた。頬がトマトの表面みたいに少し膨らんで、赤から黒に変わってきている。改めて怒りが湧いてきた。女の顔を殴るなんて、最悪を通り越している。
「よかったわね。殴ってもらえて」
「え?」
「これでトップワンは、私たちの活動に介入できなくなった。これ以上私たちに干渉するようなら、警察に行く――そう言われたら、それ以上何もできない」
「このまま済ませるつもりですか。殴られたんですよ」
「私が尚人を告発したりしたら、〈XNS〉は激しいバッシングに晒される。〈陰謀論の女が尚人をハメて、ありもしない被害をでっち上げている〉――そんな風に言い出す人間が出てきて、私や会員の個人情報をネットで晒す人も出てくるかもしれない。正義感と被害者意識が暴走したときの〈あれ〉は、本当に怖いわ」
令那さんはそう言うと、スマホで自分の顔写真を撮りはじめる。証拠を残すつもりのようだった。
〈なら、これも陰謀論か?〉
尚人はそう言って殴りかかってきた。本人は皮肉のつもりだったのだろう。
――でも、それも陰謀論なんだ。
尚人が令那さんを殴った。あのとき確かに起きたたったひとつの事実からは、無限のストーリーを作り出すことができる。尚人は本当は殴っていない。令那さんと尚人は会ってもいない。令那さんがナイフを持ち出したから、抵抗しただけだ。作られた様々な物語は〈あれ〉を駆け巡り、みんなが自分の信じたいものを選んで信じるようになる。結果、〈XNS〉への批判の声もたくさん上がるだろう。この世界がそういうところまで来てしまったことを、あたしは知っている。返り血を浴びるのが嫌なら、事実をなかったことにするしかない。
「もしかして令那さん――最初から、これが狙いだったんですか」
尚人に危害を加えさせ、トップワンからの妨害をやめさせる――そのために令那さんは、あんなにも彼らを煽っていたのではないか。
あたしはそこで、自分が小さな陰謀論を作ろうとしていることに気がついた。あたしの言っていることには、何の根拠もない。令那さんが肯定しても否定しても、真実は彼女にしか判らない。
あらゆる陰謀論は、こうやって生まれていくのか。
あたしたちは生きているだけ、話しているだけで山のような陰謀論を生み、それを信じて生きている。令那さんが言っていた意味が、少し判った気がした。あたしたちは陰謀論を通してしか、この世界に接続できない――。
「手当てしてくれて、ありがとう」
〈そろそろ帰ってほしい〉と匂わせるように、令那さんが言った。
「さすがに疲れたわ。また連絡する。今日はありがとう」
「いえ。本当に遠慮しないでくださいね。痛みがひどくなったらいつでも連絡してください」
「ありがとう。少し、眠るわね」
ソファベッドに寝転がった令那さんは、クッションに深く頭を預けた。すぐにすやすやと寝息を立てはじめる。玄関の鍵はどうすればいいんだろう。開けたまま外に出ちゃって、大丈夫だろうか。
――ん。
ふと、座卓の上にノートがあるのが目に入った。
今日カフェで会ったとき、令那さんは一心不乱に何かを書いていた。そういえば最近、〈XNS〉の会合でもよく書きものをしている気がする。何をしているのだろう。
あたしは何気なくノートに指をかける。
藍について短い文章が書かれていた。
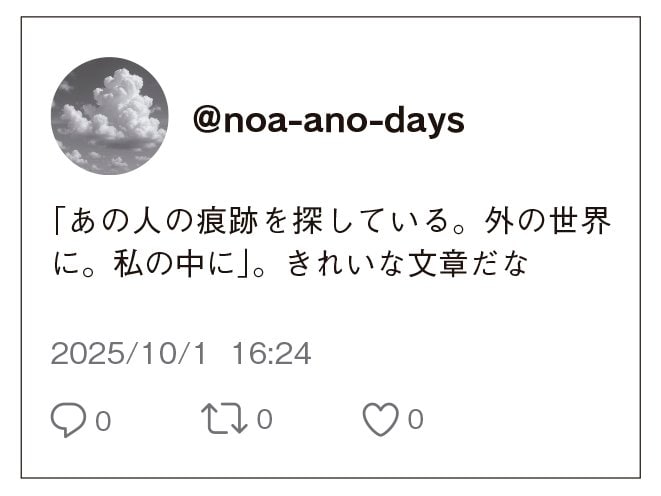
19
突然だが、いまからこの物語の作者である私が、この本を読んでいるあなたのことをひとつ予知したい。いまから私が言うことが間違っていたら、この本の代金を全額お返しする。版元に振込先の口座番号を送ってくれ。
では、予知をはじめよう。
周囲を見回してほしい。よく見たか? じっくり見るまで、先を読んではいけない。
もういいか? では。
――さっき見たあなたの視界のどこかに、必ず数字がある。
どうだ、当たっているだろう。
というような本を読んだのは、いつのことだっけ。何の本かも覚えていないし、この予知自体も出来がいいとは思えないが、心に引っかかっていて時折思い出す。街中を歩いていて、ふと立ち止まって周囲を見回すと、壁に向かって立っているのでもない限り、視界のどこかに必ず数字があるからだ。どこまでも追いかけられているみたいに。
『舞依は、数字が好きなんだね』
子供のころ、与えられた電卓でひたすら四則演算を繰り返していた私に、母がそう言った。〈数字が好き〉というよりも、私は数字を理解したかったのだと思う。この不思議なものを。世界の隅々まで根を下ろし、その葉をあまねく撒き散らしている、世界樹のことを。
『数は力だ』という田中角栄の言葉がある。一理あるし正しいと思うが、私に言わせれば『数はすべて』だった。この世界に存在するもので、数が支配していないものは存在しない。音楽は演奏時間やBPMや周波数によって成立しているし、絵画も可視光線の波長がひたすら重なり合うことでできている。生物は脈拍や体温が正常な数を保つことで生きることができ、時間や距離といった数字はこの宇宙の隅々まで浸透している。人類の最大の功績は、言語の発明や火の制御ではなく、数の発見だろう。数こそが、この世界そのものなのだから。
「納得できませんって言われてもさ……」
喫茶店の中、乃愛が心春先生の横で頭をかいている。会合の一時間前、ふたりには三十分という約束で時間を作ってもらった。
「もう遙人の家も使えないんだし、これ以上メンバーが増えたら会合すらできないでしょ。一旦メンバー募集は止める。理解してくださいよ」
「場所なんか探せばいい。公民館でもレンタルスペースでも、いくらでもある」
「いまは色々ゴタついてるでしょ? 揉めごとが収まってから立て直せばいいじゃんか。なんでそんなに人数を増やそうとするんだよ」
「心春先生は、どう思うんですか」
問い掛けても、心春先生はぼんやりした目で頷くだけだった。最近の先生は、そこに肉体はあるのに、心がどこかに行ってしまっている感じがする。それでも祈りがはじまると、すべてが吸い込まれそうな磁場が生まれるので不思議だ。
――いまは、拡大局面なのに。
〈XNS〉の実務を取り仕切っている乃愛は、ガールズバーで働いているだけでろくに社会人経験もないという。仕事とは、やるべきときに徹底的にやらなければ中途半端に終わるのだ。数を増やせるときに増やしておかないで、どうする。
去年まで、広告代理店で働いていたことを思い出す。
官公庁から宇宙開発ベンチャーまであらゆる顧客を抱える業界大手で、プロモーションビデオの制作にディレクターとして携わる中で〈XROS〉の案件も手がけた。ユーチューブの登録者数が百五十七万人、動画の総再生回数が十二億五千万、SNSの合計フォロワー数が三百万人以上と、アーティストもここまで来ると纏う空気が違ってくる。特に、フォトエッセイを十万部売り上げていた楠木藍は、そこにいるだけで身体が輝いているみたいに見えた。それ以来推しになり、残業が七十時間を超える日々を過ごす中、心の支えにして生きてきた。その結果、こんな場所に流れ着くことになるとは、思ってもみなかったけれど。
私は、藍が生きているとは思っていない。
ほかの参加者がどう考えているのか判らないが、明確に生を否定しているのは少数派だろう。
ただ、〈XNS〉にいると、藍の魂を感じることができる。彼の息づかいに触れ、心臓の音を感じ、心の平穏を取り戻すことができる。それは心春先生のわけの判らない力のおかげだし、先生を信奉する人々の信仰心の強さのおかげでもある。どちらが足りなくとも、〈XNS〉は成立しないだろう。
いまでも〈XNS〉は様々な妨害を受けている。この活動を未来永劫続け、より深く、より本質的なところにたどり着くには、数が必要なのだ。乃愛がそのことを理解できる知性がないのが、もどかしかった。
「ひとつ、提案があるんですけど」私は、用意してきた言葉を言う。
「〈XNS〉の公式アカウント、私に任せてくれませんか」
「駄目だよ。あれは令那さんのものだ」
「その令那さんだって、まともに運用してないですよね。アンチのリプライは野放し、トップワンからの抗議は無視、ろくに主義主張を書くこともなく、メンバー募集も停止。運用する力がないんですよ。私がやれば、会員はいまの五倍、フォロワー数は十倍になります」
「あのさあ……」乃愛が困ったように言う。そして迷った様子で何かを考えてから、言った。
「実は、トップワンとは話がついたんだよ」
「え? そんな話は聞いてないですけど」
「令那さんがつけてくれたの。もうトップワンとの揉めごとは完璧に片づいたから、安心してくれ。あの人はあの人で〈XNS〉のことを考えてやってるんだからさ、そんなにひどいことを言わないでくれよ」
「どうやって話をつけたんですか。信じられません」
「いい加減にしろよ。そこまで文句があるなら、別の団体でも作ってそっちでやりゃいいだろ。ちょっとは令那さんの気持ちも考えてくれよ」
乃愛は「トイレ」と言い、店の奥に行ってしまう。交渉は決裂してしまったが、悪いことばかりではない。乃愛と令那の結束が思いのほか強いことが判ったのは収穫だ。このふたりをセットで追い出さないと、〈XNS〉の方針を変えることはできない。とはいえ、そのとき心春先生はどうなるのだろう。この会は心春先生がいないと成立しない。乃愛だけを切り離して追い出すことなど、できるのだろうか。
――できるか、できないか。そんなことは考えても意味がない。
やるだけだ。〈XNS〉はこのままだとジリ貧になって終わる。そんなことは、あってはならない。
心春先生は、いつの間にか眠ってしまっている。祈りのときの得体の知れないエネルギーを知っているだけに、彼女がこんなにも無防備な寝顔を晒していることに、却って凄みを感じる。
「あのさ」
「わっ」
突然隣から声がして、私は驚いた。
そういえば、シズクがいたのだった。ずっと黙っていたから、存在を忘れていた。
「ボクも、賛成。もっと〈XNS〉は人数を増やしたほうがいいと思う」
「いきなり、何? シズクさんは、むしろ人を減らせって言っていたんじゃなかった?」
「状況が変わった。いま、藍は遠くに行こうとしてる。引き戻すには、もっと強い力が必要なんだ」
「遠くって?」
「遠くは遠くだ。このままだと、藍に会えなくなるよ。人手がいる。もっとほかのものもいる」
さすがリスカ痕のあるメンヘラ女子だ、何を言っているのかわけが判らない。それでもシズクの口調は、怖いほどに真剣だった。
「令那さんには、出てってもらわないといけないかもしれない。どんな手を使っても」
(つづく)
