16 @noa-ano-days 2025/09/30 15:13
「どういうことですか、令那さん」
遙人の部屋に舞依がやってくるなり、令那さんに詰め寄る。「どういうことって?」と、令那さんが疲れたように応じる。
「ふたつあります。一点目――〈あれ〉に来ているトップワンからの警告を、なぜ無視してるんですか」
舞依の声は大きくて、空気がびりびりと震えるのを感じる。いきなりはじまった口論に、あたしはうんざりした。
「私は、ネットで論争をするつもりはないの。トップワンに返信するつもりはない」
「なんでですか。アンチたちに『返事をしろ』と煽られてますよ。いいんですか、このままで」
「SNSで論争をしても意味はない。揚げ足を取られ、悪いようにねじ曲げて解釈され、新しい攻撃材料を与えるだけ。頭がおかしくなっちゃう」
「それは、反論が下手だからです。私がやりましょうか? アカウントを使わせてください」
「やめましょう。私たちは誰かと争うために、この活動をしているんじゃない。藍のことを感じて、彼の復活を待つためにやっているの」
「納得できませんよ。いまが大切なときなのに……」
舞依は、悔しそうに唇の端を噛む。
『私はいま、休職してるんです』。前の会合のときに、舞依は言っていた。もともとエリート会社員で、あたしでも名前を知っている大手広告代理店で働いていたけれど、あまりにも忙しくて身体を壊し、休んでいる間に〈XROS〉にのめり込んだと言っていた。
あたしは、周囲を見回した。
遙人の部屋には、もう十五人くらいの会員が集まっている。ふたりの口論に呆れている人が多いかと思ったら、意外と舞依に同調しているような人がいる。令那さんがどんな苦労をしているのかも知らないのに――。
「ボクからも、いい?」
さらに食ってかかろうとする舞依に割り込むように、シズクが言った。
「ボクはこれ以上、人数は増やさないほうがいいと思う。ついでに、〈あれ〉のアカウントは消してほしい」
「え? なんでよ」
「メンバーの質が下がると、霊感が鈍る。霊感が鈍ると、藍のことを感じられなくなる。心春先生にも負担がかかるから、これ以上変な人を入れないでほしい」
「私が変な人を入れてるって言いたいの?」
「変な人を入れてるっていうか、舞依自体が変な人だと思う」
「なんだよ、その口の利きかたは」
「ボクはみんなのために言ってるんだ。もっと純度を保たないと、祈りの質が……」
「『だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である』」
令那さんの言葉に、舞依とシズクが口論を止めた。「マタイによる福音書」と、令那さんは微笑む。
「イエスもそう言っている。トップワンがどう出てくるか判らないし、〈XNS〉にこれから素晴らしい人が入ってくるかもしれない。何より私は、同志への門戸を閉ざしたくないの。流れに任せて、私たちのペースでやっていこう。ね?」
「はあ……」
白けたような舞依のため息の中、令那さんが意味ありげな視線を送ってくる。腕時計を見ると、もう十三時を回っていた。そろそろ、出かけなければいけない。
部屋を出るときに、一瞬、心春と目が合った。
心春は、この場所にいないみたいだった。
部屋の中で起きている揉めごととは、全く別のところにいるみたいだった。
秋の匂いがする。
藍が死んだのは二月の末、冬の終わりのころだった。あのときには、まさか自分がこんなことに巻き込まれているとは、思いもしなかった。
令那さんに言いたいことは〈ふたつあります〉と舞依が言っていた。ふたつ目は間違いなく、オニマルのことだろう。どこから手に入れたのか知らないが、藍の死体の画像をロシアのサイトに上げて、リンクを貼っていた。藍は間違いなく死んでいる――その証拠を突きつけて、〈XNS〉を攻撃する意思を感じた。
それが、三日前のことだ。新しい入会希望者は、激減した――。
と思いきや、問い合わせの数は一気に二倍になったみたいだ。今日も五人の入会希望者がいて、あたしが一時間置きに案内することになっている。あれほど明確に〈藍が死んだ〉という証拠が出てきたのに、なぜだろう。とはいえ、これ以上人数が増えるのは、いいことなんだろうか。
このところ、〈XNS〉の中での諍いが増えてきた。
今日の揉めごとはまだマシなほうで、前はお祈りをするときに頭を下げるか下げないかで、シズクと楓が延々と揉めていた。そのたびに令那さんが仲裁してくれるけれど、聖書の引用にもみんなが慣れて、効き目が薄れている感じもした。高校のときの会合ではこんなことは起きなかったが、あのときのメンバーは四人だ。人数が増えると色々なことが起きるのだ。
心春は、大丈夫だろうか。
会が分裂したら、心春はまた孤独になってしまう。藍が死んだあとの虚無みたいな日々を、また送ることになる。
前の〈XNS〉も、入れてはいけない人を入れた結果、崩壊してしまったと聞いた。そのときは、もっとメンバーを選べよと思ったけれど、自分が同じ立場になってみると難しい。舞依がこんなに主張し出すなんて、最初の段階では見抜けなかった。
いっそ、全部断ってしまおうか――。
窓口になっているあたしが、入会希望者を全員追い返せば、これ以上人は増えない。舞依は激怒するだろうが、一旦シズクの言う通りにしたほうがいいんじゃないか――。
ぐるぐると考えていたら、待ち合わせ場所の公園に差し掛かっていた。顔を上げて、公園の中に入る。
思わず、足が止まった。
待ち合わせ場所は、遙人の家の近所にある、小さな公園だ。
ベンチのあたりに、ふたりの男がいた。
ふたりとも、背が低い。片方は一六〇センチのあたしと同じくらいの体格だった。ただ、雰囲気が普通じゃなかった。いまそこに死体を埋めたとでもいうような、ヤバい空気が溢れていた。
ひときわ小さいほうと、目が合う。
あたしは次の瞬間、公園に背を向けて歩きはじめていた。
『二十代の男性が、藍の話を聞きたいって言ってるの』
と令那さんには言われていたが、どう見てもあいつは、男性アイドルを推すような人種じゃない。アンチが藍のファンを装って、応募してきたのだろうか。ただ、さっきの男たちのヤバいオーラは、そんなことでは説明できない気がする。
鞄の中に、手を突っ込む。
スマホのフロントカメラをオンにして、さり気なく背後を映す。小さいほうの男が、あたしのあとをつけてきていた。
――やっぱり、あたしを待ってたんだ。
あいつらは〈XNS〉の窓口を捕まえるために待っていた。でも、公園に入ろうとした女が本当にそうなのか、確信が持てなかった。だからひとりを残して、もうひとりが追いかけてきた。
――慌てるな。
おかしな素振りを見せたら、男はすぐに襲ってくるかもしれない。こんな住宅街で拉致なんて普通は考えられないけれど、常識が通じる相手じゃない気がする。とにかく、遙人の家に戻るわけにはいかなかった。このままどこかで時間を潰して、男が諦めるのを待つしか――。
あたしはそこで、息を呑んだ。
鞄につけた十字架のチャームが、ジャラッと鳴った。
そうだ。待ち合わせの目印にと、藍のグッズをつけてきたのだ。
小さな十字架だ。まだやつらに見られていない確信はあった。気づかれてはいけない。あたしが〈窓口〉だと、その瞬間にばれる。
人通りの少ない、閑静な住宅街が広がっている。大通りはどこだった? スマホで背後を見るわけにはいかない。もう一度そんなことをしたら、いくらなんでも怪しまれる。いや、もう充分怪しまれているかもしれない。男が距離を詰めてきている気配を感じた。殺気が後頭部に向けられている。いや、まだ大丈夫だ。いや、もう駄目だ――。
――逃げたい。
混乱の渦から、言葉が浮かび上がってきた。逃げたい。逃げよう。自分が正常な判断をできているのか判らなかった。走って逃げたところで、ひと気のあるところまでたどり着けるだろうか。捕まってどこかに連れていかれる可能性もある。それでも、ジワジワと首を絞められているみたいなこの時間を終わりにすることは、できる。
――心春。
あたしは、腹を決めた。
――また、会えるかな。
混乱を振り切るように、あたしは地面を蹴った。
水の中を走っているみたいに、前に進まない。それでも全力で走る。
最初の何歩かで、ろくに運動もしていない身体が悲鳴を上げた。痛みを放つ身体に鞭を打って、あたしは次の一歩を踏み出した。
背後から、男が迫ってくるのを感じた。身体の軋みが、一瞬でどこかに行った。脳内から麻薬がドバドバ溢れ、身体がふわっと軽くなった。逃げろ。逃げろ。麻薬でも中和できない恐怖が、ふわふわした感覚の奥から染み出してきていた。
――お母さん。
走りながら――あたしは高校生時代の、駅前のロータリーにいた。
あの日、お母さんは友達三人と話をしていた。今日と同じような、なんでもない一日だった。
一台の車が、異常なスピードでやってきた。日常を引き裂くような速さで車は迫り、雑談の輪に突っ込んだ。ガラスの割れるような音がした。友達がひとり撥ね飛ばされて、壁に叩きつけられた。車は友達の身体を叩き潰すように、壁に突っ込んだ。
男が降りてきた。追突で怪我をしたはずなのに、その影響を感じさせなかった。男は禍々しい形をした、大きなサバイバルナイフを持っていた。お母さんは逃げようとした。身体が上手く動かなかった。突っ込んできた車のどこかにぶつかったのだろうか。なんとか背を向ける。それでも、足が踏み出せなかった。怖い。怖い――。
あのときお母さんは、こんなことを感じていたんだ。
死んだ母の恐怖が、初めて判った気がした。
男が迫ってくる。足音がすぐ後ろにある。
肩を掴まれた。ぐいっと後ろに向かって、身体を引っ張られた。悲鳴を上げようとした。声が出なかった。
「乃愛さん!」
聞き慣れた声がした。
「どうしたんですか、しっかりして!」
振り返ると、マスク姿の大川誠也がいた。
何が起きているか判らないまま、周りを見回す。
あたしを追いかけていた男は、いなくなっていた。
誠也は〈XNS〉の会合に出るために、遙人の家に向かっていた。
その途中で、何かから逃げるように走っているあたしの姿を見つけたと、誠也は教えてくれた。追いかけている男の姿など、どこにもなかったそうだ。
「そいつ、トップワンの人間かもしれないです」誠也は申し訳なさそうに言った。「根来社長ならやりかねないです。最近、藍周りの陰謀論にかなり怒っていますから。危ないことに慣れている人間を送り込んできたのかもしれない」
「そういう誠也さんは、大丈夫なの? こんな会合に参加して」
「ばれたら終わりでしょうね。もうトップワンにはいられない」
「いいの? そうなっても」
「藍は生きています。俺は陰謀論だなんて思ってない。そんなことも判らない組織なんて、どうでもいいですよ」
マスクに覆われて見えないけれど、誠也は満面の笑みを浮かべていた。少し、胸が痛んだ。彼はいいのかもしれない。でも、彼についている大勢のファンはどうなんだろう。陰謀論に引きずり込んだ結果、芸能人生命を終わらせてしまう。そんなことをする権利が、あたしたちにあるのだろうか。
別に構わない、とすぐに打ち消す。誠也はもともと〈藍は生きている〉と信じたい人なのだ。〈XNS〉がなかったら、おかしな占い師とか宗教家とかにハマっていただろう。
遙人のマンションについた。預かっているオートロックのキーでエントランスに入り、エレベーターで五階まで上る。
マンションの廊下を歩き、遙人が住む角部屋に向かう。そこで、あたしは足を止めた。
遙人の部屋の前に、ふたりの男が立っていた。さっきの小男たちじゃない。年配の男性と、プロレスラーみたいに大きな男だった。
「開けろ!」
年配の男が、顔を真っ赤にして玄関のドアを叩いている。そのあまりの剣幕に、あたしと誠也は思わず目を見合わせた。
〈XNS〉の活動を支える土台が崩れていくのを、あたしは感じていた。
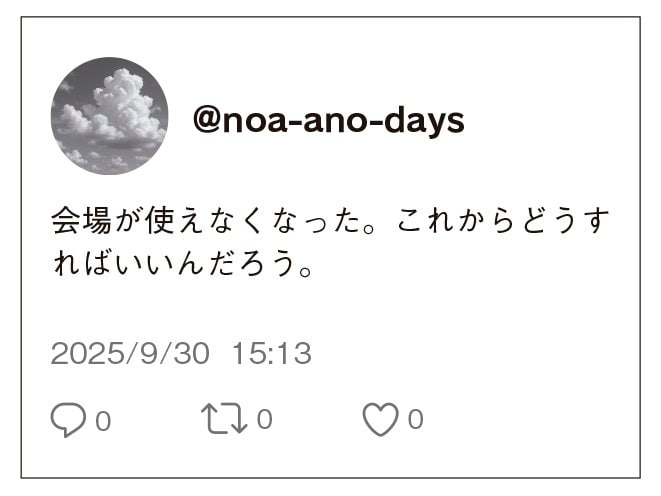
(つづく)
