8 @noa-ano-days 2025/8/21 21:20
『すごいことになったよ!』
『藍は生き返る! 聖書にもそう書いてあった!』
『藍はキリストなんだ! Goooooood!!』
心春から来たLINEを読んだ瞬間、あたしはベッドから飛び起きた。『いまどこにいるの?』と光の速さで送って、シャツとジーンズを着る。眉毛だけを描いて、日焼け止めを塗ったところでもう一度スマホを見ると、『ここ!』と地図のリンクが送られてきていた。杉並区のカフェか。ちょっと遠いな。リュックを背負って、あたしは家を出た。
――クソ。
歩いている間も、心春はトんでるみたいにLINEを送りまくってくる。ダルいけど、スルーしてると連絡が取れなくなるのは判ってるから、当たり障りのないスタンプをその都度送り返す。心春とのラリーで、あっという間に画面が埋まっていく。
楠木藍が死んでから、心春はヤバくなっていた『藍が私の部屋に来てくれた』とか言い出して、ほとんど家の外に出なくなってしまった。本当はあのとき、メンクリに連れていったほうがよかったんだろう。放置していた結果が、このザマだ。ミスった。クソ、クソッ。
でも。
――それは心春のために、なるんだろうか。
いままで何度も思ってきたことだった。心春を〈治す〉べきなのか。そもそもあれは、〈治る〉ようなものなのか。心春は〈治る〉ことを望んでいるのか。〈治っ〉た心春は、心春なのだろうか。
結論はいつも同じだ。心春は、そのままでいい。あなたはあなたのままでいい――そういう善人ヅラした無責任なクソ台詞が昔から大嫌いだけど、現実問題、心春はおかしなままでいたほうが幸せなのだろうと思う。
――心春は、あたしが守ればいい。
いつも同じところに戻ってくるのに、どうして何度も同じことを考えてしまうのか。つくづく自分のバカさ加減にうんざりしたところで、駅についた。電車に乗る。
その間もひっきりなしにLINEは送られてきていて、もはや何を言いたいのか判らないくらいめちゃくちゃになっていた。目的の駅までの三十分くらいが、永遠に感じた。スタンプを返し続けながら、あたしはのろのろと進む電車を蹴飛ばしたい気持ちになった。
最寄り駅に着く。そこで、LINEが止まった。
『大丈夫かー?』『もう着くよ?』。送ってみても、既読にすらならない。嫌な予感がする。まさか、ハイになりすぎて倒れたんじゃないだろうか。
心春に言われたカフェに着いた。半分駆け込むように、中に入った。
「心春……!」
奥の席に、椅子に身体を預けて、目を閉じている心春がいた。疲れて、眠ってしまっているみたいだった。もともと小さな身体が、子供みたいに見えた。
その対面に、女性が座っていた。
「あのー、あなたは?」
声をかけると、女性は驚いたようにあたしを見上げてくる。
綺麗な人だった。一回りくらい年上に見える。暗い目をした人だった。
「心春って……この人のことですか?」
「そうですけど。心春、どうしたんですか。何か変なLINEを送りまくってくるから、慌てて来たんですけど」
「どうしたも何も……ここに連れてこられて、私はずっと話を聞いていただけですけど」
「えーと……」
成り行きがよく判らない。あたしは沈没している心春の隣に座った。心春はすーすーと寝息を立てている。なんだこいつは。呑気にもほどがあるだろ。
「なんか迷惑をかけたみたいですみません。あたしは乃愛って言います。こいつの昔からのツレです。こいつ、ブッ飛んじゃってたと思いますけど、気にしないでください。躁が入ると、こうなるんです。道端の人を捕まえて、永遠にわけの判んないこと言ってたり、ずっと走り回ってたり。変な薬物とかじゃないから、安心してください」
「大丈夫ですよ。ちょっとびっくりしたけど、楽しい時間を過ごさせてもらいました」
「そんな気遣ってもらわなくて、大丈夫ですから」
「気遣いなんかしてないです。心春さん、楠木藍のことが好きみたいですね。私もファンだったから、色々話せて嬉しかった」
「まさか、藍と一緒に住んでたとか言ってました?」
思わず声が跳ね上がってしまった。心春がそんなことまで口にするのはレアだ。ここ数日おかしかったと思っていたけれど、相当メンタルがヤバかったんだろうか。
「すみません、全部こいつの思い込みです。昔からこうで、本人に悪気はないんです」
「思い込みって?」
「見えないものが見えると言ったり、死んだはずの人が生きていると言ったり。迷惑かけてすみません。起きたら、キツく叱っときますから」
「その話、詳しく聞かせてくれません?」
女性は身を乗り出してくる。純粋にあたしの話が聞きたいみたいだった。
もしかして――。
心春がトんだのは、この人のせいなんじゃないのか?
たぶん異常なテンションで話しまくっていた心春を見たはずなのに、全然引いていない。こんな人は、いままでいなかった。「はい……」。自然とあたしは口を開いていた。
「あたしと心春は、中高でタメだったんです。もともと茨城県出身で、いまは東京に出てきて、同じアパートに住んでるんですけど」
「仲、いいんですね。ルームシェアしてるなんて」
「いや、隣の部屋に住んでるんです。まあこいつ生活力ないんで、あたしが世話してるんですけど……」その辺の説明をするとややこしいので、あたしは口ごもった。
「昔からこいつは、自分の世界に生きてるんです。幻覚が見えるっていうか、妄想する力がすごいっていうか……」
最初は、中学一年生のころだった。
心春の家にいた、ジュンって名前の犬が死んだ。心春が生まれる前からいるおじいちゃん犬で、ほとんど兄妹みたいな存在だったと言っていた。あたしも子供のころ、猫が死んでめちゃくちゃ哀しかったことがあった。『気持ち、判るよ』と話しかけたら、心春はけろりとした感じで言った。
『何のこと? ジュンなら、家で留守番してるよ』
当たり前みたいな口調だったので、一瞬、ジュンが死んだのはデマだと信じかけたくらいだった。でも、デマじゃなかった。心春のママに聞いたら、骨になって仏壇に祀られているって言っていた。
それでも心春は、犬の散歩を続けていた。
空中でリードを持つ仕草で近所を歩いていた。『何してるのって、ジュンを散歩させてるんだよ』。見れば判るじゃんとでも言いたげな心春を前に、こいつには本当に見えているんだと思った。
「中二か中三のときだったかな……クラスで、明晰夢ってのが流行ったんです。夢を見ている最中に〈いま夢を見ている〉って気づいて、あとはその夢の中でやりたい放題やるってやつなんですけど……心春だけが、全然このブームに入ってこなかったんです。たぶんこいつ、現実で明晰夢みたいなことができるんですよ。自分が見たいものを、リアルに見れるんです」
「それは、どうやって見るの? 信じたいことを、一生懸命信じ込むということ?」
「うーん……最初はたぶん、そうなんだと思います。ジュンは死んでないとか、信じたくない現実を強く否定して思い込んで……でも途中からは、そんな無理してる感じはしないんですよね。一度思い込みが上手くいったらあとはボールが坂を転がるみたいに、自然と思い込み続けられるっていうか」
「それは、すごい能力ですね……」
ここまで話しても、女性は全然引いた様子がない。むしろどんどん興味が増している感じがする。
「ここまでの話だけだと、乃愛さんと心春さんはそこまで仲がよかったようには感じられないんだけど……どうして隣に住むくらいの仲に?」
「仲いいっていうか、こいつ、危なっかしいでしょ? 誰かが近くにいてやらないと、ポックリ死んじゃうなって思って。だからです」
言いながら、返事になってないなと思った。誰かがついていないと死ぬのは間違いないけど、あたしじゃなくてもいい。
「高校三年生のときに、あたしたちの住んでた街で、事件が起きたんです」
こんなことまで話すことになるとは、思っていなかった。
思い出すだけで最悪な気持ちになる、通り魔事件だった。
駅前にたまっていた人たちに車が突っ込んで、運転席から出てきた男が、倒れている人たちをサバイバルナイフでメッタ刺しにした事件だった。四人が殺されて、十人が怪我して、犯人は近くのマンションに十二時間立てこもったあとに捕まった。『あいつらを殺せと宇宙大統領から命令をされた』とか裁判で言い続けた、イっちゃってる犯人だった。
殺された四人は、全員あたしの学校の生徒の、母親たちだった。そのうちのひとりは親友だった茜のママで、何度も話したことがある人だった。学校の空気は、最悪に重くなった。茜はショックで寝込み、しばらく学校に来なかった。
そんなときだった。
『なかったことにすればいい』
心春が、そう言い出したのは。
「……通り魔事件なんかなかったって、思い込もうってこと?」
「そうです。あんな事件はなかったし、死んだ人もみんな生きてる。そういうことにして生きていけば、つらいことは何もなくなるって……クラスメイトが集まってる場所で、言い出したんです」
「そんなことをしたら、怒り出す人もいるんじゃない?」
「めちゃくちゃいました。怒鳴る子が出てきて、心春は職員室に呼び出し食らって、反省文とか書かされてました。でも心春は、言ったことを取り消さなかったんです。むしろ、なんでみんながつらい現実をそのまま受け止めようとするのか、不思議に思ってるくらいな感じでした。そんな中、茜から電話が来たんですよ。心春の話を誰かから聞いたんでしょうね。茜は、言いました」
『乃愛は、ママが死んだのを、なかったことにしてもいいと思う?』
翌日。
登校してきた茜に『近くにいてほしい』と言われて、あたしたちは三人で会った。茜は心春の提案にすっかりのめり込んでいた。『どうやって、なかったことにすればいいの?』と聞いていた。
「まずは思い込むところからだよ、と心春は言いました。ママは生きてる。ママは死んでない。家の中の見えないところにいて、一緒に生活をしている。そうやって思い込んでいるうちに、本当に声が聞こえてくる。匂いがしてくる。椅子に残った体温を感じる。姿が、見えてくるって。でも茜は、自信なさそうでした。いきなりそんなこと言われても、困りますもんね」
「それで、どうなったの……?」
「『じゃあ、みんなで信じよう』って、心春が言いました」
ひとりで信じることができなくても、同じことを信じている人が大勢いれば、気持ちを強く保てるかもしれない。だから、信じたい人をもっと集めてほしい。
茜は人望があった。事件に傷ついていた女子を数人集めて、全員で通り魔事件などなかったことにした。茜たちの周囲では、死んだ人々は全員生きていて、街は何事もなくずっと平和だということになった。
「そうしたら、茜の調子がよくなりました。ちょっと、引くくらいのペースで」
死体みたいだった顔色がもとに戻って、茜は毎日学校に来るようになった。行事にも積極的に参加して、テストの点も前よりよくなったくらいだった。『ママがスコーンを焼いてくれて、それを夜食に頑張ってるんだ』『ママが最近変えた美容液、借りたんだけどすごい肌の調子がいいんだよ』――嬉しそうに言う茜を見て、通り魔事件なんか本当になかったんじゃないかと、錯覚しそうになるくらいだった。
「心春がいたからなんです。こいつには、才能があるんですよ。妄想の中で生活できるだけじゃなくて、周りを妄想に巻き込める才能が」
あのときの茜たちは、幸せそうだった。クソみたいな現実を無視して、美しい妄想の中で生きることができていたからだ。
ただ、その時間は、長くは続かなかった。
ひとりの親が、学校に怒鳴り込んできたからだ。『私の妻が生きているなどと言っている生徒が、おたくにはいるらしいな』『どういうつもりだ。人の死を弄んで楽しいのか』『すぐにやめさせろ。教育委員会に持ち込むぞ』――心春は今度こそ徹底的に反省させられて、学校の中でも外でも、おかしな集まりを開いてはいけないと誓わされた。
「卒業のタイミングで、心春が『東京に行く』って言い出したんです。こいつ、親とめちゃくちゃ仲悪くて、半分追い出されるみたいな感じで。あたしは心春が心配で、ついてきたんです。それからずっと隣に住んでます」
「心配だからついてきたって……いつの間にそんなに仲よかったんですか」
「心春には、すごく感謝してるんです」一瞬迷ったけれど、その先を言うことにした。
「その怒鳴り込んできた親、あたしの父なんです」
女性は、目を丸くした。
母が殺されたあと。
あたしは茜と違って、登校を続けていた。通り魔のクソ野郎のせいで、残り少ない高校生活を台なしにされるんて、あってはならないと思ったからだ。
でも、本当は無理だったんだと思う。心の底では悲鳴を上げているのに、それを無視して学校に通い続けたせいで、あたしの身体はおかしくなった。あちこちに吹き出ものができて、生理が止まって、身体が鉛みたいに重くなって動かなくなった。すごい眠くなったかと思えば、夜に目が冴えて、朝まで眠れなくなったこともあった。
「心春は恩人なんですよ。あんな事件はなかったし、母はどこかで生きている。そう思い込んだら、すごく心が軽くなった。母には悪いことをしたとちょっと後悔しているけど、正直、ああでもしないとキツかったんじゃないかな。本当に病んでたかもしれないです」
「そうだったんですね……」
女性の声は、軽く震えていた。こんな話を真正面から聞いてくれるなんて、本当に変わった人だ。
東京に出てきてから三年、心春はいつの間にか楠木藍のファンになっていた。
アイドルを推すなんてイメージが全然なかったのでびっくりしたけれど、心春に言わせれば『藍はほかのアイドルとは全然違う』らしい。コンサートに行くようになって、部屋に藍のポスターやグッズが増えて、遊びに行くと〈XROS〉の曲がかかっているようにもなった。心春が楽しいならいいかと、あたしは放っておいた。
そして藍は死んだ。
自殺の理由も判らないうちに、〈XROS〉まで解散してしまった。
心春はそれを全部、なかったことにした。
「信仰……」
「え?」
いつの間にか女性は、思い詰めたみたいな顔になっていた。
「何が真実かなんて、究極のところは判らない。この世界には真実はなく、真実らしいものがあるだけ。そしてその真実らしさは、信仰する人の量で決まる――」
「はい? どうしたんですか、急に」
「心春さんの気持ちが、私には判る。真実を信じるんじゃない。信じたものを、真実にすればいい。この世界はそうやって動いている。みんな多かれ少なかれ、そうやって生きている」
「はあ……」
「藍の死を受け入れられないなら、生きていることにすればいい。大切な人を失ったのなら、なかったことにすれば……」
「その通り」
舌っ足らずな高い声が、あたしの鼓膜を撫でた。
眠っていた心春が、半目を開けていた。
「乃愛ちゃん、この人はすごいよ。藍がキリストだって教えてくれたんだ」
「は? キリスト?」
「藍は復活するんだよ。そのときに、備えなきゃいけないんだ。私は判ったんだよ。この人のおかげで、やるべきことが……」
心春はそこまで言うと、がくりとうなだれて、また寝息を立てはじめた。すーすーと鼻を鳴らす。ムカつくくらい、気持ちよさそうだった。
「あの……すみません。あなたは、誰ですか」
そういえば、まだ名前すら聞いていなかった。女性もそのことに気づいたのか、目を見開く。少し迷った素振りを見せたあと、軽く髪をかき上げた。
「私の名前は――」
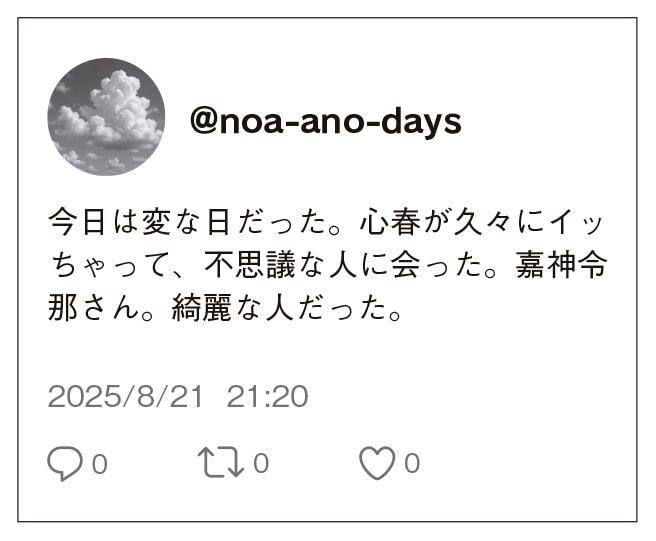
(つづく)
