15
令那さんの家は、彼女が通っている教会から歩いて十分ほどの、閑静な住宅街の中にあった。
これまで見てきた令那さんの優雅な佇まいとは似ても似つかない、少し大きめの地震が来たら潰れてしまいそうな、みすぼらしい外観の二階建ての日本家屋だった。表札には、〈加賀〉と書かれていた。
インターホンを鳴らす。
少し間が空いて、「こんにちは」と令那さんが玄関から顔を覗かせた。見られたくなかったものを見られたとでもいうような、気まずそうな表情をしていた。
「祖父母の代から住んでてね。数年前に母も死んだから、いまは私だけ。ひとり暮らしだと持て余すけど、処分して引っ越すのも大変だしね」
一階のリビングに案内されると、そこは〈書庫〉と呼ぶのがふさわしいような部屋だった。四方の壁が本で埋め尽くされていて、本来窓がある場所も本棚で潰されている。薄暗い中、北欧を思わせるお洒落な照明の下に、古いソファセットがあった。
煙草の臭いが充満していた。ソファテーブルに、吸い殻が盛られたガラスの灰皿がある。令那さんから感じていた優雅なイメージとあまりにも異なっていて、私は戸惑った。
「すごい本ですね……全部読んだんですか」
心のうちを隠すように、本棚を見上げる。
「まさか。置いてあるだけよ」
「それでもすごいです。読書家なんですね」
「ほとんどが読みやすい小説だから、こんなものを読書と言っていいのかは判らないけどね」
確かに、並んでいる本は小説が中心のようだった。私でも知っているような文豪の全集から、ミステリーやライトノベルの新刊も大量に並んでいる。それらを見上げているうちに、私の中に、不思議な感慨が生まれていた。
――この人は、フィクションに囲まれている。
本など数えるほどしか読んだことがないが、出版されている小説とは、才能のある人間が脳を搾るようにして一文字一文字を刻み込んだ、結晶のようなものだろう。とてつもない密度で凝縮されている虚構を、令那さんは大量に読み込んでいる。令那さんは、虚構に魅せられている。
令那さんが一冊の本を抜き出し、ソファテーブルに置いた。
『煩がしい舞踏 加賀美玲』
古びた、ハードカバーの本だった。
「加賀美玲――これが、令那さんの本名なんですか」
「ううん。〈みれい〉は、音は一緒だけど、漢字が違う。一冊だけ出版して消えた、塵みたいな作家よ」
「そんな。本を出すなんて、すごいことですよ」
「だいぶ前に絶版になったんだけどね。もうどこにも流通していない」
「いまはもう書いてないんですか」
「書いてない」
「書けないんですか。書かないんですか」
「どうしてそんなことを聞くの? あまり行儀のいい質問じゃないわね」
「〈シリウス・ミラージュ〉は、小説を書けないことの代替行動なんですか?」
令那さんは返事をせずに、煙草をくわえて火をつけた。所作は落ち着いて見えるが、心は揺れている気がした。
「令那さんは本当は小説が書きたいのに、書けなくなった。占いは、物語を作って相談者に与える仕事です。令那さんは小説の代わりに、占いをしていた。違いますか」
私の言葉を無視するように、令那さんは煙草を吸い続けている。
「〈XNS〉も、そうなんじゃないですか。藍の死に関する物語を考えて、私たちを揺さぶる――そうやって令那さんは、書けない心を癒やしていたんじゃないですか。本当は藍のことなんか、どうでもいいんじゃないですか?」
令那さんは唐突に立ち上がった。吸いかけの煙草を灰皿に置き、本棚に手を伸ばす。
テーブルに置かれたのは、藍の撮った写真集、『Indigo』だった。
「発売日に買ったわ。レシートも見せようか?」
「……ごめんなさい。失礼なことを言ってしまいました」
「いいのよ。判ってもらえたんなら」
ブーンと、スマホが振動する音が鳴る。
チェストに置かれた令那さんのスマホに着信が来ているらしく、鳴り止まずに振動し続けている。「出ていいですよ」と水を向けたが、令那さんは首を横に振っただけだった。
「〈シリウス・ミラージュ〉の客から、連絡が来るのよ。未来を教えてほしい。私の物語を聴きたいって。もう占いの活動なんかしてないのに、ずっと電話がかかってきてる。着信拒否すればいいのかもしれないけど、つながらない電話をかけることが、生きがいになっているのかもしれないし」
「なぜ占いをやめたんですか」
「もう、書いたから」令那さんは再び煙草をくわえる。「彼らが読みたいお話は、ほとんど同じ。あなたは大丈夫。いまはつらくても我慢しましょう。いつか絶対に上手くいく……同じプロットを、表現を変えて量産するだけ」
「だから、〈XNS〉をはじめたんですか」
「私は藍のことを、本当に愛しているわ」
「それはそうなのかもしれません。でも令那さんには、もうひとつの動機があった。陰謀論を作って読者に読ませ、心を揺さぶりたい――〈嘉神令那〉は、〈加賀美玲〉の身代わりだったんじゃないですか」
「藍は、自殺なんかしてない」
突然の強い語気に、私の背中が、びくりと震えた。
令那さんは煙草を灰皿に押しつけて、立ち上がった。ついてきなさいと、無言の背中が言っていた。
二階に上がり、並んでいるドアのひとつを開ける。向かって左側の壁にスクリーンが、天井や隅など部屋のあちこちにスピーカーが設置されている。シアタールームのようだった。
スクリーンの反対側に、ふたり掛けのソファがある。令那さんはそこに腰掛け、隣の席を軽く叩く。私は誘われるがままに、空いたところに腰を下ろした。
「私は子供のころ、もっと広い家に住んでいた。父は小さな会社の社長で、娘に教養を身につけさせようと、ピアノだバレエだ塾だと、ずいぶんあちこちの習いごとに通わせた。友達もろくにできないし、遊ぶ時間も取れない……そんな中、一番の楽しみは、聖書を読む時間だった。〈はじめに神は天と地を創造された〉――天地創造からはじまる聖書の物語は波瀾万丈で、哲学的で、グロテスクな部分も多くて、読んでいて本当に楽しかった。何度読み返しても、新しい発見があった。
小学校の高学年に上がったころ、父の会社の経営が傾いて、両親の不仲が深刻になった。もともと、お金だけで無理やりつながっていたような夫婦だったから、鎖が切れればバラバラになる。家の中の空気は、凍りついたみたいに寒々しくなった。そのころが一番、本を読んでいたかな。ページをめくって、過去や未来に行ったり、あちこちの国や星を旅したり、戦場や殺人現場を覗いたり……本を読んでいるときだけ、目の前に広がる惨めな現実とは、別の空間に逃げることができた。
遊びで文章を書きはじめたのも、そのくらいのころかな。物語を書くことは楽しくて、他人が書いたものを読むよりも、濃密な時間を送れた。見せる友達もいなかったし、ネットで公開するつもりもなかった。ただノートを埋めるみたいに、ポツポツと物語を書いていた」
「でも、作品を発表したんですよね」
「いまから思えば、それが間違いだった」令那さんの声に、影が差した気がした。
「いつも読んでいた文芸誌に、新人賞の募集要項が載っていたの。規定の分量の原稿が、いくつか手元にあった。魔が差したんだと思う。それを送ったらどうなるのか……試してみたくなった。
本が出たときは嬉しかったけど、続かなかった。もともと書きたいように書いていただけだったから、仕事で求められて書くことに全く対応できなかった。作品を書いても突き返される、『こうやって直せ』と言われた通りに直しても、『そうじゃない』と言われる……創作意欲が、ズタズタに引き裂かれていくのが判った。私は、一文字も書けなくなった。ペンを持つと手が震えて、吐き気もするようになって……何も、浮かばなくなった」
令那さんの手が、小刻みに震え出す。
そっと握りしめると、その手の冷たさに驚いた。血が通っていないガラス細工のようだった。
「私は二十代半ばになっていた。両親はとっくに離婚していて、この家で母方の祖父母と暮らしていた。ろくに仕事をしたこともなくて、何かでお金を稼ぐ必要があって、〈シリウス・ミラージュ〉は、そのころに使っていた占い師としての芸名。小説は書けなかったけれど、それ以外の文章は書けた。
阿漕な仕事だったわ。運営会社のサイトに、タロット占いの結果を表示してくれる機能があるから、そこにアクセスして結果を見て、返信を考えて、お客さんにメールを送るだけ。最初は物語を考えているみたいで面白かったけど、占いの結果なんてそんなにバリエーションがあるわけじゃない。すぐに飽きて、自分が詐欺師になったみたいな気がして、つらかった。それでも喜んでくれる人がいたことが、救いだったかな」
「文才があるからだと思います」
「ありがとう。そんな繰り返しみたいな毎日だったけど……ふと見ていたテレビの中に、彼がいたの」
――藍が。
「それまでアイドルに興味を持ったことなんかなかったけれど、妙に目を惹かれた。ダンスも、歌も、顔も、身体も――藍のやることすべてに、私は目を奪われていた。調べてみたら、彼が優れた写真家であり、作曲家でもあることを知った。そういう文化的なところに惹かれたんだと思う。追いかけはじめて、二年くらいかな。にわかファンでごめんね」
令那さんが傍らにあるリモコンを操作すると、スクリーンに藍の姿が映し出された。武道館でのライブ映像だったが、音は出ていない。藍はステージの片隅でスポットライトを浴び、汗だくになって、激しいダンスを踊っていた。
「藍は、自殺なんかしていない――そのことは、確信してる。彼はそんなことをする人じゃない」
「本当にそう思っているんですか。警察が発表しているんですよ」
「何かが間違ってるのよ。律さんも、私と同じ意見じゃなかったの? 一緒に〈XNS〉をやってくれるって、言っていたはず」
「そのつもりです。でも、自信がなくて」
自殺現場を見ると、藍は自殺したのではなく、同行者に殺されたのではないかという思いが強くなった。だけど、それには何の根拠もない。そもそも警察が、殺人の痕跡を見逃したりするだろうか。
「警察が自殺だと発表していることを、否定する――普通、それは陰謀論と呼ばれます。あらゆる説をフラットに考えてしまったら、虚無主義に陥る――ならば、警察が捜査をして導き出した答えは、本物なんじゃないでしょうか。少なくとも、素人の私たちが頭だけで考えた説よりは、信憑性が高い。私も藍は、自殺するような人じゃないと思います。でも、性加害をするような人だとも思っていなかった。自身が持てないんです」
「律さんは、週刊誌の記事が真実だと思ってるの?」
「少なくとも、プロの記者が取材をして書いたことです。私たちの何の根拠もない空想よりは、真実に近い可能性が高い」
気がつくと、拳を握りしめていた。
ほとんど懇願するような口調で、私は言った。
「本当のことを教えてください。令那さんはいまでも本当に、藍が自殺していないと思っているんですか。それとも、本当は自殺だと思っているのに、そうじゃないと思い込もうとしているんですか」
あなたは〈XNS〉を、何のために作ったんですか。
物語を書くために、作っていたのではないですか――。
そこまでは口に出せなかった。
うなだれた。ひどい疲労が、肩にのしかかっていた。
「――律さんは」
どれくらい時間が経っただろう。
静寂に満ちたシアタールームに、令那さんの声が厳かに響いた。
「信仰について、どう思う?」
顔を上げる。
令那さんは、スクリーンに映る藍を、真剣な眼差しで見つめていた。
「なんですか? 信仰……?」
「何回か教会に来たでしょう。キリスト教を信仰する人たちのことを、どう思う?」
教会の座席で両手を握り合わせていた、令那さんの佇まいを思い出す。真摯に祈りを捧げている姿は、それ自体が聖なるもののように美しかった。あの教会では、何人かのキリスト教徒を見た。皆、大切なものとつながろうとするかのような、凛とした雰囲気があった。
「信仰は、とても崇高なものだと思います」
「なぜ?」
「信者のかたが自らを律して、全身全霊で神様に向き合っている感じがするからです。令那さんに比べて、無宗教の私は未熟だなと思います」
「じゃあ、新興宗教はどう? 拝金主義のあくどい教祖に騙されて、家族の反対を押し切り、全財産を喜捨してまで教団に搾取されている――そういう人を見て、崇高なものだと思う?」
「いえ、かわいそうだと思います。でもそんな変な宗教とキリスト教は、全然違うじゃないですか。教会は、財産をむしり取ろうとしませんよね」
「トカゲ型宇宙人や、ディープステートを信じている人はどう? 栗林さんを見て、崇高だと感じる?」
「感じません。あんなもの、ただの陰謀論でしょう」
「何が違うの? トカゲ型人間は、財産をむしり取るわけじゃない」
「何がって……」
私は、息を呑んだ。
問い掛ける令那さんの目は、怖いほどに真剣だった。彼女にとってこの設問は、際どい冗談や、意地の悪い試験ではない。魂を懸けるほどに、真剣なものなのだ。
「〈はじめに神は天と地を創造された。地は形なく、むなしく、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた。神は『光あれ』と言われた。すると光があった〉」
「それは、聖書の最初の文章ですよね……」
「そう。いつの間に覚えたの?」
「令那さんの影響で、パラパラと読んでるだけです。詳しくはないです」
「『創世記』では、神がこの世界を作ったとされている。でもいまの科学では、百三十八億年前にビッグバンが起きて、宇宙が生まれたことが判っている。高熱だった宇宙はやがて冷え、ガスが集まって塊になり、星が生まれた。『創世記』に書かれている天地創造は、科学的事実とは食い違った作り話にすぎない。まっさらな目で、比較してみて? トカゲ型人間が地球を支配しようとしている――そんなレベルの話と、どう違うの?」
「そんなことを言って大丈夫なんですか。キリスト教徒なのに」
「聖母マリアはヨセフと結婚する以前、男と交わることなくイエスを処女懐胎した。ソドムとゴモラが神に滅ぼされるとき、ロトの妻が言いつけに逆らって振り返ってしまい、塩の柱になった。イスラエル人による出エジプトの際、モーセが手をかざすと海が割れ、乾いた土地を渡って逃げることができた。イエスが埋葬された三日後、墓から復活してやがて天に昇っていった。いまの科学では説明できない――いや、常識的にも考えられないことが聖書には堂々と書かれていて、私たち信者は色々な理屈をこねて信仰を続けている。これは陰謀論と何が違うの? こんなものを信じている私のことを、なぜ崇高だと思ったの?」
「確かに、聖書に書かれている内容はありえないかもしれません。でもそこに書かれている精神や規範は、尊いものでしょう。トカゲ人間が、私たちに何を与えてくれるんですか」
「宗教のせいでたくさんの戦争が起きてるのに? 十字軍の遠征、三十年戦争、スペインによるラテンアメリカへの入植……〈よい〉とされる信仰のせいで、すさまじい量の血が流されてきたのに?」
「いい加減にしてください。何が言いたいんですか」
ほとんど悲鳴を上げるように言った。令那さんから押し寄せる知識の圧力に、心が潰されそうだった。
「この世界には、真実は存在しない。あるのは、ただ、信仰の強さだけ」
「は?」
「聖書を信じることも、トカゲ型人間やディープステートを信じることも、全部同じようなもの。陰謀論を信じている人を律さんは馬鹿にするかもしれないけど、大差なんかないのよ。律さんも神社に行ったら、神様に祈りを捧げるでしょう? そんなものいないのに。身内が死んだら、お葬式を挙げて故人の冥福を祈るでしょう? 冥土なんか存在しないのに」
「確かに――私含めて、人間が非合理なことをするのは認めます。でも、真実が存在しないとは、言いすぎじゃないですか。さっき令那さんは、この宇宙はビッグバンで誕生したと言ったじゃないですか」
「それも世間で言われているだけで、本当かどうかは判らない。地球が本当は平面で、闇の政府が世界を支配していたとして……律さんはそれを否定できる?」
「それは、虚無主義です」
令那さんが否定していた、〈過度な相対化〉だ。あらゆる説をフラットに並べていったら、この世界は秩序を失い、めちゃくちゃになってしまう。
「だから、信仰が必要なの」
令那さんは、落ち着いた声色で言った。
「聖書の内容もトカゲ型人間もディープステートも科学も、どれも真実だとは証明できない。この世界は虚無で、私たちは何も判らない。それでも人間は、何かを信じないと生きていけない。虚無に、虚構を貼りつける必要がある。
信仰する対象なんて、どれも馬鹿馬鹿しいものよ。でもその中には、キリスト教みたいに多くの人に信仰されている虚構もある。その数こそが、本質なの。信じる人の気持ちの量が、馬鹿馬鹿しいフィクションに力を与え、人々から信じられることにより、虚無に意味が生まれる。〈本物〉になっていく。二十億人に信仰されたら、トカゲ型人間も〈本物〉になる。むしろ信じていない人間のほうが、信仰を持たない未熟な人に見えるようになる」
「何が、言いたいんですか……」
「藍も、そういうことにしよう。私と、一緒に」
令那さんの声が、凄みを増す。
「彼は自殺なんかしていないし、性加害もしていない。何かの犠牲になって、彼は尊い死を遂げた。私が望んでいる世界は、そういうもの。律さんはどうなの?」
「私が望んでいるもの――」
「私たちは、藍に見捨てられたわけじゃない――そういうストーリーを望んでいるんじゃないの? 多くの人に信仰されれば、虚構は〈本物〉になる。私とあなたなら、きっと強い信仰を作ることができるわ」
私が望んでいる世界は――。
無音の中、藍は必死に踊っている。彼はそこらのアイドルのように、安い笑顔を振りまいたりしない。ただ純粋なパフォーマンスのみで観客を魅了し、私の現実を彩ってくれた。
その藍は、もういない。彼は女性に性加害をし、週刊誌報道が出ることを恐れて自殺した。彼は、俗物だった。私の世界は、意味を大きく失ってしまった。
その意味を、少しでも取り戻せるのなら――。
藍は何かに巻き込まれて、殺された――その物語を信じられるのなら。
「私は」
声がかすれた。
私は、藍は自殺したんだと思います。
いま本心が判りました。私は、警察発表が正しいと、ずっと思っていたんです。本心から目を逸らしていました。ごめんなさい。
令那さんが私を見つめる目が、どんどん光を失っていく。浮かんでいる言葉を口に出せているのか、判らなかった。それでも気持ちが伝わっているのだと思った。
「――ちょっと待って」
令那さんが、唐突に言った。
「何か、臭いがする」
「え?」
「ほら……焦げたような臭いが……」
令那さんが呟いた瞬間、スクリーンに映し出されている藍の姿が、陽炎のように揺らいだ。
床からうっすらと、煙が立ち上っていた。
「煙草……」
令那さんは、リビングで煙草を吸っていた。吸い終わった煙草を灰皿に押しつけ、吸い殻の山に押し込んでいた。
あのとき、火は充分に消えていただろうか。
燻った灰が吸い殻を熱し、やがて出火した。リビングには、大量の本がある。わずかに熾った火はあっという間に燃え広がり、本を呑み込んでいって――。
床下から湧いた煙は、いつの間にか部屋に充満していた。プロジェクターから照射される光が、空中に乱反射している。木の床が、にわかに熱を帯びている。パチパチという木が爆ぜるような音が、階下から響く。
「逃げよう」
令那さんは、窓に手をかけていた。二階から飛び降りるつもりだ。
私は――。
「ちょっと待って。どこに行くの?」
「逃げてください。私は下に行きます」
「は?」
「絶版なんですよね、あの本」
私の言っていることを理解したのだろう。令那さんの目が、驚きに見開かれた。
「だからなんなの。私の書いた本なんて、何の価値もない」
「そんなことはないです。尊いものですよ」
「もう燃えてるわ。あんなものどうでもいい。行くわよ」
私は言うことを聞かず、外に出るドアに手をかけた。
「逃げてください。私もすぐに行きますから」
「待ちなさい! 律さん……!」
返事をせずに、ドアを開けた。ごうっと、強い風が階下から吹き上げてきた。熱い。太陽がすぐ近くにあるみたいに、熱源が空気を焼いている。
藍のことは、もう諦めた。それでも、この虚無に意味を与えるものがあるとするのなら――。
私は階下に向かって、身体を躍らせた。
16 @nihon-tsushin 2025/07/22 19:05
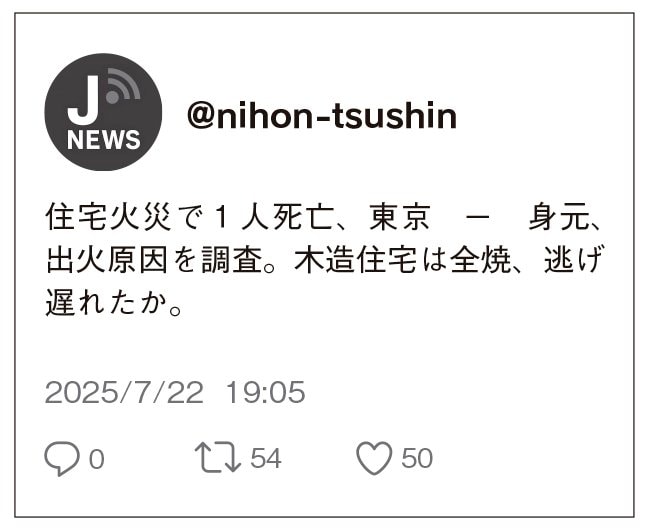
(つづく)
