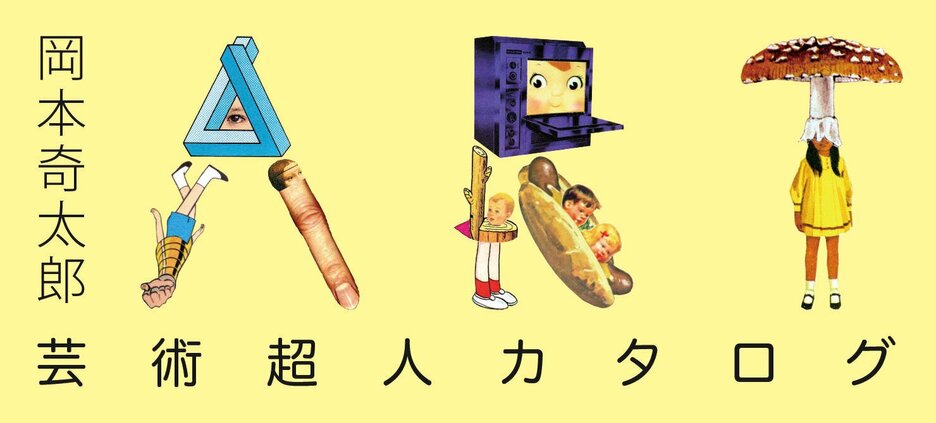2011年に始まった『芸術超人カタログ』は今回で最終回になる。当連載で僕が意識していたのは、芸術に興味を持たない人に向けて、理解しやすい文章を書くことだった。一見、高尚な趣味と捉えられがちな芸術を1人でも多くの人に身近に感じてもらいたい。そう願うのは、僕自身が芸術と向き合うことで生きがいや心の安寧を得ることが出来たからだ。
しかし、その啓蒙活動は容易ではない。家族や友人にさえ一緒に美術館に行くと、感嘆する僕の隣で「私にはわからない」と眉をひそめる人がいる。そのように、わかる/わからないと美術鑑賞を難しく考える人は、芸術家とは哲学的であり、作品には何かしらの意図があるという固定観念に強く縛られているように感じる。確かにそのような芸術家や作品が存在するのも事実だ。だが、まずは理解するよりもどう感じるか、自分の心の声に耳を傾けることが最初の一歩になる。好みの作品が見つかれば芸術に目を向けるきっかけになるだろうし、たとえひと目見て興味が持てない作品だったとしても、作家のバックボーンなどを知ることで意識が向かうこともある。その一助を担いたいとの想いで今日まで僕は書き続けてきた。
一方で、芸術家の半生を調べて書くことや、作家本人に直接取材をして意見を聞くことは、その人の人生を疑似体験するような感覚があり、毎日なんとなく生きているだけだった僕の意識をも変革した。
当連載を始めた時、僕は会社勤めをしていた。それが今では、万事順調というわけではないが、美術作家としての活動で暮らしを立てている。
これまで度々触れてきたが、僕が芸術に関心を持つようになったのは、雑誌編集者時代に担当した吉永嘉明氏との出会いがきっかけだった。5年の間に仕事仲間と親友と妻を相次いで自殺で亡くし、極度の鬱状態に陥った吉永氏は、自身の希死念慮を振り払うためにコラージュの制作に没頭していた。その常軌を逸した作品群を目の前にした時、わかる/わからないを超えて強い衝撃を受けたのだ。
それから僕は美術鑑賞をするようになった。目的はまだ見ぬ刺激的なものに出会いたいということには違いなかったが、同時に非日常的な世界に没入することで、日々の仕事による精神的負担から一時でも解放されたいという切実な悩みもあった。そうして現実逃避と原稿執筆を繰り返すうちに、芸術家たちは当たり前の日常から訣別したからこそ、今こうして僕を勇気づけてくれる存在になったのではないかと考えるようになった。
江戸時代、40歳で弟に家督を譲り、画業に打ち込むようになった伊藤若冲が、もしもそのまま京都錦市場の青物問屋『桝屋』の主人だったら、彼の存在を知ることはなかったはずだ。
戦後、流派に所属し弟子を育てることで成り立ついけ花の世界で、中川幸夫がフリーのいけ花作家の道を歩まず、池坊門下として留まり続けていたら、「世界の現代アートの前衛」などと評されるわけがない。


1980年にニューヨーク近代美術館で開催されたピカソ展に触発されて『画家宣言』をした横尾忠則が、画家になることなく未だグラフィックデザイナーだったら──
皆、それまでの環境を断ち切り、ただ自分の信じた道に舵を切ったからこそ、手に入れた未来ではないだろうか。憧れの芸術家たちのターニングポイントや覚悟を決めた瞬間を知れば知るほど、僕自身にも会社勤め以外の生き方があるのではないかと思いを巡らせた。
「とりあえず何かやってみたらいいんじゃないですか」
そのように何人かの取材した作家に背中を押してもらい、切って貼るだけのコラージュから始めて今に至る。誰にでもすぐに出来る技法だが、実際にやるかやらないか。それが運命の分かれ道だったように思う(今後の保証も何もないが)。
いくつもの作品に心躍らされ、数々の芸術家の生き様を知って、連載開始前には想像すらしなかった人生を歩んでいる。当連載を通して芸術が人に与える影響を身をもって知ることになったからこそ、今後も芸術について発信することを止めるつもりはない。