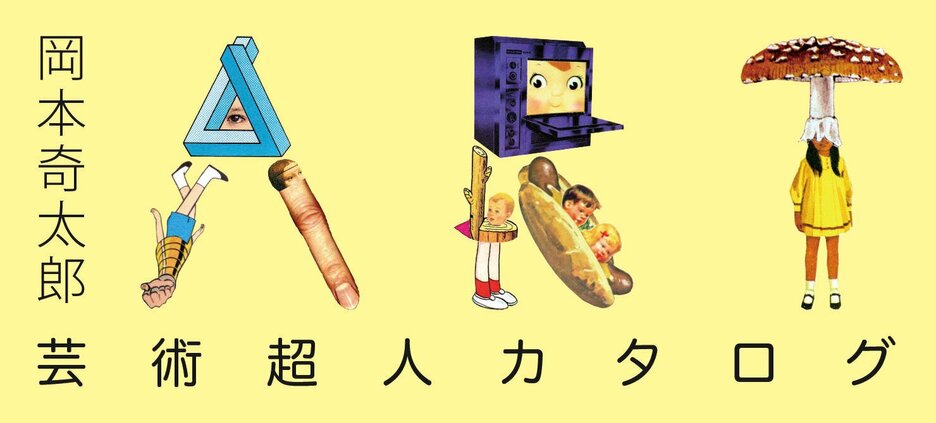今年2月、日本芸術院に新設された「建築・デザイン」分野の会員に横尾忠則が選出された。1981年のいわゆる「画家宣言」以降、あらゆる制約から解放された状態で絵画を描き続ける美術家が、なぜこのタイミングでデザインを評価されるのか。それはこれまでの日本芸術院という組織の在り方が関係していると考えられる。
日本芸術院は、院長1名と終身の会員120名以内で成り立つ「芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関」で、その歴史は100年以上にも及ぶ。会員は〈美術〉〈文芸〉〈音楽・演劇・舞踏〉の三部門の芸術家で構成され、各部門に設けられた複数の分野それぞれに定数が定められている。だがその分野は2022年に組織改革が行われるまでほとんど変化はなく、〈美術〉部門においては100年近く、「日本画」「洋画」「彫塑」「工芸」「書」「建築」というジャンル分けがなされてきた。横尾忠則を「日本画」もしくは「洋画」で括るのは違和感を覚えるし、コンセプト重視の現代アートなどはここに入り込む余地すらなかったのだ。
そうしてようやく昨年、時代とともに多様化する芸術に対応すべく分野が見直され、「日本画」「洋画」は「絵画」、「彫塑」は「彫刻」に再編、「工芸」「書」はそのままに、「建築」は「建築・デザイン」に変更、新たに「写真・映像」が追加されることになった。
今回は「建築・デザイン」分野の会員に選出された横尾だが、たとえ「絵画」で選ばれていたとしても腑に落ちただろう。しかし一方で、これまでデザインや絵画をはじめ、舞台美術、映画出演、小説など、あらゆるジャンルを越境しながら活動してきた横尾忠則という作家を、そもそも一ジャンルで捉えることなど不可能だと思う気持ちもある。
現在、ギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中の『横尾忠則 銀座番外地 Tadanori Yokoo My Black Holes』(6月30日まで)は、日本芸術院に選出された主な評価理由でもある「文学、演劇、音楽、映画、ファッション等、様々な分野に活動の場を拡げた43年前のデザイン」(1960~80年代)に焦点を当てた展覧会だ。しかしデザインの完成品ではなく、作品を構成するラフスケッチ、アイデアノート、版下、色指定紙など、作品完成以前の「デザイン表現のプロセス」を公開するという一風変わった展示内容となっている。
会場で色指定紙などに鉛筆で書き込まれた横尾による指示の痕跡を見ながら、僕は浮世絵のことを考えていた。絵筆を用いて自分一人で完結させる絵画と違い、ここにあるデザインは出版社や印刷所の人間など、第三者の手が加わってようやく印刷物というカタチになることが本展を観ればよくわかる。それが絵師、摺師、彫師の三者協業で作品を完成させる浮世絵を思わせたのだ。加えて浮世絵自体が、江戸時代においては雑誌やポスターといった広告メディアであり、今回の展示物と機能的にも一致する。
デザインも浮世絵も厳密には芸術ではないが、こと横尾のデザインに関しては、1968年にニューヨーク近代美術館で開催された世界ポスター展で、60年代の最も重要な作品として選出された『腰巻お仙』が、同館にコレクションされるなど世界が認めるアートである。またポスター同様、大量生産されるものの中にも十分芸術的価値が宿ることを先立って証明したのが浮世絵だった。

東京国立近代美術館 ポスター(色指定紙)1968年

ポスター(アイデアスケッチ) 1969年
そしてアメリカのライフ誌が選んだ『この1000年で最も重要な人物100人』に日本人で唯一ランクインしたのが浮世絵師・葛飾北斎である。
横尾忠則と葛飾北斎。両者は共に広告仕事も絵画制作も手掛け、森羅万象をテーマの対象として描く姿が重なる。
死の間際、「あと10年、いや5年の命を与えてくれれば、本物の絵描きになることができるのに」と言い残して90歳で亡くなった葛飾北斎。日本芸術院の選出に際し、「これからが本番です」と語った横尾忠則現在87歳。
これまでも散々見せ付けてくれた横尾忠則が、この先の本番で何を見せてくれるのか。まだまだ目が離せそうにない。