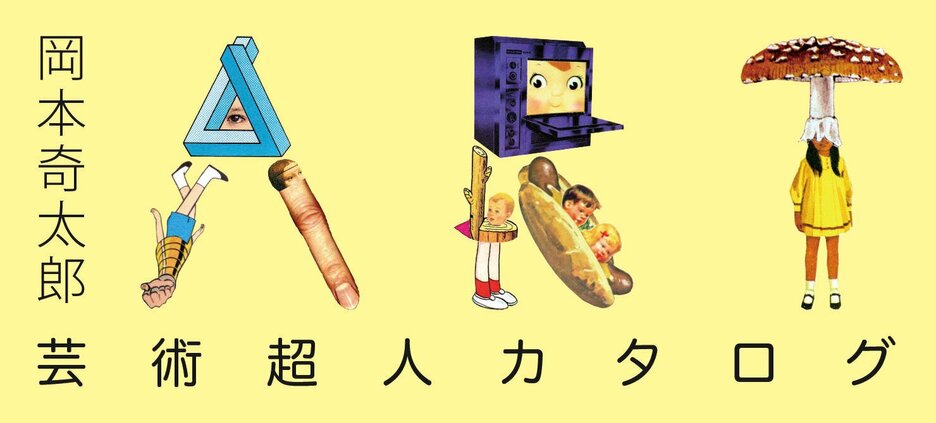当連載ではこれまで、名もなき職人の手仕事によって作られた日常の生活道具である『民藝(民衆的工藝)』と、その提唱者の柳宗悦について度々紹介してきた。そして柳が中心となり東京・駒場に創設された日本民藝館にも、僕は幾度となく足を運んできた。
僕にとって日本民藝館は、他人の意見や評判に惑わされない審美眼を磨くための道場のような場所である。どういうことか。民藝とは柳宗悦が直観によって見出した美を指すが、直観で物を観るのに知識は必要ない。むしろ知識に囚われると直観が鈍る可能性があるため、日本民藝館では作品に対しての説明書きが最小限に留められている(品名と時代程度)。そのままに観て何を感じるか。その時に、暮らしの中にある無銘の雑器の美にピントが合えば、僕は自分自身の眼が育っていることを実感するのだ。
現在開催中の『聖像・仏像・彫像―柳宗悦が見た「彫刻」』(9月3日まで)は、彫刻という観点から館のコレクションに目を向ける試みとなっている。一見、民衆の生活とは関係が薄いように思われる彫刻から見える民藝とは──
柳宗悦が深く関わったはじめての彫刻作品は、「近代彫刻の父」と称されるオーギュスト・ロダンのブロンズ像だった。1910年、柳も創刊に参加した文芸美術雑誌『白樺』がロダン号を発行したことを機に、本人から小品3点が送られてきた。その初来日のロダン彫刻を横浜港に引き取りに行ったのが柳だった。それまで日本には仏像彫刻は存在したが、西洋的な「彫刻」という概念はなく、ロダンの作品を実見した柳は衝撃を受け、「そのときの想いは全く筆には書けません」と『白樺』に記すほどだった。
そのような貴重な体験を経て、彫刻の知見を深めた柳が見出したのが、本展でも展示されている木喰の仏像だ。江戸時代の造仏聖(放浪しながら仏像をつくる遊行僧)として、今では円空(本展出展)と共に取り上げられることが多い人物だが、柳が調査に乗り出すまでは、全くと言っていいほど知られていなかったという。しかし、僕自身がはじめて興味を持った仏像彫刻の作者が、まさにこの木喰と円空だった。興味を持った一番の理由は、アマチュア故に正統的な仏師が生み出すような、形式化された造形からはみ出していたことが大きい。両者とも木という素材を生かしつつ、穏やかな微笑みがとりわけ印象的な木喰仏と、形象を必要最低限に単純化し、現代のオブジェのような円空仏。そこには伝統的な仏像が持つような荘厳さが欠片もない代わりに、だからこそ湧く親近感がある。
木喰も円空も庶民信仰の要求に応える小規模な社寺に遺品を多く残し、時に一宿一飯の恩義にあずかった庶民宅で発見されることもあった。概して「彫刻」は民衆の生活に不要に思われるが、木喰と円空の仏が宗教の対象として人々の生活に埋め込まれていたことを考えると、作品ではなく日用の品に近く、民藝との繋がりを強く感じさせる。
沖縄の石像彫刻も柳との関わりは深い。1938年から40年の間に4度沖縄を訪ねている柳は、玉陵をはじめとする王陵(王の墓)、墳墓に納められた石棺、石橋の勾欄の浮彫などに感嘆し、日本民藝館には当時撮影された写真が数多く残る。中でも屋根獅子(画像上)は「琉球に於ける民間彫刻として最も興味深い」と評している。建築物の一部のため蒐集は叶わなかったが、後に柳の長男の宗理が日本民藝館の館長をつとめた時代に、8体の屋根獅子をコレクションに加えており、その内の2体が今回展示されている。

20世紀前半-中葉 高38.4cm *柳宗理蒐集
日本民藝館蔵

19-20世紀 高64.3cm *芹沢銈介旧蔵
日本民藝館蔵
最後に付け加えたいのが、本館1階玄関で特集展示されている『民族の仮面』である。ここで展示されているアフリカとアジアの他、世界各地の仮面は、そのままに観て何を感じるかという意味では、最もインパクトを与えるであろう。かつて民俗資料として扱われていた造形は、ピカソをはじめとする前衛的な芸術家たちが注目し、強烈なインスピレーションを得て、新たな時代を切り拓く表現の糧となった。造形的な面白さに目は行きがちだが、個人的にはこれらの仮面を眺めていると、その土地に住む人々が語り継いできた歴史や文化の気配を感じずにはいられない。あなたなら直ちに何を観るだろうか。