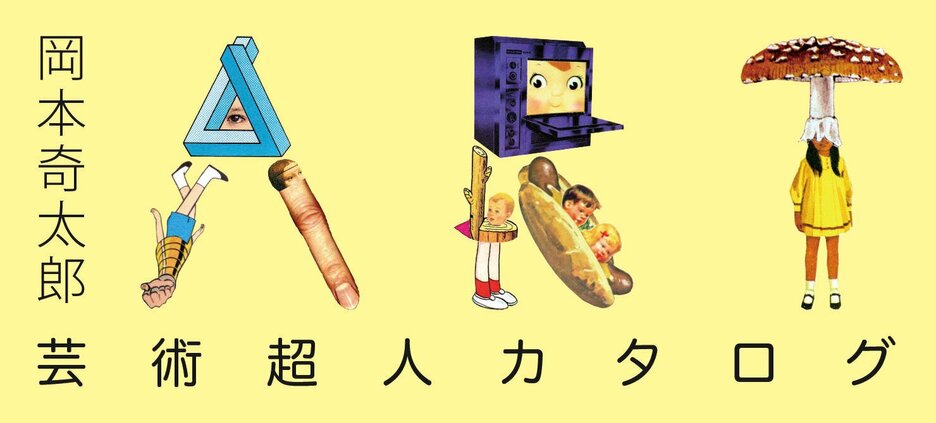前回、前々回と僕の人生を予期せぬ方向に導いた岡本太郎について書いてきたが、自分の生き方を左右するほどの人物を褒め称えるのは難しいことではない。紙幅の都合上、書けなかったが特筆すべき点もまだまだある。だが相反するものをぶつけ合せ、その結果生まれる不協和音を良しとした『対極主義』の実践者・岡本太郎について語る時、優れた部分だけを取り上げて無難に着地させるわけにはいかないだろう。そもそも僕には「法隆寺は焼けてけっこう」「ピカソをのり超える」等、権威に屈することなく、あえて否定することで新しい創造を掴み取ろうとする太郎の姿勢に鼓舞された想いがある。最終回ではそんな太郎に倣って、巨大な存在をただ崇めることを止め、さらに岡本太郎を掘り下げてみようと思う。
現在大阪中之島美術館で回顧展『展覧会 岡本太郎』(10月2日まで。以後、東京、愛知を巡回予定)が開催中だ。今展のことは当連載で取り上げるテーマの候補のひとつとして、担当編集者のTさんから半年近く前に知らされていた。しかし岡本太郎に関しては、今更新しい発見もないだろうと、その案内メールも一瞥しただけだった。何より僕は太郎の著作を通して語られる言葉には大いに刺激を受けてきたが、絵画作品はつまらないものが多すぎると思っている。正確にはある時期を境に退屈になったという印象だ。
18歳でヨーロッパに渡った岡本太郎は、1930年代をパリで過ごし芸術家としての基盤を築いてゆく。パリに移り住んだ当時の太郎は、自分と同じく日本から留学で渡った画家たちが、一様に日本人にとって必然性のないパリの街角や金髪美人を描くことに強い抵抗を感じたという。その結果、太郎が最初に探求した表現が抽象絵画だった。
「この形式は世界共通語として、だれにでも語りかけることができる(中略)地理的、民族的なズレもありません」。
次いで太郎は夢や無意識の非合理の世界を描く、抽象表現主義へのアンチテーゼとして起こった超現実主義(シュルレアリスム)を自分の中に吸収しようとする。そして「抽象的要素と超現実的要素の矛盾のままの対置」を強調し、創造へと転換する「対極主義」を生み出した。この抽象と具象が交錯したような独特のスタイルで描かれたものが僕が好きな岡本太郎の絵画作品で、時期的にはパリ時代(第二次世界大戦の勃発により日本へ帰国するまでの約10年)から51年に東京国立博物館で縄文土器に出会うまでに描かれている。
それ以降は縄文土器から感じ取った呪力のイメージを、梵字を彷彿とさせるような文様として作品に取り入れるようになった。それはヨーロッパで芸術を学んだ太郎が帰国後、ヨーロッパそのものに対する極として日本独自の縄文をぶつけ合わせ、世界的に類を見ない新たな芸術を創出しようとした証かもしれない。しかしその結果確立したスタイルを太郎は手放そうとしなかった。著書『自分の中に毒を持て』の冒頭にある、「瞬間瞬間に新しく生まれかわって運命を開くのだ」「今までの自分なんか、蹴トバシてやる」という勇ましい言葉とは裏腹に、(ある時期を境に)代わり映えしない絵を終生描き続けた太郎には正直がっかりである。一ファンとしては、のり超えてやると挑んだピカソのように、自己模倣を拒否し、常に破壊と再生を繰り返しながら新境地を開拓し続ける太郎の姿が見たかったからだ。

川崎市岡本太郎美術館蔵

ソロモン・R・グッゲンハイム美術館蔵
(ニューヨーク)
そういうわけで気に留めもしなかった展覧会だったが、ちょうど来阪する用事があったり、友人からチケットをもらうなどの偶然が重なり足を運んでみて驚いた。そこには今までに見たことがない、いかにもパリ時代を彷彿とさせる『露店』という作品が展示されていたからだ。僕が見たことないのも当然で、日本での公開は約40年ぶり。さらに対極主義誕生前夜の31年から33年に描かれたと推測される未発表作品3作も出品されている。最初期から最晩年までの代表作・重要作を網羅した没後最大規模の大回顧展は、岡本太郎入門編としては勿論、僕のように「今更新しい発見もないだろう」と高を括っている連中にも、目を開かせる画期的な展覧会といえるだろう。