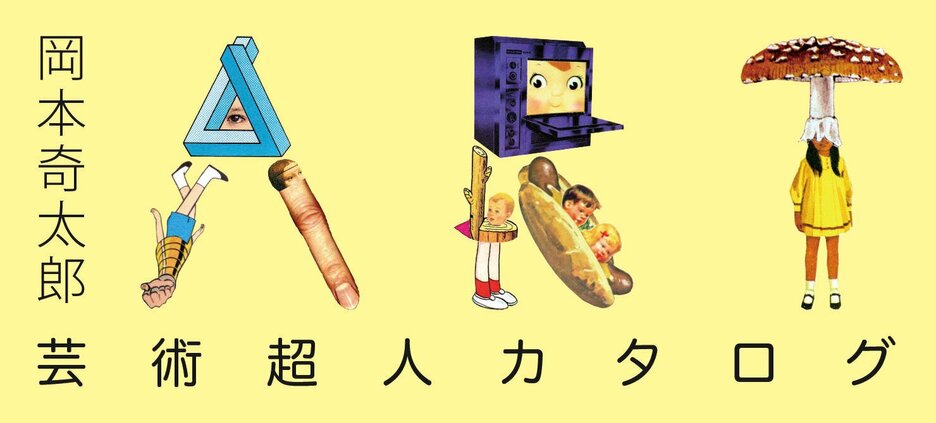春になると府中市美術館で開催される『春の江戸絵画まつり』に足を運ぶようになって10年近くが経つ。美術館は府中の森公園内にあり、鑑賞後はビール片手に花見を満喫するのがいつものお決まりのコースだ。毎回来てよかったという満足感のある内容だが、近年は特に企画タイトルから驚かされ、独自の切り口の展示を楽しませてもらっている。
『へそまがり日本美術』では徳川家光の類をみないユルすぎる絵の横に、蛭子能収さんの作品を配置するという展示構成に意表を突かれ、『ふつうの系譜』では“奇想”が人気の昨今の江戸絵画ブームの中で、あえて“ふつう”にこだわることが普通じゃない展示に思えた。そして現在開催中の『江戸絵画お絵かき教室』(5月7日まで)もまた、絵画の展覧会なのに『お絵かき教室』と銘打つところが、実に府中市美術館らしいタイトルで期待が高まった。
絵を描いて遊ぶ子どもたちが描かれた長沢蘆雪の『唐子遊図屏風』(図右)の露出展示から始まる本展は、府中市美術館として初めての試みとなる、描くという視点から江戸絵画を楽しむ展覧会になっている。
まずは江戸絵画の主な題材である山水(風景画)、人物、花、動物の4つのテーマの絵の展示とその描き方についてである。
普段から友人知人に江戸絵画の魅力を触れ回る中で感じるのは、江戸時代の絵に対して、古臭く堅苦しいという先入観を持つ人の多さである。しかしここで展示される円山応挙の子犬(図左)は現代人が見ても明らかに可愛く、耳鳥斎が『絵本水や空』で描く歌舞伎役者たちは、時代を超えてなお面白おかしく映るに違いない。
そしてそれらはイラストレーターの長田結花さんによる描き方のコツとともに紹介されており、会場内のお絵かきコーナーでその通り描いてみると発見があった。実際に人物や動物を自分の目で見て描くと苦戦することは長年の経験上わかっているが、既にある絵を手本にするとそれなりに描けてしまうのだ。
江戸時代の絵画の習得方法がまさに素晴らしい絵を真似ることが主流だった。現代では他人の作品を真似ることは「パクリ」と非難されるが、一方で「学ぶ」の語源は「真似ぶ」という説もある。会場に中国の絵、雪舟の絵、オランダ本の絵などに学んだ作品が並ぶのは、多くの画家たちが手本となる絵の模倣を繰り返すことで画法を吸収してきた歴史があるからだ。
これは江戸絵画に限った話ではない。僕が習う茶道の世界に「守破離」という学びの段階を示す言葉がある。始めに師匠に教わった型を徹底的に守り、次に他の教えも学ぶことで既存の型を破る。そして独自の境地を切り拓いて最初の型から離れるという意味だ。
いつまでも他人の真似に終始すれば確かに退屈に違いないが、模倣を繰り返し、自身の技量を高めた先に独創は生まれるのではないだろうか。
本展では「守」から離れ、オリジナリティを追求する画家の痕跡も見られる。


江戸絵画の展示を観に行くと虎の絵をよく目にするが、江戸時代の日本に虎は生息していなかった。そのため画家たちが描くのは中国の絵の中の虎か、想像を膨らませて描いた、今見るとちょっとおかしな虎の絵が多い。しかし本展では輸入された虎の毛皮を研究した円山応挙の調査報告的な『虎皮写生図』や、岸駒が入手した虎の頭蓋や四股の資料など、本物に迫ろうとした画家たちの執念までもが展示されている。
またそれらを描くための画材や作品を彩る表具まで、ただ絵を観るだけでは知り得ない情報をも見られるのが本展の特徴だ。
例えば当時の絵具は、現在のようにチューブから出してそのまま使えるわけではなく、植物、昆虫、鉱石などから抽出して作っていたこと。そしてそのレシピ。
実際に江戸絵画を目の前にすると、絵自体とそれを装飾する表具が一体で作品とわかるが、どのような狙いと手順で取り付けられるかなど。
そして一般的な江戸絵画の展示では知る由もない情報の紹介を差し引いても、本展が豪華過ぎる“江戸絵画オールスター”による展覧会であることを最後に付け加える。