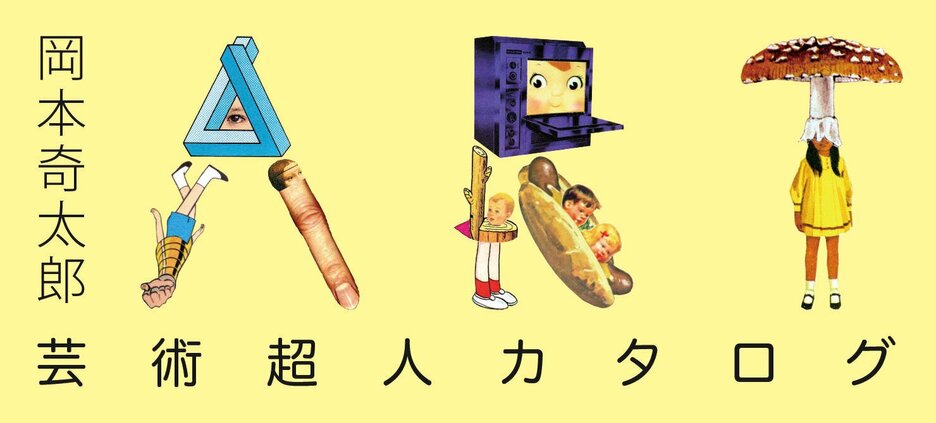表千家茶道の稽古を始めて2年半が経つ。その間に出会った人に、「趣味で茶の湯を」などと言うと、大体「それはそれは」と感心したような反応が返ってきた。かつての僕自身もそうだったが、お茶の世界と繋がりを持たない人にとって、茶の湯とは難解な日本の伝統文化というイメージがあるのかもしれない。一方で、缶チューハイ片手に街中を徘徊するいつもの僕を知る友人には、「なんで奇太郎が?」と薄ら笑いされる。しかしそれも茶の湯を一段高いところにあるものとして見ている証ではないか。「あんたは茶室で抹茶より赤ちょうちんでお酒でしょ?」ということだろうが、僕の中では両方とも似たようなものなのだ。
かの千利休が和歌に託して茶の湯の教えを示した『利休百首』の中に、「茶の湯とはただ湯をわかし茶をたてて飲むばかりなる事と知るべし」というものがある。確かに茶の湯にはさまざまな作法があるが、それらに縛られず、ただ美味しく飲めばいいとなれば緊張も解けてくる。僕にとっては呑み屋で刺身や焼き鳥を食らう時、日本酒や焼酎が呑みたくなるように、茶室で食べる和菓子には抹茶が合うというだけのことだ。
しかし極まって酒を呑んでいるとアル中呼ばわりされるのに、茶を飲むことを極めようとすると茶道というひとつの道になるのはなぜだろうか。素人同然の僕には未だ知り得ないが、今回は酔っ払い男が茶の湯の道に迷い込んだ経緯について書きたいと思う。
最初のきっかけは、千利休の弟子で茶の湯に魂を奪われた戦国武将・古田織部を描いたギャグマンガ『へうげもの』(山田芳裕)だった。それを手に取る前は、冒頭でも述べたように堅苦しい作法に則ってただお茶を飲む文化程度に思っていた。しかし物語が進むにつれ、どうやら茶の湯とは大人が懸命にのめり込む壮大なお遊びの世界であり、様々な文化を内包する総合芸術であることがわかってきた。
それから数年が経ち、ひょんなことからアナログコラージュという手法で平面作品をつくるようになった僕は、次第に陶芸やいけ花表現などにも興味が湧くようになった。しかしそれぞれを習うのは時間的に厳しい。そんな時、茶の湯なら先の2つに加え、書画、工芸、建築、庭園など網羅的に美術を学ぶことが出来るのではと考え、稽古に通うようになった。


実際、茶事や茶会で亭主を務めるとなると、いつ誰を招くかによって、茶碗をはじめ、花、掛物などあらゆるものを選び、一期一会の空間を演出することになる。
当然そこに型は存在するが、利休の茶は「山を谷、西を東と茶湯の法度を破り、物を自由にす」(『山上宗二記』)と記されている。とはいえ、それは茶聖と讃えられる利休だからこそであり、“型破り”な振る舞いは一通りの本筋を知った上でなければ“型なし”になることは、茶の湯に限らず、あらゆる伝統文化に共通することだろう。
伝統文化などというと一気にかび臭くもなるが、茶の湯には現代美術に先んじた「見立て」という発明がある。見立てとはもともと他の目的で作られた物の価値を転換する行為を指す。
1917年、「現代美術の父」とも称されるマルセル・デュシャンが、男性用小便器に署名を施し、『泉』というタイトルをつけ、既製品を自身の作品へと転換した美術史上名高い事件がある。しかし利休はその事件の400年も前に、京都・桂川の漁師から譲り受けた魚籠を花入として見立て、茶室に飾ったといわれる。
伝統文化は一見、約束事でがんじがらめな世界に思われるが、茶の湯には既存の価値観に縛られない創意工夫を受け入れてきた歴史がある。僕が面白みを感じるのはまさにそこだ。
茶の湯の文化に触れ、利休を知れば知るほど、僕の中では所謂“侘び”とは対極のアヴァンギャルドな精神の持ち主に思えてならない。利休のように自分流の崩しを楽しむためにまずは稽古に精進したい。そしてこれからも幅広い文化に触れ、自分自身の視点を磨き、いつしか独自の茶のあり方を切り開けるように、この道を歩み続けたいと思う。