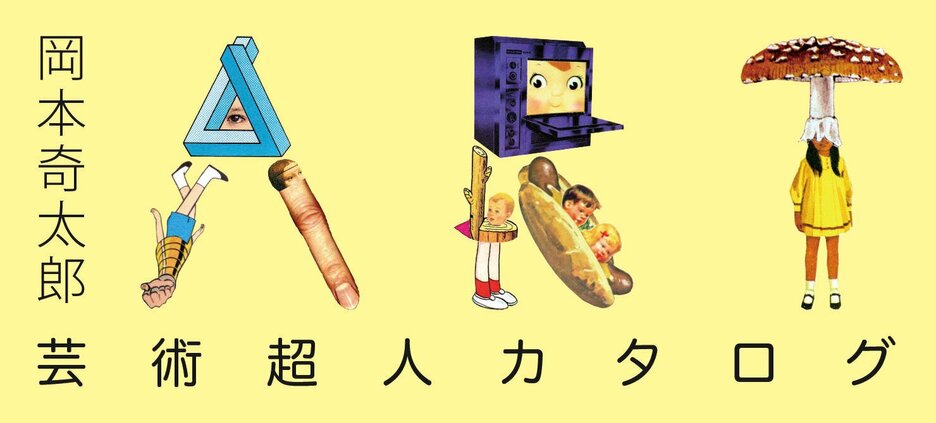2023年は、国際的な評価を得た版画家・棟方志功の生誕120年にあたる。これを記念して現在、東京国立近代美術館では、「世界のムナカタ」の幅広い制作活動の全貌を紹介する大回顧展『棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』が開催中だ(12月3日まで)。
僕にとって棟方志功は過去の人という印象がない。それは棟方の表現活動が複数制作を可能とする版画が中心で、今でも毎年のように、どこかで棟方の作品を観る機会に出くわすからだ。
また棟方の作品を知るよりも前に見た、極度の近視ゆえ、板に顔を擦り付けるように近付け、猛スピードで彫刻刀を操る彼の制作風景に迫った映像が、未だ脳裏にこびりついて離れないことも理由としてある。
しかし棟方の創作の原点は版画ではなかった。少年時代の棟方は、地元・青森の伝統工芸品である凧絵の表現やねぶたの色彩にのめりこみ、口癖は「世界一の画家になる」。あだ名は「世界一」だった。やがて友人から見せてもらった、雑誌『白樺』掲載のゴッホの『向日葵』に感動し、洋画家の道を歩むようになった。
棟方の当面の目標は官設の帝展に入選することだった。帝展の実情は派閥争いや情実が横行していたが、そんなことを知る由もない田舎の青年画家は、「日本のゴッホ」になるために上京した。結果、5度の挑戦で念願の帝展入選を果たしたが、不遇の数年間を過ごした棟方は、洋画の在り方に疑問を持つようになっていた。
「日本人のわたくしには、日本から生まれ切れる仕事こそ、本当のモノだ」と自覚し、「この国のもの」をつかまなければ「わたくしの仕業にならない」と考えた。そして自らの創作を模索する中で、「ゴッホが発見し、高く評価して、賛美をおしまなかった木版画があるではないか」という啓示を得る。ゴッホが浮世絵版画に魅了され、作品を蒐集し、模写したことは有名な話である。こうして版画家・棟方志功は生まれた。
小説家の谷崎潤一郎は「棟方志功君は奇人である。一度同君に面接した経験のある人なら、私のこの説に同感しない者はあるまい」と言ったが、棟方は実に交友関係が広く、多くの人たちから愛される人物だった。とりわけ棟方が生涯を通じて絶対的な師匠と仰いだ民藝運動の父・柳宗悦との邂逅は、「世界のムナカタ」誕生に多大な影響を与えた。
元々、版画は葉書や本の挿絵として冊子体で流通していたが、作品として展覧会に出品されるようになると、額装して壁に掛けられるようになった。一方で、棟方が版画を屏風という室内調度品に組み込んだのは、表具の設計デザインを得意とする柳との関わりが大きいだろう。屏風に複数の版画を貼り込むことで、与えられた壁を自作で埋めることができ、出品規約の点数制限などには、「屏風一点」と回避できる利点もあった。


参考文献
『生誕120年 棟方志功展
メイキング・オブ・ムナカタ』図録
本展展示の『幾利壽當頌耶蘇十二使徒屏風』(図上)は、当時の日展(第9回)の出品規約にあった「横六尺以内、縦は制限しない」に対しての最大サイズで屏風に仕立てられた作品だ。それゆえの極端に縦長の形状であり、尚且つただ屏風に版画を貼り付けるだけではなく、黒衣と白衣の人物を交互に配置するなど、全体の構成も抜かりなく計算されている。
屏風は伝統的な形式でありながら、近代的な展示空間にも適応できる形状でもあり、棟方が国際展の舞台に立つ際も功を奏した。中でも1956年の第28回ヴェネチア・ビエンナーレの際は、作品の全てを屏風装で出品。見事グランプリを受賞し、「世界のムナカタ」の名声を決定づけた。
本展では「ゴッホになる」と絵筆を握った活動初期の作品から屏風に仕立てられた版画の大作の他、版木の入手に窮した戦中戦後の疎開先で描いた倭画(肉筆画)や書、本や雑誌の装画(挿絵・装幀)、包装紙などの商業デザインに至るまで、幅広い領域を横断した棟方の軌跡に触れることができる。その膨大な仕事量には圧倒されるばかりで、生誕120年にして尚、「ムナカタ」は健在だと感じる充実した展覧会だった。