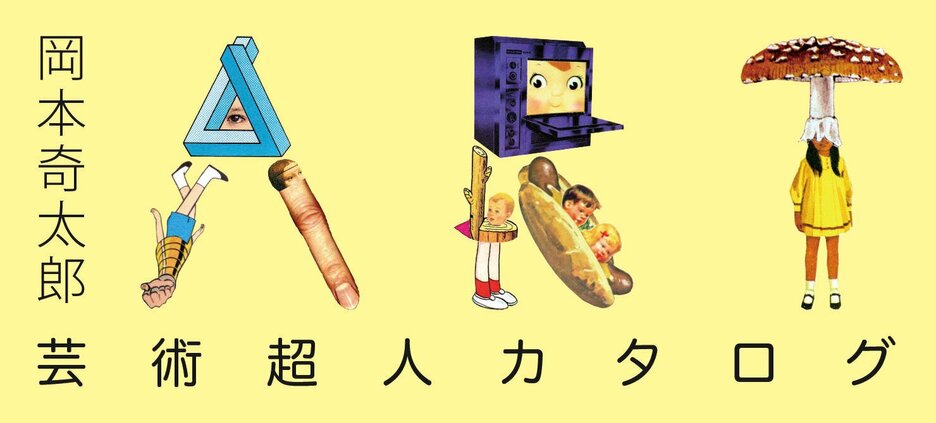20代のころ岡本太郎の思考や思想に強烈に影響を受けた。それによって僕に起こった一番の変化は、理性よりも感性を重視するようになったことだと思う。そしてバランス良く生きるために無理をすることを止め、会社勤めも辞め、気づけば岡本奇太郎などとふざけた名前で、フリーランスとして創作活動するようになった。
家族からは変わり者呼ばわりされているが、変わり者だからこそ、当たり前を当たり前と思わず、皆が気づかないようなことに気づくときがある。太郎による“縄文の発見”も、まさにそうした変わり者の視点から見出されたものではないだろうか。
縄文の発見といっても、発掘現場から未知なる縄文土器を見つけたわけじゃなく、東京国立博物館で太郎は発見した。それまで考古学の資料でしかなかった縄文土器は、太郎が偶然目にし、「全身の血肉がぐっと充実し、熱くなった」「思わず叫びたくなる凄み」を感じるほどの衝撃を受けて以降、芸術として鑑賞し得る造形物だということが発見されたのだ。その後、研究を進めた太郎が雑誌『みずゑ』(1952年2月号)に発表した『縄文土器論』は、美術界や建築界など各方面で話題になった。今や日本美術史の概説書の冒頭に必ず掲載される縄文土器だが、『縄文土器論』以前は飛鳥時代からはじまることがほとんどだった。
この芸術と見なされていなかったものに芸術性を見出すという感覚は、僕が好きになる芸術の成り立ちに共通してみられる要素だということに最近気づいた。
本来茶の湯の道具ではなかった品々を茶道具として見立てた千利休。無名の工人の手仕事によって作られた日用雑器に美を見出した柳宗悦の民藝。赤瀬川原平らが発見した街中の無用の長物的物件トマソン。バンクシーをはじめ「ストリートアート」としてアート市場で高値で取引されるようになった路上の落書き等々。これらはその物体やイメージが誕生した瞬間は芸術ではなかった。しかし既存の価値観に縛られず、自分独自の視点で見る者達がいた。それらの考えに触れたことで、芸術作品という枠の外にあるものは、より一層興味深い表現として僕の目にも映るようになった。そのように物を観るコツみたいなものを、僕はこの太郎が博物館で縄文を(鑑賞ではなく)発見したというエピソードから掴むことができた。
さらに僕の趣味嗜好に影響を与えたのは、岡本太郎の文化人類学者としての一面だった。
10代の頃からパリへ留学し、芸術を学んでいた太郎は、一方で「文化人類学の父」と言われるマルセル・モースから文化人類学の基礎を学んでいる。その眼を持った上で帰国した太郎は、縄文の発見以降、雑誌の取材で日本各地を旅するようになった。それらは岡本太郎の日本紀行三部作として、『日本再発見―芸術風土記』『忘れられた日本―沖縄文化論』『神秘日本』にまとめられた。失われゆく日本の原風景を追い求めて、現地の人の話に耳を傾け、写真を撮って、調べて書くこの一連のフィールドワークは、太郎の芸術にも多大な影響があったと考えられる。


具体的には60年以降の太郎の作品からは、以前の抽象画とシュルレアリスム絵画が合わさったような作品は鳴りを潜め、代わりに空海が書く飛白体を彷彿とさせるような文様が頻繁に登場するようになった。それは日本列島を旅して感じた「呪力」のイメージを、作品に反映させるようになった結果ではないだろうか。しかしそうなってからの岡本太郎の絵画作品は、僕の中では興味を持てるものは少なく、それについては次回書きたいと思う。
しかし僕は太郎の紀行文や写真からは多大な刺激を受け、太郎が立ち寄った場所や祭りを中心に、日本古来の生活やカタチを見て回る旅に出た。特に祭りに関しては、お酒を呑みながら楽しめるフェスのような感覚で通うようになったが、次第に古代と現代、聖と俗、生と死といった相反する二極が同居する空間として感じられるようになった。この対極にある概念をぶつけ合わせ、その結果として生まれる不協和音を良しとする『対極主義』こそが、太郎が生涯実践した独自の思想であり、僕は太郎の作品よりも太郎の足跡を追うことで、岡本太郎に魅せられるようになっていった。