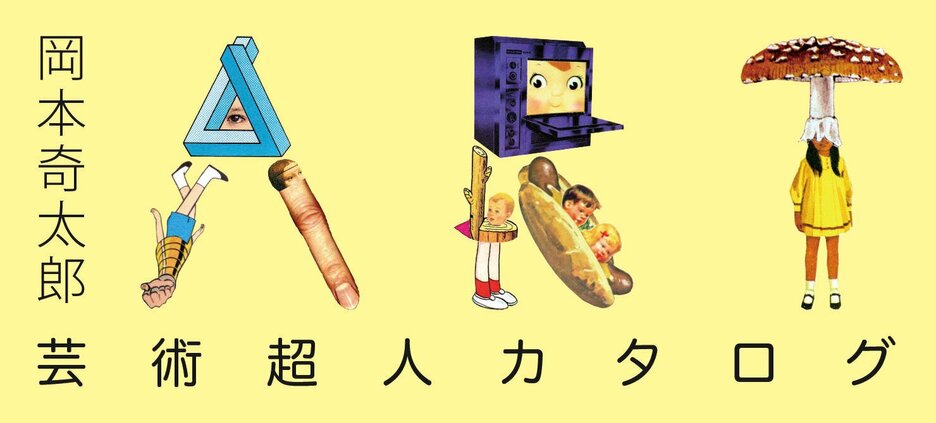昨年、郷土玩具や民藝好きの間で話題になった『世界の民芸玩具』という本がある。発売後まもなくして僕の耳にも入ってきたその話題の書は、日本玩具博物館学芸員の尾崎織女さんが、同館の9万点を超えるコレクションの中から選び抜いた味わい深い郷土玩具を解説したものだ。なんて興味をそそる博物館名だと思いきや、なんとそこは僕の実家から車で10分ほどの距離にある施設だと知って驚いた。今夏、たまたま帰省する用事があったので、両親を誘い一緒に博物館に向かった。その道中、30年近く前、かつて自分がそこに行った記憶がおぼろげながら蘇ってきた。

日本玩具博物館は、日本民俗学の父・柳田國男の生家「日本一小さな家」から南へ約6キロ、兵庫県姫路市の北東部、香寺町に位置する私設の博物館だ。白壁土蔵造の建物内に入り、まず目に飛び込んでくるのは、天井に吊るされた大凧である。しばらくそれを眺めていると、スタッフの方が展示物についての解説をはじめてくれた。するとうちのオヤジが「以前、競馬場で凧の解説をしていませんでしたか」と言い出した。近所の姫路競馬場で、バカでかい凧やビヨーンという音を鳴らしながら揚がる凧など、ものめずらしい凧が飛び交う『全国凧あげ祭り』なる催しが開催されており、小さいころ毎年のようにオヤジに連れられて行ったことが急に思い出された。その当時、会場でマイク片手に全国各地の郷土凧を解説していたのが、目の前にいる日本玩具博物館の館長・井上重義氏だった。

この個性的な博物館を紹介する前に、僕個人の考えを少し述べておきたい。普段から僕は目新しいものより古くから伝わるものに惹かれるところがある。それは過去に新しいものばかりに食いついた反動と、20代を雑誌編集者として、そして今は美術作家として創作物を制作していることが大きく関係していると思っている。
20代のころの僕は、人里離れた公園やキャンプ場などで開催されるレイヴパーティによく遊びに行った。やれUKで脚光をあびるDJだの、デトロイトテクノの旗手として知られるミュージシャンだの、新しいサウンドを追い続けた結果、毎度打ち鳴らされる4つ打ちのリズムに飽き、次第に足が遠のくようになった。全国各地の日本の祭りを巡るようになったのはちょうどそのころで、地域によって全く異なる祭囃子という名のダンスミュージックが、とんでもなく新鮮に聴こえてきたのだった。
アートも同様で、小難しいコンセプト在りきの現代アートに辟易としていたころ、何よりもフレッシュに見えたのはいにしえの表現だった。原初的な荒々しさを特徴とする縄文土器や宇宙人のような土偶、円空や木喰、伊藤若冲や曾我蕭白らが活躍した18世紀の京都画壇、超絶技巧の宮川香山などをきっかけに、僕は日本古来の創造物に魅せられ、今も追い続けている。その理由としては、次々にあらわれてはあっという間に淘汰されたり、時にはブームになったり、その結果出てくる二番煎じ三番煎じが横行する新しい表現よりも、単に刺激的だからというのも確かにある。しかし作家として自らの肥やしとなる何かをインプットするとき、同世代の人たちが惹かれがちな目新しいものより、過去にそれを求める方が存在としてまれという打算的な考えもある。そうして先人が作ってきたものから刺激を受け、変化を加え、新たなカタチを生み出すのが僕のやり方だ。否、僕のやり方というより、その連続こそが芸術の歴史そのものではないだろうか。
もしも今現在、新しいものより古いものの方が皆に注目されていれば、僕が古来の表現にここまでのめり込むことはなかったかもしれない。あまのじゃくということは重々自覚している。皆が過去の遺産を「古臭い」「新しいものの方が面白い」と軽視すればするほど、僕自身にとっては好都合だ。一方で、新しいものより、はるかに斬新で刺激的なものが、過去にはたくさんあることを皆に知ってほしいという気持ちもある。
次号では、失われようとしている子どもの文化遺産である郷土玩具を、並々ならぬ情熱で蒐集する井上重義氏と、氏が館長をつとめる日本玩具博物館について詳しく紹介したい。