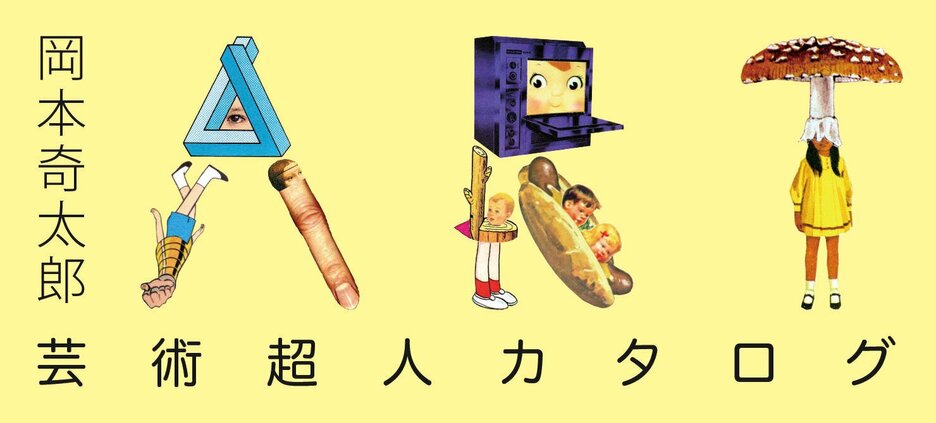一冊の本との出会いが人生を左右することがある。僕にとってのそれは林文浩氏が書いた『外道伝』という本だった。その本には今や映画監督として有名になった園子温氏をはじめ、林氏のまわりにいる特異な才能や人生観を持った人たちが紹介されていた。そこに登場する12名はそれぞれ強烈に違いなかったが、読後に僕が感じたのは、「この本に出てるみんなと呑んだり暴れたりしてる林さんが一番楽しそう」ということだった。そして林氏が『DUNE』というファッション誌の編集長だったこともあり、編集者になれば自分も型破りな人たちと繋がれるかもしれないと思った21歳の僕は、DUNE編集部に乗り込み、やがて編集者になった。そして、望んだ通り常軌を逸した人たちにもまれる日々を過ごし、今はこうして自分のまわりの特異なものについて書いている。
先月号で紹介した日本玩具博物館の館長・井上重義氏もまた、24歳の時(昭和38年)、郷土玩具がいかに日本人の美意識や幸福感を反映し作られたものかが綴られた『日本の郷土玩具』(斎藤良輔著)という一冊の本を偶然手にしたことで、その後の人生が大きく変わったという。そして当時、すでに失われつつあった郷土玩具に対し、「だれかが、その生い立ちや実情を調べて記録しておくことが大切ではあるまいか」という同書の記述に奮起し、巻末に記された全国の郷土玩具作者の一覧表をもとに、休日を利用して訪ねる旅がはじまった。

井上氏の蒐集の指針は、先の本の影響もあり、みんなから忘れ去られ消滅しようとしているものを集めるということ。ここ数年、日本のアート市場に雨後の筍のごとくあらわれた、「完売作家」や似たり寄ったりの今風を買い求めるアートコレクターとは根本的に違い、独自の審美眼を頼りに、価値評価されていないものに価値を見出す。誰かの後追いとは無縁の蒐集活動は、道なき道を行くもので、その労力は計り知れないものだ。
井上氏と各地の郷土玩具との出会いや研究は膨大かつ深遠につき、紙幅の都合上、ここでは割愛させていただくが、蒐集をはじめて11年目に、自宅の一部に展示スペースとして井上郷土玩具館をつくった。当時は鉄道会社勤務の傍らでの運営だったため、土・日のみの開館だったが、その10年後、会社を退職し、1984年に日本玩具博物館と名称を変更した。
僕がはじめて日本玩具博物館に足を運んだのは、一日中ファミコンのことしか考えていなかった子供の頃。「古いオモチャしかない」と不貞腐れていたことが思い出される。あれから30年が経ち、かつては退屈に見えたものが、今はどれも魅力的に映るのはなぜだろうか。ファミコン世代の僕からすると、展示されている玩具は決して昔馴染みというわけではないが、妙に懐かしくくつろいだ気分にさせてくれる。玩具といえば子供のためのものと思われがちだが、のどかな心持ちをもたらしてくれるこの効きは、日々の仕事やプレッシャーで疲弊した大人にこそ必要なものかもしれない。

日本玩具博物館は、「人類の文化遺産を蒐集保存し、後世に伝える」ことに専念した結果、2016年にミシュラン・グリーンガイドで2つ星に認定されるなど、国際的に高い評価を受けるまでになった。それにもかかわらず、入館者数は年々減り続けているという。とはいえ、同館所蔵品による他館でのここ数年来の特別展は、通常入館者数を大きく上回る成果を上げており、決して日本玩具博物館自体の魅力が低下しているわけではない。入館者減少の要因は、同館へのバス便の大幅な減便や地域力の低下が考えられる。そして何より問題なのは、博物館相当施設として文部科学省からも認定された同館に対し、国や自治体からの公的支援がないに等しいということだろう。これまでは奇跡的に入館料や所蔵品の貸出料、出版物の印税などで、独立採算の運営が出来たが、昨年からのコロナ禍により同館も大打撃を受けている。
日本玩具博物館が所蔵する9万点を超える資料が、社会が守るべき文化遺産として認識され、公的財産として後世に継承されることを切に願う。