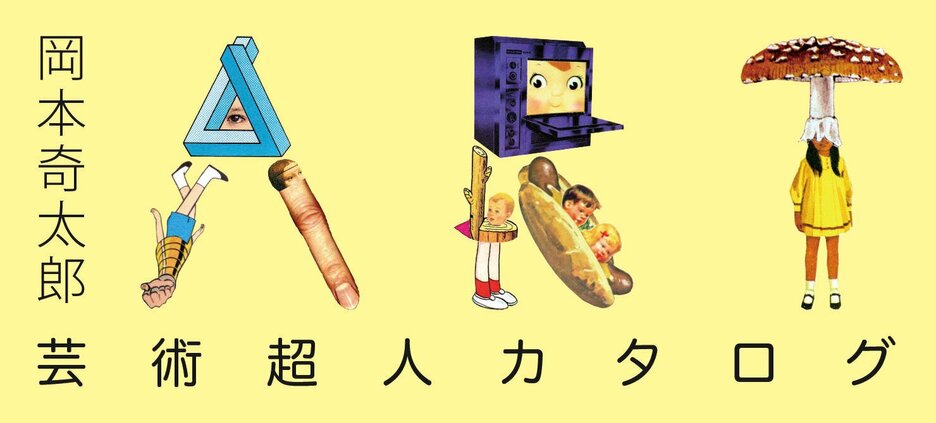『諸国畸人伝』という風変わりな画を描いた江戸時代の絵師10人を紹介する展覧会が、2010年に板橋区立美術館で開催された。それを観に行って以来、僕は同館の大ファンになった。
当時すでに「若冲ブーム」という言葉は耳にしていたが、若冲以外に畸人として括られていたのは、辻惟雄氏の名著『奇想の系譜』で紹介された絵師たちと、次いで河鍋暁斎くらいで、それ以外の絵師となると一般的に知られているとは言い難い状況だったと記憶している。
そのような時期に、『奇想の系譜』掲載の曾我蕭白はともかく、まだ本格的な回顧展が行われる前の狩野一信(『五百羅漢―増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信』2011年)や白隠慧鶴(『白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ』2012年)らをいち早く取り上げ、それまでに見たことがない奇抜な画で埋め尽くされた展示会場に度肝を抜かれた。中でも画面内の輪郭線から色面までが、緻密な経文の集積で構成された加藤信清の文字絵との出会いは衝撃的だった。当時はまだ信清のウィキペディアすら存在しておらず、これほどの絵師が知る人ぞ知る人物であることに、江戸絵画の奇想の文脈の深遠さを感じずにはいられなかった。
また美術館のまわりには、溜池や木々で覆われた小高い丘があり、地元の人たちが釣りやバードウォッチングを楽しんでいる。付近にはさらに、赤塚植物園や『江戸名所図会』にも描かれている松月院、乗蓮寺の東京大仏や江戸時代に富士講が身を清めた禊ぎ場・不動の滝などもあり、散歩に持ってこいの心地良い周辺環境も、僕が同館を好きな理由のひとつだ。
現在、板橋区立美術館で開催中の『狩野派以外学習帳』(10月1日まで)は、古来より画題として好まれてきた「富士山」と「牡丹」に着目し、江戸狩野派と民間の絵師たちの画風を比較しながら鑑賞できる展覧会となっている。
江戸時代、画壇の中心には幕府御用絵師集団・狩野派が君臨し、その主導的立場にあった狩野探幽は、余白を活かした瀟酒端麗な江戸狩野様式を確立した。図上は探幽による「江戸絵画の手本となった富士山」で、墨画部分と余白のバランスに富んだ淡白な富士図は、時代の規範として位置づけられた。
富士図は権威の象徴としての側面があり、その制作は幕府御用絵師の狩野派の重要な仕事のひとつだったが、この日本一の山に格別の親しみと畏敬の念を抱いていた民間の絵師たちもまた、盛んに富士山を描いた。
先祖伝来の絵手本(粉本)模写を軸とした教育体制により、創造性を欠いた形式的な画風に陥りがちとも言われた狩野派の絵師と違い、民間の絵師は様々な流派の様式を取り入れ、既存の殻を打ち破る自由な発想や画技により個性豊かな作品を次々に生み出した。
紙幅の都合上、全ての出展作品に触れることはできないが、遠くに富士山を眺め、手前に都市の湾岸風景を描いた司馬江漢の『鉄砲洲富士遠望図』などは、江戸(東京)に暮らす人々にとって馴染み深い構図で、そのような現下の景色は、守るべき型があった狩野派画人が決して掘り下げることがない領域だっただろう。

板橋区立美術館

板橋区立美術館
富士山同様、あらゆる絵師によって描かれた牡丹図は、豪華で美しいばかりでなく富貴の象徴として尊ばれた。花鳥画においても狩野派では、流派の画技を保ち継承するため古典の模写が徹底されていたが、民間の絵師たちの多くは諸派兼学の姿勢で、これまでにない表現を模索し続けた。
『牡丹小禽図』(図下)を描いた宋紫石は、1731年に長崎に渡来した中国清朝の画家・沈南蘋の噂を聞きつけ、江戸から長崎に遊学し、彼の通訳をしていた熊斐に師事して南蘋画法を学んだ。従来の狩野派の画にはない、写実的な細密描写による質感表現と洗練された色彩感覚は、江戸の人々を魅了した。
本展を含み、同館は入館料無料の館蔵品展が多いのも嬉しく、また毎年取り替えられる美術館横ののぼり旗のメッセージには、思わずクスッと笑わされる。「永遠の穴場」板橋区立美術館に足を運んだ際は、そこもあわせてチェックしてみてほしい。