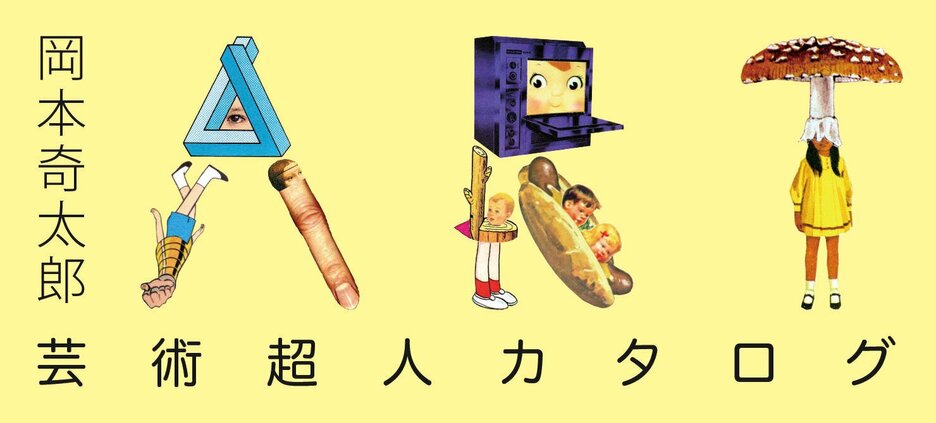1925年に柳宗悦を中心に、濱田庄司、河井寛次郎らによって提唱された民藝という美の概念がある。民藝とは民衆的工藝の略であり、“ごく普通の暮らしの中にある実用品”が持つ素朴な味わいや美しさを表し、柳の「直観」、読んで字のごとく直ちに観ることで発見された。
その柳が中心となって、東京・駒場に1936年に開設された日本民藝館には、これまで数え切れないほど足を運んだ。歩くたびに心地よくきしむ床板、作品の陳列棚、各部屋に配置された休憩用の椅子、そして窓から覗く外の景色に至るまで、建物全体が簡素で温かみがあり民藝品そのものといえる。そこに柳が美しさを見出した、無名の工人の手仕事によって作られた“日常生活で用いられてきた品々”が陳列されている。この場が持つ空気と展示物の関わりが生み出す心地良い雰囲気は、よそではなかなか味わえないもので、何度行っても飽きることがない。また他の美術館と違い、作品についての解説が最小限(品名と時代程度)で、先入観抜きで作品と向き合えるのも日本民藝館の特徴だろう。
この場所で僕が柳から学んだことは、他人の意見や評判に惑わされず自分自身の眼で観る姿勢だ。日本民藝館で「美の標準」に触れると、魅力的な作品というのは高額で取引されたり、有名作家が作るものだけじゃないということを痛感させられる。そうして思うのは、世間的に評価されたものにしか価値を見出せない人たちの多さである。
例えば、近頃ではすっかりお茶の間の人気者になったバンクシーの影響で、存在感が高まるグラフィティやストリートアート。それらは急に現れたわけじゃなく、ずっと前から公共空間に無数に拡散されてきたものだった。美術館に展示されている作品よりもはるかに人目に付いたはずだが、多くの人には日常の風景として見過ごされてきた。その間もグラフィティを街中で観られる至極のアートとして純粋に楽しむ人たちはいたが、オークション市場で高値で落札されるや否や状況は一変。今まで見向きもしなかった人たちが一斉に騒ぎ出したが、彼らにとっては、バンクシーもタピオカもSupremeも大差ないだろう。
路上に描かれた至極のアートと同様、日常に当たり前のようにあったものから見出された民藝。現在も色あせることがないその美の概念において、価値評価されていないものに価値を見出した柳の審美眼の確かさは疑う余地もない。それだけにこれまで民藝をテーマに扱う展覧会は、柳宗悦という個人の眼や思想を中心に構成されるものがほとんどだった。しかし現在、東京国立近代美術館で開催中の『民藝の100年』(2022年2月13日まで)は、民藝の思想の種が蒔かれてからのおよそ100年を、俯瞰的な視点から捉え直す意欲的な展覧会となっている。

左:雑誌『工藝』第1号-第3号 1931年(型染・装幀 芹沢銈介)写真提供:日本民藝館
100年経った今も民藝が語り継がれるのは、柳一人の功績ではなく、「美術館」「出版」「流通」という3本の柱がもたらした影響が大きい。「美術館」はもちろん日本民藝館。「出版」を担うのは、機関誌『工藝』(写真左)や『月刊民藝』などを発行した日本民藝協会。そして民藝品を販売するセレクトショップ・たくみ工藝店の「流通」。これら自前のメディアを駆使することが、工藝品を通して社会やライフスタイルを美的に変革しようという民藝運動にとって重要だった。またローカルなネットワークとの協働も不可欠だった。そもそも優れた民藝を生み出す技術は、各々の地方で伝統を維持しており、焼物、木工、竹工、塗物、染織、和紙など、“日々用いる工藝品”として日本中に息づいている。今展ではそのような地方の担い手の具体的な活動も取り上げられている。
それら民藝の実践が、かつて柳宗悦に、“近代美術館は、その名称が標榜してゐる如く、「近代」に主眼が置かれる。民藝館の方は、展示する品物に、別に「近代」を標榜しない” “近代美術館が今迄取り扱った材料を見ると、大部分が所謂「美術」であって、「工藝」の部門とは縁がまだ薄い”(『民藝』第64号)と批判された、東京国立近代美術館という場で今回紹介されるのだ。近代という時代と美術という領域を扱う展示空間と民藝が、どのような化学反応を起こすのか。自分の眼で観て体感してみてほしい。