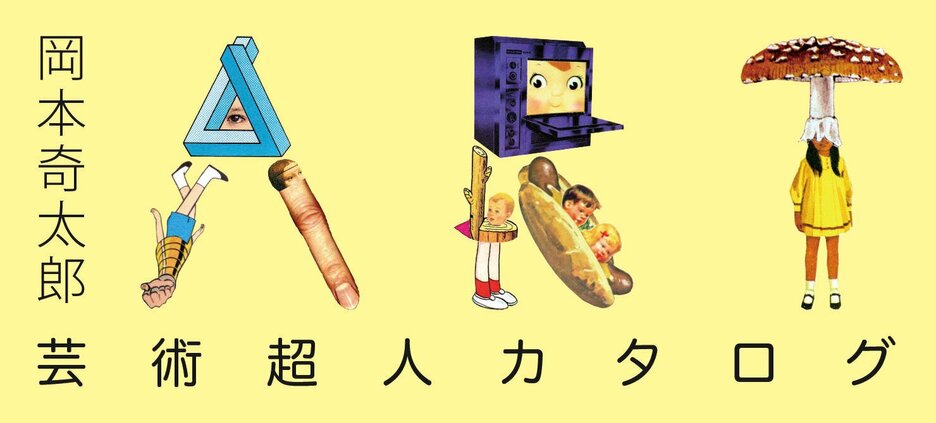僕は自分がつくった作品を展示する時、鑑賞者の反応見たさに会場に立つことがある。すると大体お客さんから「この作品のコンセプトは?」と尋ねられるのだが、すんなり答えられたことがなかった。というのも僕の作品はそもそもコンセプトなどないのでどうしようもない。だから昨年から作品に“THIS IZ NOT ART”と記すことにした。「これは芸術じゃないんですよ」と言えばお客さんがそれ以上意味を求めてくることはないし、あとはその人が好きなように観ればいいと思う。
芸術を鑑賞する――という行為を堅苦しく考えている人は少なくないだろう。こと現代美術は作品の意味やコンセプトが必ずあり、それを「わかる人」だけが楽しむ特別なものと誤解されていないだろうか。確かに鑑賞者に小難しい観念を押し付けてくる作家はいる。しかし僕は芸術作品は理解するものではなく感じるものであってほしいと思うし、観念を振りかざすことなく鑑賞者の視覚を楽しませるアーティストがいることも知っている。そのひとりが松村咲希である。
松村の作品は観る人のテンションを上げるような激しい色使いがまず目を引くだろう。そして奥行きが感じられるのも特徴のひとつだ。鮮やかな色面とそれを際立たせる白いライン(何も塗らないことで表出した下地)や、シルクスクリーンでドットや月面写真を拡大したものを刷った部分など、複数のレイヤーが画面内に混在し、さらに実際に絵の具を盛ってつくられた凹凸もある。奥行きが感じられるのは当然だ。
2015年までの松村は油絵の具を素材に、重たい色使いでおどろおどろしいモチーフを描いていた。現在の作品とは似ても似つかない、一言で言えば暗い印象の絵だ。その当時の松村は、絵画というものはモチーフを上手く描写し、作家の心情を表すものという固定観念に縛られていたという。そして心象風景を描くために自分自身が抱く生きづらさと向き合い続けた結果、絵を描くこと自体に辛さを感じるようになった。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の学生だった松村は、同校の全国でも珍しい展示作品を販売するアートフェア形式の卒業・修了制作展で、友人の作品が完売し、自分は風景画1点しか売れなかったことにショックを受ける。描くこと自体に行き詰まりを感じていた松村はこの経験を機に作風を見直した。
描くことが辛くなった原因は自分の中のネガティブな感情にとらわれすぎたことだと踏んだ松村は、「ドロドロした内面を見せない」というルールをつくった。そして重厚感のある油絵の具は軽さのあるアクリル絵の具へ、暗い色から明るい色、モチーフをなしにするなど、これまでの反対を選択していく。そうしてたどり着いたのが今の作風である。
現在の松村は「絵を描く」ではなく「絵をつくる」と言う。絵筆はあまり持たず、スプレータイプのアクリル絵の具を吹いて色面を塗り、絵の具をキャンバスに投げつけたり、自作した道具でそれを引っ掻いて凹凸をつける。時間をかけて描写することをやめシルクスクリーンで刷ってしまう。かつては絞っていた色数が今では劇的に増え、色彩の対比も思案するようになった。制作の手法をひとつひとつ変えることで再び絵画制作を楽しめるようになった松村。現在の作品には以前のような内面的な感情の跡は影を潜め、代わりにいくつもの工程を全身を使って「つくった」動作の跡が見られるようになった。

2020

2021
2015年以前の暗く具象的な絵画とは一転し、ド派手な抽象画に変貌を遂げた松村の作品に、「パワフルでエネルギッシュ」というポジティブなパワーを感じ取る鑑賞者を実際僕は何人も目にしている。しかし本人は「観た人の反応は気になるけど、別に元気にするつもりはないんですよ」と笑う。だが、たとえアーティスト本人に意図がなくても、観た人が勝手に何かしら受け取ってしまうほどの力があるものが、芸術作品としては理想的ではないだろうか。
何が描かれているかは重要ではない。外界の光景を超えた視覚を生み出す松村の絵画があなたの魂に何を語りかけるか。是非とも作品の前に立って感じてみてほしい。