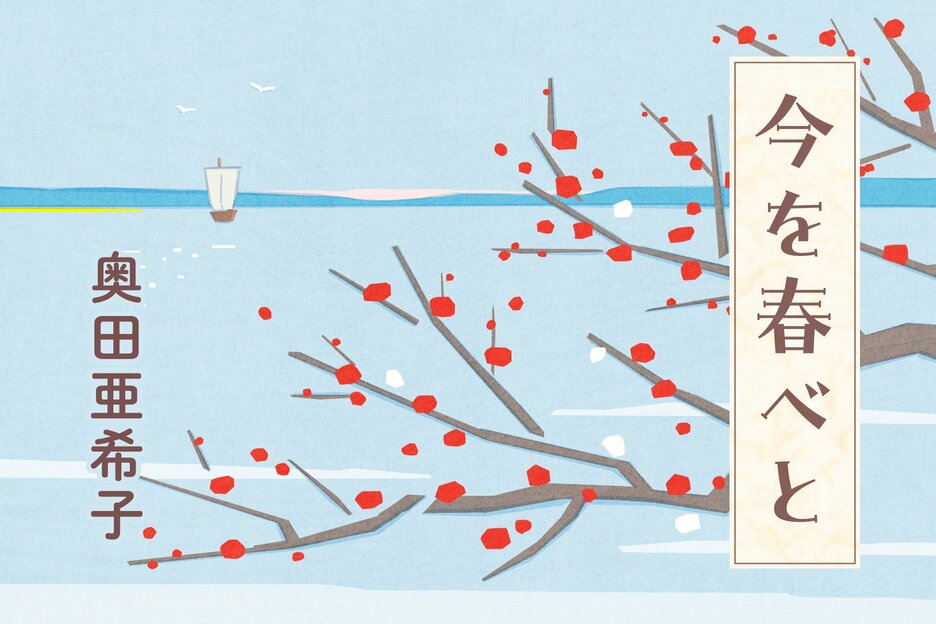一回戦の読手の名前が告げられ、希海は試合開始の挨拶をした。
「〈なにわづに さくやこのはな ふゆごもり いまをはるべと さくやこのはな〉」
二度目の下の句に備えて構えの体勢をとる。その刹那、希海は唐突に理解した。この序歌の梅は、春の兆しを感じて〈いまをはるべと〉咲いたわけではない。今が、今こそがそのときだと、自分が咲く瞬間のことを〈はる〉に決めたのだ。北風が吹いていても雪が降っていても、自分が咲けば、その季節は春。
私が〈いま〉を〈はる〉にする。
「〈いまをはるべと さくやこのはな〉」
下の句が繰り返された。
「〈よも――〉」
敵陣の右中段に腕を伸ばす。〈ねやのひまさへつれなかりけり〉と書かれた取り札の〈さへ〉のあたりを中指が弾いた。陽和の指が〈かり〉に触れるのが視界の端に見えたような気もしたが、ほんのわずかに自分のほうが速かったという確信があった。陽和が立ち上がろうとするのを気配で制し、希海は飛んだ札を拾いに行った。
「あの、今のはうちのほうが速かったと思うんですけど」
自陣の〈ゆふ〉を送り札に差し出すと、陽和は大仰に首を傾げた。またか、と希海は内心で嘆息した。
「いえ、私がここを触ったあとに、そちらがこのあたりを触られました」
次の歌が読まれないように左手を挙げたまま、希海は〈よも〉の札を敵陣に戻して今の再現を試みた。しかし陽和は、「触った場所はそのとおりですけど、うちのほうが速かったです」と食い下がった。彼女の発音には関西弁のニュアンスがあった。
「いや、私のほうが先でした」
「それはないです。少なくとも同時です」
「……わかりました」
希海は不承不承、送り札を引っ込めた。両者が同時に札に触れた場合はその札が自陣にあった側の取りとなる。競技かるたの試合には基本的に審判はつかず、どちらが取ったか微妙な場合は選手同士の話し合いで解決することになっていた。今のは絶対に自分の取りだった、と希海は思うが、相手の意見をひっくり返せるほどの反論材料は持ち合わせていない。これ以上の話し合いがただの主観の押しつけ合いになるのは明白だった。
陽和は得意札と思しき数枚は目を疑うほど速かったが、あとの札は自陣さえ場所があやふやな様子だった。ただし主張が強く、まだ半分も歌が読まれていないであろううちからすでに三度揉めている。光のどけき会の練習では相手が同会の仲間だからか、それともあくまで本番の試合ではないからか、話し合いの際に誰もそこまで激しい主張はしない。「揉め」がこれほど精神力を削ぐものだとは知らなかった。希海は息を吐いて気持ちを整えた。周囲から大人げないと思われないよう、相手が子どもだと、納得できなくてもつい譲ってしまう。その鬱屈が身体の中に溜まっていくのを感じた。
「〈ねやのひまさへ つれなかりけり〉」
希海は敵陣の奥のほうに視線を据えて次の音を待った。
「〈ゆふ――〉」
数分前に一旦、送り札に選んだことで、敵陣にあるイメージが生まれていた。希海は出遅れ、陽和にやすやすと右下段を抜かれた。勇助の札を取られた。希海は自分の額に拳を軽く打ちつけた。
「〈あらざらむ――〉」
次の歌は空札だった。もっと集中。希海は自分に言い聞かせた。
「〈なげ――〉」
敵陣の〈なげき〉に手を伸ばす。またも陽和が追随する。手が札の上にかかったとき、耳が三音目の〈け〉を捕まえた。〈なげき〉じゃない、〈なげけ〉だ。希海は手首を返し、自陣の左上段を押さえた。それと同時に敵陣の札が乱れる。陽和が〈なげき〉を払ったらしい。彼女のお手つきだった。
希海はペナルティに〈いまこ〉を送った。今回、場にある〈い〉札はこの一枚のみ。一音目から敵陣に攻め込める盤面を作りつつ、〈いまは〉の共札でまたお手つきしてくれないだろうかというたくらみもあった。
「あの、今のは共お手ですよね?」
希海は陽和の言葉を呑み込めず、真顔で数回まばたきした。
「……共お手?」
「そちらの手にぶつかって、うちはお手つきをしたので」
「ぶつかったって……そんなに強くは当たっていないと思うんですけど。そちらの片お手ですよ」
せいぜい手が手をかすったくらいだ。共お手は両者に責任のあるお手つきのことで、ペナルティが相殺される。競技かるたにおいて、お手つきが流れを変えることは多い。今までの我慢もあり、これは認めがたかった。
「いえ、共お手です。そちらの手がこう来たときに下に押されました」
「押していません。私は押す間もなく自陣に戻りました。片お手です」
「いや、でも――」
「どうしましたか?」
収束しない揉めを見かねたらしい役員の一人がやって来た。希海と陽和は自分の意見を順に説明する。彼は「なるほど」と頷いたのち、「共お手で」と判断を下した。
「……失礼しました」
役員の誰かが応急処置として審判についた場合、その人の言うことには必ず従わなければならない。希海は〈いまこ〉の札を自陣に戻したが、怒りで身体が熱くなるのを感じていた。陽和はすべて本気で主張しているのだろうか。それとも微妙な取りでは積極的に揉め、絶対に譲らないと決めているのだろうか。顔を見る限り嘘を吐いている感じはない。それでも希海は思った。
こんクソガキが。
これ以上の隙は見せない。もっと速く、もっと正確に取る。
希海は場にある札を確認した。〈あらし〉は共札の〈あらざ〉が、〈かぜを〉は〈かぜそ〉が読まれ、それぞれ〈あら〉と〈かぜ〉決まりになった。〈きり〉は〈きみがためは〉と〈きみがためを〉がすでに出ていて、早くも〈き〉決まりだ。陽和の実力では決まり字の変化を正しく追えているとは思えない。最短のタイミングで動き出せば、陽和を突き放せるだろう。決まり字が長いときや出遅れたときには払いではなく、手のひら全体で押さえるように札を取ろうか。押さえ手は選手同士の接触の可能性が高く、怪我をしたりさせたりするリスクもあることから推奨はされていない。しかし、先に出札を手で完全に覆えば、さすがの陽和も自分の取りだとは言えないような気がした。
「〈はるの――〉」
希海は狙いどおりに自陣の左中段を押さえ手で取った。陽和の指が手の甲に当たる。彼女が悔しげに顔をしかめたのがわかった。
「〈たき――〉」
今度は敵陣の左下段を払った。陽和は〈た〉札が得意ではないようだ。序盤に〈たち〉と〈たま〉が読まれたときも身体が硬直していた。送り札には〈あし〉を選んだ。そこからは空札が四枚続いた。
「〈む――〉」
陽和が自陣の右下段を払って守った。若い子の陣にある〈む〉〈す〉〈め〉〈ふ〉〈さ〉〈ほ〉〈せ〉には手も足も出ない。そんなことは郁登と対戦していたころからわかっている。希海は気持ちを切り替えて次の歌を待った。
「〈き――〉」
脳に電流が流れた。狙い札のひとつだ。希海は敵陣を目がけ、思いきり腕を振り抜いた。手のひらが畳を叩く小気味いい音がした。
希海が荷物を置いたスペースに帰ると、奈穂は先に戻っていた。役員に報告する姿を見ていたのか、奈穂は親指を立てて希海を祝福した。まだ試合が続いているために声を発することはできない。やがて最後の札が読まれ、全員で拍手する。その音が鳴りやむなり、奈穂が身を乗り出した。
「希海さん、おめでとう。何枚差だったの?」
「八枚。でも、もうくたくた」
終盤はこの世界に自分と陽和と読手しかいないような気がするほど集中していた。あの数十分間、武道場よりも体育館よりもはるかに広い空間に、たった三人で存在していたのだった。
「お疲れさま。デビュー戦で白星は幸先がいいね」
「奈穂さんは? 勝ったんだよね?」
「うん、十三枚差で男子大学生に」
「さすが。奈穂さんもおめでとう」
その場で手早く昼食にした。希海がおにぎりを食べながら揉めの多い相手だったことを小声で話すと、奈穂は「いるねえ、そういう子。自分の動きに自信があって羨ましくもある」と笑った。希海はその表情を目にしただけで怒りの残滓が消え、身体の力が抜けたように思えた。
「奈穂さんはなんでかるたを始めたの?」
希海がふと疑問に思い尋ねると、「話したことなかったっけ?」と奈穂はきょとんとした。
「聞いてないと思う」
「花琉が学童で人から教えてもらって、もっとやりたいっていうから近くにあるかるた会を探したんだよ」
「でも、子どもがハマっても親はやらない家のほうが多いよ。なのにどうして奈穂さんは始めることにしたのかなあと思って」
「ああ。最初は花琉の送り迎えだけしてたんだけど、そのうちに琉宇もかるたをやりたいって言い始めて、そうなると、毎週土曜の昼を私と旦那の両親の三人ですごすことになっちゃうじゃない? それが嫌で、私も練習会に参加することにしたの。百人一首には全然興味がなかったんだけどね」
「そういう理由だったんだ」
子どもの教育のためとか親子間のコミュニケーションのためとか、もっと前向きな動機があるのかと思っていた希海は驚いた。
「始めはね。もちろん、今は好きでやってるよ」
「そういうモチベーションだと、百首を覚えるの、辛くなかった?」
「辛かったよー。ひとつ覚えたそばからひとつ忘れちゃうから、百首は永遠に揃わないと思った。私さ、中高生のときに一番苦手だった科目が古典なんだよね。大人になった喜びのひとつがもう古文を読まなくてもいいことだったのに、なんでこんなことをやってるんだろうって何回も思った」
奈穂は当時の大変さがぶり返したかのように眉をひそめたのち、「ま、始めるきっかけなんてなんでもいいってことだね」と笑った。
二回戦はその約十分後に組み合わせが発表された。希海の相手は神奈川やそしま会の平藤唯という、四、五年生くらいの女子小学生だった。切れ長の目は意思が強そうで、希海はまたも陽和のような子かもしれないと不安になったが杞憂だった。唯とは取った取られたの感覚が一致していた。だから音に反応して身体を動かし、相手よりも速く札に触れることに集中できる。唯は所作も美しく、自分のお手つきで希海の陣を大きく乱した際には「失礼しました」と一礼した。
中盤まではシーソーゲームだった。どちらも敵陣が出れば抜き、時折自陣を守って二度ずつお手つきをした。唯は希海よりも二十センチほど身長が低かったが重心の移動がうまく、こちらの下段もきれいに払った。
「〈あさぼ――〉」
大山札だ。希海は自陣の〈あさぼらけう〉を手で囲った。共札の〈あさぼらけあ〉は今回の場にはない。耳を澄ませて六音目を待った。
「〈――らけう――〉」
手を伏せるようにして札を取る。秋ごろから囲い手の動きはできるようになっていたが、慌てるあまり、出札でないほうのときもつい手を倒してしまうことが多かった。だが、今回は成功した。希海は安堵の息を吐いた。
「〈ゆ――〉」
先に〈ゆら〉が読まれ、〈ゆ〉決まりになっていた〈ゆふ〉の札は唯に猛スピードで抜かれた。〈ゆふ〉、全然取れないよ、と希海は心の中で勇助に嘆いた。唯は自陣にのみ〈あ〉札があるのを気にしたらしく、二枚のうち〈あま〉決まりになっている〈あまの〉を送ってきた。これで場の札の数は、希海が四枚で唯が五枚。試合は終盤から最終盤に突入しつつあった。
空札が続く。終盤以降の空札は焦らされることに耐えなければならない。慌てない、と希海は呪文のように唱えた。序盤と最終盤ではお手つきの重みが月と地球の重力くらい違う。敵陣五枚のうち、特に狙うべきは〈おも〉と〈たか〉と、数枚前に〈あき〉決まりになった〈あきか〉か。〈う〉決まりになっている〈うら〉も抜きたいが、〈ゆ〉に対する唯の反応を考えると厳しいような気がする。自陣も〈わび〉と〈きみがためは〉は守りたい。大山札である〈きみがためは〉は、先刻の〈あさぼらけう〉と同じ要領で取れるはずだった。
「〈む――〉」
また空札。しかし、唯の手が己の右下段をすぱっと払った。希海はとっさにはなにが起きたのかわからなかった。
「あっ」
唯の口からかすかな悲鳴が漏れた。そこに「〈――めの つゆもまだひぬ まきのはに――〉」と読手の声が重なる。唯が血の気の引いた顔で拾い上げて自陣に戻したのは、〈こひにくちなむなこそをしけれ〉と書かれた〈うら〉の札だった。唯は〈む〉を〈う〉と聞き間違えたのだ。希海はようやく事態を察した。このふたつの音は、読手によっては確かに似ていた。
希海は自陣の〈みせ〉を差し出した。喫茶たまさかのマスターの札、東北の太平洋の札だ。これで場の札の数は希海が三で唯が六。〈みせ〉の札を手にした唯の唇が震えている。泣き出す寸前というよりも茫然自失の様子だ。唯はまるで札が何百グラムもあるかのような動きで〈みせ〉を左下段に置いた。
「〈きりたちのぼる あきのゆふぐれ〉」
下の句が始まり、希海は腰を浮かせた。唯も構えの姿勢を取る。だが、先ほどまでのような意気込みが正面から伝わってこない。次の歌は空札で、希海は歌が読まれているあいだに唯の表情を盗み見た。唯の目は暗かった。
あ、折れた。
心が折れ、集中が切れた。唯がこの試合を見限ったことを希海は悟った。まだ大丈夫だよ、と胸中で語りかける。三対六は諦めるような局面ではまったくない。相手が同格の場合は、そもそも定位置が頭に入っていて、相手よりも直線距離が近い自陣は狙いさえすれば守れる確率のほうが高い。敵陣を優先していた意識をわずかに自陣に割く。それで充分立て直せる。今まで充実した勝負をしていたではないか。それは双方とも全力だったからできたことだ。最後まで一緒にやろうよ、と唯の両肩に手を置いて希海は言いたかった。
競技かるたはスポーツだ。どんな内容でも勝てれば嬉しく、負ければ悔しい。選手の大半は勝つために練習を重ねている。しかし、一枚でも多く会心の取りをすることや、ベストを尽くすこと。勝利の次に大切なのは、おそらくそういうことだ。そして、それらと勝つことのあいだに実は大きな差はない。〈む〉と〈う〉の音の違いほどもないはずだった。
自分が勝つことに絶対的な意義を感じていないのは、大人になってからかるたを始めたからなのだろうか。それならば、光のどけき会の門を叩いたのがあのタイミングでよかった。希海は初めて心の底からそう思った。
「〈みせ――〉」
希海は刺すような勢いで敵陣の左下段に指を突き立てた。
(つづく)