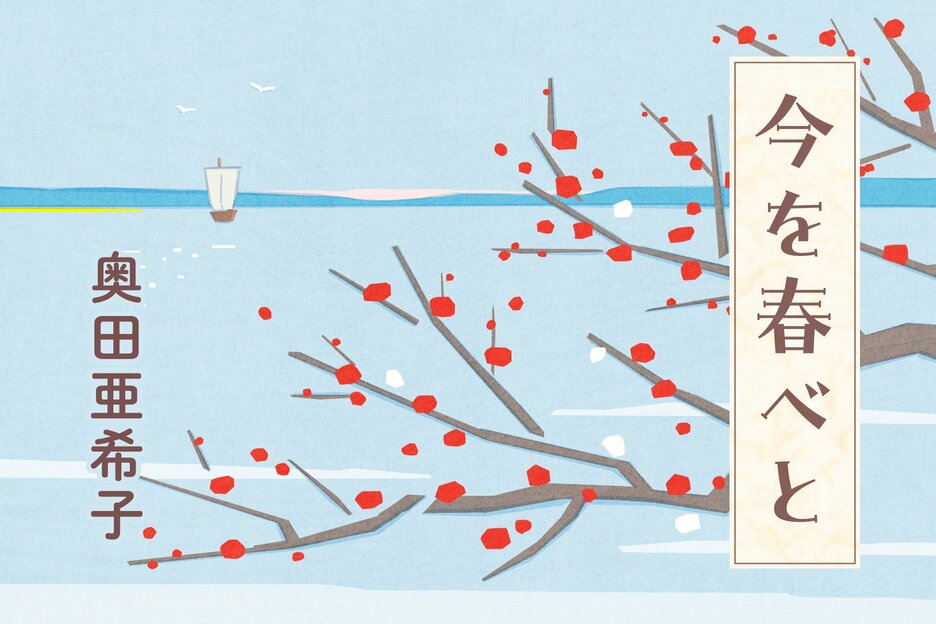卒園式の日は入園式ぶりに着たセレモニースーツの下で肌が汗ばむほどの陽気だった。すずがも幼稚園の園庭には、小ぶりの桜の木が一本植わっている。三月の下旬、花はちらほら散り始めていたが、そのさみしさにも情緒が溢れ、桜の木の前は家族の絶好のフォトスポットになっていた。
「写真なんてどこで撮っても同じだよ」
二十組を超える行列に並ばされた郁登は、先ほどから退屈そうに卒園証書のファイルを開けたり閉じたりしている。勇助が「桜と一緒に、郁登の最後の園服姿を撮りたいんだよ」と言って、郁登の髪を後ろからわしゃわしゃとかき混ぜた。勇助は卒園式に出席するために会社を休んだ。昔は平日に開かれる子ども関連の行事に母親以外が参加することはまれだったが、今日の園はごく当たり前のように、多くの父親や祖父母でにぎわっている。式の最中、勇助は郁登が卒園証書を受け取った瞬間に、「うう……」と呻いてハンカチで目もとを押さえていた。もちろん希海も泣いた。保護者と先生ばかりが泣き、子どもたちは普段どおりにささいなことで笑っている。幼稚園の卒園式らしい光景があちこちで繰り広げられていた。
「神奈川のじいじとばあばも、郁登の写真を待ってるよ」
「朝、家の前でも撮ったよ。あれを送ればいいのに」
勇助がなにを言っても郁登は不満そうだ。正午をすぎて空腹なのだろう。希海は郁登
「問題です」と切り出した。
「百人一首の中に桜という言葉が出てくる歌はみっつあります。なにとなにとなにでしょう?」
「えーっ、桜?」
郁登は視線をぐるんと回し、考え始めた。正解は〈いにしへの〉と〈たかさごの〉、そして、先月希海が初めて払えた〈もろともに〉の三首だ。どの歌も、決まり字や下の句には桜は含まれていない。歌を成す五・七・五・七・七のうち、三番目の五に入っている。競技かるたで札を取るための暗記をしている郁登には少し難しい問題だった。
「あ、〈いに〉に入ってたかも」
「正解」
〈いにしへの ならのみやこの やへざくら けふここのへに にほひぬるかな〉は、旧都の桜が新都でも美しく咲いているさまを詠んだものだ。桜は時を駆ける。園庭の木に、希海は上京直後に川沿いで見上げた満開の桜を重ねた。あのとき、自分は東京に歓迎されていると感じたのだった。
「あとふたつかあ。ママはわかるの?」
「わかるよ」
思い返すのに時間がかかるものや助詞があやふやなもの、意味を咀嚼できていないものはいくつもあるが、希海は小倉百人一首をひととおり頭に入れることに成功した。覚えてみようと思い立ってからの三ヶ月間は、自分は勉強が嫌いではないどころか、わりと好きだったことを再認識する日々だった。いつからか東京に行くための手段としてのみ勉強を捉えるようになっていたが、昔は知識が増えるたび、自分と世界との接地面が広がっていくような感覚を、九州の片田舎で楽しんでいた。先日、つっかえながらも初めて全首を暗唱できたとき、希海はそのことを久しぶりに思い出した。
「ヒントは? ヒントちょうだい」
「一枚は〈た〉札。〈た〉から始まる歌だよ」
「〈た〉ってなにがあったっけ? えっと、〈たご〉と〈たき〉と……」
郁登がぶつぶつ呟いているあいだにも列は進んだ。先に桜の木との撮影を終えたママ友家族とすれ違うたび、希海は「またね」「春休みとか遊べたらいいよね」と挨拶した。やはり子ども同士のほうが別れには淡泊だ。「ばいばーい」となおざりに手を振っている。希海たちの八組前が高橋一家だった。今日の愛桜はピンクのリボンを髪に編み込んだ、凝った髪形をしていた。愛桜の隣に立っているのは彼女の姉だろうか。よく似ている。列の先頭にいた男性が愛桜の父親らしき人物から一眼レフカメラを預かり、一家にレンズを向けた。笑顔になった愛桜の前歯は一本抜けていた。
撮影を終えた高橋家が行列の横をとおりかかった。希海と愛桜の母親の視線がふいに重なる。高橋のアイラインはにじんでいた。目を逸らす選択肢も頭をよぎったが、希海は踏みとどまり、小さく頭を下げた。
「あの、いろいろと……ごめんなさい」
高橋は足をとめ、首を横に振った。
「郁登くん、百人一首大会では大活躍でしたね。くじら組が優勝して、うちの子も大喜びでした。素敵な思い出をありがとうございました」
愛桜本人は母親が立ちどまったことに気づかず、姉と父親と先に進んでいた。愛桜の母親に警戒していた郁登が、突然の褒め言葉に驚いたように目をしばたたかせる。愛桜が難関私立小学校に合格したことは、園中の噂になっていた。地元の公立小学校に進む郁登とは進路がわかれる。あの日、「イルカの公園」で遊んでいたのは、束の間、受験勉強から休息していた高橋母娘だったのかもしれない。そんなことを思った。
「今のは誰? なんでママが謝るの?」
高橋が立ち去るやいなや、勇助は希海に耳打ちした。郁登と愛桜のトラブルについては話してあったが、彼女がその母親だとは気づかなかったのだろう。だが、どんなに丁寧に説明しても、今、自分と高橋が言葉の裏でなにを交わしたのかは、おそらく勇助には伝わらない。自分でも胸に広がるこの感情の正体がわからないのだ。「たいしたことじゃないよ」と希海が返すと、「ふーん」と勇助は急に興味を削がれたような顔になった。
卒園式から小学校の入学式までは、およそ三週間の春休みだった。さすがにずっとパートを休むわけにもいかず、希海は三月末日までは卒園生が利用できるすずがも幼稚園の特別保育に郁登を預け、四月からは区のファミリーサポート制度を頼った。一日だけ、勇助にも有給を取ってもらった。人事部で働く彼は育休や産休の手続きを扱うことが多く、「今はそういう時代だから」と子育てや妻の仕事のために休むことには理解があった。
入学した郁登は同じ幼稚園出身の子とはことごとくクラスがわかれた。だが、すぐに隼大というクラスメイトと仲よくなったようだ。隼大は顔が広いらしく、彼を通じて友だちが増えた。このごろでは昼休みになると男子五、六人で校庭に飛び出し、毎日のように鬼ごっこやサッカーで遊んでいるという。「隼大が」というのが最近の郁登の口癖になりつつあった。
「郁登、ご飯のあとでかるたやろうよ」
「ええーっ、俺、テレビが観たかったのに。今日の七時から鬼ごっこのテレビがあるんだって。隼大が最強におもしろいって言ってたよ」
「昨日もそう言ってかるたをやらなかったでしょう? テレビは録画しておくから、今日はやろうよ」
「録画してくれるなら、まあ、いいけど」
郁登は顎をしゃくるようにして頷いた。郁登が小学生になって以来、希海からかるたの練習に誘うことが増えた。天野から決まり字の変化について教わったのが契機だったかもしれない。決まり字には一字決まりから六字決まりまでの六種類がある。一字決まりは歌が何首読まれても変わらないが、ほかの札、たとえば〈も〉札には〈もろ〉が決まり字の〈もろともに〉と、〈もも〉が決まり字の〈ももしきや〉があり、どちらかの歌が読まれた時点で、もう片方は〈も〉の一音で取れるようになる。これが決まり字の変化だ。〈あはじ〉が決まり字の〈あはじしま〉は共札の〈あはれとも〉が先に出れば、そこからの決まり字は〈あは〉になる。〈あ〉札は百首の中でももっとも多く、全部で十六枚。もし〈あはじしま〉が十六枚目に読まれる〈あ〉札なら、そのときには〈あ〉の一字決まりになっている、という話だった。
これを意識し始めたことで希海は俄然強くなった。読まれた札を頭の中のみで把握していくのは、郁登にはまだ難しかったようだ。希海に勝てなくなったことも彼の情熱が冷めた一因だろう。だが、それだけではないと希海は睨んでいる。運が味方して勝てたときも、郁登は前のようにはしゃがなくなった。放課後も隼大たちと学校近くの公園で遊びたがり、「俺、天野先生は木曜だけでいい」と言うようになっていた。
ゴールデンウィークが明けると、間もなく郁登の誕生日だ。今年は運動会と日程が近く、誕生日祝いと運動会の応援を兼ね、希海の両親が福岡から遊びに来ることになっていた。運動会前日の夕方、二人は半日足らずの東京観光を終え、大荷物で希海たちのマンションを訪れた。
「お邪魔します。あらあ、郁登。大きくなったね」
「おお、日によう焼けとる。やっぱ子どもはこんくらい黒かほうがよかたい、健康的で」
「おばあちゃん、おじいちゃん、こんにちは」
「電車の乗り換えは大丈夫だった? 混んでなかった?」
玄関で両親を出迎えた希海は、近い将来に子ども部屋にするつもりの洋間に二人の荷物を運びながら尋ねた。
「駅員さんに教えてもらったとよ。いやあ、浅草もスカイツリーも外人さんがたくさんおった。外国んごたった。怖かったあ」
「スカイツリーって、要は福岡タワーと同じテレビ塔っちゃろう? あげん高くする必要があるとかね。あ、希海、ほら、お土産」
「ありがとう」
父親から手渡された紙袋は地元の和菓子屋のものだった。今回も中身は饅頭だろう。おいしいが、もっと凝った和菓子が東京にはいくらでもある。素直に空港で明太子を買ってきてくれればいいのに、と希海は思っていた。
「疲れてるなら先にお風呂の用意をするけど」
「そうさせてもらおうかな。汗ばかいたけんね」
「ちょっと待ってて」
希海はバスタブに栓をして、湯の音に紛れるようにため息を吐いた。今夜、両親はあの洋間に一泊する。顔を合わせてまだ数分しか経っていないのに、すでに若干疲れていた。娘だったころの感覚と母親である感覚を調和できない。方言がぽろっと口をつかないよう気を張るのにも精神力を要していた。
希海がタオルを用意して洋間に戻ると、郁登が百点のテストを二人に見せているところだった。
「いやあ、郁登はほんなこつ賢かね」
「あとね、ここにはないけど算数も百点だったよ」
「字もきれいか。小学一年生でこげんうまく書ける子はそうはおらんよ」
ここの払いが、ここの撥ねが、と父親は郁登の筆跡まで褒めた。希海が戻ってきたことに気づいた母親が振り返り、
「郁登は勇助くん似たい」
と言って、地元では決して使わないだろう、真っ赤な口紅を塗りたくった唇の両端を上げた。「そうかもね」と希海は平坦な声音で応えた。
今夜は勇助も定時に仕事を切り上げて帰宅した。夕飯は五人でホットプレートを囲んだ。肉や野菜など、銘々好きなものを焼いて食べ、郁登はジュースを、大人たちは酒を飲んだ。数日早い誕生日プレゼントとして、郁登は祖父母から海賊船を組み立てるブロックのキットをもらった。半年以上も前からリクエストしていたものだ。そこそこ大きいにもかかわらず、宅配便で送らずに自分たちの手で持ってくるところがこの二人らしい、と希海は思った。
父親は勇助に酒をどんどん注ぎ、自分も飲んだ。勇助はもとはアルコールに強くなかったが、医者を接待するうちに飲めるようになり、酒の味も好きになったと言っていた。これも接待の成果か相槌がうまく、両親の自尊心を絶妙にくすぐっている。父親は「勇助くんみたいな甲斐性のある男にもらってもらえて、希海は幸せたい」と言って目の縁を赤くし、母親は「私が家のことをろくに教えんうちにこの子は東京に出たけん、勇助くんに迷惑ばかけとるんじゃないかと心配しとったとよ」と言って眉尻を下げた。
「いやあ、親はいつまで経っても親だね」
郁登も両親も寝静まったあと、勇助は希海が淹れたコーヒーを啜り、ややあきれ顔で笑った。普段、勇助は寝る直前のカフェインを避けているが、今夜は酔い覚ましにと自分も飲みたがったのだった。
「やっぱりママのコーヒーが一番だな。職場のコーヒーメーカーのものと同じ飲みものには思えないよ」
「当たり前でしょう。こっちは百グラム千二百円の豆なんだから。そのへんの茶色いお湯と一緒にしないで」
「失礼しました」
勇助はおどけたように頭を下げた。「わかればよろしい」と希海は大仰に頷いた。
「でもさ、本当にかわいいんだね」
「なんの話?」
「だから、自分の子ども。三十九歳の娘でもかわいくて、心配なんだなって、今日、お義父さんとお義母さんを見てて思った」
「そうかなあ」
不自由なく育ててもらったのは確かだ。しかし、両親からかわいがられていると感じたことはあまりない。父親も母親も、希海が勉強でどれほどいい成績を収めても褒めることはなく、むしろ、「女の子はあんまり優秀じゃなかほうが……嫁のもらい手がなくなるけん」と渋い顔をした。ふたつ上の兄が中学生のときに簡単な英語の試験に合格し、ケーキとゲームソフトで祝われたのとは対照的だった。
今も両親は娘婿と孫息子に鼻が高いだけなのだろう。あの二人に実の娘を誇るポイントがあるとすれば、難関国立大学出身で病院勤務の男性と結婚したことと、活発で物怖じしない息子を産んだこと以外にはないような気がする。希海はマグカップに口をつけた。実家の記憶はおしなべて孤独感と結びついている。息を吐くと、芳醇なコーヒー豆の香りが鼻からも抜けた。
翌日の運動会の五十メートル走で、郁登は一着を獲った。希海の両親は「すごか」と手を叩いて喜んだ。郁登はダンスの振りつけも完璧だった。運動会のプログラムは午前中で終わり、児童は教室でクラスメイトと弁当を食べる予定だったため、大人四人は近所の蕎麦屋で昼食を済ませた。蕎麦を食べているあいだもマンションに戻る道すがらも、父親と母親は郁登を褒めちぎり、勇助の遺伝子を讃えた。希海も、「希海の子育てもたいしたもんたい」「仕事に復帰せんかったのは正解やったね」とは言われた。
学校から帰宅した郁登とおやつを食べたのち、両親は空港に発った。
「今度は福岡に来んね」
「おばあちゃん、郁登のことを待っとるけん」
「気をつけて帰ってよ。駅まではお兄ちゃんが迎えに来るんだよね?」
十二年前に結婚した希海の兄は、妻と二人の娘と実家から徒歩三分のところに住んでいる。行きも地元の駅までは兄が車で送ったと聞いていた。
「来てくれるよ。それまで酒ば飲まれんけん、文句は言っとった。ばってん、なんだかんだ言っても、あの子は優しいけん」
郁登を撫でる母親の目がまるで小さいころの兄を見ているかのようで、希海はこめかみが引き攣りそうになった。しかし、東京の大学に行ったきり地元に戻らず、一年に一度帰省すれば多いほうという娘に比べれば、切れた電球を交換したり重いものを代わりに運んでくれたりする息子のほうが優しいのは、誰が見ても明らかだろう。たとえ度重なる喫煙が原因で高校を中退した過去と、親の金でパチンコとスロットに明け暮れる二年弱の月日が兄にあったとしても。希海は笑顔を作り、「お兄ちゃんたちにもよろしくね」と二人をマンションのエントランスで見送った。
空港まで付き添う元気は残っていなかった。
(つづく)