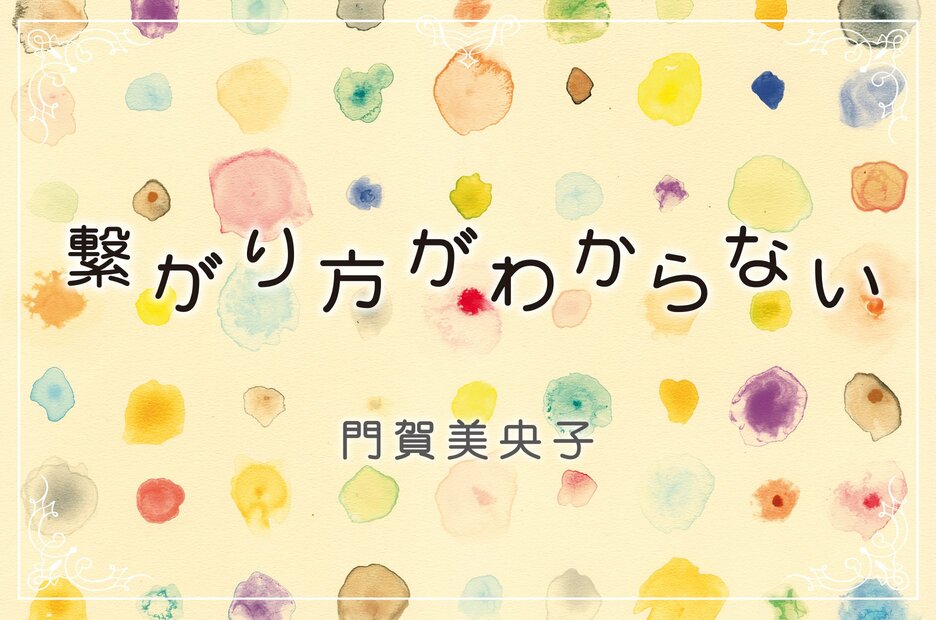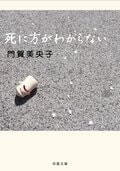ローンウルフもいいじゃない
さて、前回までは互助会計画に浮かれ気味だったが、こういうことの計画者としていろいろと立ち上げられるのは、やはり私が物書きとして名前を出して活動するタイプの仕事をやっているからという側面があるのは確かだ。
人前で話したり、文章を書いたりすることに慣れている職業柄、取り組みを始めるにしても心理的なハードルは低い。
けれども、互助会とか無理! という向きがいるのも重々承知している。組織を作るなんて所業は言うまでもなく、入るつもりも関わるつもりないという人の気持ちもわかるのだ。私だって、『死に方がわからない』『老い方がわからない』を書いていなければ、互助会を立ち上げようなんて大それたことは思わなかっただろう。
それに、依然として完全なローンウルフとして独り者ライフをやっていきたいという気持ちも残っている。本当はその方が気楽だからだ。今なお、人との関わりは時に疲れる。常に誰かと繋がっていることが義務のように感じられると息苦しい。
だから、互助会という仕組みに頼らなくても、市井の一個人として、豊かな孤独生活を楽しむための孤立防止方法があればそれがベストだと思っているのだ。
よって、最後に、組織的な何かに所属しなくても、孤立を防ぎながら独りの生活を楽しむ方法を考えておきたい。
まず考えられるのは、「顔なじみの場所を持つ」ということである。
手っ取り早いのは近所のスナックや喫茶店、食堂などの常連になることだ。常連になれば自然と顔を覚えてもらえる上、毎週決まった曜日に通うなど、ある程度パターン化することで変化も察してもらいやすくなる。さらに、店の人や他の常連客との関係を築いておけば、いざというとき、「あの人、最近見ないけど大丈夫かな」と気にかけてもらえるだろう。この程度のゆるやかな関係でも、孤立防止の観点からは非常に価値がある。
今回、取材をする中、タケダさん(仮名)からこんな話を聞いた。
タケダさんはとある田舎町にある喫茶店の常連客だ。
毎日来る客はほぼ全員が顔見知り。毎日来るほどの常連客であれば、マスターが連絡先を把握している。お互いの持病や体調などもある程度把握しているし、生活習慣もわかっている。だから、しばらく来ない人がいるとマスターが心配し、ときには電話をかけて安否確認をすることもあるという。
このような関係性は、互助会のような組織に属さなくても自然に生まれる、貴重なセーフティネットといえるだろう。
また、地域社会で存在感をアピールしておくのも重要だ。
新人漫才師のいう「今日は名前だけでも覚えて帰ってもろたら」である。
そして、そのためには「定期的な習慣を持つ」のが第一歩になるようだ。
例えば、毎朝同じ時間に近所を散歩する、週に一度は喫茶店でお茶、月に一度は散髪しに行くなど、定期的な外出の機会を意識的に作ることで、社会との接点を維持できる。
そう、社会との接点の維持。これが案外ミソなのだ。
接点さえあれば、やがて同じく定期的に訪れる人との緩やかな繋がりが生まれることもあるだろう。挨拶を交わす程度の関係性でも、互いに顔を認識していることで安心感が得られる。接点が無くなると、本当に透明な人間になり、そのまま消滅するか、最悪の場合「無敵の人」になってしまう。
接点の維持には「公共サービスの積極的活用」も有効だ。図書館や公民館、コミュニティーセンターなどの公共施設には無料で利用できる設備などが用意されているが、単に利用するだけでなく、そこで開催される講座やイベントに参加すれば繋がりを持つ一つのきっかけになる。
もう少し積極的になれるのであれば、「ボランティア活動への参加」も検討する価値があるだろう。特定の組織に所属しなくとも、単発的なボランティアとして活動すれば、社会貢献しながらも自分のペースを保つことができる。ネットで「地域名+ボランティア」で検索すれば必ず地域のボランティア活動を包括する団体のサイトがあがってくる。そこで自分の都合に合わせて参加できる活動を探せば何かしらはあるだろう。清掃活動や災害支援、福祉施設でのお手伝いなど、内容は多彩だが、誰かの役に立つという実感は、自己肯定感を高め、孤独を和らげる効果もある。
や、拙者は働きたくないでござる、なら「趣味のコミュニティーに参加する」のも一つの方法だ。互助会のような相互扶助を目的としたコミュニティーではなく、単に同じ趣味を楽しむためのグループであれば、参加のハードルも低い。読書会、写真サークル、園芸の集まり、料理教室など、興味のある活動を通じて自然と人との交流が生まれる。組織への帰属意識を持たなくても、活動そのものを楽しむことを主目的として参加できるのが魅力だ。
「テクノロジーの活用」も現代的な選択肢だ。スマートスピーカーや見守りセンサー、緊急通報システムなどのテクノロジーは、物理的な人との接触を最小限にしながらも安全を確保する手段となる。音声での会話ができるAIアシスタントは、ちょっとした話し相手になることで、声を出す機会を作り出し、孤独を和らげる効果もあるという研究結果もある。
ただし、上記の手段はすべてあくまできっかけに過ぎず、きっかけを手がかりに「安否確認」をしてくれるような段階にまで人間関係を進めておかなくてはならない。つまり、「私を何日か見かけなかったら何かアクションを起こして下さい」と頼めるような間柄だ。
しかし、「何かのアクション」とは具体的になんだろうか?
今のところ、身寄りがない場合に有効な手段として考えられるのは、地域警察官(いわゆる交番のお巡りさん)が巡回連絡に来た場合しっかりと自分の情報を伝えておくこと、くらいだろうか。
巡回連絡とは、警察官が直接各家庭を訪問して家族構成や連絡先などを尋ねる制度で、聴取した結果は巡回連絡カードに書き込まれる。この時に「なにかあった時は見に来てください」と伝えておけば、周囲の人にも「私を見かけなくなったら警察に連絡して」と頼んでおける。「あなたが私の様子を見に来て」だと頼む方も頼まれる方もハードルが高いだろうが、「警察に連絡して」ならまだしも、だろう。しかも、「警察には自分の巡回連絡カードがあるから」とあらかじめ言っておけばなおさらだ。
警察官が回ってこないなら、自分から交番に出向けばよい。事情を話せばカードを作ってくれるし、今後何かあった時もスムーズに動いてくれるだろう。
警察を信用するかどうかは個人の思想の自由の範疇に入ってくるので私としてはなんとも申し上げられないが、あくまで自衛手段だ。やるかやらないかの判断は自分をどれだけ守りたいかによるのだろう。
いずれせよ、どの方法が一番かは、その人の性格や環境、健康状態や経済状態などによって異なる。
大切なのは、自分自身の心地よさを優先しつつも、社会との繋がりを完全に絶たないバランスを見つけることなのだと思う。
私自身、今後も互助会の活動を続けていくつもりだが、同時にこうしたローンウルフ的な選択肢も並行して実践するつもりである。互助会が一つのコミュニティーとして機能するまでには時間がかかるだろうし、仮に機能したとしても、常に誰かと繋がっていると時に疲れることもある。だからこそ、一人の時間も大切にしながら、緩やかな社会との接点を持つ方法を模索し続けたいのだ。
結局のところ、「独り者」の生き方に正解はない。互助会のようなコミュニティーに積極的に関わる人もいれば、最小限の社会的接点を保ちながらローンウルフとして生きる人もいる。どちらが正しいということではなく、その人にとって心地よい距離感を見つけることが大切なのだ。互助会を通じてでも、個人的な工夫を通じてでも、「ちょうどよいつながり」を絶やさない努力を続けていきたいと思う。私の場合、努力しないとそれを実現できないので。
いずれどのような選択をするにせよ、完全な孤立だけは避けたい。
完全孤立だけはどう考えても百害あって一利なし、だ。
繋がりは人生サバイバルにおける十徳ナイフのようなもの。
なくても生きられるが、なかったら超不便。
そういうことなのだと思う。