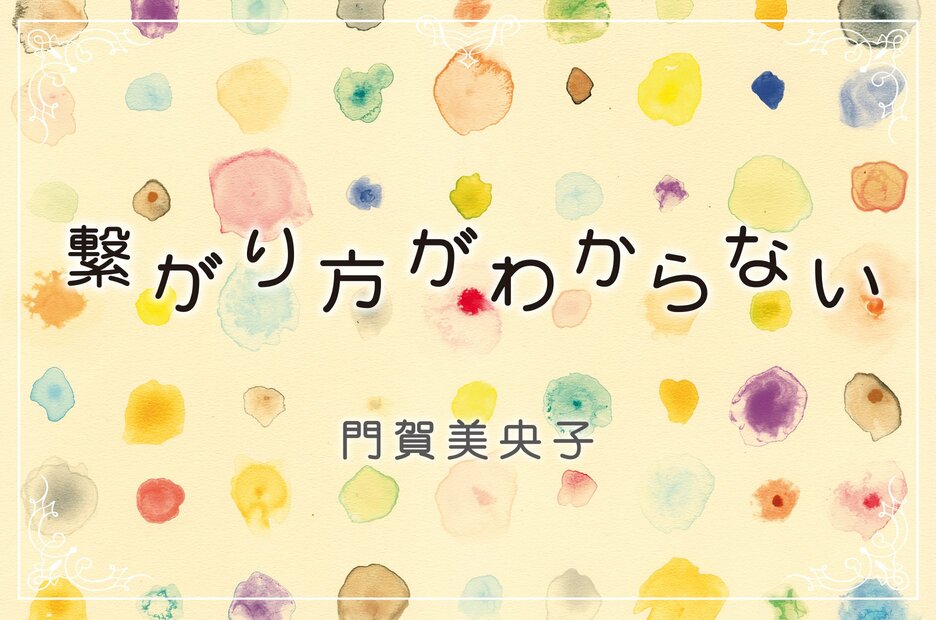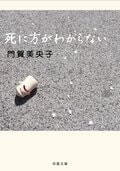とりま、やってみる
前回までつらつら書いてきた通り、独り者互助会を立ち上げることにした。名前の通り、独りで生きる人たちが互いに助け合うためのコミュニティーである。
助走として、まずは自分のSNSでゆるく募集を始めた。
特別な宣伝文句もなく、ただ「独り者同士で助け合う会を作ります。興味のある方はご連絡ください」という程度の投稿である。大げさに宣伝するのも気が引けたし、どのような形にしていくかもまだ漠然としたイメージしかなかったからである。
そんな程度の投稿でも、反応はそれなりにあった。
とはいえ、今のところ「私も参加したいです!」という積極的な人は十人を少し超える程度だ。
しかし、それは織り込み済みである。最初からわーっと人が集まってくる状況を期待しているわけではない。むしろ、静かな出発は自然なことだと考えている。人が集まるのには時間がかかるものだ。特に「独り者」という言葉には、まだ社会的に微妙なニュアンスがある状況において、反応するのすら気が引ける人もいることだろう。そう考えると反応はむしろ上々だったのかもしれない。
もちろん、正直なところを吐露すれば、少しさびしい気持ちはある。協力者になりましょうぞと手を上げてくれる人が続出しないか、内心ちょびっとだけ期待していたからだ。
しかし、さすがにそれはなかった。けれども、それも仕方のないことだと思う。むしろあんなゆるい呼びかけに応えてくれた方々がいたことをこそ嘉すべきで、ありがたいことなのだ。私だったら絶対ためらう。なにせ、疑り深い性格なので。
いずれにせよ、新しいコミュニティーを作るというのはそう簡単なことではないのは重々承知の上だ。
コミュニティーを形成するには様々な障壁があるだろう。
私が馬の骨であることはひとまず置いといたとして、今回主な対象が「独り者」だというのは、常に頭に置いておかなければならない。そもそも、ちょっとした呼びかけにフットワーク軽く集まれるほど気楽な性格なら長らく独り者なんぞやっていないはずだ。
また、互助会の求心力は「孤立の不安」が核になるはずだが、それだけで果たして助け合いができるほどの強いつながりが生まれるかどうか。もう一段上、互いに何を共有し、どのような価値を見出すのかを明確にしていく必要がある。かといって、価値の押し付けはしたくないし、されたくない。
さらに、コミュニティー運営の労力を負おうと思う人がどれほどいるか。
あらゆる運営資源の確保、日程調整、活動内容の企画など、誰かがその役割を担わなければならない。
ひとまずはWEB上に設けた準備室で、連絡先と実名を提示できる人だけを対象にしたが、それはスタートアップの時点では本気で会をやろうと考える人にだけ来て欲しいからだった。
しかし、そんな人たちでも、自発的に動いてくれる人はどれほどいるものだろう。
私は発起人として、人より多くの役割と責任を担う覚悟はあるが、もし全てを引き受けることになったら早晩嫌になって精神的に引きこもりに後戻りするだろう。これでは話にならない。
だから、最初からある程度役割を引き受けてくれる人に参加してもらう必要がある。そのためには人間関係の構築が必須になってくるが、それには時間がかかる。見ず知らずの人同士がお互いを理解し、信頼関係を築くには、何度も顔を合わせ、共に時間を過ごす必要があるものだが、今回の計画に関してはこれが難しい。
もちろんオンラインでの交流はやるつもりだが、どこまで功を奏するか。ある程度の忍耐と継続的な努力が求められるだろう。けれども、参加者の誰もがそこまでの労力を費やす準備ができているとは限らない。
どう考えても新しいコミュニティーの形成は一朝一夕にはいかないのである。
しかし、そのような困難があることを理解した上で、それでも挑戦する価値があると感じている……というか、やらなきゃ自分が困る。
ただ、一ついいことがある。年を取ってきたせいだろうか、私自身がすぐに成果が出なくても種を蒔いておけばいつか芽吹くだろうと、のんびり構えられるようになっているのだ。
若い頃は何事も即座に結果が欲しかった。卓球レベルでのクイック・レスポンスがないとイライラしたものだった。
しかし今は、何事も熟すのに必要な時間というものがあると理解できるようになってきている。この互助会ものんびりやっていけば、必要としている人に見つけてもらえ、自然と人が集まってくるのではないかと思う。それに、どういう互助会にすればいいのか、いろいろと考えるのは楽しいことではあるのだ。
私は「独り者互助会」は人体のようなものになるのではないかと考えている。
人間の身体は、様々な器官や組織が絶妙に連携することで機能している。
心臓は血液を送り出し、肺は酸素を取り込み、筋肉は動きを生み出す。
細胞それぞれが自らの特性に合った役割を担い、全体として一つの生命体を形成している。
独り者互助会も同様に、各メンバーがそれぞれの得意分野や可能な範囲で貢献することによって、全体の健全な機能を維持するのだ。
技術的な話だとITやAIあたりの知識を持つ人がいるとそれはもう大変ありがたい。また、法律や行政に詳しい人、福祉のスペシャリストなんかがいればもう御の字だ。
でも、なんらかのスペシャリスト、あるいはプロフェッショナルでなくても、絶対できることはある。
ほぼ自宅警備員の人ならばSNS運用や問い合わせへの一次対応なんかを任せることができる。
計算が得意、あるいは経理的な仕事をやったことがあるならば会計を任せられる。
細かいチェックが得意なら監査をお願いできるだろう。
全体の進捗管理をやる人や、運用チェックをする人だって重要だ。
これらは家にいながらにしてできる。
また、フットワーク軽く動ける人や人脈が広い人なんか大歓迎である。
重要なのは、人体においてどの器官も単独で全てを司ることができないように、互助会もトップダウン型の指揮系統ではなく、水平的で網羅的な協力関係で成り立たせないといけないという点だ。
どんな立派なものであっても脳だけでは身体は機能しない。同様に、代表者や発起人がいたとしても、その人だけが責任や権限を持つのではなく、メンバー全員が自分の役割を自発的に果たすことで、組織は健全に機能すると思うのだ。
また、どれだけ健康な身体でも時に病気にかかるように、互助会でも必ずトラブルは発生するだろう。メンバー間の意見の相違や、負担の偏りはもちろん、時には癌細胞のように組織全体を危険に晒すような破壊的な存在が現れるかもしれない。だからこそ、人間が定期健診を受けるように、互助会も常に自己点検を行う必要がある。あらゆるリスクに対する予防措置も必要だ(たぶん、これが一番の大仕事になる)。
何事であれ、問題が小さいうちに対処するのが肝要。必要であれば病巣を取り除く決断も辞さない覚悟が運営には求められる。それは時に厳しい選択を伴うかもしれないが、組織全体の健全性を保つためには避けては通れない道である。生ぬるい覚悟では決してやれないし、やってはいけないのだろう。
人体のあらゆる細胞は、互いに支え合い、影響し合いながら、一つの生命として生き続ける。
独り者互助会も同様に、それぞれが独立した個人でありながらも、互いの存在が互いの安心を支える共生関係を目指す。一人では対処できない困難も、複数人の知恵と力を合わせれば乗り越えられることがある。
共存し、お互いに、お互いの安心に寄与する。まるで、数兆個の細胞が協調して一つの人体を形成するように。
互いに役割を果たしながら繋がり合うことで、一人ひとりが人生を安心して送ることができる。
誰もが助けられる一方でも、助ける一方でもなく、必ず自分ができることをやる。
それが独り者互助会の理想的な姿だ。
そして、もし可能であればだが、分科会的な機能に特化した組織システムを作るといいんじゃないかと思う。