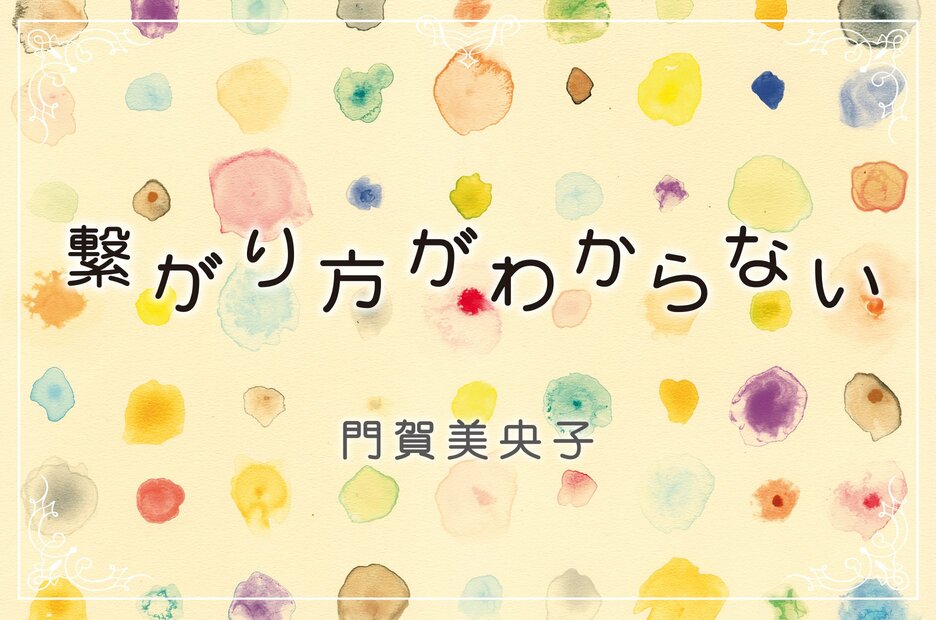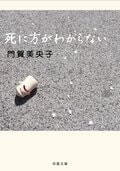人間関係の築き方を考える
広い人脈によって人生を充実させ、活躍の場を広げている。
私からはそう見えている御三方に話を聞いたことで、私の人間関係構築力&持続力に欠けているものが見えてきた。それを念頭に、しばらくは自力で人間関係の形成について考えを深めたいと思う。モンガーズにも引っ込んでいてもらうことにしよう。
さて、まず大きな前提を再度共有しておきたい。
現代社会は人間関係が希薄になった、といわれている。その渦中にいてさらに己の人間関係は希薄だと感じているのだから、それはもう相当希薄なのだろう。お母さんが作るカルピスどころの騒ぎではない。この希薄さが私を自由にしている一方、将来、自分が弱った時の生活を不安定にする要因になるのは素直に認めなくてはならない。
けれども、私は自由が失われたら精神的に参ってしまう。だから、自由を保障したまま安定した人間関係を築くことを目標としなければならないわけだが、「個の自由」と「関係性の安定」は両立させようとすると、ある種のジレンマを抱えることになる。
さて、ここからはちょっとマジメになる。ゆえに、なんだか小難しく賢しげな単語が増えるかもしれないが、少しだけ許してほしい。こう見えてもワタクシ、漢字で考えたほうが思考をまとめやすい性質ですの。
などと、余計な前置きをしつつ。
まず、安定的な人間関係の基盤として重要なのは自他ともにその選択や生き方を尊重しながら、なおかつ関係性を築いていく姿勢だろう。
では、その姿勢とはどのようなものだろうか。
今のところ、次の四つが考えられる。
一、ゆるやかな紐帯
普段は適切な心理的距離を保ちながら、必要なときには支え合える関係性を作ること。常に密接な関わりを持つのではなく、むしろ適度な距離感を保つことで関係の持続可能性を高める。
二、選択的関与
人生や日常、全ての場面で関わりを持つのではなく、お互いの状況や必要に応じて関与の度合いを調整する。つまり、問題ごとに頼れる場所/人を分けることで、一箇所への負担増を避け、リスク分散する。
三、互助関係の強化
世は押し並べてギブ・アンド・テイク、頼り頼られ振り振られが基本と心得る。「振り振られ」が入る理由はたったひとつ。時には拒否することも必要だし、拒否されてもそれはそれで相手の選択として尊重せねばならないからだ。
四、「自己開示」と「境界設定」のバランス
オンラインオフライン問わず、コミュニケーションにおいて他者との信頼関係を築くために必要な自己開示と、個としての境界を守ることの両立を意識する。
以上である。
この四つを心構えとしておけば、淡白な関係でも希薄化ではなく、むしろ成熟した関係性と呼べるものにしていけるのではないだろうか。それはより深い信頼関係の土台となり得る。
土台の構築には、過干渉と無干渉の中庸を取らねばならない。だが、何を以て過干渉、あるいは無干渉とするか、そのボーダーは人によって異なる。一律でここまでOK、ここからはOUTと切り分けできない、対象に合わせて逐次調整しなければならないのが、私のようなコミュ不全には面倒に感じられる最大の難点になっているわけだが、人間関係維持に必要なコストと考えるべきなのだろう。
そして、それは相手が自分とは異なる価値観や選択を持つ独立した存在であることを理解し、受け入れることでしか果たされない。単に「違いの容認」するだけでは足りず、その人固有の人生の文脈や成長の過程を理解しようとする積極的な姿勢も時には必要になるはずだ。
では、実生活の中で、それらをどう読み取っていけばいいのだろうか。
第一段階は「観察」と「理解」だ。
相手の言動や反応から、その人が望む関与の度合いを読み取らなければならない。
たとえば、SNSに投稿するたび、同じ人物から逐一々いいねがついたり、コメントが加えられたりしたとしよう。
私には、完全に過干渉としか思えず、不気味にすら感じる。私の場合、いいねは本当に「いいね」と思った時や賛同など比較的積極的に意思を表示したい時にのみ行う。一方、世の中には「そのポストを見ましたよ」という印の代わりに「いいね」をするタイプもいる。そこには「いいね」やコメント行為への意識のギャップが存在しているのだ。
日常会話でも同様に、相手の一言一句に相槌をうったり目に見える形でリアクションをするのが好きな人もいれば、私のようにじっと聞いてここぞという時にだけ何らかの動作を加える方がよいと考える人間もいる。
このあたりの機微は、読み取るのがなかなか難しい。顔が見えないコミュニケーションだと余計に、だ。
よって、明らかに害悪や多大なストレスにならない限り、ある程度の違和感は容認する、つまりスルーすることも必要だとは思っている。「あの人には他意はなかろうから」と済ませた方がお互いのため、ということもあるのだ。
第二段階は対話による確認だ。
だが、我慢するばかりではうまくいかないのも事実である。だから、時には明示的なコミュニケーションを通じて、お互いの期待や境界線について理解を深める必要もあるだろう。
要するに「悪いけど、毎回されたらワシはキモいわ」という内容も、失礼にならないよう、傷つけないよう言葉を工夫すれば、表明することそれ自体は問題ないわけである。むしろ、自分を守るために必要だ。とはいえ、たったこれだけのことでもサラッとできる人と畢生の一大事になってしまう人とに分かれる。後者の人にとって、明示行為の心的コスト感は半端ではないわけだが、それでも我慢し続けて最後にいきなりキレるよりはマシ、と思わなければしょうがない。
まともな人間であればそこで関わり方を調整してくれるはずだ。してくれないような相手はそもそも安定した持続的な関係性を求めるような相手ではない。さっさと離れるのが吉である。
第三段階は調整と再確認だ。
関係性が進展すれば、相手へのコミュニケーションにかかる心的コストも漸減していくはずだ。つまり、信頼度が深まり、相手の言語感覚や他者との距離感を理解していけば「悪いけど、毎回されたらワシはキモいわ」をそのままの言葉で告げても悪意からの発言ではないとわかってくれるはずである。
一方、悪意がなくてももう少し言い方を工夫してくれよと感じるのであれば「悪いけど、ワシはその言われ方はされたないわ」と応じればよい。
これが関与の度合いを柔軟に調整していく、ということではないか。これもまた自然にできる人とそうでない人がいるだろうが、そもそも人間は可塑的存在だ。つまり、経験を重ねるうちに慣れていく。
また、この段階では「関与の非対称性」を認識することが特に重要になってくる。つまり、同じ関係性の中でも、一方が より深い関与を望み、他方がより大きな距離を必要とする場合があることをしっかりとわきまえておく、ということである。この非対称性を自然なものとして受け入れることが、関係性の健全な維持には不可欠なのではないだろうか。
次に関係性の境界設定だが、これはなかなか難しい。
ボーダーラインは、その人が生育した環境の文化的背景や価値観がベースにあった上で、現在の生活状況や社会的役割、成育歴や過去の人間関係、さらにはその時々の精神的/身体的状態によって変化する。
このうち、比較的固定的なのは生育した環境の文化的背景や価値観だろうか。Stingの「Englishman in NEW YORK」、あるいはBOROの「大阪で生まれた女」などの名曲で歌われているように、背景文化が違えば同じ言語を話していても相互理解や環境への溶け込みは難しく、関係性に歪みが生じる。正直、私も大阪から東京へ越してきた後の数年間は会話のリズムが掴めずになかなか大変だった。関東の水に馴染んだ今は逆に大阪で面食らうことも増えているし。
また、体調がいい時には楽々な徒歩通勤が、風邪で大熱が出たらデッドロードに変わるように、その時の気分次第で相手の出方が妙に気に触ったりすることもある。
このように、境界はあいまいかつフレキシブルなものとわきまえた上で、お互いの「心地よい距離」を見出していく過程そのものが、関係性を深める機会になるはずだ。つまり、安定的な人間関係を構築するには、ある程度まとまった時間が必要だ、という至極当たり前の結論に至る。
しかし、タイムパフォーマンス重視の風潮が蔓延する現代社会において、相手にも時間的コストをかけてくれるように求めたら、それ自体を過度の負担として捉えられかねない。
ぶっちゃけ言ってしまうと、そこまで考え始めたらもう自縄自縛になるだけだよな、とは思う。思うけれども、今ここで考えることを放棄したら本連載の存在意義を自己否定することになりかねないので、一応解決策を見出したいと思う。
時間効率と関係性の深化という一見相反する要素を両立させるには、スキマ時間利用レベルの低負担を重視したアプローチが有効ではなかろうか。
そのためには、日常的に小さな観察の蓄積していくことが大切だ。つまり、相手の些細な反応や表情の変化に注意を払うことで、特別な時間を設けなくても、通常の交流の中で理解を深めていくのだ。
また、必ずしも積極的な交流だけが理解を深める機会ではないだろう。連絡や会話が途切れる期間も、関係性を考える上での重要な機会であると思えばいい。むしろ、隙間があることで、お互いの心地よい距離が自然と見えてくることもあるはずだ。
また、意図的な「小さな実験」を試みるのも悪くないかもしれない。些細な提案や協力の申し出を通じて、相手の反応を見るのだ。決して大きな負担にならない程度の関わりから始め、相手の反応に応じて、徐々に関係性の深さを調整していく。これらは一見効率が悪そうだが、普段の関わりの質を高める試みとしてはむしろ一番楽なのではないかと思う。
結局、相手が人間である以上「効率的に親密になる」のはほぼ無理なのだ。日常の中で、自然に理解を深めていくしかない。時間をかけることで、自分への負担も相手への負担も最小限にできる。
こうなってくると、やっぱり活用すべきは一般マナーと常識、という話になってくる。社会的な文脈や立場に応じた一般的な距離感、基本的なマナーや慣習をスタートラインにして、そこからの微調整を図っていくしかない。詰まるところ、やっぱり常識やマナーは大事、なのだ。
だが、これだけをテンプレート的にやっていたら、無難なだけで記憶に残らない人間になる。記憶に残らなければ関係性云々すらできない。それを避けるためには、なにかインパクトのあることをやる……のではなく、再会時に関係性の継続を示す行動が取れなければならないのではなかろうか。
簡単に言うと「ちゃんと覚えておく」である。
実はつい先日、とある取材で御一緒したカメラマンの女性に「数年前に一度お会いしましたよね」と声をかけてもらったのに、こっちはまったく覚えていなかった、という恥ずかしい出来事があった。
言い訳をすると、その方と過ごした時間はおそらくものの十数分に満たなかった。というのも、私が取材を受けた時に写真を撮ってくださったカメラマンさんだったからだ。
先方は私の顔を撮影時に見ただけでなく、画像データを処理する間も眺めておられたことだろう。一方、私は最初と最後の挨拶時以外はカメラ越しにしかお姿を拝見しておらず、しかも当日は事情があって撮影後すぐに辞去されたので、お顔を覚える暇もなかったのだ。たしかバタバタで名刺交換すらできなかった気がする。
だから、覚えていなくても無理はない、と思う。しかも、シチュエーション自体はきちんと覚えていたので、ちょっと話を振られたらすぐにその時お世話になった方だと思い出せた。おかげできちんと無礼を詫びた上で、その折のお礼を申し述べることができたのだが、もしそれさえ覚えていなければ大変失礼な結果になっただろう。名前と顔を覚えるのは苦手だが、シチュエーションは比較的記憶に留めることができる特性のおかげで最悪の事態は免れたわけだ。
しかし、もし私がそのカメラマンさんの名前をきちんと覚えていたらどうだっただろう。
実は、撮ってもらった写真がとても素敵で、大のお気に入りになったので、その後別の媒体で二次使用させてもらったことがあったのだ。それほど気に入っていたのであれば、撮ってくれた方のお名前ぐらい覚えていてもおかしくはない。それなのにまったく記憶になかったのだから、これはもう駄目である。
我ながら「おまえ、ほんまそういうとこな」と思った出来事だった。
正直な話をすると、現場で一度御一緒しただけのような方の顔と名前をすべて記憶に留め置くことは無理だ。けれども、なにか特別なことがあったのであれば話は違う。つまり、相手と共有した何らかの記憶は、重要度に応じて保持すべきなのだ。
実際、現場で繰り返しお会いすることで、雑談をするようになったカメラマンさんもいるし、私が今対外向けに使っているポートレート(いわゆるアー写的なやつ)はそうした方々のうちのお一人に撮ってもらったものだ。これぞ最初にあげた四条件のうち、三つまでを満たした関係性といえる。
とにかく、私はまず少なくとも繰り返しお会いする可能性のある人の顔と名前ぐらいはしっかり覚えること。恥ずかしい話だが、ここから始めるのが良さそうである。